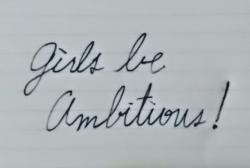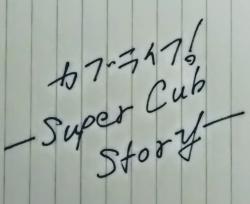マヤは背を向けていた。
「マヤは偉いよね。みんながしんどいときに一人だけ、ちゃんと暗闇の中から出口を見つけ出すのがうまくて、そこへみんなを導いてゆく。私はマニアックなアニメの物真似、好きだったなぁ」
向き直ることはなかったが、肩が震えている。
「千波は天真爛漫で、発想が豊かで、どうしたらそんな曲が出来るのか私はいつも不思議だった。私は楽器が出来ないから、それだけで尊敬していたし、あなたには遂に勝てなかった。すごいよ」
千波は涙を流しながら微笑んだ。
最後に唯、と藤子は、
「私とは幼稚園からの付き合いで、今じゃ私の両親より一緒の時間が長くなって、まるで熟年夫婦みたいな関係性だけど、でも私をたしなめたり、ときには矢となり盾となって、いつも一緒に戦ってくれた。いつも唯はアイドルは戦士で、武器がないと勝ち残れないって言ってた。私なんか大した武器もないから足手まといだったかも知れないけど、何とか死なずに済んだのはあなたのおかげ。ありがとう」
たまらず、唯は藤子を泣きながらハグした。
「ひとしきり泣いたら、あとは笑おう」
藤子は立ち上がると、スカートの埃を軽く払った。