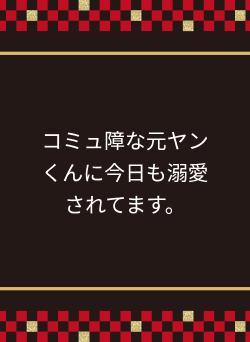「よ、よかったの…?」
「全然。今日は円と一緒にいたかった。」
そんなことをサラッと言ってのけるのは、さすが。
王子様と噂されるだけある。
そんな人の…彼女…
「えへへ…」
「なんだよ、気持ちわりぃな。」
「宮の彼女って響きが…もう最高。」
「また何言ってんだバカ。」
宮は私の頭をぺしっと叩くと、
口許に手を当てて咳払いした。
あ…これ、照れてる…?
気持ち悪くてもなんでもいい。
「えへへ…」
嬉しくてしょうがないんだもん。
「コホンッ、えーっと…
円、昨日なんで休んでたんだよ。」
私がずっとニヤニヤしていると、宮はそう尋ねてきた。
「ああ、眠れなかったの。」
「えっ…そ、それって…」
「うん。宮にキスされて、でも宮が嫌そうな顔してたから…気になって。」
「ごめん!!」
珍しく宮が大きな声を出して謝ってきたから、
私は驚いて立ち止まった。
「俺、あのとき…円が眠れなくなるくらい悩めばいいって…思った。
だから…俺のせいだ。」
「違うよ。私がしつこかったから…」
「いや…」
宮はきつく唇を噛んでいる。
心の底から後悔している様子だ。
眠れなくなるくらい悩めばいいなんて、
正直思われても私は問題ない。
それくらい宮も私のことで悩んでくれていたっていうことだし。
そもそも考えるのは自由だ。
気持ちは伝わらなければ、存在しないのと同じなんだ。
それに宮が私を好きでいてくれるなら、私はずっと快眠できる気がするし。
「いいよ。これから宮が私のそばにいてくれるなら、一日眠れなかったことなんてすぐ忘れる。」
「…ああ。」
「宮って意外と気にしい?
私がいじめられないようにとか気にしてくれるしね。」
私がクスクスと笑いながら言うと、
宮は私のほっぺをつねった。
「そんないいやつじゃねぇっつーの。」
「へへ…心優しい王子様!」
宮は照れたように私から顔を背けると、
強引に手を握って早歩きし始めた。