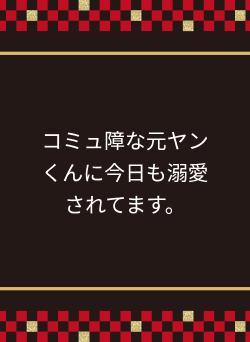**
「そうだ。思い出した。
私が…」
前、クラスの女の子にひどいこと言って、"後悔""私のせい"っていう気持ちに、とてつもない吐き気を感じたのも
遊園地で後ろを振り返ることに恐怖したのも
全部この事実から逃げるためだったんだ。
お母さんのようにそのまま死んでしまいそうだから眠るのが怖いっていうのは後付けの理由だ。
私に『寝るな。』と囁いていたのは防衛本能じゃない。頭の中の母親だ。
「円…」
宮は悲しそうな顔をしている。
いっぱいいっぱいの頭の中、それだけはわかった。
「私がお母さんのこと殺したんだった。
それだけじゃなくて、自分の罪も忘れてのうのうと生きてた。」
「円っ…!」
「もうやだ。つらいよ…。
自分のことが嫌いで仕方ない。
汚い、自分の心が!
私なんて…私なんて…」
「……。」
自分が眠るためにお母さんを死なせて、
自分が責められないために嘘をついて、
自分が傷つかないために都合よく忘れて、
私ってどうしてこんなに嫌なやつなんだろう。
汚い。自分の全身が汚く感じる。
私なんて。
私なんて…
この世にいない方が…
ポツンと
水が落ちる音が聞こえた。
思考を止めて、顔を上げると、
もういっかい
ポツンと
落ちた。
「宮…なんで」
「っ…
お前はキレイだ。見た目も心も。」
「へ…?」
「いつも思ってた。
汚いのは俺だ。いつもお前が輝いて見えた。
純粋で、人を悪く言わない。
ただ、まっすぐに困難に立ち向かってた。」
「……」
「お前が羨ましい。」
羨ましい?
宮が?私を?
友達がいっぱいいるのに、私なんかに協力してくれる優しい宮が?
私に同情して、こんなにきれいな涙を流してくれる優しい宮が?
「もっと思い出せ。
お前の母親はお前を恨むような人なのか?
不慮の事故を、お前のせいだって責める人なのか?」
もういっかい
宮の涙が床に降った。