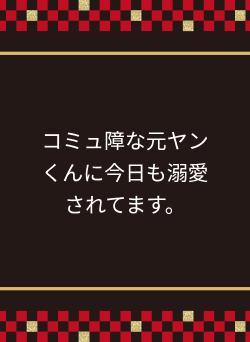「…そうか。」
お父さんは涙を拭い、呟いた。
怒られるかな…
不眠症を黙っていたこと。
毎日男子のそばで眠っていたこと。
まぁ怒られてもしょうがないけど。
そう思っていたけれど、
お父さんの口からでたのは意外な言葉だった。
「円、ごめんな。」
「へ…?」
「お前が苦しんでるのに、気づいてやれなくて。」
「いや、それは私が隠してたから…」
「ごめん。
ごめんな。」
なんでそんなに謝るのか。
お父さんが頭を下げるたびに目頭が熱くなり、
私はぎゅっと口を結んで目をそらした。
「宮くん…って君だよね?」
お父さんは隣で静かに聞いていた宮に話しかけた。
「はい。」
宮はふてぶてしく返事をする。
珍しく猫を被っていない。
「ありがとう。」
「……。」
「娘が今生きているのは君のお陰かもしれない。」
「そんなこと…」
宮は否定しようとしたが、
私の頭の傷を見て言葉をつまらせた。
たしかにそうだね。
私、宮が協力してくれなかったら、
とっくの昔にぶっ倒れてた。
「結ちゃんも、いつもありがとう。」
「いいえ。友達ですから!」
お父さんはようやく弱々しい笑顔を浮かべた。