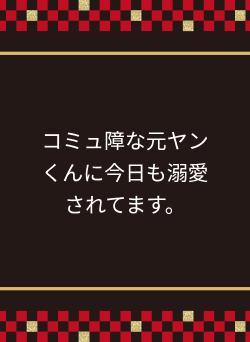おそるおそる宮を見上げると、血が出るんじゃ
ないかってくらいきつく下唇を噛んでいた。
「み、宮…」
「お前はバカかよ…。
意地張って無理して、
倒れるまで我慢するか?普通。」
「宮に…バレたくなかったの。」
「それでいろんな人に心配かけてんじゃねぇ!」
「…
ごめん…。」
私が心から謝ると、宮は
「バカ女。」
と呟いて、私を優しく抱きしめた。
久々の…
宮の匂いだ。
私の目からも涙がこみ上げてくる。
私、本当はずっと…
この匂いに包まれて眠りたかった。
「みっ…宮に嫌われて…辛くて…
これ以上嫌われたくなかった…。
私は宮のこと友達として好きだったから…!
本当はこの一週間、本当に苦しかったっ…」
「悪かった。俺がガキだから、
むきになってあんなこと言ったんだよ。」
「っ…うっ…わ、私のこと嫌いじゃない?」
「前言ったろ。お前のこと結構好きだって。」
「友達?」
「だから友達だって。」
「っ、ふえぇ…」
私が宮をぎゅっと抱きしめ返すと、
宮も私を抱きしめる力を強めた。
嬉しい。
良かった。
嫌われてたわけじゃなかったんだ…!
凍らせていた心が溶けてく。
溶けた氷たちが私の目から涙となって
ポツポツと降り注いだ。
「んー、こほんっ」
私たちが抱きしめあっていると、
結の気まずそうな咳払いが聞こえた。
「お二人さん、私の目の前でイチャイチャ
しないでくださいます?」
「イチャ…!?ち、違う…!」
私と宮は慌てて離れた。