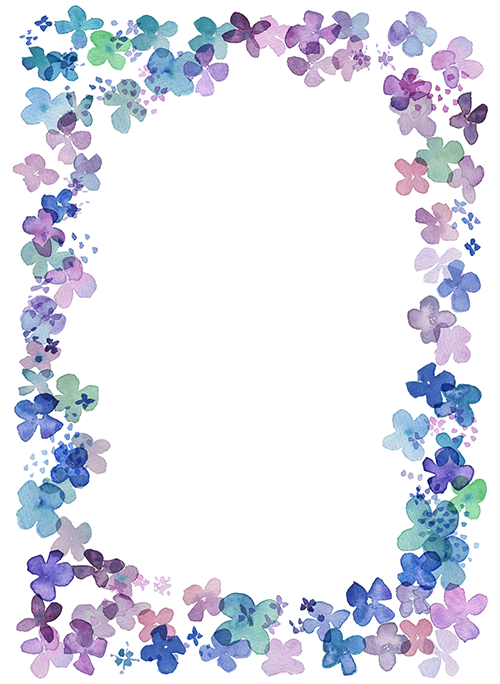禍根
晩夏の時期にその場所を訪れたのは、単なる知的好奇心の延長線上にある行動であった。
私は独自の風習や土着の信仰に関心を持っており、余暇を見つけては地方の記録や古い文献を調査することを習慣としていた。その過程で、深い山間に位置する過疎化が進んだ集落の存在を知った。文献に記されたその集落の記述は極めて断片的であったが、外部の人間が立ち入ることを強く拒む場所が存在し、そこには言葉そのものに事象を引き起こす力が内包されているという信仰が根付いているという。現代の都市部で生活する人間にとって、言葉とは単なる意思疎通のための手段に過ぎない。しかし、その集落においては、発言された言葉が言霊として影響を及ぼすと信じられているようだった。私はその迷信を自らの目で確認したいという欲求に駆られ、一人で旅行へ出かけることにした。数日間の滞在に必要な最低限の衣類と記録用の束ねた紙、そして筆記用具を鞄に詰め込み、私は住み慣れた街を離れた。
集落へ至る道のりは、およそ平坦とは言い難いものであった。出発地から複数の鉄道路線を乗り継ぎ、都市部の喧騒が完全に後退した場所に位置する小さな駅から、さらに路線バスを利用する必要があった。そのバスは数時間に一度しか運行されておらず、乗客は私一人であった。窓の外を流れる風景は次第に人工物から自然物へと占有率を変え、やがて視界の左右は険しい山肌によって塞がれた。
終点の停留所で下車した後も、目的地まではさらに長距離の歩行が要求された。舗装が行き届いていない山道が、等高線を無視するように上り勾配を描いて続いている。周囲は背の高い針葉樹に覆い尽くされており、密集した枝葉が天空を遮断しているため、日中であるにもかかわらず日光の多くは地面まで到達しない。道幅は自動車が一台通れる程度であったが、轍の跡は古く、長らく車両が通行した形跡は見受けられなかった。
私は一定の歩調を保ちながら、傾斜のある未舗装の道を進んだ。気温は決して高くなかったが、継続的な筋肉の運動によって皮膚の表面にじわじわと汗が滲み出してくる。関節には疲労が蓄積し、歩みを進めるごとに靴の底と砂利が擦れる単調な音が周囲の静寂に吸い込まれていった。道中、視界に入るのは樹木の幹と、路肩に群生する名も知らぬシダ植物ばかりであった。人工的な標識や案内板は一切存在せず、自分が正しい進路を辿っているのかという不安が頭をもたげたが、私は歩調を緩めることなく歩き続けた。
集落に近づいたと理解できたとき、時刻はすでに午後の遅い時間帯に差し掛かっていた。山の斜面に沿うようにして、古い木造の家屋が点在しているのが見えた。しかし、それらの建物には、まったく生活の気配はなかった。外壁の板は長年の風雨に晒されて黒ずみ、あるいは白く退色している。屋根の一部が崩落し、内部の構造材がむき出しになっている家屋も複数見受けられた。窓ガラスは埃で曇り、あるいは割れたまま放置されており、建物の周囲には雑草が人の背丈ほどにまで成長している。
私はあらかじめ連絡を入れておいた、その集落内で唯一営業していると思われる簡素な宿泊施設に向かった。施設の入り口は引き戸になっており、声をかけると奥から中高年の主人が姿を現した。主人は私の姿を視界に入れると、歓迎の意を示すこともなく、ただ事務的な手順に従って短い挨拶を交わした。割り当てられたのは二階の角にある小さな和室であった。私は鞄を畳の上に置き、周囲を見渡した。室内は清掃こそされているものの、長年染み付いた古い家屋特有の匂いが、そこに滞留していた。
宿の主人は、私に対して最低限の言葉しか発しなかった。食事の時間と入浴の設備について端的に告げた後、すぐに一階へと戻っていった。その態度の底には、外部の人間に対する明確な警戒感と、できれば関わり合いになりたくないという拒絶の意思が見えた。しかし、私は土着の風習を調査するという目的を持っていたため、その程度の排他性は想定の範囲内であった。主人の態度を深く追及することはせず、私は予定通り、日が落ちるまでの時間を利用して周辺の散策を開始することにした。
集落内の道は、バス停から続いていた山道よりもさらに狭く、未舗装の土がむき出しになっていた。私は特に明確な目的地を定めることなく、家屋がまばらになっていく村の外れに向かって歩を進めた。すれ違う村人の数は極めて少なかった。ところどころに開墾された小さな畑があり、そこで農作業をしている高齢の男女を数名見かけた。彼らは土に向かって黙々と作業を続けていたが、私の足音が近づくと一様に手を止め、顔を上げた。しかし、私の姿を視界に入れた瞬間、彼らは即座に視線を外し、何事もなかったかのように無言のまま作業を再開した。その一連の動作には、不自然なほどの斉一性があった。彼らは私という存在を無視しているのではなく、関わりを持つこと自体が何らかの規則に抵触するかのように、意図的に無視をしているようであった。
私は彼らの行動を静かに観察しつつ、集落の外れへと移動を続けた。家屋の数はさらに減少し、やがて完全に途絶えた。しばらく歩くと、周囲の樹木の密度が再び高くなり、人の手が加わっている形跡が急速に減少していった。道幅は人一人がようやく通れる程度にまで狭まり、地面には長年にわたって堆積した落ち葉が厚い層を形成していた。歩くたびに、水分を含んだ落ち葉が沈み込む感触が足の裏に伝わってくる。
その場所で、私は管理されず放置された古い木造の建築物を発見した。
樹木の隙間に隠れるようにして建つその建造物は、外観こそ一般的な神道の社殿に類似した構造を持っていた。しかし、そこには神聖な場所を示すための基本的な設備が存在しなかった。入り口を示す鳥居はなく、身を清めるための手水舎も見当たらない。ただ、一段高くなった石の基部の上に、木材が組み上げられた簡素な建物が鎮座しているだけであった。
私は建物の正面に立ち、その構造の細部を観察した。木材の表面は極度に乾燥し、無数のひび割れが走っている。塗装が施された形跡はなく、木肌は長い年月を経て周囲の樹木と同化するかのような暗い灰色に変色していた。周囲の地面は背の高い雑草や蔦に完全に覆われており、建物に向かって伸びる道らしきものも存在しない。日常的な清掃や手入れが行われている様子は皆無であり、人々の信仰の対象から外れ、打ち捨てられた施設であるように見受けられた。
私は建物の正面から側面へとゆっくりと移動した。壁面に設けられた窓にあたる部分は、分厚い木製の板で厳重に塞がれており、内部の様子を視覚的に窺い知ることは不可能であった。隙間から内部を覗き込もうと試みたが、板の継ぎ目には泥や植物の繊維が詰まっており、光が入り込む余地はなかった。周囲は静寂に包まれており、私が足元の落ち葉を踏むくぐもった音だけが耳に届く。
そのまま側面を通り過ぎ、建物の裏手へと回った。そこは山の斜面が建物のすぐ背後まで迫っており、樹木の枝葉が密集しているため、日中であっても光が全く当たらない暗がりとなっていた。
そこで、私は特異な外見を持つ存在と遭遇した。
その存在は、建物の裏側の壁面に背を向けるようにして、静かに立っていた。身長や体格から推測するに、一般的な成人女性と同程度であると認識できた。しかし、その姿は周囲の荒廃した風景の中で、あまりにも異常な存在だった。
その存在は、足元までを完全に覆い隠す白い着物を身にまとっていた。その周囲には土や苔、泥濘が存在しているにもかかわらず、着物の布地には一切の汚れが付着していなかった。それは、不自然なほどの純白さを保っていた。
さらに私の視覚情報を混乱させたのは、頭部、すなわち顔面に該当する部分の造形であった。顔面には、細長い長方形の紙片――無数のお札が貼り付けられていた。それも一枚や二枚ではない。夥しい数のお札が何層にも重なり合い、顔の全体を完全に覆い隠していた。目や鼻、口といった人間の顔を構成する基本的な器官を確認することは不可能であった。お札の表面には、墨で書かれたと思われる黒い文字が記されていたが、紙が複雑に重なり合い、一部がめくれているため、個々の文字を判読することはできなかった。
山から吹き下ろす微風を受けて、顔面に貼り付けられたお札の端の部分が小刻みに動いていた。紙と紙が擦れ合う微かな音が、静寂の中で際立って聞こえた。
私はその存在から数メートルの距離を保ったまま足を止めて、その状況をなんとか合理的に理解しようと試みた。しかし、私がこれまで生きてきた中で蓄積した常識や経験則のどこを探っても、目の前に存在する事象との間に整合性を見出すことはできなかった。それは人間が何かの宗教的な装束を身につけているだけなのか、あるいは全く別の何かであるのか、判断を下すためのすべての理解は不足していた。
私の中に生じたのは、明確な恐怖というよりも、根源的な疑念であった。状況の異常性を理解した私は、自らの安全を確保することが最優先事項であると判断した。不用意に接近したり、声をかけたりする行為は避けるべきである。私は視線を対象から外さないまま、足音を立てないようにゆっくりと背を向けた。そして、早足で来た道を戻り、宿泊予定の施設へと帰還する手順を無言のまま実行した。
施設に到着し、自室に戻った直後であった。私の身体に、突如として急激な不調が発生した。
最初は視界の端が気になる程度であったが、それは数秒の間に激しい眩暈へと進行した。そして、平衡感覚を維持することが著しく困難になり、私はたまらず畳の上に座り込んだ。視界が不規則に回転し、足元の床がすり鉢状に傾いているような錯覚に陥った。天井の木目が渦を巻き、壁が呼吸をするように伸縮して見える。
同時に、私の意識を別の感覚が支配し始めた。周囲のあらゆる方向から、複数の視線を向けられているような強い感覚である。
部屋の中にいるのは私一人である。ドアは閉まっており、窓の外には誰もいない。それにもかかわらず、壁の隙間から、天井の板目から、床の畳の目から、あるいは空間そのものから、無数の目が私の存在を注視しているという認識が、私の脳内を強圧的に占拠した。それは物理的な視線というよりも、私の存在を標的にして集束していく、圧倒的な敵意を持った圧力であった。
私は壁に手をついて姿勢を維持しようとした。しかし、顔面から血の気が急速に引いていき、指先がひどく冷たくなっていくのが自分でも理解できた。呼吸の頻度が増加し、酸素が十分に取り込めていない感覚があった。空気の粘度が上がり、喉に詰まるようだった。
このまま部屋に留まることに危機感を覚え、私は壁を伝いながら立ち上がり、廊下へと出た。階段の手すりに寄りかかって荒い呼吸をしていると、階下から上がってきた宿の主人が私の様子に気がついた。
主人は私の異常な顔色を見ると、階段を駆け上がり、言葉少なに事情を問い質した。顔は青ざめ、額には脂汗が浮かんでいる。私は呼吸を整えながら、村の外れにあった古い木造建築物まで歩いたこと、そして、その建物の裏手で遭遇した、顔にお札を貼り付けた白い着物の存在について言及した。
その内容を聞いた瞬間、主人の表情が明確にこわばった。それまで見せていた事務的な冷淡さは消え失せ、代わりに明白な焦燥と畏怖が顔に浮かんだ。主人は私の状態を気遣う言葉を発することもなく、それ以上私に質問をすることもなかった。ただ「動くな」とだけ短く言い捨てると、通信機器のある一階へと駆け下りていき、即座に村の神職を呼び寄せる手配を行った。
私は廊下に座り込んだまま、空間全体から向けられる視線の圧力と眩暈に耐え続けた。時間感覚が鈍麻していく中、数十分後、施設に中高年の男性が到着する足音が聞こえた。
階段を上がってきたその男性は、日常的な衣服ではなく、儀式に用いるような伝統的な装束を身にまとっていた。生地は古いが手入れが行き届いており、その威厳のある佇まいから、村の古い社を管理する神職であると推測された。
神職は私の姿を確認すると、表情を変えることなく私の前に立ち、威圧感を伴う低い声で短く言葉を発した。
「踏み込んではならぬ場所に、足を踏み入れたな」
それは確認や質問ではなく、確定した事実に対する宣告であった。神職の言葉は、私が村の禁忌に触れたこと、外部の人間が決して立ち入ってはならない領域に侵入したことを厳しく非難する内容であった。神職は私の体調や同意を確認することなく、私の腕を掴み、強制的に立ち上がらせた。そして、荷物をまとめる暇も与えず、私を宿の外部へと連れ出した。
私は眩暈と、依然として続く監視されている感覚に悩まされながら、神職の歩調に合わせて夜の道を移動した。集落の道には街灯がなく、神職の持つ手持ちの明かりだけが頼りであった。目的地は、村の中央付近の小高い丘に位置する、規模の大きな神社の本殿であった。
本殿の内部にはいくつかの部屋が存在し、神職は私をその中の一つである和室へと連行した。室内には家具や装飾品は一切配置されておらず、色褪せた畳が敷かれているだけの簡素な空間であった。壁には窓がなく、外部と繋がるのは出入り口のふすまのみである。
神職は私を部屋の中央に座らせると、見下ろすようにして言った。
「明日の朝を迎えるまで、いかなる理由があろうともこの部屋から出てはならない。何が聞こえようとも、何が起きようともだ」
それは忠告というよりも、絶対的な命令であった。神職はそれだけを言い残し、ふすまをピシャリと閉めて部屋を立ち去った。外側から何らかの固定具が掛けられる音が聞こえ、私が隔離されたことを示していた。
私は部屋の中央に座り、時間が経過するのを待った。室内には光源が一つも配置されておらず、日が完全に落ちると、真の暗闇が空間を支配した。自分の手先すら視認できないほどの暗黒である。外部からの音は一切聞こえず、厚い防音材に包まれたかのような無音の状態が継続した。
私は自分の規則的な呼吸音と、姿勢を変えるたびに衣類が擦れる微かな音だけを認識しながら、夜の時間を過ごした。施設で感じた急激な眩暈はいくぶん収まっていたが、全方向から監視されているという感覚は依然として続いており、私を休ませることを許さなかった。
どれだけの時間が経過したのか、時計がないため正確に把握することはできなかった。深夜と推測される時間帯になったとき、静寂に包まれた和室のふすまの向こう側に、何かが接近するのを認識した。
足音は聞こえなかった。ただ、気配だけが移動してきた。完全に光が遮断された暗闇の中であっても、ふすまの向こう側にある「それ」は、周囲の暗さとは異なる存在であることが感覚的に理解できた。光を遮る黒い塊のようなものが、ゆっくりと、しかし確実に私のいる部屋へと近づき、ふすまのすぐ外側で停止した。
室内の空気が急激に重くなり、呼吸が苦しくなった。全方向から向けられていた視線の圧力が、ふすまの向こう側の一点にあることを感じた。
その直後、音が発生した。
それはふすまの向こう側にいる存在の口から発せられた声とも、あるいは私の頭の中に直接伝達された音ともつかない形式であった。耳がその音を拾ったのか、頭の中へ直接的に話しかけてきたのか、判別がつかない。それは、抑揚のない一定のリズムで発音された。
「■■■■」
その言葉を認識した瞬間、私の身体に異常事態が発生した。
私自身の口が、無意識のうちにその言葉を発声していたのである。
「■■■■」
私の意志に反して、下顎の筋肉が独りでに動き、閉じられていた唇が開く。
舌が持ち上がり、口内の口蓋に接触して空気を押し出し、特定の音を形成する。自らの耳に、自分自身の声帯を震わせて発音された「■■■■」という言葉が届いた。
私はその行為を止めようとはしなかった。自らの意志とは無関係に自らの肉体が動いているという事実に対して、驚愕や恐怖といった感情を抱くよりも前に、ある直感が私の意識を支配したのだ。
その言葉を連続して口に出し続けることが、現在直面している状況を打開し、自らの身を守るための唯一の手段である、と。
そのように強く思い込んだ。あるいは、そのように思い込まされた。私は途切れることなく、口が動くままに、「■■■■」という言葉を発声し続けた。
発声を継続していると、ふすまの向こう側に存在していた黒い塊の気配が、わずかに薄れていくのがわかった。部屋を満たしていた空気の圧迫感が消え始め、監視されている感覚も和らいだ。私が発声する言葉が、まるで障壁となって怪異の侵入を防いでいるかのように感じられた。
私は休むことなく口を動かし続けた。暗闇の中で、自らの声だけが等間隔に聞こえてくる。どれほどの時間が経過したのかを正確に理解することはできなかった。ただ、一定の動作を反復する作業の中に意識が没入していき、完全に時間感覚が喪失していた。数時間が経過したようにも、数分しか経っていないようにも感じられた。
やがて、ふすまの向こう側の気配は完全に消失した。室内の空気の圧迫感が通常のレベルまで低下し、周囲を取り囲んでいた視線も消え去った。ふすまのわずかな隙間から、青白い光が差し込み始めているのが見えた。夜が明け、朝を迎えたのだと私は理解した。
緊張が切れ、私は畳の上に倒れ込んだ。疲労で感覚が麻痺していた。
午前中の早い時間帯に、外側から固定具が外される音がして、神職がふすまを開けて部屋に入ってきた。神職は床に倒れている私を見て、生きていることを確認すると、すぐに村から退去するように指示を出した。
「すぐに発て。二度と戻ってくるな」
私に昨晩の出来事について説明を求めることはなく、また神職側から事情を説明することもなかった。ただ速やかにこの集落から私という存在を排除しようとする意思だけが感じられた。宿に置いたままの私の荷物は、後日指定の住所へ配送される手筈となった。
神職自身が、本殿の裏に停められていた古いセダンを運転し、私を最寄りの交通機関の駅まで移送することになった。私は促されるままにセダンの助手席に座り、シートベルトを装着した。
車はエンジンを始動し、集落を抜けて未舗装の山道を下り始めた。窓の外には、昨日自らの足で歩いた針葉樹の風景が、後方へと足早に流れていった。私はその景色をぼんやりと眺めながら、ようやく深く息を吐き出した。これで異常な事態から解放され、元の日常へと帰還できるのだという安堵の認識が、少しずつ脳内に広がっていった。
しかし、車が山道を数分間走行した頃、私は重大な違和感に気がついた。
私の口が、その私の意志とは無関係に、運動を継続していたのである。
口は半開きになり、無意識のうちに、昨晩の暗闇の中で繰り返していたあの一節を、声帯を震わせない程度の小さな息の漏れとともに発声し続けていた。
「■■■■」
「■■■■」
「■■■■」
私は即座に発声を辞めようと試みた。顎の筋肉に強い力を入れ、上下の唇を強く密着させることで口を完全に閉ざそうとした。
しかし、口は私の意志を全く受け付けなかった。舌が独立した生き物のような動きを見せ、歯の裏側を規則的に叩き、肺から送られてくる空気を押し出して特定の音を形成しようとする。閉じたはずの唇が、内側からの舌と空気の圧力によって強制的に押し開かれ、再び言葉が漏れ出す。
「■■■■」
それは強迫的な反復運動であった。私の意志とは別に、口が独立した運動機関として動いている状態であった。私が意識的に発声を止めようと努力すればするほど、舌や顎の筋肉はそれに反発するように強い力で動き、決められた言葉を形成し続けた。
私は両手で自分の口元を強く覆い、物理的な力で口の動きを止めようとした。しかし、発声は止まらなかった。手の中で、唇が微細な動きを繰り返し、空気が指の間から漏れ出していく。皮膚の下で筋肉が痙攣するように蠢くのがわかった。
状況の異常性に激しく困惑した私は、視線を車内の前方へ向けた。運転席の神職は前を向いたまま無言であり、私の異変に気づいているのかいないのか、横顔からは読み取れなかった。私はフロントガラスの上部に設置されたルームミラーを確認した。後方を確認することで、現状を客観的に把握し、乱れた意識を正常な状態に引き戻そうとする無意識の行動であった。
ルームミラーに映し出された後部座席には、村の外れの古い建物で遭遇した存在が座っていた。
顔の全面に夥しい数のお札が貼り付けられた、純白の着物の女であった。
女は後部座席の中央に静かに座っており、無数の紙片で覆われた顔を真っ直ぐに、助手席に座るこちらに向けていた。車内の空気の動きに合わせて、お札の端がわずかに揺れている。お札の表面に書かれた墨の文字が、ミラー越しでもはっきりと視認できた。
私はその瞬間、この集落に起きた出来事の真相ともいうべき事象の意味を本能的に理解した。
昨晩、隔離された和室で、ふすまの向こう側の気配が発する音を自らの口でなぞり続けた行為。私はそれを、自らの身を守り、怪異を遠ざけるための防衛手段であると思い込んでいた。
しかし、それは決定的な間違いであった。
集落に根付く言霊信仰の通り、言葉そのものに事象を引き起こす力が存在している。私が夜通し唱え続けた「■■■■」という言葉は、自らを守る呪文などではなかった。それは、私自身の存在を、あの女が属する場所へと引きずり落とすための「宛名」であったのだ。
言葉を発声するたびに、私の存在を構成する要素が、人間としての存在が、あちらの世界へと少しずつ引き渡されていく。口が自律的に運動を継続しているのは、私という存在がまだ、この世にあるためであった。
日常へ戻るはずの車内で、助手席に座る私の意識は、絶え間ない言葉の発声とともにかすれていった。ミラーに映る女の姿が次第に鮮明になり、存在感を増していくのとは反対に、私自身の思考能力が急速に低下していくのがわかった。
もはや恐怖を感じる思考すらも奪われていく。口は休むことなく動き続け、私は支配された。視界が徐々に白く塗り潰されていく中で、私は静かに消えていった。
晩夏の時期にその場所を訪れたのは、単なる知的好奇心の延長線上にある行動であった。
私は独自の風習や土着の信仰に関心を持っており、余暇を見つけては地方の記録や古い文献を調査することを習慣としていた。その過程で、深い山間に位置する過疎化が進んだ集落の存在を知った。文献に記されたその集落の記述は極めて断片的であったが、外部の人間が立ち入ることを強く拒む場所が存在し、そこには言葉そのものに事象を引き起こす力が内包されているという信仰が根付いているという。現代の都市部で生活する人間にとって、言葉とは単なる意思疎通のための手段に過ぎない。しかし、その集落においては、発言された言葉が言霊として影響を及ぼすと信じられているようだった。私はその迷信を自らの目で確認したいという欲求に駆られ、一人で旅行へ出かけることにした。数日間の滞在に必要な最低限の衣類と記録用の束ねた紙、そして筆記用具を鞄に詰め込み、私は住み慣れた街を離れた。
集落へ至る道のりは、およそ平坦とは言い難いものであった。出発地から複数の鉄道路線を乗り継ぎ、都市部の喧騒が完全に後退した場所に位置する小さな駅から、さらに路線バスを利用する必要があった。そのバスは数時間に一度しか運行されておらず、乗客は私一人であった。窓の外を流れる風景は次第に人工物から自然物へと占有率を変え、やがて視界の左右は険しい山肌によって塞がれた。
終点の停留所で下車した後も、目的地まではさらに長距離の歩行が要求された。舗装が行き届いていない山道が、等高線を無視するように上り勾配を描いて続いている。周囲は背の高い針葉樹に覆い尽くされており、密集した枝葉が天空を遮断しているため、日中であるにもかかわらず日光の多くは地面まで到達しない。道幅は自動車が一台通れる程度であったが、轍の跡は古く、長らく車両が通行した形跡は見受けられなかった。
私は一定の歩調を保ちながら、傾斜のある未舗装の道を進んだ。気温は決して高くなかったが、継続的な筋肉の運動によって皮膚の表面にじわじわと汗が滲み出してくる。関節には疲労が蓄積し、歩みを進めるごとに靴の底と砂利が擦れる単調な音が周囲の静寂に吸い込まれていった。道中、視界に入るのは樹木の幹と、路肩に群生する名も知らぬシダ植物ばかりであった。人工的な標識や案内板は一切存在せず、自分が正しい進路を辿っているのかという不安が頭をもたげたが、私は歩調を緩めることなく歩き続けた。
集落に近づいたと理解できたとき、時刻はすでに午後の遅い時間帯に差し掛かっていた。山の斜面に沿うようにして、古い木造の家屋が点在しているのが見えた。しかし、それらの建物には、まったく生活の気配はなかった。外壁の板は長年の風雨に晒されて黒ずみ、あるいは白く退色している。屋根の一部が崩落し、内部の構造材がむき出しになっている家屋も複数見受けられた。窓ガラスは埃で曇り、あるいは割れたまま放置されており、建物の周囲には雑草が人の背丈ほどにまで成長している。
私はあらかじめ連絡を入れておいた、その集落内で唯一営業していると思われる簡素な宿泊施設に向かった。施設の入り口は引き戸になっており、声をかけると奥から中高年の主人が姿を現した。主人は私の姿を視界に入れると、歓迎の意を示すこともなく、ただ事務的な手順に従って短い挨拶を交わした。割り当てられたのは二階の角にある小さな和室であった。私は鞄を畳の上に置き、周囲を見渡した。室内は清掃こそされているものの、長年染み付いた古い家屋特有の匂いが、そこに滞留していた。
宿の主人は、私に対して最低限の言葉しか発しなかった。食事の時間と入浴の設備について端的に告げた後、すぐに一階へと戻っていった。その態度の底には、外部の人間に対する明確な警戒感と、できれば関わり合いになりたくないという拒絶の意思が見えた。しかし、私は土着の風習を調査するという目的を持っていたため、その程度の排他性は想定の範囲内であった。主人の態度を深く追及することはせず、私は予定通り、日が落ちるまでの時間を利用して周辺の散策を開始することにした。
集落内の道は、バス停から続いていた山道よりもさらに狭く、未舗装の土がむき出しになっていた。私は特に明確な目的地を定めることなく、家屋がまばらになっていく村の外れに向かって歩を進めた。すれ違う村人の数は極めて少なかった。ところどころに開墾された小さな畑があり、そこで農作業をしている高齢の男女を数名見かけた。彼らは土に向かって黙々と作業を続けていたが、私の足音が近づくと一様に手を止め、顔を上げた。しかし、私の姿を視界に入れた瞬間、彼らは即座に視線を外し、何事もなかったかのように無言のまま作業を再開した。その一連の動作には、不自然なほどの斉一性があった。彼らは私という存在を無視しているのではなく、関わりを持つこと自体が何らかの規則に抵触するかのように、意図的に無視をしているようであった。
私は彼らの行動を静かに観察しつつ、集落の外れへと移動を続けた。家屋の数はさらに減少し、やがて完全に途絶えた。しばらく歩くと、周囲の樹木の密度が再び高くなり、人の手が加わっている形跡が急速に減少していった。道幅は人一人がようやく通れる程度にまで狭まり、地面には長年にわたって堆積した落ち葉が厚い層を形成していた。歩くたびに、水分を含んだ落ち葉が沈み込む感触が足の裏に伝わってくる。
その場所で、私は管理されず放置された古い木造の建築物を発見した。
樹木の隙間に隠れるようにして建つその建造物は、外観こそ一般的な神道の社殿に類似した構造を持っていた。しかし、そこには神聖な場所を示すための基本的な設備が存在しなかった。入り口を示す鳥居はなく、身を清めるための手水舎も見当たらない。ただ、一段高くなった石の基部の上に、木材が組み上げられた簡素な建物が鎮座しているだけであった。
私は建物の正面に立ち、その構造の細部を観察した。木材の表面は極度に乾燥し、無数のひび割れが走っている。塗装が施された形跡はなく、木肌は長い年月を経て周囲の樹木と同化するかのような暗い灰色に変色していた。周囲の地面は背の高い雑草や蔦に完全に覆われており、建物に向かって伸びる道らしきものも存在しない。日常的な清掃や手入れが行われている様子は皆無であり、人々の信仰の対象から外れ、打ち捨てられた施設であるように見受けられた。
私は建物の正面から側面へとゆっくりと移動した。壁面に設けられた窓にあたる部分は、分厚い木製の板で厳重に塞がれており、内部の様子を視覚的に窺い知ることは不可能であった。隙間から内部を覗き込もうと試みたが、板の継ぎ目には泥や植物の繊維が詰まっており、光が入り込む余地はなかった。周囲は静寂に包まれており、私が足元の落ち葉を踏むくぐもった音だけが耳に届く。
そのまま側面を通り過ぎ、建物の裏手へと回った。そこは山の斜面が建物のすぐ背後まで迫っており、樹木の枝葉が密集しているため、日中であっても光が全く当たらない暗がりとなっていた。
そこで、私は特異な外見を持つ存在と遭遇した。
その存在は、建物の裏側の壁面に背を向けるようにして、静かに立っていた。身長や体格から推測するに、一般的な成人女性と同程度であると認識できた。しかし、その姿は周囲の荒廃した風景の中で、あまりにも異常な存在だった。
その存在は、足元までを完全に覆い隠す白い着物を身にまとっていた。その周囲には土や苔、泥濘が存在しているにもかかわらず、着物の布地には一切の汚れが付着していなかった。それは、不自然なほどの純白さを保っていた。
さらに私の視覚情報を混乱させたのは、頭部、すなわち顔面に該当する部分の造形であった。顔面には、細長い長方形の紙片――無数のお札が貼り付けられていた。それも一枚や二枚ではない。夥しい数のお札が何層にも重なり合い、顔の全体を完全に覆い隠していた。目や鼻、口といった人間の顔を構成する基本的な器官を確認することは不可能であった。お札の表面には、墨で書かれたと思われる黒い文字が記されていたが、紙が複雑に重なり合い、一部がめくれているため、個々の文字を判読することはできなかった。
山から吹き下ろす微風を受けて、顔面に貼り付けられたお札の端の部分が小刻みに動いていた。紙と紙が擦れ合う微かな音が、静寂の中で際立って聞こえた。
私はその存在から数メートルの距離を保ったまま足を止めて、その状況をなんとか合理的に理解しようと試みた。しかし、私がこれまで生きてきた中で蓄積した常識や経験則のどこを探っても、目の前に存在する事象との間に整合性を見出すことはできなかった。それは人間が何かの宗教的な装束を身につけているだけなのか、あるいは全く別の何かであるのか、判断を下すためのすべての理解は不足していた。
私の中に生じたのは、明確な恐怖というよりも、根源的な疑念であった。状況の異常性を理解した私は、自らの安全を確保することが最優先事項であると判断した。不用意に接近したり、声をかけたりする行為は避けるべきである。私は視線を対象から外さないまま、足音を立てないようにゆっくりと背を向けた。そして、早足で来た道を戻り、宿泊予定の施設へと帰還する手順を無言のまま実行した。
施設に到着し、自室に戻った直後であった。私の身体に、突如として急激な不調が発生した。
最初は視界の端が気になる程度であったが、それは数秒の間に激しい眩暈へと進行した。そして、平衡感覚を維持することが著しく困難になり、私はたまらず畳の上に座り込んだ。視界が不規則に回転し、足元の床がすり鉢状に傾いているような錯覚に陥った。天井の木目が渦を巻き、壁が呼吸をするように伸縮して見える。
同時に、私の意識を別の感覚が支配し始めた。周囲のあらゆる方向から、複数の視線を向けられているような強い感覚である。
部屋の中にいるのは私一人である。ドアは閉まっており、窓の外には誰もいない。それにもかかわらず、壁の隙間から、天井の板目から、床の畳の目から、あるいは空間そのものから、無数の目が私の存在を注視しているという認識が、私の脳内を強圧的に占拠した。それは物理的な視線というよりも、私の存在を標的にして集束していく、圧倒的な敵意を持った圧力であった。
私は壁に手をついて姿勢を維持しようとした。しかし、顔面から血の気が急速に引いていき、指先がひどく冷たくなっていくのが自分でも理解できた。呼吸の頻度が増加し、酸素が十分に取り込めていない感覚があった。空気の粘度が上がり、喉に詰まるようだった。
このまま部屋に留まることに危機感を覚え、私は壁を伝いながら立ち上がり、廊下へと出た。階段の手すりに寄りかかって荒い呼吸をしていると、階下から上がってきた宿の主人が私の様子に気がついた。
主人は私の異常な顔色を見ると、階段を駆け上がり、言葉少なに事情を問い質した。顔は青ざめ、額には脂汗が浮かんでいる。私は呼吸を整えながら、村の外れにあった古い木造建築物まで歩いたこと、そして、その建物の裏手で遭遇した、顔にお札を貼り付けた白い着物の存在について言及した。
その内容を聞いた瞬間、主人の表情が明確にこわばった。それまで見せていた事務的な冷淡さは消え失せ、代わりに明白な焦燥と畏怖が顔に浮かんだ。主人は私の状態を気遣う言葉を発することもなく、それ以上私に質問をすることもなかった。ただ「動くな」とだけ短く言い捨てると、通信機器のある一階へと駆け下りていき、即座に村の神職を呼び寄せる手配を行った。
私は廊下に座り込んだまま、空間全体から向けられる視線の圧力と眩暈に耐え続けた。時間感覚が鈍麻していく中、数十分後、施設に中高年の男性が到着する足音が聞こえた。
階段を上がってきたその男性は、日常的な衣服ではなく、儀式に用いるような伝統的な装束を身にまとっていた。生地は古いが手入れが行き届いており、その威厳のある佇まいから、村の古い社を管理する神職であると推測された。
神職は私の姿を確認すると、表情を変えることなく私の前に立ち、威圧感を伴う低い声で短く言葉を発した。
「踏み込んではならぬ場所に、足を踏み入れたな」
それは確認や質問ではなく、確定した事実に対する宣告であった。神職の言葉は、私が村の禁忌に触れたこと、外部の人間が決して立ち入ってはならない領域に侵入したことを厳しく非難する内容であった。神職は私の体調や同意を確認することなく、私の腕を掴み、強制的に立ち上がらせた。そして、荷物をまとめる暇も与えず、私を宿の外部へと連れ出した。
私は眩暈と、依然として続く監視されている感覚に悩まされながら、神職の歩調に合わせて夜の道を移動した。集落の道には街灯がなく、神職の持つ手持ちの明かりだけが頼りであった。目的地は、村の中央付近の小高い丘に位置する、規模の大きな神社の本殿であった。
本殿の内部にはいくつかの部屋が存在し、神職は私をその中の一つである和室へと連行した。室内には家具や装飾品は一切配置されておらず、色褪せた畳が敷かれているだけの簡素な空間であった。壁には窓がなく、外部と繋がるのは出入り口のふすまのみである。
神職は私を部屋の中央に座らせると、見下ろすようにして言った。
「明日の朝を迎えるまで、いかなる理由があろうともこの部屋から出てはならない。何が聞こえようとも、何が起きようともだ」
それは忠告というよりも、絶対的な命令であった。神職はそれだけを言い残し、ふすまをピシャリと閉めて部屋を立ち去った。外側から何らかの固定具が掛けられる音が聞こえ、私が隔離されたことを示していた。
私は部屋の中央に座り、時間が経過するのを待った。室内には光源が一つも配置されておらず、日が完全に落ちると、真の暗闇が空間を支配した。自分の手先すら視認できないほどの暗黒である。外部からの音は一切聞こえず、厚い防音材に包まれたかのような無音の状態が継続した。
私は自分の規則的な呼吸音と、姿勢を変えるたびに衣類が擦れる微かな音だけを認識しながら、夜の時間を過ごした。施設で感じた急激な眩暈はいくぶん収まっていたが、全方向から監視されているという感覚は依然として続いており、私を休ませることを許さなかった。
どれだけの時間が経過したのか、時計がないため正確に把握することはできなかった。深夜と推測される時間帯になったとき、静寂に包まれた和室のふすまの向こう側に、何かが接近するのを認識した。
足音は聞こえなかった。ただ、気配だけが移動してきた。完全に光が遮断された暗闇の中であっても、ふすまの向こう側にある「それ」は、周囲の暗さとは異なる存在であることが感覚的に理解できた。光を遮る黒い塊のようなものが、ゆっくりと、しかし確実に私のいる部屋へと近づき、ふすまのすぐ外側で停止した。
室内の空気が急激に重くなり、呼吸が苦しくなった。全方向から向けられていた視線の圧力が、ふすまの向こう側の一点にあることを感じた。
その直後、音が発生した。
それはふすまの向こう側にいる存在の口から発せられた声とも、あるいは私の頭の中に直接伝達された音ともつかない形式であった。耳がその音を拾ったのか、頭の中へ直接的に話しかけてきたのか、判別がつかない。それは、抑揚のない一定のリズムで発音された。
「■■■■」
その言葉を認識した瞬間、私の身体に異常事態が発生した。
私自身の口が、無意識のうちにその言葉を発声していたのである。
「■■■■」
私の意志に反して、下顎の筋肉が独りでに動き、閉じられていた唇が開く。
舌が持ち上がり、口内の口蓋に接触して空気を押し出し、特定の音を形成する。自らの耳に、自分自身の声帯を震わせて発音された「■■■■」という言葉が届いた。
私はその行為を止めようとはしなかった。自らの意志とは無関係に自らの肉体が動いているという事実に対して、驚愕や恐怖といった感情を抱くよりも前に、ある直感が私の意識を支配したのだ。
その言葉を連続して口に出し続けることが、現在直面している状況を打開し、自らの身を守るための唯一の手段である、と。
そのように強く思い込んだ。あるいは、そのように思い込まされた。私は途切れることなく、口が動くままに、「■■■■」という言葉を発声し続けた。
発声を継続していると、ふすまの向こう側に存在していた黒い塊の気配が、わずかに薄れていくのがわかった。部屋を満たしていた空気の圧迫感が消え始め、監視されている感覚も和らいだ。私が発声する言葉が、まるで障壁となって怪異の侵入を防いでいるかのように感じられた。
私は休むことなく口を動かし続けた。暗闇の中で、自らの声だけが等間隔に聞こえてくる。どれほどの時間が経過したのかを正確に理解することはできなかった。ただ、一定の動作を反復する作業の中に意識が没入していき、完全に時間感覚が喪失していた。数時間が経過したようにも、数分しか経っていないようにも感じられた。
やがて、ふすまの向こう側の気配は完全に消失した。室内の空気の圧迫感が通常のレベルまで低下し、周囲を取り囲んでいた視線も消え去った。ふすまのわずかな隙間から、青白い光が差し込み始めているのが見えた。夜が明け、朝を迎えたのだと私は理解した。
緊張が切れ、私は畳の上に倒れ込んだ。疲労で感覚が麻痺していた。
午前中の早い時間帯に、外側から固定具が外される音がして、神職がふすまを開けて部屋に入ってきた。神職は床に倒れている私を見て、生きていることを確認すると、すぐに村から退去するように指示を出した。
「すぐに発て。二度と戻ってくるな」
私に昨晩の出来事について説明を求めることはなく、また神職側から事情を説明することもなかった。ただ速やかにこの集落から私という存在を排除しようとする意思だけが感じられた。宿に置いたままの私の荷物は、後日指定の住所へ配送される手筈となった。
神職自身が、本殿の裏に停められていた古いセダンを運転し、私を最寄りの交通機関の駅まで移送することになった。私は促されるままにセダンの助手席に座り、シートベルトを装着した。
車はエンジンを始動し、集落を抜けて未舗装の山道を下り始めた。窓の外には、昨日自らの足で歩いた針葉樹の風景が、後方へと足早に流れていった。私はその景色をぼんやりと眺めながら、ようやく深く息を吐き出した。これで異常な事態から解放され、元の日常へと帰還できるのだという安堵の認識が、少しずつ脳内に広がっていった。
しかし、車が山道を数分間走行した頃、私は重大な違和感に気がついた。
私の口が、その私の意志とは無関係に、運動を継続していたのである。
口は半開きになり、無意識のうちに、昨晩の暗闇の中で繰り返していたあの一節を、声帯を震わせない程度の小さな息の漏れとともに発声し続けていた。
「■■■■」
「■■■■」
「■■■■」
私は即座に発声を辞めようと試みた。顎の筋肉に強い力を入れ、上下の唇を強く密着させることで口を完全に閉ざそうとした。
しかし、口は私の意志を全く受け付けなかった。舌が独立した生き物のような動きを見せ、歯の裏側を規則的に叩き、肺から送られてくる空気を押し出して特定の音を形成しようとする。閉じたはずの唇が、内側からの舌と空気の圧力によって強制的に押し開かれ、再び言葉が漏れ出す。
「■■■■」
それは強迫的な反復運動であった。私の意志とは別に、口が独立した運動機関として動いている状態であった。私が意識的に発声を止めようと努力すればするほど、舌や顎の筋肉はそれに反発するように強い力で動き、決められた言葉を形成し続けた。
私は両手で自分の口元を強く覆い、物理的な力で口の動きを止めようとした。しかし、発声は止まらなかった。手の中で、唇が微細な動きを繰り返し、空気が指の間から漏れ出していく。皮膚の下で筋肉が痙攣するように蠢くのがわかった。
状況の異常性に激しく困惑した私は、視線を車内の前方へ向けた。運転席の神職は前を向いたまま無言であり、私の異変に気づいているのかいないのか、横顔からは読み取れなかった。私はフロントガラスの上部に設置されたルームミラーを確認した。後方を確認することで、現状を客観的に把握し、乱れた意識を正常な状態に引き戻そうとする無意識の行動であった。
ルームミラーに映し出された後部座席には、村の外れの古い建物で遭遇した存在が座っていた。
顔の全面に夥しい数のお札が貼り付けられた、純白の着物の女であった。
女は後部座席の中央に静かに座っており、無数の紙片で覆われた顔を真っ直ぐに、助手席に座るこちらに向けていた。車内の空気の動きに合わせて、お札の端がわずかに揺れている。お札の表面に書かれた墨の文字が、ミラー越しでもはっきりと視認できた。
私はその瞬間、この集落に起きた出来事の真相ともいうべき事象の意味を本能的に理解した。
昨晩、隔離された和室で、ふすまの向こう側の気配が発する音を自らの口でなぞり続けた行為。私はそれを、自らの身を守り、怪異を遠ざけるための防衛手段であると思い込んでいた。
しかし、それは決定的な間違いであった。
集落に根付く言霊信仰の通り、言葉そのものに事象を引き起こす力が存在している。私が夜通し唱え続けた「■■■■」という言葉は、自らを守る呪文などではなかった。それは、私自身の存在を、あの女が属する場所へと引きずり落とすための「宛名」であったのだ。
言葉を発声するたびに、私の存在を構成する要素が、人間としての存在が、あちらの世界へと少しずつ引き渡されていく。口が自律的に運動を継続しているのは、私という存在がまだ、この世にあるためであった。
日常へ戻るはずの車内で、助手席に座る私の意識は、絶え間ない言葉の発声とともにかすれていった。ミラーに映る女の姿が次第に鮮明になり、存在感を増していくのとは反対に、私自身の思考能力が急速に低下していくのがわかった。
もはや恐怖を感じる思考すらも奪われていく。口は休むことなく動き続け、私は支配された。視界が徐々に白く塗り潰されていく中で、私は静かに消えていった。