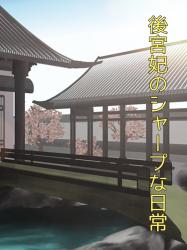喫茶レーベルへ来たのは、美愛の彼氏である田辺優希が、ここで働いていると聞いたからだ――田辺優希は、三日前から行方が分からなくなっていた。
「来週から始まるオリジナルブレンドのコーヒー、飲んでいかれませんか?」
そろそろ帰ろかと思っていたが、不意に先ほどの店員が現れて、小さな紙コップに入ったコーヒーをテーブルの上へ置いていた。
「ありがとうございます」
急いで帰ることもないと思った私は、出されたコーヒーに口をつけた。
「あれ? そんなに苦くない?」
「そちらはスッキリした味わいのコーヒーになるので、コーヒーが苦手な方にもおすすめなんです」
彼女になら、聞けるかもしれない――そう思った私は、思い切って田辺君のことを聞いてみた。
「田辺君は、小さい頃から知ってるけど、真面目でいい子だから、急に何日も休んで心配してたんです。ねえ、田中さん。何か知ってる?」
店の奥にいた小柄でおっとりとした男性は、こちらを見ると首を横に振っていた。
「いえ、何も……。三日前の夕方は、僕と入れ違いで――確か、夕方の五時から九時までバイトをしてたのは知ってるんですが、その後は来てないですね」
どうやら本当に行方知れずになっているらしい。お店の人によれば、三日前の閉店時は店長と田辺優希の二人だけだったという。店長の所在を訪ねると、分からないということだった。
「店長は、もともと隣の家に住んでいたんですけど、個人経営のお店ということもあって、ほとんどお店にいないんです」
「では、今どちらに?」
「たぶん、良質のコーヒー豆を求めて南アフリカ辺りに……」
その言葉を聞いて、私は唖然としてしまった。そうか、だからお店の中に世界各国のコーヒー豆が――いや、これだけあれば充分ではないか。
「田辺君、確かこの近くに住んでるはずです。お友達に住所を聞いてみて、行ってみてはいかがですか?」
「……そうですね。そうしてみます」
門田美愛からのメールに田辺優希の住所が書いてあったのを思い出し、スマホを取り出すとマップでナビを見ながら、彼の自宅へ向かった。
(探しても見つからないのであれば、自宅にはいないわよね。何か、手掛かりがあるといいけど……)
私達は田辺優希の自宅へ向かった。辺りは既に暗く、今にも雨が降り出しそうだった。スマホのマップ画面に自宅へは徒歩7分という文字が点滅している。雨が降る前に到着したいと足を早めたが、ふと脇道に目を向けると、住宅街の塀と塀との間に小さな祠があるのを見つけた。街中で見かける小さい祠よりも、更に一回り小さな祠だった。
「結愛、どうしたの?」
塀の奥には公園らしきものが広がっているのが見えたが、雑草が延びて荒れ果てていた。
「なんでもない」
田辺優希の自宅は、トタン屋根の木造一階建てだった。近くまで行って、玄関先の呼び鈴を鳴らしてみたが誰も出ない。
「玲奈、ちょっと待って。呼び鈴壊れてるかも」
耳を澄ましてみれば、呼び鈴を鳴らしても家の中で鳴っている音がしない。私と玲奈は目を合わせると、鍵の掛かっていない玄関の中へ入り、声を掛けた。
「田辺さん、いらっしゃいますか?」
しばらくすると、返事をする声が聞こえた。誰かいたことに安心して溜め息をつくと、部屋の中から白髪のおばあさんが出てきた。
「あら、優希のお友達? ごめんねえ、ブザーが壊れてて。今、お茶を入れますから、上がってちょうだい」
「いえ、すぐに帰りますからお構いなく。少し、お聞きしたいことがあるのですが……」
「でも、こんなところで立ち話もなんですから、中へどうぞ。私も、少し膝を痛めてますので、そうしていただけると助かります」
「……分かりました。それでは、お邪魔させていただきます」
初対面の私たちを心よく迎え入れてくれたおばあさんは、台所へ行くと湯を沸かし始めた。
「来週から始まるオリジナルブレンドのコーヒー、飲んでいかれませんか?」
そろそろ帰ろかと思っていたが、不意に先ほどの店員が現れて、小さな紙コップに入ったコーヒーをテーブルの上へ置いていた。
「ありがとうございます」
急いで帰ることもないと思った私は、出されたコーヒーに口をつけた。
「あれ? そんなに苦くない?」
「そちらはスッキリした味わいのコーヒーになるので、コーヒーが苦手な方にもおすすめなんです」
彼女になら、聞けるかもしれない――そう思った私は、思い切って田辺君のことを聞いてみた。
「田辺君は、小さい頃から知ってるけど、真面目でいい子だから、急に何日も休んで心配してたんです。ねえ、田中さん。何か知ってる?」
店の奥にいた小柄でおっとりとした男性は、こちらを見ると首を横に振っていた。
「いえ、何も……。三日前の夕方は、僕と入れ違いで――確か、夕方の五時から九時までバイトをしてたのは知ってるんですが、その後は来てないですね」
どうやら本当に行方知れずになっているらしい。お店の人によれば、三日前の閉店時は店長と田辺優希の二人だけだったという。店長の所在を訪ねると、分からないということだった。
「店長は、もともと隣の家に住んでいたんですけど、個人経営のお店ということもあって、ほとんどお店にいないんです」
「では、今どちらに?」
「たぶん、良質のコーヒー豆を求めて南アフリカ辺りに……」
その言葉を聞いて、私は唖然としてしまった。そうか、だからお店の中に世界各国のコーヒー豆が――いや、これだけあれば充分ではないか。
「田辺君、確かこの近くに住んでるはずです。お友達に住所を聞いてみて、行ってみてはいかがですか?」
「……そうですね。そうしてみます」
門田美愛からのメールに田辺優希の住所が書いてあったのを思い出し、スマホを取り出すとマップでナビを見ながら、彼の自宅へ向かった。
(探しても見つからないのであれば、自宅にはいないわよね。何か、手掛かりがあるといいけど……)
私達は田辺優希の自宅へ向かった。辺りは既に暗く、今にも雨が降り出しそうだった。スマホのマップ画面に自宅へは徒歩7分という文字が点滅している。雨が降る前に到着したいと足を早めたが、ふと脇道に目を向けると、住宅街の塀と塀との間に小さな祠があるのを見つけた。街中で見かける小さい祠よりも、更に一回り小さな祠だった。
「結愛、どうしたの?」
塀の奥には公園らしきものが広がっているのが見えたが、雑草が延びて荒れ果てていた。
「なんでもない」
田辺優希の自宅は、トタン屋根の木造一階建てだった。近くまで行って、玄関先の呼び鈴を鳴らしてみたが誰も出ない。
「玲奈、ちょっと待って。呼び鈴壊れてるかも」
耳を澄ましてみれば、呼び鈴を鳴らしても家の中で鳴っている音がしない。私と玲奈は目を合わせると、鍵の掛かっていない玄関の中へ入り、声を掛けた。
「田辺さん、いらっしゃいますか?」
しばらくすると、返事をする声が聞こえた。誰かいたことに安心して溜め息をつくと、部屋の中から白髪のおばあさんが出てきた。
「あら、優希のお友達? ごめんねえ、ブザーが壊れてて。今、お茶を入れますから、上がってちょうだい」
「いえ、すぐに帰りますからお構いなく。少し、お聞きしたいことがあるのですが……」
「でも、こんなところで立ち話もなんですから、中へどうぞ。私も、少し膝を痛めてますので、そうしていただけると助かります」
「……分かりました。それでは、お邪魔させていただきます」
初対面の私たちを心よく迎え入れてくれたおばあさんは、台所へ行くと湯を沸かし始めた。