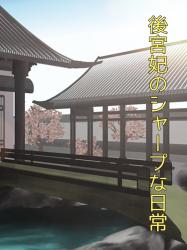「神隠しねぇ」
そう呟いたのは、同じサークルに所属する友達の田代玲奈だった。
授業を終えて喫茶レーベルに着いたのは、午後六時を少し過ぎていた。私たちの通う埼玉県春日部市にある玉越大学から、電車で約二時間。そこから歩いて十五分の場所に、その喫茶店はあった。
閑静な住宅街の中に、ひっそりと佇むレンガ造り。その建物は、西洋の建物を彷彿とさせた。お店を取り囲むようにしてある雑草や蔦が異様な雰囲気を醸し出している。
ここで、大学の文化祭で知り合った友達と会う予定だった。私が所属しているサークルはミステリーサークルという、ミステリー小説が好きな人達の集まりだったが、彼女が所属していたのはオカルト研究部だった。私の何が気に入ったのか、彼氏と連絡が取れなくて、一緒に探して欲しいと頼まれたのだ。
「絶対浮気だって。心のどこかでそう思ってるから、結愛にお願いしたんでしょ?」
玲奈がそう言いながら喫茶店のドアを開けると、店の奥から店員と思われる女性がこちらへ歩いて来た。
「いらっしゃいませ。二名様でいらっしゃいますか?」
メイドの恰好をした店員に席まで案内されると、開いたメニューを手渡された。
「あとから一人来ます」
「かしこまりました。先に注文されますか?」
「はい」
アイスコーヒーを頼むと、私は店内を見回した。コーヒー専門店らしく、世界各国のコーヒー豆が所狭しと並んでいた。メニュー表には酸味があってコクがあるとか、後味すっきりなどど書かれていたが、ミルクが無いと飲めない私には、あまり参考にならない言葉だった。
「レトロじゃない純喫茶って感じね」
店員の制服は準メイド風、準執事風だったが、それはあまり気にならない。客もコーヒーを求めてやって来ているという感じの客ばかりであった。しばらくすると、アイスコーヒーが運ばれてきた。
「アイスコーヒーは、まずブラックでストローを使わずに、一口飲んでみなさい。美味しいから」
近くの席にいたおじいさんに話しかけられて、言われたとおりにすると、いつもと違って美味しい気がした。ブラックでも飲める苦さだ。玲奈も満足げに目を細めている。
「ありがとう、おじいさん。美味しいです」
玲奈がそう言うと、おじいさんは満足そうに頷いて席へ戻っていった。おじいさんは、カウンターで新聞を広げて読んでいる。常連客だろうか──そう思っていると、スマホが鳴った。
「玲奈、美愛からメール。講義が長引いて来れなくなったみたい。これ飲んだら出ようか?」
「自分から誘っておいて何なのよ……」
「まあ、そんなもんよね」
そう言って、ブラックで飲んでいたコーヒーにミルクを入れると一気にストローで飲み干した。私にはミルクコーヒーが、まだまだ似合っている気がする。
そう呟いたのは、同じサークルに所属する友達の田代玲奈だった。
授業を終えて喫茶レーベルに着いたのは、午後六時を少し過ぎていた。私たちの通う埼玉県春日部市にある玉越大学から、電車で約二時間。そこから歩いて十五分の場所に、その喫茶店はあった。
閑静な住宅街の中に、ひっそりと佇むレンガ造り。その建物は、西洋の建物を彷彿とさせた。お店を取り囲むようにしてある雑草や蔦が異様な雰囲気を醸し出している。
ここで、大学の文化祭で知り合った友達と会う予定だった。私が所属しているサークルはミステリーサークルという、ミステリー小説が好きな人達の集まりだったが、彼女が所属していたのはオカルト研究部だった。私の何が気に入ったのか、彼氏と連絡が取れなくて、一緒に探して欲しいと頼まれたのだ。
「絶対浮気だって。心のどこかでそう思ってるから、結愛にお願いしたんでしょ?」
玲奈がそう言いながら喫茶店のドアを開けると、店の奥から店員と思われる女性がこちらへ歩いて来た。
「いらっしゃいませ。二名様でいらっしゃいますか?」
メイドの恰好をした店員に席まで案内されると、開いたメニューを手渡された。
「あとから一人来ます」
「かしこまりました。先に注文されますか?」
「はい」
アイスコーヒーを頼むと、私は店内を見回した。コーヒー専門店らしく、世界各国のコーヒー豆が所狭しと並んでいた。メニュー表には酸味があってコクがあるとか、後味すっきりなどど書かれていたが、ミルクが無いと飲めない私には、あまり参考にならない言葉だった。
「レトロじゃない純喫茶って感じね」
店員の制服は準メイド風、準執事風だったが、それはあまり気にならない。客もコーヒーを求めてやって来ているという感じの客ばかりであった。しばらくすると、アイスコーヒーが運ばれてきた。
「アイスコーヒーは、まずブラックでストローを使わずに、一口飲んでみなさい。美味しいから」
近くの席にいたおじいさんに話しかけられて、言われたとおりにすると、いつもと違って美味しい気がした。ブラックでも飲める苦さだ。玲奈も満足げに目を細めている。
「ありがとう、おじいさん。美味しいです」
玲奈がそう言うと、おじいさんは満足そうに頷いて席へ戻っていった。おじいさんは、カウンターで新聞を広げて読んでいる。常連客だろうか──そう思っていると、スマホが鳴った。
「玲奈、美愛からメール。講義が長引いて来れなくなったみたい。これ飲んだら出ようか?」
「自分から誘っておいて何なのよ……」
「まあ、そんなもんよね」
そう言って、ブラックで飲んでいたコーヒーにミルクを入れると一気にストローで飲み干した。私にはミルクコーヒーが、まだまだ似合っている気がする。