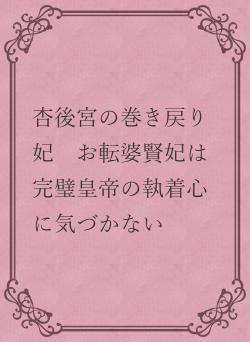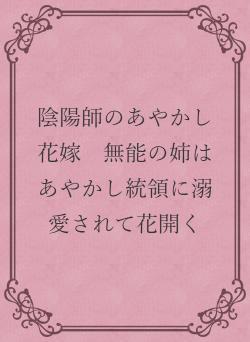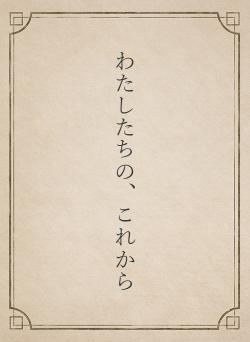『おまえとバンドやってても楽しくないわ』
『これ以上、おまえと続けるのは無理だ』
『てか、俺たちといてもおまえも楽しくないだろ』
とある冬の日。
バンド練習のために予約していたスタジオに向かうと、すでにメンバーがそろっていた。いつもおれが一番乗りだったからついにみんなもやる気を出したのかと喜んだのもつかの間、口にされたのは脱退宣言だった。
頭にこびりついて離れない、かつてのバンドメンバーたちの冷たい声。
できないことを指摘しただけなのに、練習に遅刻したことを少し咎めただけなのに、もっと真面目にやろうと言っただけなのに、将来の夢を語っただけなのに。
……みんなと、もっと音を奏でていたかったのに。
おれの願いは、メンバーたちの言葉によりあっけなく崩れてしまった。
冬の冷たい海の底に沈んでいくように、体中が痛い。呼吸が苦しい。
あの日から、おれはギターを握っていない。
いや、握れていないんだ。
◇
「紫月、聞いてる?」
考えごとに耽っていたおれは、友人の声で我に返った。
はっとして顔をあげると、春の生ぬるい風がワイシャツを揺らす。
花の匂い、土の香り、生命の息吹。真夏の草いきれほどではないが、ときおり思い出したかのように吹く風にはいろんな香りが混ざっている。春はなんでこんなに騒がしいのだろうか。
周囲に目を向けると、通学路を彩るように並ぶ桜の木はもうすっかり緑が生い茂っていた。
そうだ、いまは桜が咲く時期だ。あの冬の日ではない。
伊達眼鏡越しに陸を見ると、あきれたように笑っている。
「あ、ああ……ごめん。で、なんだっけ」
「うちのクラスに転校生が来るって噂あったじゃん。あれ、今日かもしれないんだって」
陸の瞳は期待を隠しきれていなかった。いつなんどきもニコニコしているのんびり屋の陸だが、ここまで楽しそうにしているのはめずらしい。
たしかに近ごろ、おれたちのクラスに転校生がやってくるのではないかと生徒たちの間で噂されていた。
ただの転校生ならいい。
噂によると、そいつはどうやら韓国でアイドルをめざしていたらしい。
日本で生まれたもののアイドルをめざして韓国に渡り、向こうで長く生活をしていたとか。信じられないほど小顔で、目鼻立ちははっきりしていて、肌は透き通るほど白く、プロポーションもすばらしいのだとか。
学校中のあちこちに存在するK-POP好きの生徒たちが鼻息荒くして転校生のことを噂している。
韓国の音楽やアイドル文化に疎いおれからすると、だからなんだとしか思えない。そもそも、噂のもとがどこなのかも不明だし、同じ教室で授業を受けるだけのやつにそこまで興味を持とうとも思えない。
だが、もし転校生の噂が本当だとすると、バンドが、音楽ができなくなったおれからしたらあまりうれしいことではなかった。
バンドのことを思い出すと、いまでも胃がずっしりと重くなる。
信頼していたメンバーに裏切られたおれは、あの日以来、幼なじみの陸以外の人の目を見て話すのが怖くなってしまった。だから極力人と目があわないように前髪を伸ばし、伊達眼鏡をかけて生活している。
陸はあまり乗り気ではないおれを一瞥して、口をとがらせる。
「興味ない?」
「……興味あるもなにも、先生がなんにも言ってなかったなと思って」
「でもみんな噂してる」
「まあな」
「本当に興味なさそうだね」
紫月らしいけど、と陸は付け足した。
学校まではあと少し。ここから別の話題を探すのもコミュ障で口下手なおれには難易度が高いし、かといって無言も気まずい。悩んだ末に、転校生の話題を続けることにした。
「K-POPのことをよく知らないから盛りあがるに盛りあがれないというか」
「あーたしかに。正直、ぼくもよくわかんないんだけど、佐藤さんとかがすっごいはしゃいでるから楽しみになっちゃってる節はあるかも」
クラスメイトの佐藤七菜を思い出す。
肩くらいまでの髪を明るい茶色に染めていて、目が大きくて、声もデカければ背もデカい、生命力にあふれているバレーボール部のあいつだ。
たしかに佐藤は、韓国アイドルの熱狂的なファンだった。
隣の席だからなにかと会話する機会があるが、事あるごとに「○○の新曲、超よかったからCD貸してあげる!」やら「××事務所から新しいアイドルがデビューするんだけどさ~」などと聞いてもいないのにいろいろとK-POPにまつわる情報を教えてくれる。おかげでアイドルたちの顔こそ曖昧なものの、流行りの曲はおさえていた。
「佐藤が言うなら本当なのかもな」
「どうだろうね。まあどちらにしても、新しいクラスメイトが増えるのは楽しみ」
「まあな」
寝起きでぼやけている思考のまま、とりとめのない会話をしているうちに、いつの間にか学校に到着していた。
コンクリート造りのやたら大きい校舎は、春の騒がしい気配にも動じずにどっしりと学生を迎え入れる。荘厳すぎる見た目に入学当初は萎縮したものの、時間が経てば見慣れた建物でしかない。
「二年生になってしばらくはイベントってないじゃん。だから、本当に転校生が来るなら楽しみだよ。仲よくなれるかなぁ」
「ああ」
下駄箱で靴を脱ぎながら、陸の話に適当に返事をする。
落とすように乱暴に置いた上履きが地面とぶつかる音が、やけに耳に残った。
◇
「小高朝日です。よろしくお願いします」
朝のホームルームがはじまって早々、担任と一緒に入ってきた新クラスメイトにクラス中が息をのんだ。
「超イケメンじゃん」
「え、あの噂、マジなの?」
「うそでしょ!」
「背、高すぎ……」
みなが噂していた転校生が本当にやってきたのだ。
ただの転校生ならいい。
ゆうに百八十センチは越えているのではと思うほどの長身、姿勢よくしゃんと立つ姿、人のよさそうな笑顔。大きな目は目じりが少し垂れていて人懐っこさを感じさせる。
どこからどう見てもただの高校生ではないような完璧な容姿をしていた。
アイドルに疎い俺ですら、小高が放つ輝きに度肝を抜かれていた。
少女漫画とかでヒーローが出てくるときみたいに、きらきらとか花とかが舞っているように見える。とても同じ高校二年生とは思えない。
信じられない思いで壇上の小高を眺めていると、ふと隣の席の佐藤が静かなことに気づく。連日あんなに騒いでいたのにおかしい。
体調でも悪いのかと思ってさりげなく隣に目を向けると、そこにはまたしても信じられない光景が広がっていた。
佐藤が静かに涙を流していたのだ。
「ど、どうしたんだよ、佐藤……」
思わず小声で声をかけるも、佐藤は返事をしないどころかおれの声に気づいている様子すらない。
朝一から隣の隣の隣のクラスまで響くほどの大声でおしゃべりに興じる普段の佐藤からはかけ離れた姿に動揺し、控えめに肩に手をかけて再び呼びかけると、ようやくこちらを向いた。
「おい、具合悪いなら保健室に――」
「……やばい」
「え?」
表情の抜けた顔は亡霊のようで正直怖い。そんな佐藤の口から出たのは、蚊の鳴くような声だった。
「やばいよ……! 日野、やばいんだって!」
「ちょっ……佐藤、落ちつけ。痛いから」
佐藤は急発進した自動車のような勢いで、おれに迫ると背中をばしばしと叩いてきた。
転校生のおかげで教室は騒がしく、いつもの朝のホームルームのしんとした気配とはかけ離れていたが、それでも佐藤とおれは注目を浴びた。
クラスメイトたちの視線が痛い。ほとんどが「また佐藤が騒いでるよ」「日野くんが巻き込まれてる……」なんてあきれと同情の色がにじんだ目だったが、人の目が怖いおれには刺激が強い。
耐えきれなくなって俯きそうになっていると、佐藤が大声をあげた。
「なんでそんなに冷静なの⁉ 韓国の大手芸能事務所からデビュー予定だった、あのアサヒくんだよ!」
「はあ……」
「歌もダンスも完璧で、楽器が得意で、作詞作曲もできて、人懐っこい笑顔がトレードマークで、大型犬みたいなかわいい男の子だってみんなに言われてた、あの朝日くんだよ!? 信じられない……!」
「い、いや、おれはなんにも知らないし……」
というかなんでまだデビューしていない仮にも一般人の情報を、こいつはそんなに詳しく知っているんだ。そんなことを疑問に思いつつもまずは佐藤を落ちつかせなければと必死になっていると、おれたちの騒ぎに気づいた小高と目があう。
佐藤の話が本当かはわからないが、もし小高が高校生活を送るために日本に戻ってきたのだとしたら、転校早々、自分の過去の経歴を大声でしゃべられたら迷惑極まりないだろう。しかし、小高はいやな顔一つせずににこりと微笑んだ。
するとその瞬間、佐藤はこれまでの騒ぎようが嘘のように直立不動になり、すとんと席に座る。そんな挙動不審のクラスメイトの頬にまた涙が流れた。
「本当に……ぶじでよかった……」
「は?」
祈るようなポーズでそうつぶやいたきり、佐藤はおとなしくなった。
いったいなんだったんだ。
感情の乱高下についていけずドン引きしていたおれだが、先生がパンパンと手を叩いた音でわれに返る。
「小高はみんなと同じで、この学校に勉強しに来ているんだぞー。学友として仲よくするように」
先生はそう釘を刺すと、小高に一言なにか言うようにうながした。小高は「はい」とうなずくと、すうっと息を吸う。
壇上に立つ小高とそれを見つめるクラスメイトたち。みなの瞳には、羨望や憧れだけではなく、無遠慮に詮索しようとしているあからさまな気配もにじんでいた。
開け放たれた窓から、春のぬるい風とともにひと足先にホームルームが終わった学生が外で騒いでいる気配が届く。なんでもない朝の学校の風景なのに、小高というフィルターを通すと学園ドラマの一コマみたいに見えてくる。
窓の外に向けていた視線を壇上に戻すと、ちょうど小高が口を開こうとしたところだった。上品な唇がすぅっと息を吸うだけで、みんながはっとする気配が伝わってきて、おれはあきれと驚きで笑ってしまいそうになる。まるでステージに立つアイドルと観客席のファンみたいだ。
「軽音楽部があると聞いたので、入部したいと思っています。みんなと過ごす学生生活が楽しみです。これからよろしくお願いします」
穏やかにそう言った小高と目があったような気がしたのは、きっと気のせいだ。胃のあたりがずんと重くなり、おれは机の中の教科書を探すふりをして俯いた。
たしかにこの学校に軽音楽部は存在している。
だが、部員数は定員ぎりぎりの三名。ドラム、ベース、ギターボーカルと、いい感じに得意分野がわかれたのはよかったが、そのうちの一人がほぼ幽霊部員なせいで実際はほとんど活動できていない。各部活に与えられる部室はほぼ荷物置き場と化し、楽器はほこりを被っている。
この春に新しい部員が入らなければ、廃部も検討すると先生に言われていた。
なんでこんなに軽音楽部の事情に詳しいのかと言うと、おれがその軽音楽部の部員――しかも廃部危機の元凶である幽霊部員の張本人だからだ。
音楽ができなくなったことで部室に行くのもいやになり、しばらく顔を出せていない。 バンドが解散してから、部活からも足が遠のき、家と学校と塾を行き来するだけの退屈な日々を過ごしていた。
でもそれでいいんだ。どうせすぐに大学受験がやってくるし、きっと社会に出るまでもあっという間なのだから。
幽霊部員のおれには部員が増えようと関係のないことかもしれないが、さっき目があった小高の表情が頭から離れず、なんだかいやな予感がしていた。
◇
転校生・小高朝日の人気はすさまじかった。
偶然空いていたおれのうしろの席に座った小高は、休み時間のたびに学校中の生徒に囲まれて質問攻めにあっていたのだ。
「韓国で練習生してたって本当?」
「どうしてやめちゃったの?」
「もうアイドルやらないの?」
そんな感じで、噂されている経歴にまつわる質問が四方八方から飛んでくる。あまりにも明け透けで無遠慮な言葉たちにおれは辟易していたが、いやでも聞こえてしまう距離だから、次の授業の準備をしつつ耳に届く小高の返事をなんとはなしに聞いていた。
「練習生だったのは本当だよ。でも家庭の事情で日本に帰国することになったんだ。こっちでは普通の高校生活を送りたいと思ってるから、みんな仲よくしてくれるとうれしいな」
小高がそう言うと、みなの気配があからさまに浮き立ったのを肌で感じた。きっと小高が微笑んだかなんかだろう。おれは同級生の現金な態度にあきれる気持ちを隠しきれなかった。
ちなみに佐藤はその輪には加わらず、いつもの騒がしさも嘘のように存在感を消してスマホをいじっていた。
「おい佐藤、やっぱりどっか悪いんじゃ……」
「え?」
「だっておまえ、あいつのファンだったんだろ? だったら、あの人だかりに交じりたいんじゃないかと思って」
小高を取り巻く人々は興奮して矢継ぎ早に質問を繰り出しているので、おれたちの会話なんて聞こえているわけがない。しかし、念には念を入れて顔を寄せ、小声でそう聞くと、佐藤は心外だと言わんばかりに眉をひそめた。
「あたしはそういうんじゃないの! ただ、アサヒくんがぶじだったのがうれしくて……」
またしても意味不明な発言をして、再びスマホに顔を戻すのだった。
さっきも「ぶじでよかった」と言っていたが、そんなに小高が人々の前から姿を消したのは急なことだったのだろうか。
そんな考えごとをしはじめて、おれははっとわれに返る。
これではおれもあの野次馬たちと同じだ。
小高は己にまつわる下世話な噂話や、人々の下心のある言動をまるで気にしていないようにふるまっている。さすがの元アイドルのたまごだと思うものの、だからといってそういう無遠慮な行動を是とするのもおかしい。
そもそもおれはあいつに関わる気がないのだから、わざわざ詳しくなる必要はない。
それ以降の休み時間は、イヤフォンをつけて適当にゲーム実況を流し見たり、陸と購買に行ったりして時間をつぶした。
◇
放課後になり、部活や塾に向かうクラスメイトを横目に帰宅準備をしていると、おれの机に影が落ちた。なんだろうと思って顔をあげると、話題の転校生こと小高朝日がおれの正面に立っている。
「日野紫月くん、だよね?」
「げっ……」
顔をあげたときに目があってしまった。華やかなところが似合う小高はおれにはまぶしすぎる。スクールバッグに教科書を詰めるふりをして、さりげなく顔を伏せる。
関わりたくないと思っていたのが顔と言葉に出てしまった気がする。伏し目がちにうかがうと、いやな顔ひとつせずに「げってなに?」と笑っているからよかったが。というか、なんでもうおれの名前を知っているんだ。
なんの用だと警戒していると、小高がまるで古くからの友のような気安い口調で話しはじめた。
「紫月が軽音楽部だって聞いたんだけど、本当? だとしたら、案内してほしくて――」
――紫月。
初対面にもかかわらず下の名前を呼ぶ勇気はおれにはない。
考え方の違いなのか性格の違いなのかわからないが、おれとこいつとの間にある差を実感して絶句していると、「聞いてる?」と顔を覗きこまれる。
動揺しているのがばれないようにぱっと顔を背け、教室の前方でクラスメイトと談笑している陸を呼んだ。
「小高が軽音楽部に興味があるんだって。案内してやってくれないか」
「え、そうなの? いいよー」
陸はリュックを背負いなおすと、おれたちに近づいてくる。
「陸も軽音楽部なんだ。楽器はなにやってるの?」
「ぼくはドラムだよ。というか小高くん、みんなの名前覚えるの早いね。びっくりしちゃった」
「記憶力はいいほうなんだ。朝日でいいよ」
「あ、本当? じゃあ朝日くんで」
二人は初対面にもかかわらずぎこちなさを微塵も感じさせないやりとりをしていた。
元アイドルの転校生が来ることを楽しみにしていた陸だったが、小高の噂をまったく気にするそぶりも見せず、ただの同級生として接している。コミュニケーション能力の高さと気遣いに感心していると、陸がおれに話を振った。
「ねえ、たまには紫月も顔出そうよ。今日は塾ないんでしょ?」
「あー、おれはいいよ」
「なんで? 紫月って部員じゃないの?」
至極真っ当な疑問を口にした小高に、陸がうんざりした表情で答える。
「紫月はね、幽霊部員なんだよ。ギターとボーカルが得意で、作詞作曲もできるのにもったいない。おかげで軽音楽部は廃部寸前なんだ」
「新入部員が入れば大丈夫なんだろ」
「まあそうだけど。三人しかいなくてろくに活動してない部活に入りたいと思う? 紫月の事情もわかってるつもりだけど、たまには顔出してくれてもいいんじゃない。クロもつまんなそうだよ」
「それは……わるいと思ってる」
クロというのは、唯一の二年生である古林黒のことだ。
真っ黒な髪と瞳が印象的なかっこいい後輩なのだが、目つきが悪ければ態度もあまりよいとは言えないやつだった。群れない媚びない、さらには気まぐれなところがあって、前世は黒猫だったのではないかと思ってる。
小学生のころからベースを習っていて、コアでディープな洋楽が好きな変わり者。小高が光のイケメンであれば、クロは闇のイケメンと呼んでもいいかもしれない。
おれがしどろもどろ弁解しても、陸の文句は止まらない。
でも、陸が怒ってくれるのは正直ありがたかった。
バンドが解散したときのおれは、はたから見てもわかりやすいくらい落ち込んでいたし、見た目も変わって以前よりあきらかに暗くなった。腫れもののように扱われるよりは、面と向かって文句を言われたほうが気持ちが楽なのは事実。陸の優しさにつけこんでいるようで、自分に嫌気がさすのもまた事実だが。
とはいえ部活に行く気はない。
行ったところでギターを握れないのだから意味がない。あの冬の日以来、ギターを触ろうと思うと手が震えてしまうのだ。
もうおれに音楽は必要ないのかもしれない。
あんなにも大好きだった――人生のすべてだと思っていたのに。
そんなことを考えながら陸の小言をやり過ごしていると、小高が急に前のめりになった。
「事情はよくわからないけど、幽霊が昼間に現れちゃいけない理由なんてないんじゃない?」
「は?」
「行こう!」
「ちょっ……! おい!」
小高に腕をつかまれ、引っ張られるがままに廊下を走る。
振り払おうとしても力が強くてびくともしない。しかも運動神経までいいのかかなり足が速くて、登下校が唯一の運動であるおれはついていくので精一杯だ。「止まってくれ」と言っても、聞こえていないのか無視されているのかわからないが、一向に止まる気配がない。
すでに人がまばらになりつつあったが、男子生徒二人が走っているのはそれなりに目立つ。無数の目が、おれを見ている。その目を意識するだけで体がぎゅっと強張り、肩が縮こまってしまう。
小高を振り払うのを諦めたおれは、ぎゅっと目をつぶって人の目を見ないふりした。
◇
ベースの弦を弾く音がだんだんと近くなってくる。
音は振動だ。音の発生元――軽音楽部の部室の前に立つと、上履き越しに足の裏から振動が伝って、おれの体を震わせた。
乗り気ではなかったのに、小高に引っ張られて部室まで来てしまった。あとから追いついた陸が隣で息を整えている。
「朝日くん、部室の場所知ってたんだね」
「今朝、先生に教えてもらった」
「そうなんだ。じゃあ、中に入ろうか」
おれの胸中などおかまいなしに、二人はのんきに会話している。
この震えは音楽が怖いからではない。音が振動しているだけ。そう言い聞かせているうちに、部室の扉が開く。
「お、センパイ、ついに来たんすか――ってだれですか、こいつ」
「ぼくたちのクラスに転校してきた小高朝日くんだよ。クロからしたら先輩なんだから、こいつとか言わないの」
「……うーっす」
クロは興味なさそうに小高を一瞥すると、すぐにベースを弾く手を再開させた。緊張して手に汗がにじんでいたが、後輩のいつもどおりの様子にほっとする。
「こらクロ、朝日くんは入部希望で来てくれたんだよ。ちゃんとおもてなししてあげて」
「ああ、おかまいなく。ところで、さっき紫月は作詞作曲できるって言ってたよね。よければ聴いてみたいんだけど……」
「音源ならおれのスマホに入ってるっすよ。ちょうどさっき再生してたから、すぐ聴けると思いますけど」
クロはノールックでそう言うと、机の上に雑に置かれていた鞄からスマホを取り出し、面倒くさそうに近づいてくる。
ため息をつきそうなくらいだるそうだが、陸に言われた「おもてなし」とやらをこいつなりにやろうとしているらしい。
反抗的に見えて実は真面目で従順な後輩のかわいい一面は微笑ましいが、おれの自作曲を披露するのは勘弁してほしい。やんわりとやめてくれと言おうとしたところ、小高が「え!」と声をあげた。
「これ、イギリスのインディーズシーンで最近話題のバンドだよね? クロも好きなの?」
小高が指さしている先に目を向ける。
クロのスマホカバーは透明で、好きなバンドのステッカーをたくさん挟んでいた。そのなかのひとつが、小高の琴線に触れたらしい。
「……うす。てかあんた、そんな顔してるのにこんな曲も聴くんすか」
「アイドルもインディーズバンドもヒップホップも好きだよ。雑食なんだ」
「ふーん。じゃあこれは?」
「ああ、好きだよ。この人たちの曲ってどれもキャッチ―でいいんだけど、セカンドシングルのB面が一番好みかな」
クロは相変わらず無表情だったが、よく見ると片方の唇がにやりとあがっていた。「わかってるじゃん」と言わんばかりの表情。これは、クロが相手を認めたときによくやるくせだ。
あの媚びない・群れない性格のクロがこんなに早く懐くなんて……!
おれは信じられない思いで小高朝日を見つめていた。こいつは顔面がキラキラしているだけじゃなくて、コミュニケーション能力にも非常に長けている。本物のアイドルみたいな完璧なやつなんだ。
部室のビーズクッションに座り、クロや陸とひととおり雑談を済ますと、小高はついに本題に切り出した。
「軽音楽部に入りたいんだけど、いいかな」
「あんた、なにができるんすか」
「ギターとボーカル。あと一応、作詞作曲もできるよ。紫月と一緒だね」
笑顔で話を振られておれは固まる。
まずい。このままだとおれもこいつらとバンドをすることになってしまう。
そんな危機感を覚えていると、案の定、小高は提案をしてきた。
「僕もみんなと一緒にバンドがしたいな」
「本当!? うれしいよ、歓迎する」
「まあ、いいんじゃないすか。こいつまあまあセンスよさそうだし」
「ありがとう」
軽音楽部が好きでどうにかして廃部を免れたい陸からしたら、願ってもない提案だろう。言葉どおりにこにことしている。あのクロもすっかり懐柔されてしまい、仕方なさそうな口ぶりとは裏腹にうれしいのがばればれだ。
おれは三人と同じ輪の中にいながらも、どこか他人事のようにそれらを眺めていた。
「紫月は幽霊部員って言ってたけどさ、せっかくの機会だしよかったら一緒にバンドやろうよ」
「……は?」
「ここで出会ったのもなにかの縁だしさ、どう?」
どう、と気軽に聞かれても答えに窮する。
技術だけではなく熱意の程度も一致しないと、バンドはやっていけないということを、あの冬の日におれはいやというほど実感した。
いまは楽しそうにしている三人だが、いざ練習がはじまったらだんだんぎくしゃくしてしまうかもしれない。どうでもいいことがきっかけで口論になるかもしれない。面と向かって否定されたら、今度こそおれは立ち行かなくなってしまうだろう。
「い、いや……だ」
「え? ごめん、ちょっと聞こえなかった。もう一回言ってもらってもいい?」
「いやだ! 絶対にやらない!」
大声を出したのは、バンドでボーカルをやっていたとき以来だ。
目を丸くした小高と視線が交わる。伊達眼鏡越しに見る小高の驚いた顔も少女漫画のヒーローみたいにかっこよくて、おれはだんだん腹が立ってきた。
『これ以上、おまえと続けるのは無理だ』
『てか、俺たちといてもおまえも楽しくないだろ』
とある冬の日。
バンド練習のために予約していたスタジオに向かうと、すでにメンバーがそろっていた。いつもおれが一番乗りだったからついにみんなもやる気を出したのかと喜んだのもつかの間、口にされたのは脱退宣言だった。
頭にこびりついて離れない、かつてのバンドメンバーたちの冷たい声。
できないことを指摘しただけなのに、練習に遅刻したことを少し咎めただけなのに、もっと真面目にやろうと言っただけなのに、将来の夢を語っただけなのに。
……みんなと、もっと音を奏でていたかったのに。
おれの願いは、メンバーたちの言葉によりあっけなく崩れてしまった。
冬の冷たい海の底に沈んでいくように、体中が痛い。呼吸が苦しい。
あの日から、おれはギターを握っていない。
いや、握れていないんだ。
◇
「紫月、聞いてる?」
考えごとに耽っていたおれは、友人の声で我に返った。
はっとして顔をあげると、春の生ぬるい風がワイシャツを揺らす。
花の匂い、土の香り、生命の息吹。真夏の草いきれほどではないが、ときおり思い出したかのように吹く風にはいろんな香りが混ざっている。春はなんでこんなに騒がしいのだろうか。
周囲に目を向けると、通学路を彩るように並ぶ桜の木はもうすっかり緑が生い茂っていた。
そうだ、いまは桜が咲く時期だ。あの冬の日ではない。
伊達眼鏡越しに陸を見ると、あきれたように笑っている。
「あ、ああ……ごめん。で、なんだっけ」
「うちのクラスに転校生が来るって噂あったじゃん。あれ、今日かもしれないんだって」
陸の瞳は期待を隠しきれていなかった。いつなんどきもニコニコしているのんびり屋の陸だが、ここまで楽しそうにしているのはめずらしい。
たしかに近ごろ、おれたちのクラスに転校生がやってくるのではないかと生徒たちの間で噂されていた。
ただの転校生ならいい。
噂によると、そいつはどうやら韓国でアイドルをめざしていたらしい。
日本で生まれたもののアイドルをめざして韓国に渡り、向こうで長く生活をしていたとか。信じられないほど小顔で、目鼻立ちははっきりしていて、肌は透き通るほど白く、プロポーションもすばらしいのだとか。
学校中のあちこちに存在するK-POP好きの生徒たちが鼻息荒くして転校生のことを噂している。
韓国の音楽やアイドル文化に疎いおれからすると、だからなんだとしか思えない。そもそも、噂のもとがどこなのかも不明だし、同じ教室で授業を受けるだけのやつにそこまで興味を持とうとも思えない。
だが、もし転校生の噂が本当だとすると、バンドが、音楽ができなくなったおれからしたらあまりうれしいことではなかった。
バンドのことを思い出すと、いまでも胃がずっしりと重くなる。
信頼していたメンバーに裏切られたおれは、あの日以来、幼なじみの陸以外の人の目を見て話すのが怖くなってしまった。だから極力人と目があわないように前髪を伸ばし、伊達眼鏡をかけて生活している。
陸はあまり乗り気ではないおれを一瞥して、口をとがらせる。
「興味ない?」
「……興味あるもなにも、先生がなんにも言ってなかったなと思って」
「でもみんな噂してる」
「まあな」
「本当に興味なさそうだね」
紫月らしいけど、と陸は付け足した。
学校まではあと少し。ここから別の話題を探すのもコミュ障で口下手なおれには難易度が高いし、かといって無言も気まずい。悩んだ末に、転校生の話題を続けることにした。
「K-POPのことをよく知らないから盛りあがるに盛りあがれないというか」
「あーたしかに。正直、ぼくもよくわかんないんだけど、佐藤さんとかがすっごいはしゃいでるから楽しみになっちゃってる節はあるかも」
クラスメイトの佐藤七菜を思い出す。
肩くらいまでの髪を明るい茶色に染めていて、目が大きくて、声もデカければ背もデカい、生命力にあふれているバレーボール部のあいつだ。
たしかに佐藤は、韓国アイドルの熱狂的なファンだった。
隣の席だからなにかと会話する機会があるが、事あるごとに「○○の新曲、超よかったからCD貸してあげる!」やら「××事務所から新しいアイドルがデビューするんだけどさ~」などと聞いてもいないのにいろいろとK-POPにまつわる情報を教えてくれる。おかげでアイドルたちの顔こそ曖昧なものの、流行りの曲はおさえていた。
「佐藤が言うなら本当なのかもな」
「どうだろうね。まあどちらにしても、新しいクラスメイトが増えるのは楽しみ」
「まあな」
寝起きでぼやけている思考のまま、とりとめのない会話をしているうちに、いつの間にか学校に到着していた。
コンクリート造りのやたら大きい校舎は、春の騒がしい気配にも動じずにどっしりと学生を迎え入れる。荘厳すぎる見た目に入学当初は萎縮したものの、時間が経てば見慣れた建物でしかない。
「二年生になってしばらくはイベントってないじゃん。だから、本当に転校生が来るなら楽しみだよ。仲よくなれるかなぁ」
「ああ」
下駄箱で靴を脱ぎながら、陸の話に適当に返事をする。
落とすように乱暴に置いた上履きが地面とぶつかる音が、やけに耳に残った。
◇
「小高朝日です。よろしくお願いします」
朝のホームルームがはじまって早々、担任と一緒に入ってきた新クラスメイトにクラス中が息をのんだ。
「超イケメンじゃん」
「え、あの噂、マジなの?」
「うそでしょ!」
「背、高すぎ……」
みなが噂していた転校生が本当にやってきたのだ。
ただの転校生ならいい。
ゆうに百八十センチは越えているのではと思うほどの長身、姿勢よくしゃんと立つ姿、人のよさそうな笑顔。大きな目は目じりが少し垂れていて人懐っこさを感じさせる。
どこからどう見てもただの高校生ではないような完璧な容姿をしていた。
アイドルに疎い俺ですら、小高が放つ輝きに度肝を抜かれていた。
少女漫画とかでヒーローが出てくるときみたいに、きらきらとか花とかが舞っているように見える。とても同じ高校二年生とは思えない。
信じられない思いで壇上の小高を眺めていると、ふと隣の席の佐藤が静かなことに気づく。連日あんなに騒いでいたのにおかしい。
体調でも悪いのかと思ってさりげなく隣に目を向けると、そこにはまたしても信じられない光景が広がっていた。
佐藤が静かに涙を流していたのだ。
「ど、どうしたんだよ、佐藤……」
思わず小声で声をかけるも、佐藤は返事をしないどころかおれの声に気づいている様子すらない。
朝一から隣の隣の隣のクラスまで響くほどの大声でおしゃべりに興じる普段の佐藤からはかけ離れた姿に動揺し、控えめに肩に手をかけて再び呼びかけると、ようやくこちらを向いた。
「おい、具合悪いなら保健室に――」
「……やばい」
「え?」
表情の抜けた顔は亡霊のようで正直怖い。そんな佐藤の口から出たのは、蚊の鳴くような声だった。
「やばいよ……! 日野、やばいんだって!」
「ちょっ……佐藤、落ちつけ。痛いから」
佐藤は急発進した自動車のような勢いで、おれに迫ると背中をばしばしと叩いてきた。
転校生のおかげで教室は騒がしく、いつもの朝のホームルームのしんとした気配とはかけ離れていたが、それでも佐藤とおれは注目を浴びた。
クラスメイトたちの視線が痛い。ほとんどが「また佐藤が騒いでるよ」「日野くんが巻き込まれてる……」なんてあきれと同情の色がにじんだ目だったが、人の目が怖いおれには刺激が強い。
耐えきれなくなって俯きそうになっていると、佐藤が大声をあげた。
「なんでそんなに冷静なの⁉ 韓国の大手芸能事務所からデビュー予定だった、あのアサヒくんだよ!」
「はあ……」
「歌もダンスも完璧で、楽器が得意で、作詞作曲もできて、人懐っこい笑顔がトレードマークで、大型犬みたいなかわいい男の子だってみんなに言われてた、あの朝日くんだよ!? 信じられない……!」
「い、いや、おれはなんにも知らないし……」
というかなんでまだデビューしていない仮にも一般人の情報を、こいつはそんなに詳しく知っているんだ。そんなことを疑問に思いつつもまずは佐藤を落ちつかせなければと必死になっていると、おれたちの騒ぎに気づいた小高と目があう。
佐藤の話が本当かはわからないが、もし小高が高校生活を送るために日本に戻ってきたのだとしたら、転校早々、自分の過去の経歴を大声でしゃべられたら迷惑極まりないだろう。しかし、小高はいやな顔一つせずににこりと微笑んだ。
するとその瞬間、佐藤はこれまでの騒ぎようが嘘のように直立不動になり、すとんと席に座る。そんな挙動不審のクラスメイトの頬にまた涙が流れた。
「本当に……ぶじでよかった……」
「は?」
祈るようなポーズでそうつぶやいたきり、佐藤はおとなしくなった。
いったいなんだったんだ。
感情の乱高下についていけずドン引きしていたおれだが、先生がパンパンと手を叩いた音でわれに返る。
「小高はみんなと同じで、この学校に勉強しに来ているんだぞー。学友として仲よくするように」
先生はそう釘を刺すと、小高に一言なにか言うようにうながした。小高は「はい」とうなずくと、すうっと息を吸う。
壇上に立つ小高とそれを見つめるクラスメイトたち。みなの瞳には、羨望や憧れだけではなく、無遠慮に詮索しようとしているあからさまな気配もにじんでいた。
開け放たれた窓から、春のぬるい風とともにひと足先にホームルームが終わった学生が外で騒いでいる気配が届く。なんでもない朝の学校の風景なのに、小高というフィルターを通すと学園ドラマの一コマみたいに見えてくる。
窓の外に向けていた視線を壇上に戻すと、ちょうど小高が口を開こうとしたところだった。上品な唇がすぅっと息を吸うだけで、みんながはっとする気配が伝わってきて、おれはあきれと驚きで笑ってしまいそうになる。まるでステージに立つアイドルと観客席のファンみたいだ。
「軽音楽部があると聞いたので、入部したいと思っています。みんなと過ごす学生生活が楽しみです。これからよろしくお願いします」
穏やかにそう言った小高と目があったような気がしたのは、きっと気のせいだ。胃のあたりがずんと重くなり、おれは机の中の教科書を探すふりをして俯いた。
たしかにこの学校に軽音楽部は存在している。
だが、部員数は定員ぎりぎりの三名。ドラム、ベース、ギターボーカルと、いい感じに得意分野がわかれたのはよかったが、そのうちの一人がほぼ幽霊部員なせいで実際はほとんど活動できていない。各部活に与えられる部室はほぼ荷物置き場と化し、楽器はほこりを被っている。
この春に新しい部員が入らなければ、廃部も検討すると先生に言われていた。
なんでこんなに軽音楽部の事情に詳しいのかと言うと、おれがその軽音楽部の部員――しかも廃部危機の元凶である幽霊部員の張本人だからだ。
音楽ができなくなったことで部室に行くのもいやになり、しばらく顔を出せていない。 バンドが解散してから、部活からも足が遠のき、家と学校と塾を行き来するだけの退屈な日々を過ごしていた。
でもそれでいいんだ。どうせすぐに大学受験がやってくるし、きっと社会に出るまでもあっという間なのだから。
幽霊部員のおれには部員が増えようと関係のないことかもしれないが、さっき目があった小高の表情が頭から離れず、なんだかいやな予感がしていた。
◇
転校生・小高朝日の人気はすさまじかった。
偶然空いていたおれのうしろの席に座った小高は、休み時間のたびに学校中の生徒に囲まれて質問攻めにあっていたのだ。
「韓国で練習生してたって本当?」
「どうしてやめちゃったの?」
「もうアイドルやらないの?」
そんな感じで、噂されている経歴にまつわる質問が四方八方から飛んでくる。あまりにも明け透けで無遠慮な言葉たちにおれは辟易していたが、いやでも聞こえてしまう距離だから、次の授業の準備をしつつ耳に届く小高の返事をなんとはなしに聞いていた。
「練習生だったのは本当だよ。でも家庭の事情で日本に帰国することになったんだ。こっちでは普通の高校生活を送りたいと思ってるから、みんな仲よくしてくれるとうれしいな」
小高がそう言うと、みなの気配があからさまに浮き立ったのを肌で感じた。きっと小高が微笑んだかなんかだろう。おれは同級生の現金な態度にあきれる気持ちを隠しきれなかった。
ちなみに佐藤はその輪には加わらず、いつもの騒がしさも嘘のように存在感を消してスマホをいじっていた。
「おい佐藤、やっぱりどっか悪いんじゃ……」
「え?」
「だっておまえ、あいつのファンだったんだろ? だったら、あの人だかりに交じりたいんじゃないかと思って」
小高を取り巻く人々は興奮して矢継ぎ早に質問を繰り出しているので、おれたちの会話なんて聞こえているわけがない。しかし、念には念を入れて顔を寄せ、小声でそう聞くと、佐藤は心外だと言わんばかりに眉をひそめた。
「あたしはそういうんじゃないの! ただ、アサヒくんがぶじだったのがうれしくて……」
またしても意味不明な発言をして、再びスマホに顔を戻すのだった。
さっきも「ぶじでよかった」と言っていたが、そんなに小高が人々の前から姿を消したのは急なことだったのだろうか。
そんな考えごとをしはじめて、おれははっとわれに返る。
これではおれもあの野次馬たちと同じだ。
小高は己にまつわる下世話な噂話や、人々の下心のある言動をまるで気にしていないようにふるまっている。さすがの元アイドルのたまごだと思うものの、だからといってそういう無遠慮な行動を是とするのもおかしい。
そもそもおれはあいつに関わる気がないのだから、わざわざ詳しくなる必要はない。
それ以降の休み時間は、イヤフォンをつけて適当にゲーム実況を流し見たり、陸と購買に行ったりして時間をつぶした。
◇
放課後になり、部活や塾に向かうクラスメイトを横目に帰宅準備をしていると、おれの机に影が落ちた。なんだろうと思って顔をあげると、話題の転校生こと小高朝日がおれの正面に立っている。
「日野紫月くん、だよね?」
「げっ……」
顔をあげたときに目があってしまった。華やかなところが似合う小高はおれにはまぶしすぎる。スクールバッグに教科書を詰めるふりをして、さりげなく顔を伏せる。
関わりたくないと思っていたのが顔と言葉に出てしまった気がする。伏し目がちにうかがうと、いやな顔ひとつせずに「げってなに?」と笑っているからよかったが。というか、なんでもうおれの名前を知っているんだ。
なんの用だと警戒していると、小高がまるで古くからの友のような気安い口調で話しはじめた。
「紫月が軽音楽部だって聞いたんだけど、本当? だとしたら、案内してほしくて――」
――紫月。
初対面にもかかわらず下の名前を呼ぶ勇気はおれにはない。
考え方の違いなのか性格の違いなのかわからないが、おれとこいつとの間にある差を実感して絶句していると、「聞いてる?」と顔を覗きこまれる。
動揺しているのがばれないようにぱっと顔を背け、教室の前方でクラスメイトと談笑している陸を呼んだ。
「小高が軽音楽部に興味があるんだって。案内してやってくれないか」
「え、そうなの? いいよー」
陸はリュックを背負いなおすと、おれたちに近づいてくる。
「陸も軽音楽部なんだ。楽器はなにやってるの?」
「ぼくはドラムだよ。というか小高くん、みんなの名前覚えるの早いね。びっくりしちゃった」
「記憶力はいいほうなんだ。朝日でいいよ」
「あ、本当? じゃあ朝日くんで」
二人は初対面にもかかわらずぎこちなさを微塵も感じさせないやりとりをしていた。
元アイドルの転校生が来ることを楽しみにしていた陸だったが、小高の噂をまったく気にするそぶりも見せず、ただの同級生として接している。コミュニケーション能力の高さと気遣いに感心していると、陸がおれに話を振った。
「ねえ、たまには紫月も顔出そうよ。今日は塾ないんでしょ?」
「あー、おれはいいよ」
「なんで? 紫月って部員じゃないの?」
至極真っ当な疑問を口にした小高に、陸がうんざりした表情で答える。
「紫月はね、幽霊部員なんだよ。ギターとボーカルが得意で、作詞作曲もできるのにもったいない。おかげで軽音楽部は廃部寸前なんだ」
「新入部員が入れば大丈夫なんだろ」
「まあそうだけど。三人しかいなくてろくに活動してない部活に入りたいと思う? 紫月の事情もわかってるつもりだけど、たまには顔出してくれてもいいんじゃない。クロもつまんなそうだよ」
「それは……わるいと思ってる」
クロというのは、唯一の二年生である古林黒のことだ。
真っ黒な髪と瞳が印象的なかっこいい後輩なのだが、目つきが悪ければ態度もあまりよいとは言えないやつだった。群れない媚びない、さらには気まぐれなところがあって、前世は黒猫だったのではないかと思ってる。
小学生のころからベースを習っていて、コアでディープな洋楽が好きな変わり者。小高が光のイケメンであれば、クロは闇のイケメンと呼んでもいいかもしれない。
おれがしどろもどろ弁解しても、陸の文句は止まらない。
でも、陸が怒ってくれるのは正直ありがたかった。
バンドが解散したときのおれは、はたから見てもわかりやすいくらい落ち込んでいたし、見た目も変わって以前よりあきらかに暗くなった。腫れもののように扱われるよりは、面と向かって文句を言われたほうが気持ちが楽なのは事実。陸の優しさにつけこんでいるようで、自分に嫌気がさすのもまた事実だが。
とはいえ部活に行く気はない。
行ったところでギターを握れないのだから意味がない。あの冬の日以来、ギターを触ろうと思うと手が震えてしまうのだ。
もうおれに音楽は必要ないのかもしれない。
あんなにも大好きだった――人生のすべてだと思っていたのに。
そんなことを考えながら陸の小言をやり過ごしていると、小高が急に前のめりになった。
「事情はよくわからないけど、幽霊が昼間に現れちゃいけない理由なんてないんじゃない?」
「は?」
「行こう!」
「ちょっ……! おい!」
小高に腕をつかまれ、引っ張られるがままに廊下を走る。
振り払おうとしても力が強くてびくともしない。しかも運動神経までいいのかかなり足が速くて、登下校が唯一の運動であるおれはついていくので精一杯だ。「止まってくれ」と言っても、聞こえていないのか無視されているのかわからないが、一向に止まる気配がない。
すでに人がまばらになりつつあったが、男子生徒二人が走っているのはそれなりに目立つ。無数の目が、おれを見ている。その目を意識するだけで体がぎゅっと強張り、肩が縮こまってしまう。
小高を振り払うのを諦めたおれは、ぎゅっと目をつぶって人の目を見ないふりした。
◇
ベースの弦を弾く音がだんだんと近くなってくる。
音は振動だ。音の発生元――軽音楽部の部室の前に立つと、上履き越しに足の裏から振動が伝って、おれの体を震わせた。
乗り気ではなかったのに、小高に引っ張られて部室まで来てしまった。あとから追いついた陸が隣で息を整えている。
「朝日くん、部室の場所知ってたんだね」
「今朝、先生に教えてもらった」
「そうなんだ。じゃあ、中に入ろうか」
おれの胸中などおかまいなしに、二人はのんきに会話している。
この震えは音楽が怖いからではない。音が振動しているだけ。そう言い聞かせているうちに、部室の扉が開く。
「お、センパイ、ついに来たんすか――ってだれですか、こいつ」
「ぼくたちのクラスに転校してきた小高朝日くんだよ。クロからしたら先輩なんだから、こいつとか言わないの」
「……うーっす」
クロは興味なさそうに小高を一瞥すると、すぐにベースを弾く手を再開させた。緊張して手に汗がにじんでいたが、後輩のいつもどおりの様子にほっとする。
「こらクロ、朝日くんは入部希望で来てくれたんだよ。ちゃんとおもてなししてあげて」
「ああ、おかまいなく。ところで、さっき紫月は作詞作曲できるって言ってたよね。よければ聴いてみたいんだけど……」
「音源ならおれのスマホに入ってるっすよ。ちょうどさっき再生してたから、すぐ聴けると思いますけど」
クロはノールックでそう言うと、机の上に雑に置かれていた鞄からスマホを取り出し、面倒くさそうに近づいてくる。
ため息をつきそうなくらいだるそうだが、陸に言われた「おもてなし」とやらをこいつなりにやろうとしているらしい。
反抗的に見えて実は真面目で従順な後輩のかわいい一面は微笑ましいが、おれの自作曲を披露するのは勘弁してほしい。やんわりとやめてくれと言おうとしたところ、小高が「え!」と声をあげた。
「これ、イギリスのインディーズシーンで最近話題のバンドだよね? クロも好きなの?」
小高が指さしている先に目を向ける。
クロのスマホカバーは透明で、好きなバンドのステッカーをたくさん挟んでいた。そのなかのひとつが、小高の琴線に触れたらしい。
「……うす。てかあんた、そんな顔してるのにこんな曲も聴くんすか」
「アイドルもインディーズバンドもヒップホップも好きだよ。雑食なんだ」
「ふーん。じゃあこれは?」
「ああ、好きだよ。この人たちの曲ってどれもキャッチ―でいいんだけど、セカンドシングルのB面が一番好みかな」
クロは相変わらず無表情だったが、よく見ると片方の唇がにやりとあがっていた。「わかってるじゃん」と言わんばかりの表情。これは、クロが相手を認めたときによくやるくせだ。
あの媚びない・群れない性格のクロがこんなに早く懐くなんて……!
おれは信じられない思いで小高朝日を見つめていた。こいつは顔面がキラキラしているだけじゃなくて、コミュニケーション能力にも非常に長けている。本物のアイドルみたいな完璧なやつなんだ。
部室のビーズクッションに座り、クロや陸とひととおり雑談を済ますと、小高はついに本題に切り出した。
「軽音楽部に入りたいんだけど、いいかな」
「あんた、なにができるんすか」
「ギターとボーカル。あと一応、作詞作曲もできるよ。紫月と一緒だね」
笑顔で話を振られておれは固まる。
まずい。このままだとおれもこいつらとバンドをすることになってしまう。
そんな危機感を覚えていると、案の定、小高は提案をしてきた。
「僕もみんなと一緒にバンドがしたいな」
「本当!? うれしいよ、歓迎する」
「まあ、いいんじゃないすか。こいつまあまあセンスよさそうだし」
「ありがとう」
軽音楽部が好きでどうにかして廃部を免れたい陸からしたら、願ってもない提案だろう。言葉どおりにこにことしている。あのクロもすっかり懐柔されてしまい、仕方なさそうな口ぶりとは裏腹にうれしいのがばればれだ。
おれは三人と同じ輪の中にいながらも、どこか他人事のようにそれらを眺めていた。
「紫月は幽霊部員って言ってたけどさ、せっかくの機会だしよかったら一緒にバンドやろうよ」
「……は?」
「ここで出会ったのもなにかの縁だしさ、どう?」
どう、と気軽に聞かれても答えに窮する。
技術だけではなく熱意の程度も一致しないと、バンドはやっていけないということを、あの冬の日におれはいやというほど実感した。
いまは楽しそうにしている三人だが、いざ練習がはじまったらだんだんぎくしゃくしてしまうかもしれない。どうでもいいことがきっかけで口論になるかもしれない。面と向かって否定されたら、今度こそおれは立ち行かなくなってしまうだろう。
「い、いや……だ」
「え? ごめん、ちょっと聞こえなかった。もう一回言ってもらってもいい?」
「いやだ! 絶対にやらない!」
大声を出したのは、バンドでボーカルをやっていたとき以来だ。
目を丸くした小高と視線が交わる。伊達眼鏡越しに見る小高の驚いた顔も少女漫画のヒーローみたいにかっこよくて、おれはだんだん腹が立ってきた。