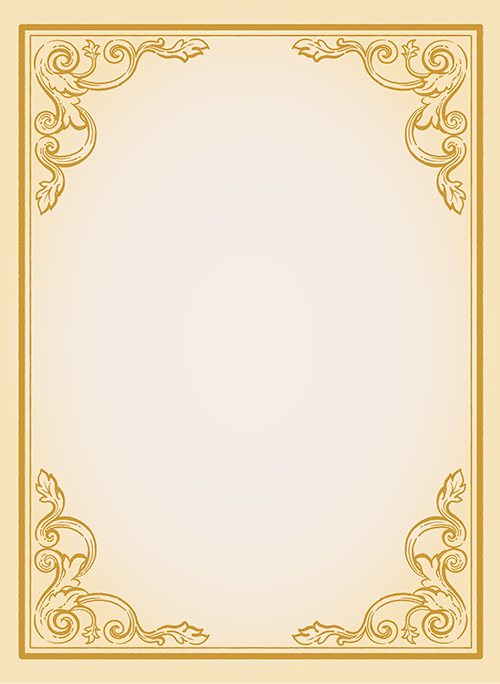◇
全て、包み隠さずに話した。
長い間話していたような気がするけれど、その間、誰も口を挟まなかった。
「私は横渕先生と何回も身体を重ねて、成績を維持しているの。これが、私の秘密。優等生なんかじゃない、私の姿」
全員の視線を一身に受け止め、己を罰する。だけど、想像していた以上に苦しくない。むしろ、抱えていた後悔や悲しみ、怒りといったたくさんの感情で押し潰されそうになっていた心がすっと軽くなった。
不思議だ。でも、ようやく話せた。自分の気持ちを話すことが出来る人たちに出会えたことが、とても嬉しい。
それでも、そんなの胡桃の勝手な気持ちの昇華だ。胡桃の心根を知った四人の心情には何も影響を及ぼさない。だから、これから胡桃に降り注ぐであろう罵倒や貶しの言葉にそっと身構え、話の終わりを告げるように静かに目を閉じた。
長い沈黙。判決を待つ罪人の気持ちって、こんな感じなのかな。
その沈黙は胡桃にとって意外な形で破られる。
突然、身体に軽い衝撃が伝わり、ぎゅっと誰かに抱きしめられた。
「えっ……?」
驚きに目を開くと、織音が胡桃の背に腕を回していた。
「染井さん?」
織音の身体は小刻みに震え、胡桃の首根に顔を埋めた彼女のすすり泣く声が聞こえる。
「辛かったね……」
「……うん。今まで話せなくて、ごめんね?」
首元で織音が頭を振る。
「違うよ。話してくれて、ありがとうって言ってるんだよ?」
優しい言葉が、胡桃を包み込む。
そっか、話して良かったんだ。
織音の身体をぎゅっと抱きしめ、燿と龍之介、凪の三人に目を向ける。三人はそれぞれ複雑そうな面持ちで胡桃を見つめていた。織音は胡桃を肯定してくれたけれど、身体を売るような人間のことを、彼らはどう思っているのだろう。
一番先に口を開いたのは、意外にも凪だった。
「ぼ、僕は柳さんのこと、すごいと思った。僕なら、きっと何も行動できない……。そのまま、親の言いなりになって傷付き続けたに違いない……。で、でも、その、柳さんのお兄さんみたいにもなれないと思ってて。えっと、僕が柳さんのお兄さんなら、多分柳さんのヒーローなんかにはなれなかったはずだから……」
「凪くん……」
凪は少し逡巡し、意を決したように声を振り絞った。
「ぼ、僕でも、変われるかな……」
相変わらず凪はおどおどとした声色を隠すこともない。彼がしたことは許されないことだ。それでも、凪が変わりたいと切望するのなら、胡桃は彼の背中を押してあげたい。
みんな、それぞれ罪を背負って生きている。
凪を許すのか、許さないのか。それを決めるのは胡桃ではない。
織音を抱きしめる力をちょっと強める。それから、彼女を離し、じっと目を合わせた。潤んでも強く輝く、羨ましいばかりの力強さの籠った光彩が胡桃を捉える。
私にも、織音のように孤独を生き抜く力があれば、何かが変わったのだろうか。
結局、みんなないものねだりだ。自分のいいところから目を背け、他人を羨ましがってばかりいる。
全員に目を向け、胡桃は思いの丈を告げる。
「きっと、私たちは綺麗であり過ぎたんだと思う。何かを変えようとする時も、綺麗に、完璧に変えられないから隠しちゃう。でもさ、もっと汚く、ぐちゃぐちゃに混ざり合った色に変わったっていいんじゃないかなって思うんだ。その結果がどうであれ、恥ずかしくも、格好悪くもない。こんな小さな端末に本音を詰め込んでいたらもったいないよ」
汗が滴る。息も上がる。場違いに明るい夏の陽射しは、一層輝いて教室に濃い影を生み落としていた。その影の中にいるのが胡桃たちだ。
決して、明るくない。きらきら輝いてなんかいない。
私たちは、底に沈殿するドロドロの絵具だ。
否定の声を上げる人はいなかった。だから、胡桃は続ける。胡桃がみんなの足がかりになるんだ。それが、優等生のせめてもの役割だと思うから。
「身体を売っている奴が何言ってんだって思われるかもしれない。腹を割っても何も変わらないかもしれない。でも、言いたいことも言えないで、一人で抱え込むのはやめにしようよ。一人だけ秘密がバレて本音を話すのは、そりゃ傷付いて辛いしのけ者にされるかもしれない。でも、みんなが平等に言い合える機会が今だと思うんだ。みんなで一緒に傷付こうよ。逃げないで、立ち止まっていないで、痛いって泣きながら、私はみんなと前に進みたい……!」
ぽたりと床に真っ赤な液体が落ちる。そして、少し遅れて口の中を鉄のような味が染み渡った。
思わず、手で口元を抑える。べっとりと手のひらに付いたのは真っ赤な鼻血だった。まるで、今話した通り、一番乗りで傷付いてやった証に思えた。
良かった。私の血はちゃんと赤い。
「さあ、みんなはどうする?」
誰も何も言わないなら、それでもいいと思った。それが、胡桃の想いを聞き届けてみんなの出した選択なら、構わない。後悔だってしない自信がある。
「……すみませんでした」
突然、燿が胡桃に向かって頭を下げた。
「何の謝罪?」
燿は唇を軽く噛みしめ、言葉を選んでいるようだった。そして、ややあって口を開く。
「誤解しないでほしいんすけど、胡桃先輩の話を聞いて、あなたは僕よりも不幸だなと思ったんで」
燿は椅子に腰を下ろし、そっと左足首のミサンガに触れる。それから、胡桃と同様にゆっくりと話し始めた。怪我のこと、そのせいで歪んでしまったこと。全部、燿は話してくれた。
「僕は、怪我で足を使う運動は二度と出来ません。みんなと同じ速度で歩くことさえ出来ないから、普段の生活だって大変なことは多いです。日常と未来を同時に奪われた気分でした。幸せのてっぺんからいきなり地獄に突き落とされて、これより下なんて存在しないと思ってた。でも、胡桃先輩はもっと下で頑張り続けていたんだなって……。もちろん、幸せのベクトルなんて僕の主観でしかないですけれど」
明け透けなく話した後の燿は下を向いていたけれど、どこか清々(すがすが)しく見えた。
「燿くん、私にはあなたの辛さが分からない。ずっと残り続ける痛みは燿くんだけのものだから。でも、周りのみんなが妬ましいって気持ち、私もよく分かるよ。みんな、私みたいになればいいのに、って思ったことだって何度もある。だから、コンクールの応募作を台無しにしたことは許せないことだけど、今の燿くんを私は嫌いにはなれない。きっと、私が燿くんみたいになっていた可能性だってあるんだから」
そうだ、いつだって胡桃はこの四人のことを嫌いになんてなっていない。嫌いになれるはずがない。
燿は胡桃にいつかのような爽やかな笑みをくれた。
「胡桃先輩にはちょっと感謝もしてるんです。僕はまだ一番下じゃないんだ。下には下がいる。そう思えるから。上を向いて歩くのが辛いのに、僕より下がいないことが何よりも苦しかった。だから、みんな不幸になればいい。そう思っていた……。でも、胡桃先輩に救われた気がします。僕、めっちゃ嫌な奴なんで、下を向いてしか生きられないんです」
胡桃はつい笑ってしまった。
「大丈夫だよ。まだまだ燿くんより不幸でいてあげるよ。任せて」
何ておかしな会話なんだろう。そう思ったら、自然と笑いが零れた。少しだけ、前みたいに一縷の疑いもなく、燿のことを見ることが出来た気がした。
だから、きっとこれが正解だ。
「私たち、上を向いてなんて生きていけないよ。そんなの最初から上にいる人たちの綺麗ごと。本当、クソ食らえだよね!」
「胡桃先輩がクソ食らえなんて言うと、めっちゃ違和感あります」
そう言って、燿も笑った。
「僕は幸せな人が許せない。みんな、頼むから死んでくれとさえ思う。だから、僕はきっとこれから先、自分が幸せになれない限り、変わることなんて出来ないと思います。だけど、その人が抱えている苦しみとかは、出来る限り理解してあげたいなって思います……」
燿がゆっくりと龍之介を見遣る。
「話してください、龍之介先輩。あの事故の後、僕に救われたあなたが何で苦しんでいるのか。僕に対してどう思っているのか。なんで、暴力沙汰なんて起こしたのか。僕は知りたいです。ちゃんと龍之介先輩の口から――あなたの本当の言葉で知りたいです」
みんなの注目が龍之介へと向く。彼は相変わらず気怠そうに少し顔を顰め、沈黙をかざしていた。不機嫌そうな態度。でも、今なら分かる。龍之介はこうやって臆病な自分を守っているんだ。
こうして燿と胡桃が全てを打ち明けてなお、龍之介はまだ自分を曝け出すことに抵抗を覚えていた。だから、あえて言ってあげようと思う。
「龍之介先輩、友人の心からの頼みや願いを断る人なんて、ここにはいません。もちろん、龍之介先輩がそんな人じゃないことも、私は知っています。自分さえ傷付いていればいいと周りを寄せ付けない。周囲に勝手に押し付けられた印象を変えるのが怖いことは、私は理解できます。でも、少しは弱いところを見せてほしい。怖がらないで。そうやっていつまでも逃げていたら、燿くんも龍之介先輩もどっちも辛いだけですよ。凪くんも一緒。言葉にしなくちゃ、何も伝わらないんだよ。今だけでいいから、一人で背負わないで、私たちにも二人の苦しみとか痛みを背負わせてほしいの」
偽善だって、分かっている。それでも、胡桃が手を伸ばしちゃいけない理由にはならない。汚れた手で綺麗なものを触るのは抵抗があるけれど、今、胡桃が掴もうとしているのは、同じように汚れた手だ。
だったら、何も関係ない。綺麗な手の人たちが助けてくれないなら、自分たちで助け合うしかない。泥だらけで、灰被りになったとしても。
「いいよ。二人がまだ決心が付かないのなら、あたしが先に話すよ」
織音が胡桃の血で汚れた手をハンカチで拭きながら言った。
「染井さん……」
織音と目が合う。そして、彼女は軽く笑って見せた。
「あたしは人に愛されることが怖い」
今一度、織音はそう前置き、みんなに向けて思いの丈を打ち明けた。両親のこと、どうして動物を殺すようになったのかということ。胡桃や燿と変わらないくらい、重く、苦しい過去を。
「本当、気持ち悪いね……。動物を殺して快楽を得るなんて。でもね、命を奪う瞬間は本当に堪らなく恐ろしいんだ。手が震えて、涙が止まらなくて、吐きそうになりながらナイフを振り下ろしてる。でも、同時にどうしようもなく高揚しているあたしもいる。身体が拒絶しているのに、脳が悦んでる。もう自分でもよく分からない。けどさ、こんなの誰にも言えるわけないじゃん……」
身に降りかかるストレスの発散か、単に嗜虐が彼女の性癖か。きっと、織音本人も分かっていないのだろう。
「染井さんはどうしたいの?」
「……分からない」
織音は少し怯えているようだった。本人すら理解できていない感情をみんなに伝えてしまうことが恐ろしいんだ。織音の中に眠る矛盾した感情は、きっと彼女にしか名前を付けることが出来ない。だけど、少なくとも、胡桃には織音の痛みを少しだけ一緒に背負ってあげることが出来た。
だから、胡桃は織音から目を離さなかった。
「大丈夫だよ。あなたを信じることが出来た私が保証してあげる。他人に自分の意見を押し付けるだけじゃ駄目だよ。どうしてあなたを愛しちゃいけないのか、分かるように話してくれなきゃ、みんなも困ってしまうから。でもね、ここにはあなたの痛みに寄り添ってくれる人は私以外にもいるはずだよ」
織音の背に手を当てる。その身体は震えていなかった。
「……あたしは多分、自分に自信がないんだと思う。あたしってみんなが思っているよりずっと弱い人間だから。自分に足りない感情とまっすぐ向き合えないでいる。人とは違う特別なことをして、無理矢理自分をつくり上げている。愛されたくないなんて感情は、あたしが臆病で弱いせいだ……」
独り言を話すように俯いていた織音が顔を上げる。
「だけど、今回のことで気が付いたよ。今まで通り独りで生きていくことは出来る。だけど、もう苦しみながら生きていきたくない。愛されることに怯えるのも、動物を殺して愛情を補完するのも、やめにしたい。だから、助けてほしい。あたし、もう逃げないから。みんなと胸張って歩んでいけるように頑張るから。あたしがみんなのことを愛せるようになるのを手伝ってほしい!」
織音はちゃんと決断してくれた。彼女の表情に曇りはなかった。
「うん。じゃあ、一緒に解決方法を探そうよ。染井さんは独りじゃない。私も染井さんと友達でいたいから」
織音は独りだから強く輝けると思う。そのステージから引きずり下ろすということは、彼女の才覚を潰すことに等しい。とても、惜しいことだと思う。
それでも、彼女がそれを望むのなら、胡桃は喜んで手を貸そう。だって、胡桃も織音を眺めているより、彼女の隣で笑い合っていたいから。
「僕も手伝いますよ」
ぶっきらぼうに燿が言う。ちょっと意外だった。
「あーあ、まさか染井先輩まで僕より下だなんて。何か、今まで妬んでいたのが馬鹿馬鹿しいっすわ。ていうか、何すか? この不幸自慢大会。染井先輩には解決しなきゃいけないことがまだあるでしょ」
つまらなそうに頭を振る燿に、織音は小さく頷いた。そして、織音はゆっくりと、ようやく凪に目を向けた。
決別した二人がどういう結末を迎えるのか、それはきっと誰にも分からない。ここから先は、胡桃が口を挟めることはないのだろう。
「あたしは愛を知らない。……愛されることが恐ろしい。あたしもちゃんと考えたんだよ。凪はあたしを裏切ったんじゃなくて、あたしのことを傷付けないようにしてくれていたんだって」
凪の性格をよく知っている胡桃だって、そう思う。彼は打算のない優しい人だ。そして、自分の意見を上手く伝えられない人だということも、みんな知っている。
「落ち着いて考えれば、凪が普通であたしが変なんだよ。人に好意を持つのって、普通のことで、その好意を拒絶しちゃうあたしがおかしいんだ。だけど、凪はそんなあたしに合わせようとしてくれたんだよね? ……実はさ、ストーカーのこと、あたしは怒ったのを後悔している。だって、凪みたいな優しい奴にストーカーなんて馬鹿なことさせたのは、あたしのせいだし。あたしが、凪まで狂わせちゃったんだ……」
凪は苦しそうに顔を歪ませ、必死に頭を振る。自分の犯した罪を赦されて、肯定されることに抵抗を覚えているのだろう。
織音は大きく深呼吸をした。
「あたしだけ一方的に気持ちを押し付けるのは違うよね。……凪の気持ち、聞かせてほしい。一度は突っぱねたくせに、都合がいいのは分かってるよ。でも、凪があたしのことをどう思っているのか、これからどうやって歩んでいきたかったのか。全部、教えてください。お願いします」
長い静寂だった。それでも、織音が凪から目を逸らさなかったから、誰も口を挟まなかった。
「ぼ、僕は……!」
沈黙を凪が破る。
凪を繋ぎ止めていた何かがちぎれたように、とても大きな声だった。短い区切りだったのに、声が震えていることが伝わってきて、彼に目を向ければ、過呼吸なんじゃないかと思うくらい浅い呼吸を繰り返している。
凪の視線はもちろん、織音へと向いていた。
そして、凪は言ったのだ。
「僕は、染井さんのことが好きです! 愛してしまっています!」
声を振り絞ったと同時に溢れ出した涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、凪は言い切った。
何も知らない人が見れば、典型的な告白の惹句を勢い任せに謳い上げたのだと思うのだろう。何の捻りもない、痛いくらいに純粋な愛の言葉を。
実際、その通りだ。でも、だからこそ胡桃は心の中で、頑張ったね、と凪を称えた。
「好きになっちゃ駄目だって、分かってた。ひ、必死に友達であろうとしたんだ……。でも、僕はどうしようもない人間だから、染井さんに惹かれてしまった。気持ちが抑えられなくて、で、でも、そんなことを染井さんに伝えるわけにはいかない。僕だって、染井さんと恋人になりたいわけじゃないんだ……。染井さんは僕の神様であってほしい。誰かと手を取り合って堕ちてほしくない。嫌かもしれないけれど、僕にとって染井さんは、一番高いところでずっと輝く星だったんだ! ……でも、染井さんは変わることを望んでいる。だから、僕も見上げるんじゃなくて、あなたの横を歩けるようになりたい」
凪の告白を聞き届け、織音はぎゅっと目を閉じる。彼女の肩は、微かに震えていた。それでも、凪の告白に何かを言い返すことはしなかった。イエスも、ノーも、何も言わなかった。
それが、織音の出した答えだ。
「……少しだけ、考えさせてほしい。ちゃんと、答えを出すから……」
告白の返事にはありがちな台詞。だけど、織音が言うのだ。それがどういうことなのか、ここにいる全員が理解していた。
織音は変わろうと努力することを選んだ。
凪は袖で乱暴に顔を拭い、これ以上泣くまいと堪えるように唇を噛みしめて頷いた。
ありきたりな告白の台詞で始まり、よくある返事で終わる。だけど、凪と織音にとってはこれ以上ない結果だと思う。
「残ったのは龍之介先輩だけっすよ」
会話が途切れて沈黙が訪れた最中、燿が呟く。龍之介に向ける燿の視線は依然として冷たい。
押し黙る龍之介に、燿は小さくため息を吐く。しかし、いつものように茶化すような言葉はかけなかった。落胆という二文字が燿から透けて見える。
「もういいっす。これで、スマホの件は終わりでいいですよね?」
「待って、燿くん」
「……何すか、胡桃先輩。時間かければいいってもんじゃないっすよ。それに、この空気じゃ無理矢理口を割らせているみたいで僕も釈然としないんで」
燿の言う通りかもしれない。だけど、胡桃には龍之介が自らの意思で話してくれるという確信があった。
「龍之介先輩、昨日話しましたよね。燿くんを一方的に苦しめているのは龍之介先輩だって。今日、ここに来てくれたのって、燿くんと話をするためですよね? そのために、私のスマホの中身が入った端末を持ってきてくれた。約束を守ってくれたんですよね?」
「それは……」
「大丈夫。傷付けることを怖がらないでほしいです。燿くんだって、さっき言ったじゃないですか。あなたの口から、本当のことが聞きたいって」
視界の端で、燿が小さく頷く。
「龍之介先輩、どうしてバスケやめたんですか?」
燿にそう問われ、龍之介は独り言のように呟く。
「別に、つまんねーなって思っただけだ」
「嘘だ。龍之介先輩が理由もなくバスケを嫌いになるはずがない」
燿は毅然と言い退けた。
二人は十年以上の付き合いだ。きっと、互いのことをよく知り過ぎている。だから、余計に摩擦が大きいのだろう。
「もしかして、僕のせいですか?」
「……ちげぇ」
「やっぱり、そうなんだ。僕がこんな足になったせいで」
「違うって言ってんだろ」
「だから、嘘吐くなよ!」
燿の振り立てた怒鳴り声が美術室に響き渡った。
「僕がどれだけあんたを見てきたと思ってんだ。小学生の時からずっと憧れて、追い付きたくて。必死にあんたの背中を追いかけてきたんだよ! 分かんないわけないだろ……」
燿の言葉に龍之介は鼻白んだ様子で押し黙る。
何も言い返さない龍之介に、燿が一層悔しそうに顔を歪めて、龍之介の胸ぐらを掴んだ。しかし、どれだけ燿が龍之介を押し倒そうと力を込めても、彼の左足は思ったように踏ん張りが利かない。だから、龍之介はびくともしなかった。
「くそっ! あんたなんか大嫌いだ! 僕の人生返せよ! そうやって、いつも俺は不幸だみたいな面しやがって、うぜぇんだよ!」
燿は握った拳で龍之介の胸を叩き、慟哭した。ひとしきり龍之介への感情をぶちまけ終えると、燿はむせび泣きと共に力なく腕を下ろす。
「僕は一体いつまで、あんたを助けなきゃ良かったって思い続けなくちゃいけないんですか……」
茫然と燿を見下ろす龍之介は、弾かれたようによろめいて一歩後ずさる。
「そんなこと言われたって……。じゃ、じゃあ、俺はどうすれば良かったんだよ! 勝手に燿に救われて、勝手に嫌われて……。俺だって、自分が怪我しちまった方がマシだって何度も思った。今でも、そう思ってんだよ!」
きっと、二人の関係に正解はないのだろう。不運な事故で、二人とも苦しみを背負ってしまった。本当にそれだけのことなのだ。
「燿がバスケを出来なくなったのに、俺がのうのうと続けられるわけがないだろ。燿の未来を奪ったのは、お前の言う通り俺だ。だから、今回の事故だってお前を救うために……」
そこで龍之介は言葉を詰まらせる。でも、一度傾いてしまったバケツは、零れる水の勢いを止めることなんて出来ない。
「何すか……それ……」
「――っ。し、仕方ないだろ……村田さんが転げ落ちそうになったその下に燿がいて……俺はそのシチュエーションが、あの時の償いのように感じて……。だから、俺は燿を助けようと……」
龍之介は訥々と、独り言のように呟いた。
龍之介を見上げる燿の表情が引きつる。
「暴力沙汰なんかじゃないじゃないっすか……何であの時、否定しなかったんですか。まさか、僕が罪悪感を覚えると思って黙ってたんすか?」
龍之介の沈黙は、肯定を意味していた。その様子に燿は肩を大きく落とす。
「そうだったんですか……。本当、龍之介先輩って大馬鹿っすよ。そんなのあの時の事故と一緒で、僕も龍之介先輩も悪くないじゃないっすか……」
「……違う。俺が悪い。結果的に村田さんを怪我させたのは俺だ」
額に手を当て、龍之介はきつく目を閉じた。
「違います」
燿は言った。
「龍之介先輩は悪くない。誰もあなたのことを悪者なんかにしていない。もちろん僕もです。恨んではいますけれど、龍之介先輩が悪い人間じゃないことは僕が一番知っています」
憧れの人を救って未来を断たれた燿と、自分を救ってくれた人の苦しみを傍らで見続け未来永劫無実の罪を背負い続けなければいけない龍之介。
二人に何も悪かったところなんてない。そして、二人とも互いを思い合ってしまったから、余計に苦しみが大きくなってしまったのだろう。
夏の陽射しが燿の顔を照らす。暗い結末だというのに、燿の表情はどこか柔らかく見えた。
ただの胡桃の気のせいかもしれないけれど、確かにそう見えたのだ。
こうして、五人の長い六日間が終わりを迎えた。
全て、包み隠さずに話した。
長い間話していたような気がするけれど、その間、誰も口を挟まなかった。
「私は横渕先生と何回も身体を重ねて、成績を維持しているの。これが、私の秘密。優等生なんかじゃない、私の姿」
全員の視線を一身に受け止め、己を罰する。だけど、想像していた以上に苦しくない。むしろ、抱えていた後悔や悲しみ、怒りといったたくさんの感情で押し潰されそうになっていた心がすっと軽くなった。
不思議だ。でも、ようやく話せた。自分の気持ちを話すことが出来る人たちに出会えたことが、とても嬉しい。
それでも、そんなの胡桃の勝手な気持ちの昇華だ。胡桃の心根を知った四人の心情には何も影響を及ぼさない。だから、これから胡桃に降り注ぐであろう罵倒や貶しの言葉にそっと身構え、話の終わりを告げるように静かに目を閉じた。
長い沈黙。判決を待つ罪人の気持ちって、こんな感じなのかな。
その沈黙は胡桃にとって意外な形で破られる。
突然、身体に軽い衝撃が伝わり、ぎゅっと誰かに抱きしめられた。
「えっ……?」
驚きに目を開くと、織音が胡桃の背に腕を回していた。
「染井さん?」
織音の身体は小刻みに震え、胡桃の首根に顔を埋めた彼女のすすり泣く声が聞こえる。
「辛かったね……」
「……うん。今まで話せなくて、ごめんね?」
首元で織音が頭を振る。
「違うよ。話してくれて、ありがとうって言ってるんだよ?」
優しい言葉が、胡桃を包み込む。
そっか、話して良かったんだ。
織音の身体をぎゅっと抱きしめ、燿と龍之介、凪の三人に目を向ける。三人はそれぞれ複雑そうな面持ちで胡桃を見つめていた。織音は胡桃を肯定してくれたけれど、身体を売るような人間のことを、彼らはどう思っているのだろう。
一番先に口を開いたのは、意外にも凪だった。
「ぼ、僕は柳さんのこと、すごいと思った。僕なら、きっと何も行動できない……。そのまま、親の言いなりになって傷付き続けたに違いない……。で、でも、その、柳さんのお兄さんみたいにもなれないと思ってて。えっと、僕が柳さんのお兄さんなら、多分柳さんのヒーローなんかにはなれなかったはずだから……」
「凪くん……」
凪は少し逡巡し、意を決したように声を振り絞った。
「ぼ、僕でも、変われるかな……」
相変わらず凪はおどおどとした声色を隠すこともない。彼がしたことは許されないことだ。それでも、凪が変わりたいと切望するのなら、胡桃は彼の背中を押してあげたい。
みんな、それぞれ罪を背負って生きている。
凪を許すのか、許さないのか。それを決めるのは胡桃ではない。
織音を抱きしめる力をちょっと強める。それから、彼女を離し、じっと目を合わせた。潤んでも強く輝く、羨ましいばかりの力強さの籠った光彩が胡桃を捉える。
私にも、織音のように孤独を生き抜く力があれば、何かが変わったのだろうか。
結局、みんなないものねだりだ。自分のいいところから目を背け、他人を羨ましがってばかりいる。
全員に目を向け、胡桃は思いの丈を告げる。
「きっと、私たちは綺麗であり過ぎたんだと思う。何かを変えようとする時も、綺麗に、完璧に変えられないから隠しちゃう。でもさ、もっと汚く、ぐちゃぐちゃに混ざり合った色に変わったっていいんじゃないかなって思うんだ。その結果がどうであれ、恥ずかしくも、格好悪くもない。こんな小さな端末に本音を詰め込んでいたらもったいないよ」
汗が滴る。息も上がる。場違いに明るい夏の陽射しは、一層輝いて教室に濃い影を生み落としていた。その影の中にいるのが胡桃たちだ。
決して、明るくない。きらきら輝いてなんかいない。
私たちは、底に沈殿するドロドロの絵具だ。
否定の声を上げる人はいなかった。だから、胡桃は続ける。胡桃がみんなの足がかりになるんだ。それが、優等生のせめてもの役割だと思うから。
「身体を売っている奴が何言ってんだって思われるかもしれない。腹を割っても何も変わらないかもしれない。でも、言いたいことも言えないで、一人で抱え込むのはやめにしようよ。一人だけ秘密がバレて本音を話すのは、そりゃ傷付いて辛いしのけ者にされるかもしれない。でも、みんなが平等に言い合える機会が今だと思うんだ。みんなで一緒に傷付こうよ。逃げないで、立ち止まっていないで、痛いって泣きながら、私はみんなと前に進みたい……!」
ぽたりと床に真っ赤な液体が落ちる。そして、少し遅れて口の中を鉄のような味が染み渡った。
思わず、手で口元を抑える。べっとりと手のひらに付いたのは真っ赤な鼻血だった。まるで、今話した通り、一番乗りで傷付いてやった証に思えた。
良かった。私の血はちゃんと赤い。
「さあ、みんなはどうする?」
誰も何も言わないなら、それでもいいと思った。それが、胡桃の想いを聞き届けてみんなの出した選択なら、構わない。後悔だってしない自信がある。
「……すみませんでした」
突然、燿が胡桃に向かって頭を下げた。
「何の謝罪?」
燿は唇を軽く噛みしめ、言葉を選んでいるようだった。そして、ややあって口を開く。
「誤解しないでほしいんすけど、胡桃先輩の話を聞いて、あなたは僕よりも不幸だなと思ったんで」
燿は椅子に腰を下ろし、そっと左足首のミサンガに触れる。それから、胡桃と同様にゆっくりと話し始めた。怪我のこと、そのせいで歪んでしまったこと。全部、燿は話してくれた。
「僕は、怪我で足を使う運動は二度と出来ません。みんなと同じ速度で歩くことさえ出来ないから、普段の生活だって大変なことは多いです。日常と未来を同時に奪われた気分でした。幸せのてっぺんからいきなり地獄に突き落とされて、これより下なんて存在しないと思ってた。でも、胡桃先輩はもっと下で頑張り続けていたんだなって……。もちろん、幸せのベクトルなんて僕の主観でしかないですけれど」
明け透けなく話した後の燿は下を向いていたけれど、どこか清々(すがすが)しく見えた。
「燿くん、私にはあなたの辛さが分からない。ずっと残り続ける痛みは燿くんだけのものだから。でも、周りのみんなが妬ましいって気持ち、私もよく分かるよ。みんな、私みたいになればいいのに、って思ったことだって何度もある。だから、コンクールの応募作を台無しにしたことは許せないことだけど、今の燿くんを私は嫌いにはなれない。きっと、私が燿くんみたいになっていた可能性だってあるんだから」
そうだ、いつだって胡桃はこの四人のことを嫌いになんてなっていない。嫌いになれるはずがない。
燿は胡桃にいつかのような爽やかな笑みをくれた。
「胡桃先輩にはちょっと感謝もしてるんです。僕はまだ一番下じゃないんだ。下には下がいる。そう思えるから。上を向いて歩くのが辛いのに、僕より下がいないことが何よりも苦しかった。だから、みんな不幸になればいい。そう思っていた……。でも、胡桃先輩に救われた気がします。僕、めっちゃ嫌な奴なんで、下を向いてしか生きられないんです」
胡桃はつい笑ってしまった。
「大丈夫だよ。まだまだ燿くんより不幸でいてあげるよ。任せて」
何ておかしな会話なんだろう。そう思ったら、自然と笑いが零れた。少しだけ、前みたいに一縷の疑いもなく、燿のことを見ることが出来た気がした。
だから、きっとこれが正解だ。
「私たち、上を向いてなんて生きていけないよ。そんなの最初から上にいる人たちの綺麗ごと。本当、クソ食らえだよね!」
「胡桃先輩がクソ食らえなんて言うと、めっちゃ違和感あります」
そう言って、燿も笑った。
「僕は幸せな人が許せない。みんな、頼むから死んでくれとさえ思う。だから、僕はきっとこれから先、自分が幸せになれない限り、変わることなんて出来ないと思います。だけど、その人が抱えている苦しみとかは、出来る限り理解してあげたいなって思います……」
燿がゆっくりと龍之介を見遣る。
「話してください、龍之介先輩。あの事故の後、僕に救われたあなたが何で苦しんでいるのか。僕に対してどう思っているのか。なんで、暴力沙汰なんて起こしたのか。僕は知りたいです。ちゃんと龍之介先輩の口から――あなたの本当の言葉で知りたいです」
みんなの注目が龍之介へと向く。彼は相変わらず気怠そうに少し顔を顰め、沈黙をかざしていた。不機嫌そうな態度。でも、今なら分かる。龍之介はこうやって臆病な自分を守っているんだ。
こうして燿と胡桃が全てを打ち明けてなお、龍之介はまだ自分を曝け出すことに抵抗を覚えていた。だから、あえて言ってあげようと思う。
「龍之介先輩、友人の心からの頼みや願いを断る人なんて、ここにはいません。もちろん、龍之介先輩がそんな人じゃないことも、私は知っています。自分さえ傷付いていればいいと周りを寄せ付けない。周囲に勝手に押し付けられた印象を変えるのが怖いことは、私は理解できます。でも、少しは弱いところを見せてほしい。怖がらないで。そうやっていつまでも逃げていたら、燿くんも龍之介先輩もどっちも辛いだけですよ。凪くんも一緒。言葉にしなくちゃ、何も伝わらないんだよ。今だけでいいから、一人で背負わないで、私たちにも二人の苦しみとか痛みを背負わせてほしいの」
偽善だって、分かっている。それでも、胡桃が手を伸ばしちゃいけない理由にはならない。汚れた手で綺麗なものを触るのは抵抗があるけれど、今、胡桃が掴もうとしているのは、同じように汚れた手だ。
だったら、何も関係ない。綺麗な手の人たちが助けてくれないなら、自分たちで助け合うしかない。泥だらけで、灰被りになったとしても。
「いいよ。二人がまだ決心が付かないのなら、あたしが先に話すよ」
織音が胡桃の血で汚れた手をハンカチで拭きながら言った。
「染井さん……」
織音と目が合う。そして、彼女は軽く笑って見せた。
「あたしは人に愛されることが怖い」
今一度、織音はそう前置き、みんなに向けて思いの丈を打ち明けた。両親のこと、どうして動物を殺すようになったのかということ。胡桃や燿と変わらないくらい、重く、苦しい過去を。
「本当、気持ち悪いね……。動物を殺して快楽を得るなんて。でもね、命を奪う瞬間は本当に堪らなく恐ろしいんだ。手が震えて、涙が止まらなくて、吐きそうになりながらナイフを振り下ろしてる。でも、同時にどうしようもなく高揚しているあたしもいる。身体が拒絶しているのに、脳が悦んでる。もう自分でもよく分からない。けどさ、こんなの誰にも言えるわけないじゃん……」
身に降りかかるストレスの発散か、単に嗜虐が彼女の性癖か。きっと、織音本人も分かっていないのだろう。
「染井さんはどうしたいの?」
「……分からない」
織音は少し怯えているようだった。本人すら理解できていない感情をみんなに伝えてしまうことが恐ろしいんだ。織音の中に眠る矛盾した感情は、きっと彼女にしか名前を付けることが出来ない。だけど、少なくとも、胡桃には織音の痛みを少しだけ一緒に背負ってあげることが出来た。
だから、胡桃は織音から目を離さなかった。
「大丈夫だよ。あなたを信じることが出来た私が保証してあげる。他人に自分の意見を押し付けるだけじゃ駄目だよ。どうしてあなたを愛しちゃいけないのか、分かるように話してくれなきゃ、みんなも困ってしまうから。でもね、ここにはあなたの痛みに寄り添ってくれる人は私以外にもいるはずだよ」
織音の背に手を当てる。その身体は震えていなかった。
「……あたしは多分、自分に自信がないんだと思う。あたしってみんなが思っているよりずっと弱い人間だから。自分に足りない感情とまっすぐ向き合えないでいる。人とは違う特別なことをして、無理矢理自分をつくり上げている。愛されたくないなんて感情は、あたしが臆病で弱いせいだ……」
独り言を話すように俯いていた織音が顔を上げる。
「だけど、今回のことで気が付いたよ。今まで通り独りで生きていくことは出来る。だけど、もう苦しみながら生きていきたくない。愛されることに怯えるのも、動物を殺して愛情を補完するのも、やめにしたい。だから、助けてほしい。あたし、もう逃げないから。みんなと胸張って歩んでいけるように頑張るから。あたしがみんなのことを愛せるようになるのを手伝ってほしい!」
織音はちゃんと決断してくれた。彼女の表情に曇りはなかった。
「うん。じゃあ、一緒に解決方法を探そうよ。染井さんは独りじゃない。私も染井さんと友達でいたいから」
織音は独りだから強く輝けると思う。そのステージから引きずり下ろすということは、彼女の才覚を潰すことに等しい。とても、惜しいことだと思う。
それでも、彼女がそれを望むのなら、胡桃は喜んで手を貸そう。だって、胡桃も織音を眺めているより、彼女の隣で笑い合っていたいから。
「僕も手伝いますよ」
ぶっきらぼうに燿が言う。ちょっと意外だった。
「あーあ、まさか染井先輩まで僕より下だなんて。何か、今まで妬んでいたのが馬鹿馬鹿しいっすわ。ていうか、何すか? この不幸自慢大会。染井先輩には解決しなきゃいけないことがまだあるでしょ」
つまらなそうに頭を振る燿に、織音は小さく頷いた。そして、織音はゆっくりと、ようやく凪に目を向けた。
決別した二人がどういう結末を迎えるのか、それはきっと誰にも分からない。ここから先は、胡桃が口を挟めることはないのだろう。
「あたしは愛を知らない。……愛されることが恐ろしい。あたしもちゃんと考えたんだよ。凪はあたしを裏切ったんじゃなくて、あたしのことを傷付けないようにしてくれていたんだって」
凪の性格をよく知っている胡桃だって、そう思う。彼は打算のない優しい人だ。そして、自分の意見を上手く伝えられない人だということも、みんな知っている。
「落ち着いて考えれば、凪が普通であたしが変なんだよ。人に好意を持つのって、普通のことで、その好意を拒絶しちゃうあたしがおかしいんだ。だけど、凪はそんなあたしに合わせようとしてくれたんだよね? ……実はさ、ストーカーのこと、あたしは怒ったのを後悔している。だって、凪みたいな優しい奴にストーカーなんて馬鹿なことさせたのは、あたしのせいだし。あたしが、凪まで狂わせちゃったんだ……」
凪は苦しそうに顔を歪ませ、必死に頭を振る。自分の犯した罪を赦されて、肯定されることに抵抗を覚えているのだろう。
織音は大きく深呼吸をした。
「あたしだけ一方的に気持ちを押し付けるのは違うよね。……凪の気持ち、聞かせてほしい。一度は突っぱねたくせに、都合がいいのは分かってるよ。でも、凪があたしのことをどう思っているのか、これからどうやって歩んでいきたかったのか。全部、教えてください。お願いします」
長い静寂だった。それでも、織音が凪から目を逸らさなかったから、誰も口を挟まなかった。
「ぼ、僕は……!」
沈黙を凪が破る。
凪を繋ぎ止めていた何かがちぎれたように、とても大きな声だった。短い区切りだったのに、声が震えていることが伝わってきて、彼に目を向ければ、過呼吸なんじゃないかと思うくらい浅い呼吸を繰り返している。
凪の視線はもちろん、織音へと向いていた。
そして、凪は言ったのだ。
「僕は、染井さんのことが好きです! 愛してしまっています!」
声を振り絞ったと同時に溢れ出した涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、凪は言い切った。
何も知らない人が見れば、典型的な告白の惹句を勢い任せに謳い上げたのだと思うのだろう。何の捻りもない、痛いくらいに純粋な愛の言葉を。
実際、その通りだ。でも、だからこそ胡桃は心の中で、頑張ったね、と凪を称えた。
「好きになっちゃ駄目だって、分かってた。ひ、必死に友達であろうとしたんだ……。でも、僕はどうしようもない人間だから、染井さんに惹かれてしまった。気持ちが抑えられなくて、で、でも、そんなことを染井さんに伝えるわけにはいかない。僕だって、染井さんと恋人になりたいわけじゃないんだ……。染井さんは僕の神様であってほしい。誰かと手を取り合って堕ちてほしくない。嫌かもしれないけれど、僕にとって染井さんは、一番高いところでずっと輝く星だったんだ! ……でも、染井さんは変わることを望んでいる。だから、僕も見上げるんじゃなくて、あなたの横を歩けるようになりたい」
凪の告白を聞き届け、織音はぎゅっと目を閉じる。彼女の肩は、微かに震えていた。それでも、凪の告白に何かを言い返すことはしなかった。イエスも、ノーも、何も言わなかった。
それが、織音の出した答えだ。
「……少しだけ、考えさせてほしい。ちゃんと、答えを出すから……」
告白の返事にはありがちな台詞。だけど、織音が言うのだ。それがどういうことなのか、ここにいる全員が理解していた。
織音は変わろうと努力することを選んだ。
凪は袖で乱暴に顔を拭い、これ以上泣くまいと堪えるように唇を噛みしめて頷いた。
ありきたりな告白の台詞で始まり、よくある返事で終わる。だけど、凪と織音にとってはこれ以上ない結果だと思う。
「残ったのは龍之介先輩だけっすよ」
会話が途切れて沈黙が訪れた最中、燿が呟く。龍之介に向ける燿の視線は依然として冷たい。
押し黙る龍之介に、燿は小さくため息を吐く。しかし、いつものように茶化すような言葉はかけなかった。落胆という二文字が燿から透けて見える。
「もういいっす。これで、スマホの件は終わりでいいですよね?」
「待って、燿くん」
「……何すか、胡桃先輩。時間かければいいってもんじゃないっすよ。それに、この空気じゃ無理矢理口を割らせているみたいで僕も釈然としないんで」
燿の言う通りかもしれない。だけど、胡桃には龍之介が自らの意思で話してくれるという確信があった。
「龍之介先輩、昨日話しましたよね。燿くんを一方的に苦しめているのは龍之介先輩だって。今日、ここに来てくれたのって、燿くんと話をするためですよね? そのために、私のスマホの中身が入った端末を持ってきてくれた。約束を守ってくれたんですよね?」
「それは……」
「大丈夫。傷付けることを怖がらないでほしいです。燿くんだって、さっき言ったじゃないですか。あなたの口から、本当のことが聞きたいって」
視界の端で、燿が小さく頷く。
「龍之介先輩、どうしてバスケやめたんですか?」
燿にそう問われ、龍之介は独り言のように呟く。
「別に、つまんねーなって思っただけだ」
「嘘だ。龍之介先輩が理由もなくバスケを嫌いになるはずがない」
燿は毅然と言い退けた。
二人は十年以上の付き合いだ。きっと、互いのことをよく知り過ぎている。だから、余計に摩擦が大きいのだろう。
「もしかして、僕のせいですか?」
「……ちげぇ」
「やっぱり、そうなんだ。僕がこんな足になったせいで」
「違うって言ってんだろ」
「だから、嘘吐くなよ!」
燿の振り立てた怒鳴り声が美術室に響き渡った。
「僕がどれだけあんたを見てきたと思ってんだ。小学生の時からずっと憧れて、追い付きたくて。必死にあんたの背中を追いかけてきたんだよ! 分かんないわけないだろ……」
燿の言葉に龍之介は鼻白んだ様子で押し黙る。
何も言い返さない龍之介に、燿が一層悔しそうに顔を歪めて、龍之介の胸ぐらを掴んだ。しかし、どれだけ燿が龍之介を押し倒そうと力を込めても、彼の左足は思ったように踏ん張りが利かない。だから、龍之介はびくともしなかった。
「くそっ! あんたなんか大嫌いだ! 僕の人生返せよ! そうやって、いつも俺は不幸だみたいな面しやがって、うぜぇんだよ!」
燿は握った拳で龍之介の胸を叩き、慟哭した。ひとしきり龍之介への感情をぶちまけ終えると、燿はむせび泣きと共に力なく腕を下ろす。
「僕は一体いつまで、あんたを助けなきゃ良かったって思い続けなくちゃいけないんですか……」
茫然と燿を見下ろす龍之介は、弾かれたようによろめいて一歩後ずさる。
「そんなこと言われたって……。じゃ、じゃあ、俺はどうすれば良かったんだよ! 勝手に燿に救われて、勝手に嫌われて……。俺だって、自分が怪我しちまった方がマシだって何度も思った。今でも、そう思ってんだよ!」
きっと、二人の関係に正解はないのだろう。不運な事故で、二人とも苦しみを背負ってしまった。本当にそれだけのことなのだ。
「燿がバスケを出来なくなったのに、俺がのうのうと続けられるわけがないだろ。燿の未来を奪ったのは、お前の言う通り俺だ。だから、今回の事故だってお前を救うために……」
そこで龍之介は言葉を詰まらせる。でも、一度傾いてしまったバケツは、零れる水の勢いを止めることなんて出来ない。
「何すか……それ……」
「――っ。し、仕方ないだろ……村田さんが転げ落ちそうになったその下に燿がいて……俺はそのシチュエーションが、あの時の償いのように感じて……。だから、俺は燿を助けようと……」
龍之介は訥々と、独り言のように呟いた。
龍之介を見上げる燿の表情が引きつる。
「暴力沙汰なんかじゃないじゃないっすか……何であの時、否定しなかったんですか。まさか、僕が罪悪感を覚えると思って黙ってたんすか?」
龍之介の沈黙は、肯定を意味していた。その様子に燿は肩を大きく落とす。
「そうだったんですか……。本当、龍之介先輩って大馬鹿っすよ。そんなのあの時の事故と一緒で、僕も龍之介先輩も悪くないじゃないっすか……」
「……違う。俺が悪い。結果的に村田さんを怪我させたのは俺だ」
額に手を当て、龍之介はきつく目を閉じた。
「違います」
燿は言った。
「龍之介先輩は悪くない。誰もあなたのことを悪者なんかにしていない。もちろん僕もです。恨んではいますけれど、龍之介先輩が悪い人間じゃないことは僕が一番知っています」
憧れの人を救って未来を断たれた燿と、自分を救ってくれた人の苦しみを傍らで見続け未来永劫無実の罪を背負い続けなければいけない龍之介。
二人に何も悪かったところなんてない。そして、二人とも互いを思い合ってしまったから、余計に苦しみが大きくなってしまったのだろう。
夏の陽射しが燿の顔を照らす。暗い結末だというのに、燿の表情はどこか柔らかく見えた。
ただの胡桃の気のせいかもしれないけれど、確かにそう見えたのだ。
こうして、五人の長い六日間が終わりを迎えた。