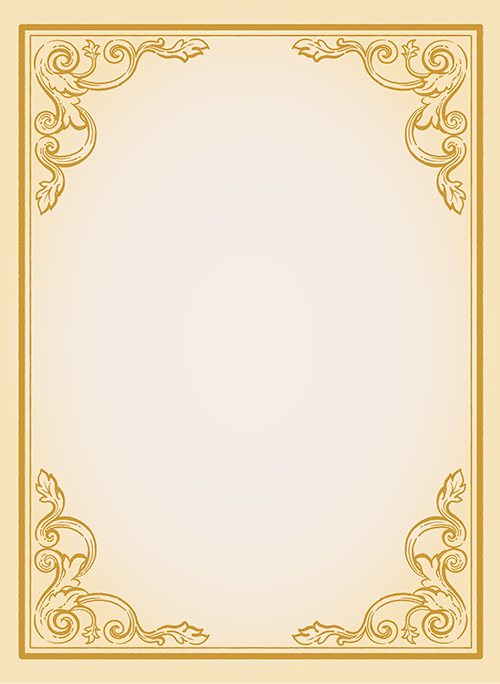それから三か月後の九月。――兄が死んだ。
自殺だった。
朝方、母に頼まれて兄を起こしに部屋のドアを開けて、首を吊っている兄を胡桃が発見した。
寝坊だろうかと呑気に考えていたのに、突然の出来事に頭が真っ白になって、しばらく宙吊りになった兄の身体を眺めてしまった。
苦しかったはずなのに、やけに穏やかな兄の死に顔はきっと一生忘れることはない。頬に残った涙の跡には、一体どんな想いが込められていたのだろうか。今でも毎日考える。
机の上に置かれた胡桃宛ての遺書には、ただ一言、『ごめん』とだけ書かれていた。
「嘘吐き……」
火葬場で灰になった兄の残骸を眺め、呟いた。
全然、知らなかった。兄が自ら命を絶つ程追い詰められていたなんて。
しかし、嘘ってわけじゃないのだろう。ただ、兄の言うキャパというものから溢れ出してしまっただけだ。
でも、どうして相談してくれなかったの?
確かに胡桃は兄のことを唯一の拠りどころとして、色々と頼り切ってしまっていたのかもしれない。だけど、弱いところの一つも見せないまま死んでしまうなんて、それは胡桃にとっても残酷過ぎるじゃないか。
一体、私はこれから何を希望として生きていけばいいのだろう。
兄が死んで、一番取り乱したのは母だ。なぜ、兄を死へと追いやった張本人がこんなにも感情的に泣きわめけるのか不思議だった。
胡桃は泣くことが出来なかった。多分、まだ兄の死を受け入れられていないから。兄の死を認めてしまったら、きっと胡桃も同じ選択をしてしまうような気がした。
だって、兄がそうするのだ。間違っているはずがない。死には意味があるに違いない。歪んだ妄想と理性の間で、結局胡桃は立ち尽くす。
散々だった高校受験はもちろん落ちて、滑り止めの地元の高校に通うことになった。受験に失敗したのは、兄の死で動揺したせいか、それともやっぱり胡桃自身の能力のせいか。
間違いなく、どちらも、だ。
兄が死んでからというものの、しばらくの間、胡桃は母の視界に入っていなかった。胡桃の心境も勉強どころじゃなかったから、ちょうど良かった。
毎日、家の中で悲嘆にくれる二つの声が重なる。不本意ながら、本当に不本意ながら、この時だけは胡桃は母と分かり合えた気がした。兄の死という、二人にとってあまりに大きな悲しみを。
どうやら、母は結局、自分のせいで兄が死んだとは露程も思っていないらしい。いや、ある意味では自分のせいだと思っているのか……。
「お母さんの育て方が悪かったわ。もっと、完璧にやらないといけなかったね。お母さん頑張るから、見ててね。ごめんね……ごめんね…………」
仏壇の前で泣きじゃくる母の背を眺め、胡桃は怒りよりも恐怖を覚えた。
私は、この悪魔から生まれたのか……。
背筋が震える程ぞっとした。この人の血が自分にも流れていると思うと、おかしくなりそうだ。
高校に入学し、桜の花が散ってじめじめとした暑さがにじり寄ってきた頃、ただ勉が再開された。母も胡桃も、兄の死からどうにか立ち直り、前を向いた最中の出来事だ。
「ただいま」
「おかえりなさい」
いつもの挨拶。そして、母は胡桃の鞄を漁り、胡桃は日記を書く。兄が亡くなっても、この家のルールは何も変わらなかった。
再開されたただ勉の初日は五時間。
次の日は、七時間。
その次の日は、五時間。
塾が終わり、二十一時に帰ってきて玄関から家に上がることを許されるのは、大抵日付が変わってからだ。時には外が明るくなっている日もあった。
一人だからスペースを広く使えてラッキー。なんて思っていたあの頃が、酷く懐かしい。
今はただ、夏でも凍えるように寒くて、暗くて、孤独だった。もうこの場所で二人、未来へのささやかで壮大な夢にはしゃぐことは叶わない。頭を撫でてもらうことも、叶わない。
厳しくなったのはただ勉だけじゃなかった。
兄が対人関係で上手くいっていなかったことが自殺の原因だと、母は勝手に思ったからだろう。胡桃は礼儀作法や心理学を叩き込まれた。
人から共感を得る方法、相手の心理を掌握する理論と色々学ばされたけれど、一体母は胡桃を何者にしたいのだろう。
クラスメートがスマホで育成ゲームのアプリをやっているのを見て、ふと思った。餌を与えられ、何の能力を伸ばそうか決められ、進むべきレールを敷かれる。
あぁ、これは私だ。
高校一年の冬、中学受験に失敗した時以来の二度目の叱責を母から受けた。テストの点がいつもよりほんの少し悪かっただけなのに。
背中を一升瓶で強く殴られ、息が詰まる。背骨を打つずんっとした重く激しい痛みに、じわりと涙が滲んだ。
「……胡桃?」
床に崩れ落ちた胡桃は感情のない声で名前を呼ばれ、込み上がる恐怖にゆっくりと振り向く。
胡桃を見下ろす母の姿。その手に持った、窓から射し込む夕焼けを艶めかしく反射する大きな瓶。
力いっぱい殴られた背中は、未だ痺れるように胡桃の鼓動に合わせて強い痛みを孕んでいた。
母が再び瓶を振り上げる。
声にならない悲鳴が喉で詰まり、胡桃は咄嗟に身を縮めて迫る瓶を避けた。
刹那、ぎゅっと瞑った暗闇に響く破砕音に目を開けると、机の角を打った瓶が粉々に砕け、大きな破片の鋭い切っ先が胡桃の顔のすぐ傍を通り落ちるところだった。一拍遅れて、中身の液体と硝子の破片が胡桃に降り注ぐ。床に落ちた鋭利な破片から、目が離せなかった。
これが、兄の見ていた景色。無意味に背負わされた勝手な期待を裏切った罰なのだろうか。
「どうして、お勉強出来ないの? なんで、いつもこんな簡単な問題を間違えちゃうの?」
そんなこと言われたって、それは胡桃が一番知りたい。必死に勉強しているのに、完璧にはなれない。こんな地獄を経験していない子たちにすら敵わない。
その日はもう二度、今度はフライパンで脇腹と背中を殴られた。
外ではひたすら優等生に努め、家に帰れば真夜中までただ勉。冷めて乾いたご飯を食べ、毎日のように母からは暴力を振るわれる。なんて生産性のない日々なのだろう。でも、そのことを母に言っても伝わらないに決まっている。
胡桃の日常は、父がたまに単身赴任先から帰ってきても当然のように行われ、父も母に何も言わなかった。
もしかしたら、と期待した胡桃が馬鹿だった。この悪魔たちは、自分たちの跡を継がせるための完璧な人間を育てようとしているだけだ。
ベッドの中で丸まり、毎日明日が来なければいいと願い続けている。兄もこんな気持ちだったのだろうか。それとも、早く過ぎ去って羽ばたく夢を思い描いていたのだろうか。
兄の残した〝ごめん〟の言葉には、どんな想いが詰まっていたのか、今ならよく分かる。
きっと、一人で耐え切れなくてごめんという意味なのだろう。胡桃に相談したことが母にバレてしまえば、自分と同じ仕打ちを胡桃も受けることになるかもしれない。だから、兄は孤独に耐え続けた。胡桃の知らないところで、兄は戦っていたんだ。
胡桃の成績は上がるどころか、下がっていく一方だった。兄という心の支えを失ってしまった胡桃には、頑張る気力も、意義も見つからない。
そもそも、胡桃は駄目な子なのだ。どれだけ勉強をしても、今が限界なのだと思う。
それなら、これ以上頑張る意味ってなんなのだろう。
真面目に痛みに耐え続けた兄は死んだ。胡桃よりもずっと優秀で、出来た人間の兄でさえ、この世界から逃げることでしか救われなかった。
高校を卒業して親と絶縁するまで、胡桃がこの地獄を耐えられるわけがない。
だから、少しだけ、ささやかに抗ってみようと思った。どうせ行き着く先が兄と一緒なら、やるしかない。
兄が出来なかったことをして初めて、胡桃は地獄から抜け出せるのだ。二人で夢見た先へ、歩いて行けるはずだから。
その教師は学生の間でちょっとした話題の人物だった。学校のある沼津からは遠く離れた小田原の街で、学生のような風貌の女性とホテルに入っていくのを見た生徒がいるらしい。
眉唾な話だが、どうやらそのホテルの周辺は援助交際――所謂、パパ活のようなものが盛んらしく、噂の一人歩きというわけでもなさそうだった。
それに、胡桃はその教師とはそれなりに話す。だって、部活の顧問だし。
「横渕先生、ちょっと話があるんですけど――」
彼は黒縁の眼鏡のブリッジを指で押し上げ、胡桃を見た。ぼさっとした髪に、温和な顔立ち。いかにも生徒に優しい先生という雰囲気を醸している。
この人が……。
「どうしましたか、柳さん?」
あまり緊張はしなかった。普段から教師の評価を得ているし、人に取り入る術は母の教育の賜物によって十分持ち合わせている。胡桃は勉強が出来ないだけで、他は全てにおいてそれなりに優秀だという自負と自信もある。
だから、大丈夫。
私は一人でも生きていける。私は私のやり方で、母や周りからの期待に応えて見せる。
「先生、私を買いませんか? お金はいりません。むしろ、困ります。だから、代わりに来週の中間テストの問題用紙をください」
「えっ……?」
戸惑いを見せる横渕先生。だけど、胡桃の言っていることを理解しているだけで、彼の噂が真実だと物語っていた。
「簡単ですよね? 各教科の問題用紙のコピーを取るだけでいいんですから」
「…………」
「では、決まりで」
「だ、駄目です……」
絞り出すように横渕先生が言う。だけど、胡桃だって必死なのだ。もう、痛いのは嫌だ。兄の生きた道をなぞるのも、嫌だ。
「お願いします。私を助けてください……」
ぐらぐらとした足元がふっと消えた気がした。ずぶんっと暗い水中に落ちる。
いや、最初からいつだって胡桃はこの暗い水の中にいる。なりふり構わずにもがいていないと、溺れてしまうのだ。
その日から、胡桃の成績はぐんっと良くなった。だけど、胡桃は優等生だから、誰にも疑われることはなかった。
今までの積み重ねがようやく実を結んだ。
そう、思ってしまったのだ。
自殺だった。
朝方、母に頼まれて兄を起こしに部屋のドアを開けて、首を吊っている兄を胡桃が発見した。
寝坊だろうかと呑気に考えていたのに、突然の出来事に頭が真っ白になって、しばらく宙吊りになった兄の身体を眺めてしまった。
苦しかったはずなのに、やけに穏やかな兄の死に顔はきっと一生忘れることはない。頬に残った涙の跡には、一体どんな想いが込められていたのだろうか。今でも毎日考える。
机の上に置かれた胡桃宛ての遺書には、ただ一言、『ごめん』とだけ書かれていた。
「嘘吐き……」
火葬場で灰になった兄の残骸を眺め、呟いた。
全然、知らなかった。兄が自ら命を絶つ程追い詰められていたなんて。
しかし、嘘ってわけじゃないのだろう。ただ、兄の言うキャパというものから溢れ出してしまっただけだ。
でも、どうして相談してくれなかったの?
確かに胡桃は兄のことを唯一の拠りどころとして、色々と頼り切ってしまっていたのかもしれない。だけど、弱いところの一つも見せないまま死んでしまうなんて、それは胡桃にとっても残酷過ぎるじゃないか。
一体、私はこれから何を希望として生きていけばいいのだろう。
兄が死んで、一番取り乱したのは母だ。なぜ、兄を死へと追いやった張本人がこんなにも感情的に泣きわめけるのか不思議だった。
胡桃は泣くことが出来なかった。多分、まだ兄の死を受け入れられていないから。兄の死を認めてしまったら、きっと胡桃も同じ選択をしてしまうような気がした。
だって、兄がそうするのだ。間違っているはずがない。死には意味があるに違いない。歪んだ妄想と理性の間で、結局胡桃は立ち尽くす。
散々だった高校受験はもちろん落ちて、滑り止めの地元の高校に通うことになった。受験に失敗したのは、兄の死で動揺したせいか、それともやっぱり胡桃自身の能力のせいか。
間違いなく、どちらも、だ。
兄が死んでからというものの、しばらくの間、胡桃は母の視界に入っていなかった。胡桃の心境も勉強どころじゃなかったから、ちょうど良かった。
毎日、家の中で悲嘆にくれる二つの声が重なる。不本意ながら、本当に不本意ながら、この時だけは胡桃は母と分かり合えた気がした。兄の死という、二人にとってあまりに大きな悲しみを。
どうやら、母は結局、自分のせいで兄が死んだとは露程も思っていないらしい。いや、ある意味では自分のせいだと思っているのか……。
「お母さんの育て方が悪かったわ。もっと、完璧にやらないといけなかったね。お母さん頑張るから、見ててね。ごめんね……ごめんね…………」
仏壇の前で泣きじゃくる母の背を眺め、胡桃は怒りよりも恐怖を覚えた。
私は、この悪魔から生まれたのか……。
背筋が震える程ぞっとした。この人の血が自分にも流れていると思うと、おかしくなりそうだ。
高校に入学し、桜の花が散ってじめじめとした暑さがにじり寄ってきた頃、ただ勉が再開された。母も胡桃も、兄の死からどうにか立ち直り、前を向いた最中の出来事だ。
「ただいま」
「おかえりなさい」
いつもの挨拶。そして、母は胡桃の鞄を漁り、胡桃は日記を書く。兄が亡くなっても、この家のルールは何も変わらなかった。
再開されたただ勉の初日は五時間。
次の日は、七時間。
その次の日は、五時間。
塾が終わり、二十一時に帰ってきて玄関から家に上がることを許されるのは、大抵日付が変わってからだ。時には外が明るくなっている日もあった。
一人だからスペースを広く使えてラッキー。なんて思っていたあの頃が、酷く懐かしい。
今はただ、夏でも凍えるように寒くて、暗くて、孤独だった。もうこの場所で二人、未来へのささやかで壮大な夢にはしゃぐことは叶わない。頭を撫でてもらうことも、叶わない。
厳しくなったのはただ勉だけじゃなかった。
兄が対人関係で上手くいっていなかったことが自殺の原因だと、母は勝手に思ったからだろう。胡桃は礼儀作法や心理学を叩き込まれた。
人から共感を得る方法、相手の心理を掌握する理論と色々学ばされたけれど、一体母は胡桃を何者にしたいのだろう。
クラスメートがスマホで育成ゲームのアプリをやっているのを見て、ふと思った。餌を与えられ、何の能力を伸ばそうか決められ、進むべきレールを敷かれる。
あぁ、これは私だ。
高校一年の冬、中学受験に失敗した時以来の二度目の叱責を母から受けた。テストの点がいつもよりほんの少し悪かっただけなのに。
背中を一升瓶で強く殴られ、息が詰まる。背骨を打つずんっとした重く激しい痛みに、じわりと涙が滲んだ。
「……胡桃?」
床に崩れ落ちた胡桃は感情のない声で名前を呼ばれ、込み上がる恐怖にゆっくりと振り向く。
胡桃を見下ろす母の姿。その手に持った、窓から射し込む夕焼けを艶めかしく反射する大きな瓶。
力いっぱい殴られた背中は、未だ痺れるように胡桃の鼓動に合わせて強い痛みを孕んでいた。
母が再び瓶を振り上げる。
声にならない悲鳴が喉で詰まり、胡桃は咄嗟に身を縮めて迫る瓶を避けた。
刹那、ぎゅっと瞑った暗闇に響く破砕音に目を開けると、机の角を打った瓶が粉々に砕け、大きな破片の鋭い切っ先が胡桃の顔のすぐ傍を通り落ちるところだった。一拍遅れて、中身の液体と硝子の破片が胡桃に降り注ぐ。床に落ちた鋭利な破片から、目が離せなかった。
これが、兄の見ていた景色。無意味に背負わされた勝手な期待を裏切った罰なのだろうか。
「どうして、お勉強出来ないの? なんで、いつもこんな簡単な問題を間違えちゃうの?」
そんなこと言われたって、それは胡桃が一番知りたい。必死に勉強しているのに、完璧にはなれない。こんな地獄を経験していない子たちにすら敵わない。
その日はもう二度、今度はフライパンで脇腹と背中を殴られた。
外ではひたすら優等生に努め、家に帰れば真夜中までただ勉。冷めて乾いたご飯を食べ、毎日のように母からは暴力を振るわれる。なんて生産性のない日々なのだろう。でも、そのことを母に言っても伝わらないに決まっている。
胡桃の日常は、父がたまに単身赴任先から帰ってきても当然のように行われ、父も母に何も言わなかった。
もしかしたら、と期待した胡桃が馬鹿だった。この悪魔たちは、自分たちの跡を継がせるための完璧な人間を育てようとしているだけだ。
ベッドの中で丸まり、毎日明日が来なければいいと願い続けている。兄もこんな気持ちだったのだろうか。それとも、早く過ぎ去って羽ばたく夢を思い描いていたのだろうか。
兄の残した〝ごめん〟の言葉には、どんな想いが詰まっていたのか、今ならよく分かる。
きっと、一人で耐え切れなくてごめんという意味なのだろう。胡桃に相談したことが母にバレてしまえば、自分と同じ仕打ちを胡桃も受けることになるかもしれない。だから、兄は孤独に耐え続けた。胡桃の知らないところで、兄は戦っていたんだ。
胡桃の成績は上がるどころか、下がっていく一方だった。兄という心の支えを失ってしまった胡桃には、頑張る気力も、意義も見つからない。
そもそも、胡桃は駄目な子なのだ。どれだけ勉強をしても、今が限界なのだと思う。
それなら、これ以上頑張る意味ってなんなのだろう。
真面目に痛みに耐え続けた兄は死んだ。胡桃よりもずっと優秀で、出来た人間の兄でさえ、この世界から逃げることでしか救われなかった。
高校を卒業して親と絶縁するまで、胡桃がこの地獄を耐えられるわけがない。
だから、少しだけ、ささやかに抗ってみようと思った。どうせ行き着く先が兄と一緒なら、やるしかない。
兄が出来なかったことをして初めて、胡桃は地獄から抜け出せるのだ。二人で夢見た先へ、歩いて行けるはずだから。
その教師は学生の間でちょっとした話題の人物だった。学校のある沼津からは遠く離れた小田原の街で、学生のような風貌の女性とホテルに入っていくのを見た生徒がいるらしい。
眉唾な話だが、どうやらそのホテルの周辺は援助交際――所謂、パパ活のようなものが盛んらしく、噂の一人歩きというわけでもなさそうだった。
それに、胡桃はその教師とはそれなりに話す。だって、部活の顧問だし。
「横渕先生、ちょっと話があるんですけど――」
彼は黒縁の眼鏡のブリッジを指で押し上げ、胡桃を見た。ぼさっとした髪に、温和な顔立ち。いかにも生徒に優しい先生という雰囲気を醸している。
この人が……。
「どうしましたか、柳さん?」
あまり緊張はしなかった。普段から教師の評価を得ているし、人に取り入る術は母の教育の賜物によって十分持ち合わせている。胡桃は勉強が出来ないだけで、他は全てにおいてそれなりに優秀だという自負と自信もある。
だから、大丈夫。
私は一人でも生きていける。私は私のやり方で、母や周りからの期待に応えて見せる。
「先生、私を買いませんか? お金はいりません。むしろ、困ります。だから、代わりに来週の中間テストの問題用紙をください」
「えっ……?」
戸惑いを見せる横渕先生。だけど、胡桃の言っていることを理解しているだけで、彼の噂が真実だと物語っていた。
「簡単ですよね? 各教科の問題用紙のコピーを取るだけでいいんですから」
「…………」
「では、決まりで」
「だ、駄目です……」
絞り出すように横渕先生が言う。だけど、胡桃だって必死なのだ。もう、痛いのは嫌だ。兄の生きた道をなぞるのも、嫌だ。
「お願いします。私を助けてください……」
ぐらぐらとした足元がふっと消えた気がした。ずぶんっと暗い水中に落ちる。
いや、最初からいつだって胡桃はこの暗い水の中にいる。なりふり構わずにもがいていないと、溺れてしまうのだ。
その日から、胡桃の成績はぐんっと良くなった。だけど、胡桃は優等生だから、誰にも疑われることはなかった。
今までの積み重ねがようやく実を結んだ。
そう、思ってしまったのだ。