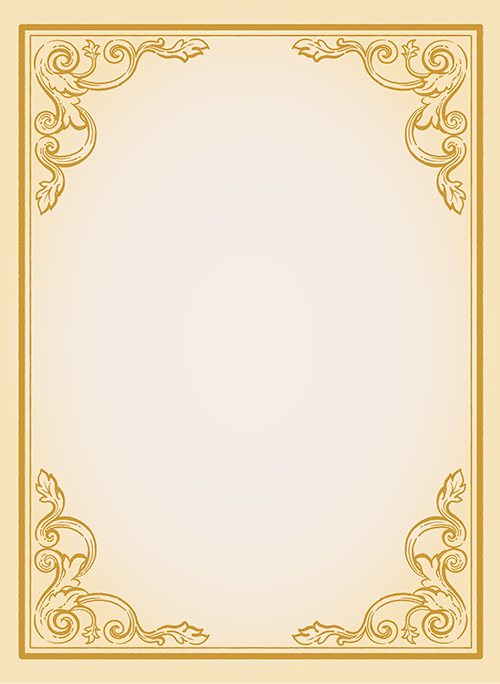一年が経ち、胡桃は小学六年生になった。兄は高校二年生。どうやら、兄は進学する大学を決めた――正しくは母に決められたらしい。家に帰ってきても、ただ勉が終われば兄はすぐ自室に籠って勉強漬けの日々で、顔を合わせることが減った。
兄はやればやるだけ成績を上げていく人だ。だから、最初は芳しくなかった模試の結果がぐんぐんと良くなっていくのを、胡桃は傍で見続けることになった。
「胡桃、四問間違えたから、四時間ね。全く、いつもいつもこんなレベルの低い問題を間違えて。お兄ちゃんを見習ってちょうだい」
尊敬と同時に劣等感が大きくなっていく。それでも、胡桃は兄のことが大好きだ。幼い頃から共通の敵を相手に共闘する仲間であり、いつも胡桃のことを気遣ってくれる優しい兄だから。
母は、敵だ。
絶対的な支配者で、逆らうことは許されない。物心が付く前から植え付けられた、この家のおかしな常識とやらが、歯向かうことを拒絶する。どうやったって倒すことの不可能な敵なのだ。
でも、結果だけに目を向ければ、母のやっていることは正しいのではないだろうか。勉強することも礼儀も外での振る舞い方も、全て母に躾けられたことだ。
胡桃は学年で上位の成績を維持できているし、何より優等生としての立場を得ることが出来ている。兄は難関高校に受かり、次は難関大学の受験すら乗り越えようとしているのだ。
親御さんの育て方がいいのね。そんなことを言われた回数は数え切れない。だから、優秀な子育てをする母を敵対視する胡桃は間違っているのだろう。
だって、結果が全てだ。この考え方も、母譲り。対外的には正しい母に教わったことなのだから。
優秀過ぎる両親から生まれ、その血筋が間違いでないことを証明し続ける兄を持ち、誰もがその兄の歩んだ功績を胡桃も辿るのだと確信している。もちろん、胡桃も嫌々だが、母の言うことを今まで通り聞いて、結局、敷かれたレールの上を歩くのだろうと思っていた。
しかし、胡桃は中学受験に失敗した。結果、市内の公立中学校に進学することになった。
受験校に落ちたことが分かった日の母の説教は、思い返すのもおぞましい。初めて肉体的な痛みを伴うこともされた。
この頃からだろう。胡桃が自らの能力に翳りを感じるようになったのは。
どれだけ勉強をしても、成績が一定のところよりも上がらなくなった。兄はこんなところで躓かなかったので、母はとても呆れていた。
どれだけ勉強をしても、テストが満点になることはないし、学年順位はいつも五番くらいをさまよっているのだから、本当に自分が欠陥品のように思えて酷く焦った。
受験に成功して、周りの人たちも頭がいいのであれば、胡桃も母も納得は出来たはずだ。しかし、胡桃の通うのは公立中学。こんな狭い箱庭ですら一番になれないのだから、胡桃は本当にどうしようもない人間なのだ。
初めて生まれる家を間違えたと思った。だって、これが他の家庭なら、きっと胡桃はちゃんと褒めてもらえる。認めてもらえるはずだ。
それなのに、胡桃が母から投げかけられる言葉には、称賛は一切含まれていなかった。兄でさえ、母に褒められたことなんて数えるくらいしかないのに、その兄よりもずっと劣る胡桃が母から認めてもらえるはずがないのは当然だ。
もちろん、ただ勉は胡桃が中学生になっても続いた。しかし、受験シーズンの兄が、模試の結果が悪ければ夜通しただ勉をしているのを見れば、たかが数時間の拘束で済む胡桃はマシな方だ。
でも、兄には申し訳なく思う。
「何を謝ることがあるんだ?」
嫌な顔一つせずに黙々とペンを走らせていた兄は、胡桃の謝罪に首を傾げた。
「だって、私が駄目な子のせいで、お兄ちゃんが余計に勉強することになってる……」
中学受験に失敗してから、胡桃に向ける母の目が明らかに変わった。関心を持たれなくなったように感じる。きっと、母は胡桃に幻滅して、諦めたのだと思う。胡桃に抱いていた期待を母は全て兄へと向けたから、胡桃の分まで兄が苦しむことになった。
立ちっぱなしは数時間でさえ、果てしなく辛い。歩き続けていた方が楽なくらいだ。それを兄は朝まで。しかもその間、食事も水分補給も許されない。
兄の苦痛を胡桃が理解するのは不可能だし、負担を押し付けたくせにおこがましい話だ。だから、ただただ胡桃は謝ることしか出来ない。
「俺なら大丈夫だよ。だって、胡桃よりも五個も上だぜ? それに、俺はクラスの我慢大会にも優勝したくらい、辛抱強いからさ」
冗談交じりに笑って見せる兄は、胡桃には遠い存在に思えた。一番近くて、胡桃の理解者なのに、どうやったって胡桃は兄に追い付くことが出来ない。
だけど、兄にはずっとそうであってほしいと願っている。いつか、兄が胡桃のことを救ってくれるはずだから。
「人にはさ、キャパってもんがあるんだよ」
「キャパ?」
胡桃が訊き返すと、兄はチラッとリビングへと続くドアを見た。そして、母が様子を見に来ないよう、声を一層潜める。
「キャパシティーのこと。耐久度って言うのかな。持久走とかだと分かりやすいのかも。一キロで辛いと思う人もいれば、十キロ走っても余裕な人だっている。もちろん、慣れとか鍛えることで、キャパは増えるんだろうけど、元の器の大きさは人によって違う。きっと、俺は心の器が最初から胡桃よりもずっと大きい。だから、俺は胡桃が考えているよりも辛くはないよ」
「本当に?」
兄は胸を張って大袈裟に答える。
「もちろん。だって、俺は胡桃の兄貴だぜ? 謝るんじゃなくて、素直に頼ってくれた方が兄としては嬉しいよ」
「……そっか。じゃあ、ありがとうだね」
「おう!」
やっぱり、兄はすごい。
「俺さ、大学は東京なんだよ。胡桃も高校は東京の学校を選んでみたら? それとなく母さんを誘導してさ。そうすれば、俺たちここから抜け出せるじゃん。流石に母さんも東京まではついてこないだろうし」
想像してみて、自然と頬が緩んだ。大好きな兄と東京で暮らせる。母のいない家に帰ることが出来る。それって、胡桃にとって本当に幸せなことだ。
「お兄ちゃん、もしかして天才!?」
受験に失敗する心配を少しもしていないのが兄らしいが、この夢のためなら、胡桃も今まで以上に頑張ることが出来る。だって、絶対に実現したい。そのためなら、こんな陰鬱な日々も簡単に耐えられる。
「で、俺が大学を卒業したら親とは縁を切る。胡桃の大学費用は俺が何とかするからさ。これで、やっと俺たちは自由になれるんだ」
「すごい! すごい! うわーっ、ドキドキしてきた。心臓バクバクしてる」
「ははっ、分かる。俺も思い付いた時、何て言うのかな、濃い霧が一瞬で吹き飛んでいったみたいな感じで、めっちゃ興奮した」
この胸の高鳴りは、きっと胡桃と兄にしか分からない特別なものだ。
何も心配はいらない。だって、兄はいつだってすごいんだ。叶うに決まっている。
東京か……一体、どんな生活が待っているんだろう。
放課後に友達と寄り道とか出来るのかな?
そうだ、バイトもしてみたい。パン屋かカフェがいいなぁ。
家に帰ったら、兄と一緒に出来立ての温かいご飯を食べる。
考えるだけでワクワクが止まらない。
兄も同じような妄想に耽っていたのだろう。胡桃と兄は視線が交わると、互いに声を立てずに静かに笑い合った。
その日の日記には、『夢が出来た。楽しみ』という無邪気な一文を添えておいた。
兄はやればやるだけ成績を上げていく人だ。だから、最初は芳しくなかった模試の結果がぐんぐんと良くなっていくのを、胡桃は傍で見続けることになった。
「胡桃、四問間違えたから、四時間ね。全く、いつもいつもこんなレベルの低い問題を間違えて。お兄ちゃんを見習ってちょうだい」
尊敬と同時に劣等感が大きくなっていく。それでも、胡桃は兄のことが大好きだ。幼い頃から共通の敵を相手に共闘する仲間であり、いつも胡桃のことを気遣ってくれる優しい兄だから。
母は、敵だ。
絶対的な支配者で、逆らうことは許されない。物心が付く前から植え付けられた、この家のおかしな常識とやらが、歯向かうことを拒絶する。どうやったって倒すことの不可能な敵なのだ。
でも、結果だけに目を向ければ、母のやっていることは正しいのではないだろうか。勉強することも礼儀も外での振る舞い方も、全て母に躾けられたことだ。
胡桃は学年で上位の成績を維持できているし、何より優等生としての立場を得ることが出来ている。兄は難関高校に受かり、次は難関大学の受験すら乗り越えようとしているのだ。
親御さんの育て方がいいのね。そんなことを言われた回数は数え切れない。だから、優秀な子育てをする母を敵対視する胡桃は間違っているのだろう。
だって、結果が全てだ。この考え方も、母譲り。対外的には正しい母に教わったことなのだから。
優秀過ぎる両親から生まれ、その血筋が間違いでないことを証明し続ける兄を持ち、誰もがその兄の歩んだ功績を胡桃も辿るのだと確信している。もちろん、胡桃も嫌々だが、母の言うことを今まで通り聞いて、結局、敷かれたレールの上を歩くのだろうと思っていた。
しかし、胡桃は中学受験に失敗した。結果、市内の公立中学校に進学することになった。
受験校に落ちたことが分かった日の母の説教は、思い返すのもおぞましい。初めて肉体的な痛みを伴うこともされた。
この頃からだろう。胡桃が自らの能力に翳りを感じるようになったのは。
どれだけ勉強をしても、成績が一定のところよりも上がらなくなった。兄はこんなところで躓かなかったので、母はとても呆れていた。
どれだけ勉強をしても、テストが満点になることはないし、学年順位はいつも五番くらいをさまよっているのだから、本当に自分が欠陥品のように思えて酷く焦った。
受験に成功して、周りの人たちも頭がいいのであれば、胡桃も母も納得は出来たはずだ。しかし、胡桃の通うのは公立中学。こんな狭い箱庭ですら一番になれないのだから、胡桃は本当にどうしようもない人間なのだ。
初めて生まれる家を間違えたと思った。だって、これが他の家庭なら、きっと胡桃はちゃんと褒めてもらえる。認めてもらえるはずだ。
それなのに、胡桃が母から投げかけられる言葉には、称賛は一切含まれていなかった。兄でさえ、母に褒められたことなんて数えるくらいしかないのに、その兄よりもずっと劣る胡桃が母から認めてもらえるはずがないのは当然だ。
もちろん、ただ勉は胡桃が中学生になっても続いた。しかし、受験シーズンの兄が、模試の結果が悪ければ夜通しただ勉をしているのを見れば、たかが数時間の拘束で済む胡桃はマシな方だ。
でも、兄には申し訳なく思う。
「何を謝ることがあるんだ?」
嫌な顔一つせずに黙々とペンを走らせていた兄は、胡桃の謝罪に首を傾げた。
「だって、私が駄目な子のせいで、お兄ちゃんが余計に勉強することになってる……」
中学受験に失敗してから、胡桃に向ける母の目が明らかに変わった。関心を持たれなくなったように感じる。きっと、母は胡桃に幻滅して、諦めたのだと思う。胡桃に抱いていた期待を母は全て兄へと向けたから、胡桃の分まで兄が苦しむことになった。
立ちっぱなしは数時間でさえ、果てしなく辛い。歩き続けていた方が楽なくらいだ。それを兄は朝まで。しかもその間、食事も水分補給も許されない。
兄の苦痛を胡桃が理解するのは不可能だし、負担を押し付けたくせにおこがましい話だ。だから、ただただ胡桃は謝ることしか出来ない。
「俺なら大丈夫だよ。だって、胡桃よりも五個も上だぜ? それに、俺はクラスの我慢大会にも優勝したくらい、辛抱強いからさ」
冗談交じりに笑って見せる兄は、胡桃には遠い存在に思えた。一番近くて、胡桃の理解者なのに、どうやったって胡桃は兄に追い付くことが出来ない。
だけど、兄にはずっとそうであってほしいと願っている。いつか、兄が胡桃のことを救ってくれるはずだから。
「人にはさ、キャパってもんがあるんだよ」
「キャパ?」
胡桃が訊き返すと、兄はチラッとリビングへと続くドアを見た。そして、母が様子を見に来ないよう、声を一層潜める。
「キャパシティーのこと。耐久度って言うのかな。持久走とかだと分かりやすいのかも。一キロで辛いと思う人もいれば、十キロ走っても余裕な人だっている。もちろん、慣れとか鍛えることで、キャパは増えるんだろうけど、元の器の大きさは人によって違う。きっと、俺は心の器が最初から胡桃よりもずっと大きい。だから、俺は胡桃が考えているよりも辛くはないよ」
「本当に?」
兄は胸を張って大袈裟に答える。
「もちろん。だって、俺は胡桃の兄貴だぜ? 謝るんじゃなくて、素直に頼ってくれた方が兄としては嬉しいよ」
「……そっか。じゃあ、ありがとうだね」
「おう!」
やっぱり、兄はすごい。
「俺さ、大学は東京なんだよ。胡桃も高校は東京の学校を選んでみたら? それとなく母さんを誘導してさ。そうすれば、俺たちここから抜け出せるじゃん。流石に母さんも東京まではついてこないだろうし」
想像してみて、自然と頬が緩んだ。大好きな兄と東京で暮らせる。母のいない家に帰ることが出来る。それって、胡桃にとって本当に幸せなことだ。
「お兄ちゃん、もしかして天才!?」
受験に失敗する心配を少しもしていないのが兄らしいが、この夢のためなら、胡桃も今まで以上に頑張ることが出来る。だって、絶対に実現したい。そのためなら、こんな陰鬱な日々も簡単に耐えられる。
「で、俺が大学を卒業したら親とは縁を切る。胡桃の大学費用は俺が何とかするからさ。これで、やっと俺たちは自由になれるんだ」
「すごい! すごい! うわーっ、ドキドキしてきた。心臓バクバクしてる」
「ははっ、分かる。俺も思い付いた時、何て言うのかな、濃い霧が一瞬で吹き飛んでいったみたいな感じで、めっちゃ興奮した」
この胸の高鳴りは、きっと胡桃と兄にしか分からない特別なものだ。
何も心配はいらない。だって、兄はいつだってすごいんだ。叶うに決まっている。
東京か……一体、どんな生活が待っているんだろう。
放課後に友達と寄り道とか出来るのかな?
そうだ、バイトもしてみたい。パン屋かカフェがいいなぁ。
家に帰ったら、兄と一緒に出来立ての温かいご飯を食べる。
考えるだけでワクワクが止まらない。
兄も同じような妄想に耽っていたのだろう。胡桃と兄は視線が交わると、互いに声を立てずに静かに笑い合った。
その日の日記には、『夢が出来た。楽しみ』という無邪気な一文を添えておいた。