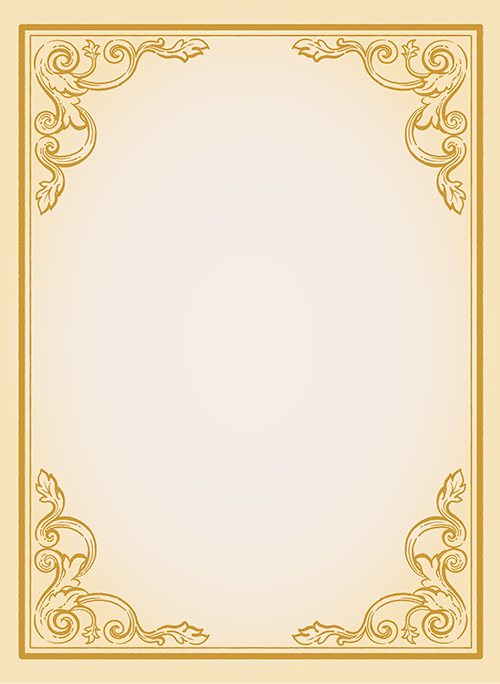◇
「うわっ、なんすか、これ……」
傍から聞こえた燿の唖然とした声で、胡桃は我に返った。瞬間、目の前がチカチカと明滅する。肩から鞄がずり落ちて、よろけたところをいつの間にか来ていた龍之介に支えられた。
「おい、大丈夫かよ」
「す、すみません……」
怪訝な面持ちの龍之介は胡桃に目をやりながらも、やはり織音のことが気がかりのようで、ちらっと視線を上げる。
立ちすくむ胡桃たちの横をすり抜け、凪が俯いたまま織音から一番遠い席へと何も言わずに座った。まるで状況を理解しているような振る舞いに、胡桃は先日の織音の言葉を思い出す。
――ストーカーしてたならさ、全部知ってるんでしょ?
つまり、これが織音の隠していた秘密……。きっと、スマホの写真フォルダにかかったパスワードを開いた先の光景が、この状況なのだろう。
教卓に横たわる血まみれのカラスは、教室の最奥からでも既に生きていないことが窺えた。
「それ、カラスの死骸っすよね。どこで拾ってきたんすか、汚い」
「あたしが殺したんだけど?」
何の躊躇いもなく言い退けた織音に、燿は顔を引きつらせる。
「座っとけ」
龍之介に腕を引かれ、胡桃は椅子に腰を下ろす。まだ足が震えて上手く立っていられなかったし、ズキズキとした頭痛が酷かった。胃はむかむかして、冷や汗も止まらない。けれど今の胡桃には、この惨劇を見守るしかなかった。
「ごめんなさい……ごめんなさい……」
気が付けば、そんな呟きが自分の口から零れていた。
「お、おい……」
龍之介に声をかけられ、我に返る。
「あっ……だ、大丈夫です……」
脳裏に滞留する過去のトラウマを振り払い、震える唇をきゅっと結ぶ。
「染井先輩、まさかのサディストっすか。また強烈なのが来ましたね。でも、ちょっと似合っていますよ」
燿がぎこちなく笑みを浮かべる。ただし、依然引きつった口元を見れば、それが強がりだということが見て取れた。
「秘密にはしてたけどさ、別にバレたからなんだって感じ。言う必要がなかっただけだし、こんなの知ったらそっちが気を遣うでしょ?」
カラスの翼を撫でる織音の手つきは優しく、彼女の表情は慈愛に満ちていた。本当に彼女がやったのか疑わしいくらいだ。
「とにかく、不快なんでさっさと片してもらえます? すっごい臭いし」
何も言わずに近付いて来る織音に、燿は一歩後ずさる。織音は燿の手に持つ龍之介のスマホ――織音のスマホの中身が入った端末を奪い取り、画面をこちらに向けた。
「あんたが一番知りたがってたじゃん、燿。ほら、もっとあたしの秘密を見なよ」
その画面を見て、胡桃は小さく悲鳴を漏らす。数え切れない程の小動物の死骸を写した写真だった。
これには流石の燿も言葉を詰まらせてたじろぐ。
「除草剤とか下剤入りの餌を食べさせて動けなくして、腹を裂くか、頭を砕くか、首をへし折るか。どれでもいいんだけどね。でも、それだけ」
織音の抑揚のない声色と、恐ろしいまでの異彩な雰囲気に、誰も動けなかった。ゆっくりと近づいて来る織音から、なぜか目が離せない。
どうして、織音はこんなにも孤独が似合ってしまうのだろうか。
周りに誰かがいる。それだけで、織音の魅力は失われてしまう。彼女は独りだからこそ、輝ける。
でも、それってとても悲しいことだ。
胡桃の隣で、燿は織音に怯えながらも弱々しく嗤った。
「染井先輩……あんたがずば抜けてやべぇっすわ」
「そんなのあたしが一番よく分かってる」
ふと、織音と目が合う。その時、胡桃は織音の瞼が薄っすら赤く腫れていることに気が付いた。多分、泣いた跡だ。
「染井、お前何考えてんだよ。普通じゃねえよ」
龍之介が織音と燿の会話に割り入る。
「あたしはカラスとか鼠みたいな小さな動物が限界。あんたみたいに人に暴力を振るったりはしないけど?」
「……そういう話をしてんじゃねぇ」
「何が違うの? じゃあ、あんたは何を考えて人に暴力を振るっているの? 教えてよ」
毅然とした態度で龍之介を睨む織音。
燿も、龍之介も、織音には敵わない。それだけ、彼女はこの五人の中で――いや、この学校の中で際立って異質で、特別だった。
気圧される胡桃たちを見つめ、織音は小さくため息を零した。
「あのさ、燿みたいに自己満足のために人の作品を台無しにする行為も、龍之介のやっぱりねっていう行動も、どっちもあたしのこれよりずっと馬鹿だと思うんだけど? あたし、誰にも迷惑かけてないし。あんたらの方がよっぽど罪深いでしょ。他人の人生の足引っ張る奴、あたし死ぬ程嫌いなんだよね」
矢継ぎ早に話す織音の表情は薄い。この状況に辟易している。胡桃にはそんな風に見えるが、きっとそれは胡桃が自らの心情に引っ張られているに過ぎないのだろう。
もう何日も、ずっと頭が重たい。気を抜けば、弱気になってしまう。
織音が燿の左足を指さす。その仕草に胡桃は嫌な予感がした。そして、彼女は触れてはいけないところまで手を伸ばすように口を開く。
「それ、龍之介を庇った結果でしょ?」
「な、なんで、それを……」
そこまで言って、燿は何かに気が付いたのか、唇を噛んで顔を歪ませる。
「『あいつのせいで、僕は』、『なんで、あいつのために僕がこんな目に』。裏垢なら、パスワードかけなって。学ばないね」
多分、織音は燿のアカウントを遡って、彼が怪我をした原因に辿り着いたのだろう。胡桃が見た時も、燿の投稿はやけに龍之介への不満が多かった。時には、胡桃たちに向けるものよりずっと感情の籠った文章も見受けられた。
――僕にちょっとでも罪悪感があるなら、出ろよ!
――燿がああなったのは、多分俺のせいだからよ。
胡桃の中で引っかかっていた燿と龍之介の発言も、織音の仮説が正しいのであれば納得がいく。
「それで、僕の怪我の原因が分かったから、何だって言うんですか?」
織音はカラスの死骸を見下ろし、ややあって言った。
「燿は自分が犠牲になってでも、龍之介を守りたかったってことだよね……。それって、愛なの? そうなら、あたしには理解できない。あたしなら絶対に自分を犠牲にしたりなんかしないから。……ねえ、教えてよ。愛を見せた対価に自由な足も、将来も――たくさんのものを失って、燿は今どんな気持ちなの?」
「そんなの知って、何になるんすか。染井先輩には何も関係ないことっすよ。そもそも、愛って。ははっ、重た過ぎでしょ」
軽い口調の燿だが、その表情は苦しそうに見える。まるで、聞かれたくないことを聞かれたとでも言いたげだった。
「後悔してるの?」
「ええ、めちゃくちゃしてますよ。人生で一番の後悔です。今後この後悔を超える出来事なんてもう起きないって断言できるくらい」
胡桃の傍らで、龍之介が舌打ちをする。それを眺め、織音は少し残念そうに息を吐いた。
「やっぱり、そうなんだ……。燿、可哀想だね。同情するよ」
そう言った織音に、燿は憤りを見せた。
「いらないっすよ、そんなの。同情するくらいなら、僕よりも不幸になってくださいよ。みんなそうやって口ばっかりで、結局、僕のために何かを犠牲にしてはくれないんだ」
「……あたしが幸せに見えるのなら、あんたはまだ十分に幸せだよ」
織音の声色が一段と低くなる。それが、一層彼女の深い闇を窺わせた。
織音に気圧された燿は、苦し紛れに話題を元に戻す。
「は、犯罪っすからね。動物を殺すのだって、犯罪だ! むしろ、倫理観で言ったら僕や凪先輩よりも酷い! 龍之介先輩と染井先輩は、僕から見れば同類っすよ! どっちも幸せなくせに誰かの足を引っ張ってる」
じっと織音は燿を見つめる。そこには怒りも、悲しみもない。だからこそ、胡桃は純粋に恐怖を感じた。織音を前にすると、感情を分かりやすく見せる燿はやけに子供のように思える。
「俺をこんなのと一緒にすんな」
龍之介が織音を指さして言う。
「一緒でしょうが。それに、凪先輩も大概っすからね。染井先輩がこんな人だって知っていて、それでもストーカーや盗聴するくらい好きだなんて、凪先輩もおかしいっすよ!」
俯いて沈黙をかざす凪に、燿は苛立ちをぶつける。
「黙ってないで、何とか言ってくださいよ」
すると、突然凪が勢いよく立ち上がった。引かれた椅子がけたたましい音を立てる。
そして、凪は逡巡する燿を脇目に、胡桃へと自らのスマホを差し出した。その画面が煌々と光を放っているのを見て、胡桃は思わず息を呑む。見慣れた背景とホーム画面。間違いなく、胡桃のものだった。
「……何、やってんすか? それに、その画面……」
「僕、何も見てないから」
それだけ言い残し、凪が逃げるように背を向けた。
「帰っちゃ駄目っすよ。逃げたら学校中にも、親にも、全部バラしますからね」
今、まさにドアに手をかけていた凪に燿が釘を刺す。
「僕はもう関係ないじゃないか……」
「そんなわけないでしょ。まだ終わってないんすよ。自分だけ逃げて楽になって、そんなの許されるわけがないでしょ。ここで逃げたら、染井先輩とは本当にお終いですよ?」
「だって、どうしたらいいのか分からないんだよ……」
狼狽する凪だが、織音は一貫して冷たい表情のままだ。しかし、織音の血に染まる手が、僅かに力が籠るのを胡桃は見逃さなかった。
凪を突き放した織音だったが、もしかしたら彼女の中ではまだほんの少し、迷いの糸が残っているのかもしれない。
「そうやって考えることから逃げるの、いい加減やめてくださいよ。何で助け船だって分からないのかな。イライラするんすけど」
燿は自らの頭を乱暴にかきむしり、戦慄く。そして、胡桃に向けて手を差し向けた。
「スマホ、貸してください」
「……どうして?」
「当たり前じゃないっすか。この中で秘密がバレてないの胡桃先輩だけっすよ。どうせ、あるんでしょ? みんなに見せたくないものが」
忙しなく脈打つ心臓の音が聞こえていないか心配だった。それでも、なるべく顔に出さないように努めるが、燿には通用しなかったようで、彼は眉をひそめる。
「ほら、見られたくないものがあるから渡せないんだ」
その時、胡桃に詰め寄る燿の腕を織音が掴んだ。
「邪魔しないでくださいよ」
「あたしは見たくない」
二人は睨み合うように視線を交わらせる。燿も織音の放つ圧に慣れたのか、もう彼女から目を逸らそうとはしなかった。
「じゃあ、染井先輩も帰ればいいじゃないですか。僕は許しませんよ。胡桃先輩だけが逃げ切るのは。それに、これだけ予想外のことが続いてるんすよ。もしかしたら、胡桃先輩の秘密はみんなの秘密よりもっとエグいかもしれないじゃないっすか」
「……だから、何? 今まで、胡桃がどれだけこの連鎖を終わらせようと声を上げ続けていたのか分かってるよね。そんな人間のことすら信じられないなんて、どうかしてるよ」
燿が織音の手を振り払う。
「だから、自分のスマホの中にも見られちゃいけないものがあるから、必死に止めようとしてたんでしょ」
「そうだとしても、胡桃の秘密を知ったって何も起きないの」
「本当にそう言えるんすか? 凪先輩の秘密を知ったせいで、染井先輩は傷付いた。もしかしたら、胡桃先輩の抱えている秘密だって、僕たちに大きく関わる何かかもしれないじゃないですか」
「それこそ、あたしは知りたくない。知らなかったら、これ以上酷くはならないんだから」
「もうどうにもならないくらい、十分酷いじゃないっすか!」
過熱する二人の言い争いの一つ一つが、胡桃の胸に破片として突き刺さる。
「それとも何すか。まだ今なら元通りになるとでも思ってるんですか? 五人仲良しこよしして、上っ面だけで会話してたあの頃に戻って満足なわけがないでしょ。あんたを裏切り続けていた奴と、もう一度友達になりたいだなんて言えないですよね、織音先輩?」
瞬間、織音の目が見開かれる。
鋭く冷たい静寂に、肌が粟立つ。
「ねえ、その名前で呼ぶなって、最初に言ったよね? あたしを怒らせて、一体何がしたいの?」
織音が一歩、燿へと詰め寄る。
「お、おい、二人とも落ち着けって」
胡桃よりも先に、龍之介が慌てて二人を止めに入った。
「染井、変な気起こすなよ?」
「変な気って? 龍之介がやったみたいに、あたしが燿に暴力を振るうとでも思ってんの?」
龍之介は何も言わなかった。それが、織音の発言への肯定と捉えられるのは必然だ。
「さっきも言ったけど、あたしは人に暴力なんて振るわないから。それより、あんたがみんなを暴力で黙らせる方が可能性高いんじゃない?」
「俺はそんなことしねぇよ」
「説得力ないんだっつーの」
あぁ、そっか。これって、私のせいでみんなが揉めているんだ。
まだ観客席にいる胡桃を舞台に引きずり出したがっているのは燿だけなのに、どうしてか全員が対立している。まるで、絡み合ってしまった糸くずみたいだ。時間がかかる程、複雑になって余計にほどけなくなる。
無意識にスマホを握る手に力が籠っていた。崩れていく五人の関係を目の当たりにして、まだ保身に走る自分の愚かさに心底落胆する。でも、このまま何も言わなくても、きっと燿以外の三人は胡桃のことを責めてはくれない。
スマホを見られるわけにはいかないけれど、口汚く罵倒されて自分はただの被害者でありたいって、とても傲慢だ。
あの時、燿のスマホの中身を見なければ、こんなことにはならなかったかもしれない。みんなが凪のスマホの中身を暴こうとするのを、必死に止めていれば良かったのに。胡桃が燿の秘密を黙っておくだけで、まだ五人は友人でいられた。
だけど、燿の言う通り、そんなの上っ面の関係だ。きっと、どこかで綻びが生まれていたに違いない。それが、たまたま今回のスマホの中身が入れ替わってしまうという不運な出来事だっただけのことだ。
「――いいよ」
無意識に口を衝いて出ていた。
震える胡桃の声は、全員の意識を一斉に引き寄せる。
みんなから向けられる色々な感情が、とても怖い。今から自分を曝け出すのだと思うと、逃げ出しそうになる。
でも、もう自分だけが逃げ続けるのは嫌だった。
自らが傷付きながらも胡桃を思ってくれる織音と龍之介の気持ちも、全員平等に罰を受け入れるべきだという燿の気持ちも、痛い程よく分かる。
スマホを机の上に置き、一歩下がる。
もう、優等生はお終いだ。
「胡桃……」
織音が目で、いいの? と訴えかけてくる。だから、小さく頷いた。
一人ずつ、全員とじっくり目を合わせる。不思議と、みんな何も言わなかった。ただ、胡桃の言葉を待っている。
一瞬だけ、胡桃たちは元通りになれたような気がした。懐かしさすら感じる空気に、身体の震えが治まる。
「私も、みんなと対等でありたい。だから、もう終わらせようよ」
綺麗ごとなんかじゃない。これは、胡桃の本心だ。
「その代わり、ちゃんとぶつかり合おう。私も全部見せる。言いたいことも、今から全部ちゃんと隠さないで話す。みんなも知られちゃいけないことを知られちゃったかもしれない。だけど、まだ隠している本音があるよね? 伝え切れていないこともあるよね。だから、全員、空っぽになるまで吐き出そうよ」
どんな結末になろうと、それでもきっとこれが正解だ。
「……分かったよ。あたしは元々、そうしたいって言ったもんね」
織音はそう言い、ようやく凪へと目を向けた。その視線を凪は咄嗟に逸らしたものの、泣きそうになりながら、もう一度織音を見つめ返す。
「ぼ、僕も……ちゃんと話したい。そうしないと、本当に後悔すると思うから……」
織音と凪のやり取りに、燿は歯を食いしばって葛藤しているようだった。正直、燿は素の自分を既に見せているし、二つ返事だと思ったが、どうやら彼にもまだ言えていないことがあるらしい。
スマホの中にはその人の真実が眠っている。だけど、結局、腹の内の全てをそこに詰め込んでいるわけじゃない。言いたいことはスマホ越しじゃなくて、ちゃんと本人の口で言うしかない。
そして、ややあって燿は決心したのか、口元の力を緩める。
「はぁ……分かりましたよ。それでいいです。ただし、胡桃先輩のスマホの中身はちゃんと見ますからね」
胡桃は確かに頷いた。もちろん、約束を違えたりはしない。
「じゃあ、見ますよ?」
全員が机を取り囲むように輪になる中、燿がスマホに手を伸ばす。その瞬間、
「――駄目だ」
黙っていた龍之介が声を発する。その言葉に、胡桃はまた足元がすっとなくなって落ちる感覚に襲われた。
「どうして……」
思わず、胡桃はそう呟いてしまう。一つになろうとしていたみんなの想いが、胡桃の一言に詰まっていた。
「俺は絶対に何も話さねぇ」
輪から外れる龍之介からは、決然とした意志を感じる。
「……またそうやって、一匹狼を気取るんですか?」
燿の声には、僅かな悲しさが孕んでいた。きっと、燿が一番本音をぶつけたいのは龍之介のはずだ。だから、胡桃の提案に乗ると決意した燿からすれば、龍之介の行動は受け入れがたいものだったのだろう。
「何を言われても、俺はお前らに――燿だけには話さねぇ」
そう告げ、龍之介は美術室を出る。その背を追いかけるように、燿と胡桃は廊下に飛び出した。
「待って!」
胡桃の懇願も虚しく、龍之介の姿が遠ざかっていく。走れば追い付けたけど、足を引きずる燿を追い越すことを、胡桃は躊躇ってしまった。
「逃げるな! ふざけないでくださいよ……。これ以上、僕の理想から遠ざかるな!」
燿の悲痛な叫びだった。
龍之介が一瞬、動きを止める。それでも、龍之介が振り返ることはなかった。
「うわっ、なんすか、これ……」
傍から聞こえた燿の唖然とした声で、胡桃は我に返った。瞬間、目の前がチカチカと明滅する。肩から鞄がずり落ちて、よろけたところをいつの間にか来ていた龍之介に支えられた。
「おい、大丈夫かよ」
「す、すみません……」
怪訝な面持ちの龍之介は胡桃に目をやりながらも、やはり織音のことが気がかりのようで、ちらっと視線を上げる。
立ちすくむ胡桃たちの横をすり抜け、凪が俯いたまま織音から一番遠い席へと何も言わずに座った。まるで状況を理解しているような振る舞いに、胡桃は先日の織音の言葉を思い出す。
――ストーカーしてたならさ、全部知ってるんでしょ?
つまり、これが織音の隠していた秘密……。きっと、スマホの写真フォルダにかかったパスワードを開いた先の光景が、この状況なのだろう。
教卓に横たわる血まみれのカラスは、教室の最奥からでも既に生きていないことが窺えた。
「それ、カラスの死骸っすよね。どこで拾ってきたんすか、汚い」
「あたしが殺したんだけど?」
何の躊躇いもなく言い退けた織音に、燿は顔を引きつらせる。
「座っとけ」
龍之介に腕を引かれ、胡桃は椅子に腰を下ろす。まだ足が震えて上手く立っていられなかったし、ズキズキとした頭痛が酷かった。胃はむかむかして、冷や汗も止まらない。けれど今の胡桃には、この惨劇を見守るしかなかった。
「ごめんなさい……ごめんなさい……」
気が付けば、そんな呟きが自分の口から零れていた。
「お、おい……」
龍之介に声をかけられ、我に返る。
「あっ……だ、大丈夫です……」
脳裏に滞留する過去のトラウマを振り払い、震える唇をきゅっと結ぶ。
「染井先輩、まさかのサディストっすか。また強烈なのが来ましたね。でも、ちょっと似合っていますよ」
燿がぎこちなく笑みを浮かべる。ただし、依然引きつった口元を見れば、それが強がりだということが見て取れた。
「秘密にはしてたけどさ、別にバレたからなんだって感じ。言う必要がなかっただけだし、こんなの知ったらそっちが気を遣うでしょ?」
カラスの翼を撫でる織音の手つきは優しく、彼女の表情は慈愛に満ちていた。本当に彼女がやったのか疑わしいくらいだ。
「とにかく、不快なんでさっさと片してもらえます? すっごい臭いし」
何も言わずに近付いて来る織音に、燿は一歩後ずさる。織音は燿の手に持つ龍之介のスマホ――織音のスマホの中身が入った端末を奪い取り、画面をこちらに向けた。
「あんたが一番知りたがってたじゃん、燿。ほら、もっとあたしの秘密を見なよ」
その画面を見て、胡桃は小さく悲鳴を漏らす。数え切れない程の小動物の死骸を写した写真だった。
これには流石の燿も言葉を詰まらせてたじろぐ。
「除草剤とか下剤入りの餌を食べさせて動けなくして、腹を裂くか、頭を砕くか、首をへし折るか。どれでもいいんだけどね。でも、それだけ」
織音の抑揚のない声色と、恐ろしいまでの異彩な雰囲気に、誰も動けなかった。ゆっくりと近づいて来る織音から、なぜか目が離せない。
どうして、織音はこんなにも孤独が似合ってしまうのだろうか。
周りに誰かがいる。それだけで、織音の魅力は失われてしまう。彼女は独りだからこそ、輝ける。
でも、それってとても悲しいことだ。
胡桃の隣で、燿は織音に怯えながらも弱々しく嗤った。
「染井先輩……あんたがずば抜けてやべぇっすわ」
「そんなのあたしが一番よく分かってる」
ふと、織音と目が合う。その時、胡桃は織音の瞼が薄っすら赤く腫れていることに気が付いた。多分、泣いた跡だ。
「染井、お前何考えてんだよ。普通じゃねえよ」
龍之介が織音と燿の会話に割り入る。
「あたしはカラスとか鼠みたいな小さな動物が限界。あんたみたいに人に暴力を振るったりはしないけど?」
「……そういう話をしてんじゃねぇ」
「何が違うの? じゃあ、あんたは何を考えて人に暴力を振るっているの? 教えてよ」
毅然とした態度で龍之介を睨む織音。
燿も、龍之介も、織音には敵わない。それだけ、彼女はこの五人の中で――いや、この学校の中で際立って異質で、特別だった。
気圧される胡桃たちを見つめ、織音は小さくため息を零した。
「あのさ、燿みたいに自己満足のために人の作品を台無しにする行為も、龍之介のやっぱりねっていう行動も、どっちもあたしのこれよりずっと馬鹿だと思うんだけど? あたし、誰にも迷惑かけてないし。あんたらの方がよっぽど罪深いでしょ。他人の人生の足引っ張る奴、あたし死ぬ程嫌いなんだよね」
矢継ぎ早に話す織音の表情は薄い。この状況に辟易している。胡桃にはそんな風に見えるが、きっとそれは胡桃が自らの心情に引っ張られているに過ぎないのだろう。
もう何日も、ずっと頭が重たい。気を抜けば、弱気になってしまう。
織音が燿の左足を指さす。その仕草に胡桃は嫌な予感がした。そして、彼女は触れてはいけないところまで手を伸ばすように口を開く。
「それ、龍之介を庇った結果でしょ?」
「な、なんで、それを……」
そこまで言って、燿は何かに気が付いたのか、唇を噛んで顔を歪ませる。
「『あいつのせいで、僕は』、『なんで、あいつのために僕がこんな目に』。裏垢なら、パスワードかけなって。学ばないね」
多分、織音は燿のアカウントを遡って、彼が怪我をした原因に辿り着いたのだろう。胡桃が見た時も、燿の投稿はやけに龍之介への不満が多かった。時には、胡桃たちに向けるものよりずっと感情の籠った文章も見受けられた。
――僕にちょっとでも罪悪感があるなら、出ろよ!
――燿がああなったのは、多分俺のせいだからよ。
胡桃の中で引っかかっていた燿と龍之介の発言も、織音の仮説が正しいのであれば納得がいく。
「それで、僕の怪我の原因が分かったから、何だって言うんですか?」
織音はカラスの死骸を見下ろし、ややあって言った。
「燿は自分が犠牲になってでも、龍之介を守りたかったってことだよね……。それって、愛なの? そうなら、あたしには理解できない。あたしなら絶対に自分を犠牲にしたりなんかしないから。……ねえ、教えてよ。愛を見せた対価に自由な足も、将来も――たくさんのものを失って、燿は今どんな気持ちなの?」
「そんなの知って、何になるんすか。染井先輩には何も関係ないことっすよ。そもそも、愛って。ははっ、重た過ぎでしょ」
軽い口調の燿だが、その表情は苦しそうに見える。まるで、聞かれたくないことを聞かれたとでも言いたげだった。
「後悔してるの?」
「ええ、めちゃくちゃしてますよ。人生で一番の後悔です。今後この後悔を超える出来事なんてもう起きないって断言できるくらい」
胡桃の傍らで、龍之介が舌打ちをする。それを眺め、織音は少し残念そうに息を吐いた。
「やっぱり、そうなんだ……。燿、可哀想だね。同情するよ」
そう言った織音に、燿は憤りを見せた。
「いらないっすよ、そんなの。同情するくらいなら、僕よりも不幸になってくださいよ。みんなそうやって口ばっかりで、結局、僕のために何かを犠牲にしてはくれないんだ」
「……あたしが幸せに見えるのなら、あんたはまだ十分に幸せだよ」
織音の声色が一段と低くなる。それが、一層彼女の深い闇を窺わせた。
織音に気圧された燿は、苦し紛れに話題を元に戻す。
「は、犯罪っすからね。動物を殺すのだって、犯罪だ! むしろ、倫理観で言ったら僕や凪先輩よりも酷い! 龍之介先輩と染井先輩は、僕から見れば同類っすよ! どっちも幸せなくせに誰かの足を引っ張ってる」
じっと織音は燿を見つめる。そこには怒りも、悲しみもない。だからこそ、胡桃は純粋に恐怖を感じた。織音を前にすると、感情を分かりやすく見せる燿はやけに子供のように思える。
「俺をこんなのと一緒にすんな」
龍之介が織音を指さして言う。
「一緒でしょうが。それに、凪先輩も大概っすからね。染井先輩がこんな人だって知っていて、それでもストーカーや盗聴するくらい好きだなんて、凪先輩もおかしいっすよ!」
俯いて沈黙をかざす凪に、燿は苛立ちをぶつける。
「黙ってないで、何とか言ってくださいよ」
すると、突然凪が勢いよく立ち上がった。引かれた椅子がけたたましい音を立てる。
そして、凪は逡巡する燿を脇目に、胡桃へと自らのスマホを差し出した。その画面が煌々と光を放っているのを見て、胡桃は思わず息を呑む。見慣れた背景とホーム画面。間違いなく、胡桃のものだった。
「……何、やってんすか? それに、その画面……」
「僕、何も見てないから」
それだけ言い残し、凪が逃げるように背を向けた。
「帰っちゃ駄目っすよ。逃げたら学校中にも、親にも、全部バラしますからね」
今、まさにドアに手をかけていた凪に燿が釘を刺す。
「僕はもう関係ないじゃないか……」
「そんなわけないでしょ。まだ終わってないんすよ。自分だけ逃げて楽になって、そんなの許されるわけがないでしょ。ここで逃げたら、染井先輩とは本当にお終いですよ?」
「だって、どうしたらいいのか分からないんだよ……」
狼狽する凪だが、織音は一貫して冷たい表情のままだ。しかし、織音の血に染まる手が、僅かに力が籠るのを胡桃は見逃さなかった。
凪を突き放した織音だったが、もしかしたら彼女の中ではまだほんの少し、迷いの糸が残っているのかもしれない。
「そうやって考えることから逃げるの、いい加減やめてくださいよ。何で助け船だって分からないのかな。イライラするんすけど」
燿は自らの頭を乱暴にかきむしり、戦慄く。そして、胡桃に向けて手を差し向けた。
「スマホ、貸してください」
「……どうして?」
「当たり前じゃないっすか。この中で秘密がバレてないの胡桃先輩だけっすよ。どうせ、あるんでしょ? みんなに見せたくないものが」
忙しなく脈打つ心臓の音が聞こえていないか心配だった。それでも、なるべく顔に出さないように努めるが、燿には通用しなかったようで、彼は眉をひそめる。
「ほら、見られたくないものがあるから渡せないんだ」
その時、胡桃に詰め寄る燿の腕を織音が掴んだ。
「邪魔しないでくださいよ」
「あたしは見たくない」
二人は睨み合うように視線を交わらせる。燿も織音の放つ圧に慣れたのか、もう彼女から目を逸らそうとはしなかった。
「じゃあ、染井先輩も帰ればいいじゃないですか。僕は許しませんよ。胡桃先輩だけが逃げ切るのは。それに、これだけ予想外のことが続いてるんすよ。もしかしたら、胡桃先輩の秘密はみんなの秘密よりもっとエグいかもしれないじゃないっすか」
「……だから、何? 今まで、胡桃がどれだけこの連鎖を終わらせようと声を上げ続けていたのか分かってるよね。そんな人間のことすら信じられないなんて、どうかしてるよ」
燿が織音の手を振り払う。
「だから、自分のスマホの中にも見られちゃいけないものがあるから、必死に止めようとしてたんでしょ」
「そうだとしても、胡桃の秘密を知ったって何も起きないの」
「本当にそう言えるんすか? 凪先輩の秘密を知ったせいで、染井先輩は傷付いた。もしかしたら、胡桃先輩の抱えている秘密だって、僕たちに大きく関わる何かかもしれないじゃないですか」
「それこそ、あたしは知りたくない。知らなかったら、これ以上酷くはならないんだから」
「もうどうにもならないくらい、十分酷いじゃないっすか!」
過熱する二人の言い争いの一つ一つが、胡桃の胸に破片として突き刺さる。
「それとも何すか。まだ今なら元通りになるとでも思ってるんですか? 五人仲良しこよしして、上っ面だけで会話してたあの頃に戻って満足なわけがないでしょ。あんたを裏切り続けていた奴と、もう一度友達になりたいだなんて言えないですよね、織音先輩?」
瞬間、織音の目が見開かれる。
鋭く冷たい静寂に、肌が粟立つ。
「ねえ、その名前で呼ぶなって、最初に言ったよね? あたしを怒らせて、一体何がしたいの?」
織音が一歩、燿へと詰め寄る。
「お、おい、二人とも落ち着けって」
胡桃よりも先に、龍之介が慌てて二人を止めに入った。
「染井、変な気起こすなよ?」
「変な気って? 龍之介がやったみたいに、あたしが燿に暴力を振るうとでも思ってんの?」
龍之介は何も言わなかった。それが、織音の発言への肯定と捉えられるのは必然だ。
「さっきも言ったけど、あたしは人に暴力なんて振るわないから。それより、あんたがみんなを暴力で黙らせる方が可能性高いんじゃない?」
「俺はそんなことしねぇよ」
「説得力ないんだっつーの」
あぁ、そっか。これって、私のせいでみんなが揉めているんだ。
まだ観客席にいる胡桃を舞台に引きずり出したがっているのは燿だけなのに、どうしてか全員が対立している。まるで、絡み合ってしまった糸くずみたいだ。時間がかかる程、複雑になって余計にほどけなくなる。
無意識にスマホを握る手に力が籠っていた。崩れていく五人の関係を目の当たりにして、まだ保身に走る自分の愚かさに心底落胆する。でも、このまま何も言わなくても、きっと燿以外の三人は胡桃のことを責めてはくれない。
スマホを見られるわけにはいかないけれど、口汚く罵倒されて自分はただの被害者でありたいって、とても傲慢だ。
あの時、燿のスマホの中身を見なければ、こんなことにはならなかったかもしれない。みんなが凪のスマホの中身を暴こうとするのを、必死に止めていれば良かったのに。胡桃が燿の秘密を黙っておくだけで、まだ五人は友人でいられた。
だけど、燿の言う通り、そんなの上っ面の関係だ。きっと、どこかで綻びが生まれていたに違いない。それが、たまたま今回のスマホの中身が入れ替わってしまうという不運な出来事だっただけのことだ。
「――いいよ」
無意識に口を衝いて出ていた。
震える胡桃の声は、全員の意識を一斉に引き寄せる。
みんなから向けられる色々な感情が、とても怖い。今から自分を曝け出すのだと思うと、逃げ出しそうになる。
でも、もう自分だけが逃げ続けるのは嫌だった。
自らが傷付きながらも胡桃を思ってくれる織音と龍之介の気持ちも、全員平等に罰を受け入れるべきだという燿の気持ちも、痛い程よく分かる。
スマホを机の上に置き、一歩下がる。
もう、優等生はお終いだ。
「胡桃……」
織音が目で、いいの? と訴えかけてくる。だから、小さく頷いた。
一人ずつ、全員とじっくり目を合わせる。不思議と、みんな何も言わなかった。ただ、胡桃の言葉を待っている。
一瞬だけ、胡桃たちは元通りになれたような気がした。懐かしさすら感じる空気に、身体の震えが治まる。
「私も、みんなと対等でありたい。だから、もう終わらせようよ」
綺麗ごとなんかじゃない。これは、胡桃の本心だ。
「その代わり、ちゃんとぶつかり合おう。私も全部見せる。言いたいことも、今から全部ちゃんと隠さないで話す。みんなも知られちゃいけないことを知られちゃったかもしれない。だけど、まだ隠している本音があるよね? 伝え切れていないこともあるよね。だから、全員、空っぽになるまで吐き出そうよ」
どんな結末になろうと、それでもきっとこれが正解だ。
「……分かったよ。あたしは元々、そうしたいって言ったもんね」
織音はそう言い、ようやく凪へと目を向けた。その視線を凪は咄嗟に逸らしたものの、泣きそうになりながら、もう一度織音を見つめ返す。
「ぼ、僕も……ちゃんと話したい。そうしないと、本当に後悔すると思うから……」
織音と凪のやり取りに、燿は歯を食いしばって葛藤しているようだった。正直、燿は素の自分を既に見せているし、二つ返事だと思ったが、どうやら彼にもまだ言えていないことがあるらしい。
スマホの中にはその人の真実が眠っている。だけど、結局、腹の内の全てをそこに詰め込んでいるわけじゃない。言いたいことはスマホ越しじゃなくて、ちゃんと本人の口で言うしかない。
そして、ややあって燿は決心したのか、口元の力を緩める。
「はぁ……分かりましたよ。それでいいです。ただし、胡桃先輩のスマホの中身はちゃんと見ますからね」
胡桃は確かに頷いた。もちろん、約束を違えたりはしない。
「じゃあ、見ますよ?」
全員が机を取り囲むように輪になる中、燿がスマホに手を伸ばす。その瞬間、
「――駄目だ」
黙っていた龍之介が声を発する。その言葉に、胡桃はまた足元がすっとなくなって落ちる感覚に襲われた。
「どうして……」
思わず、胡桃はそう呟いてしまう。一つになろうとしていたみんなの想いが、胡桃の一言に詰まっていた。
「俺は絶対に何も話さねぇ」
輪から外れる龍之介からは、決然とした意志を感じる。
「……またそうやって、一匹狼を気取るんですか?」
燿の声には、僅かな悲しさが孕んでいた。きっと、燿が一番本音をぶつけたいのは龍之介のはずだ。だから、胡桃の提案に乗ると決意した燿からすれば、龍之介の行動は受け入れがたいものだったのだろう。
「何を言われても、俺はお前らに――燿だけには話さねぇ」
そう告げ、龍之介は美術室を出る。その背を追いかけるように、燿と胡桃は廊下に飛び出した。
「待って!」
胡桃の懇願も虚しく、龍之介の姿が遠ざかっていく。走れば追い付けたけど、足を引きずる燿を追い越すことを、胡桃は躊躇ってしまった。
「逃げるな! ふざけないでくださいよ……。これ以上、僕の理想から遠ざかるな!」
燿の悲痛な叫びだった。
龍之介が一瞬、動きを止める。それでも、龍之介が振り返ることはなかった。