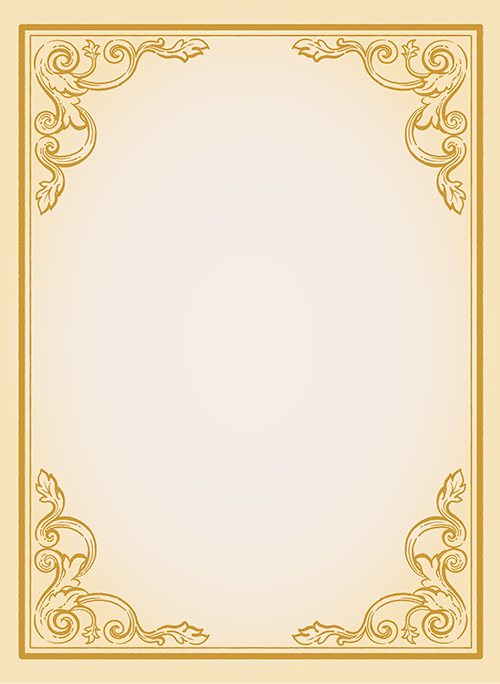織音は小さい頃から絵を描くことが好きだ。なぜなら、両親が描いて見せてくれた絵よりも、織音が描いた絵の方がずっと上手だったからだ。
日常での不満を絵に吐き出せば、どんどんと上手になっていくことが分かった。両親から愛されなければ、ずっと素敵な絵が描ける。
織音にとって、それはとても嬉しいことだった。両親から受け継がれたものじゃない、織音だけの特別な才能だと実感できる。
しかし、高校に入って間もない頃、織音はスランプに陥った。思うように絵が描けない。キャンバスを前にすると、頭が真っ白になる。どうしても、筆を持つ手が動かなかった。
原因は分かっていて、父との暮らしに慣れてしまったからだ。
織音が絵を描く原動力は不満や怒り、焦燥といった感情。きっと、満たされない感情を、絵を描くことによって補っているのだろう。自分の心のことだけど、哀れでヘンテコな理由だ。
中でも一番大きかった親への形容しがたい憤りが、最近では薄れつつある。織音の青い心が成熟するにつれて、感情の自制を覚えてしまった。ある程度、小細工で感情の繕いが出来るようになったせいだ。
外での人間関係に恵まれつつあることも、スランプの主な要因の一つに挙がるだろう。中学来の親友がいる。織音のことを理解して接してくれる同級生や後輩、鼻につくけど先輩もいる。
高校生ともなれば、名前でいじられることもほとんどない。
織音は多数派の高校生になりつつあった。
筆に乗せる感情が尽き、絵を描くことで満たされていた感情がなくなっていってしまう。胸の底に溜まった汚いヘドロが乾いてゆく。愛せていた自分が、どんどん変わっていってしまう。そのことが、本当に怖かった。
そんな恐ろしい日々を変えたのは、ある日の夜更けだ。
二十一時だというのに、今日も父は帰ってこない。もう、三日目だ。大方、どこかの女性とよろしくやっているのだろう。織音としては父が家に居なくて清々する。
普段は自炊をしているが、その日は夕食をつくる気にはなれなかった。部屋着の上にパーカーを着て、サンダルで外に出る。コンビニは少し遠いけど、今から台所に立つよりはマシだ。
街を両断するように流れる狩野川の河川敷沿いを、緩慢に歩む。川に架かる大きな橋へと上れば、先程までのノスタルジックな雰囲気とは一変する。過剰なくらいライトアップされた舗道に、横の道路を行き交う車通りの多さ。一気に人工的な景色へと引き戻された。
目がちかちかする明るさと車の騒音に、フードを目深に被る。
河川を見下ろすように歩いていたその時、前方からの鈍い音が耳に伝わった。次いで、タイヤの擦れる音。まるで、何かが車にぶつかって、慌てて急ブレーキをかけたような……。
音のする方へ視線を上げた刹那、織音の心臓が強く波を打つ。
視界を眩しく染め上げる車のヘッドライトに照らされ、空中をカラスが舞っていた。
カラスから噴き散る鮮血が、宝石のようにきらきらと輝いている。まるで、カラスの瞳から失われた光が、体外に飛び出してしまったみたいだ。綺麗な弧を描く中、不自然に折れ曲がった翼の歪さ。大きな嘴から垂れる透明な液体。あっという間に鈍い音を立てて眼前に落下するその小さな生命。
織音は思わず一歩後ずさり、尻餅を突く。背筋を駆け抜けるゾクゾクとした感覚、粟立つ肌、震える両足。その全てが、恐怖からではなく、興奮から来たものだった。
――なんて美しいのだろう。
微かに痙攣したカラスの姿を眺めて、織音ははち切れんばかりの鼓動の高まりを感じた。心が、身体が、あり得ない程に悦んでいた。
やはり、あたしは変な人間だ。
少数派という括りからすらも逸脱した、化け物だ。
そうでなければ、生命の尽き果てる瞬間を目の当たりにして快楽を覚えるなんておかしい。愛おしさすら感じた。もしかして、これが自分以外を愛するということなのだろうか。
「おかしい。おかしい。ふふっ。あーっ、おかしい!」
矛盾するように弾んだ声で繰り返し、帰路に着いた。
やっぱりと言うべきか、どうしてだろうと言うべきか、すんなりとスランプを抜け出してしまった。そのことに、また自分の異常性を認識する。
数日後には、山奥で除草剤を混ぜた餌をカラスに食べさせていた。
食べ終わって飛び立つカラスを無我夢中で追いかける。転んで泥だらけになっても、道から外れた急な斜面に爪を突き立てて登っても、徐々に飛び方が歪になっていくカラスから目を離さなかった。
やがて、力なく落下したカラスを見下ろし、織音はにんまりと笑った。誰にも見せたことのない笑顔だった。
カラスは嘴から吐しゃ物を垂れ流し、やがてぐったりとして動かなくなった。でも、どうやらまだ生きているらしい。濡羽色の艶やかな毛並みよりもずっと真っ黒な瞳が、僅かに動いている。
だから、織音は手に持った小型のナイフを勢いよく振り下ろした。
肉を裂き、骨を打つ感覚に、強烈な吐き気が込み上がる。酸っぱい液体を無理矢理押し戻して、大きく深呼吸をした。土と鉄のような血の臭い。擦りむいた膝のジンジンとした痛み。脳を揺らすどうしようもないいくつかの感情。湧き上がるインスピレーションが恐ろしかった。
人間として欠陥品だと悟ってしまった時は、自然と涙が零れ落ちていた。悦に浸って、悲しんで、忙しい奴だ。
衝動が抑えられない。勝手に笑みが浮かぶ。慈しむべきであろう欠落した感情を、悦びが塗りたくって埋めていく。
こんな自分、知りたくなかった。それでも――
誰もかれも、生きるのが下手くそだ。
だから、織音は自らを決して否定しない。
果たして、織音が自らに注いでいるものは本当に愛情なのか。他の愛情を知らない織音には分からない。それでも、織音はこの感情を愛として認識しないといけなかった。
自分自身の愛すら受け取れなくなってしまったら、本当の化け物になってしまう気がするから。
日常での不満を絵に吐き出せば、どんどんと上手になっていくことが分かった。両親から愛されなければ、ずっと素敵な絵が描ける。
織音にとって、それはとても嬉しいことだった。両親から受け継がれたものじゃない、織音だけの特別な才能だと実感できる。
しかし、高校に入って間もない頃、織音はスランプに陥った。思うように絵が描けない。キャンバスを前にすると、頭が真っ白になる。どうしても、筆を持つ手が動かなかった。
原因は分かっていて、父との暮らしに慣れてしまったからだ。
織音が絵を描く原動力は不満や怒り、焦燥といった感情。きっと、満たされない感情を、絵を描くことによって補っているのだろう。自分の心のことだけど、哀れでヘンテコな理由だ。
中でも一番大きかった親への形容しがたい憤りが、最近では薄れつつある。織音の青い心が成熟するにつれて、感情の自制を覚えてしまった。ある程度、小細工で感情の繕いが出来るようになったせいだ。
外での人間関係に恵まれつつあることも、スランプの主な要因の一つに挙がるだろう。中学来の親友がいる。織音のことを理解して接してくれる同級生や後輩、鼻につくけど先輩もいる。
高校生ともなれば、名前でいじられることもほとんどない。
織音は多数派の高校生になりつつあった。
筆に乗せる感情が尽き、絵を描くことで満たされていた感情がなくなっていってしまう。胸の底に溜まった汚いヘドロが乾いてゆく。愛せていた自分が、どんどん変わっていってしまう。そのことが、本当に怖かった。
そんな恐ろしい日々を変えたのは、ある日の夜更けだ。
二十一時だというのに、今日も父は帰ってこない。もう、三日目だ。大方、どこかの女性とよろしくやっているのだろう。織音としては父が家に居なくて清々する。
普段は自炊をしているが、その日は夕食をつくる気にはなれなかった。部屋着の上にパーカーを着て、サンダルで外に出る。コンビニは少し遠いけど、今から台所に立つよりはマシだ。
街を両断するように流れる狩野川の河川敷沿いを、緩慢に歩む。川に架かる大きな橋へと上れば、先程までのノスタルジックな雰囲気とは一変する。過剰なくらいライトアップされた舗道に、横の道路を行き交う車通りの多さ。一気に人工的な景色へと引き戻された。
目がちかちかする明るさと車の騒音に、フードを目深に被る。
河川を見下ろすように歩いていたその時、前方からの鈍い音が耳に伝わった。次いで、タイヤの擦れる音。まるで、何かが車にぶつかって、慌てて急ブレーキをかけたような……。
音のする方へ視線を上げた刹那、織音の心臓が強く波を打つ。
視界を眩しく染め上げる車のヘッドライトに照らされ、空中をカラスが舞っていた。
カラスから噴き散る鮮血が、宝石のようにきらきらと輝いている。まるで、カラスの瞳から失われた光が、体外に飛び出してしまったみたいだ。綺麗な弧を描く中、不自然に折れ曲がった翼の歪さ。大きな嘴から垂れる透明な液体。あっという間に鈍い音を立てて眼前に落下するその小さな生命。
織音は思わず一歩後ずさり、尻餅を突く。背筋を駆け抜けるゾクゾクとした感覚、粟立つ肌、震える両足。その全てが、恐怖からではなく、興奮から来たものだった。
――なんて美しいのだろう。
微かに痙攣したカラスの姿を眺めて、織音ははち切れんばかりの鼓動の高まりを感じた。心が、身体が、あり得ない程に悦んでいた。
やはり、あたしは変な人間だ。
少数派という括りからすらも逸脱した、化け物だ。
そうでなければ、生命の尽き果てる瞬間を目の当たりにして快楽を覚えるなんておかしい。愛おしさすら感じた。もしかして、これが自分以外を愛するということなのだろうか。
「おかしい。おかしい。ふふっ。あーっ、おかしい!」
矛盾するように弾んだ声で繰り返し、帰路に着いた。
やっぱりと言うべきか、どうしてだろうと言うべきか、すんなりとスランプを抜け出してしまった。そのことに、また自分の異常性を認識する。
数日後には、山奥で除草剤を混ぜた餌をカラスに食べさせていた。
食べ終わって飛び立つカラスを無我夢中で追いかける。転んで泥だらけになっても、道から外れた急な斜面に爪を突き立てて登っても、徐々に飛び方が歪になっていくカラスから目を離さなかった。
やがて、力なく落下したカラスを見下ろし、織音はにんまりと笑った。誰にも見せたことのない笑顔だった。
カラスは嘴から吐しゃ物を垂れ流し、やがてぐったりとして動かなくなった。でも、どうやらまだ生きているらしい。濡羽色の艶やかな毛並みよりもずっと真っ黒な瞳が、僅かに動いている。
だから、織音は手に持った小型のナイフを勢いよく振り下ろした。
肉を裂き、骨を打つ感覚に、強烈な吐き気が込み上がる。酸っぱい液体を無理矢理押し戻して、大きく深呼吸をした。土と鉄のような血の臭い。擦りむいた膝のジンジンとした痛み。脳を揺らすどうしようもないいくつかの感情。湧き上がるインスピレーションが恐ろしかった。
人間として欠陥品だと悟ってしまった時は、自然と涙が零れ落ちていた。悦に浸って、悲しんで、忙しい奴だ。
衝動が抑えられない。勝手に笑みが浮かぶ。慈しむべきであろう欠落した感情を、悦びが塗りたくって埋めていく。
こんな自分、知りたくなかった。それでも――
誰もかれも、生きるのが下手くそだ。
だから、織音は自らを決して否定しない。
果たして、織音が自らに注いでいるものは本当に愛情なのか。他の愛情を知らない織音には分からない。それでも、織音はこの感情を愛として認識しないといけなかった。
自分自身の愛すら受け取れなくなってしまったら、本当の化け物になってしまう気がするから。