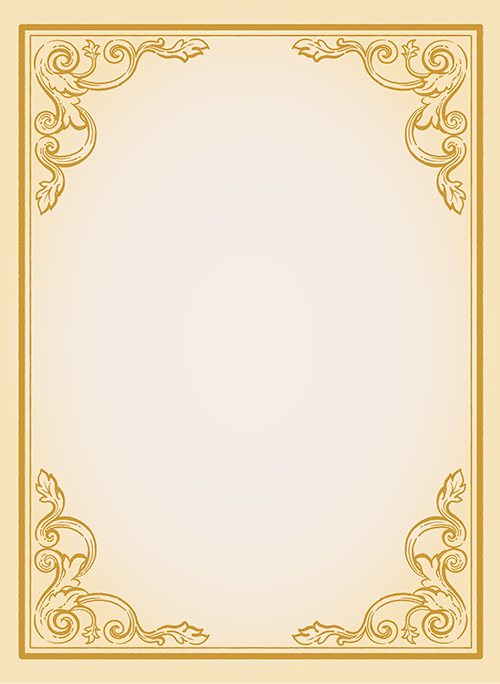昨日は寝苦しい夜だった。汗だくで目覚めた時は見ていた夢の内容を覚えていたけれど、すぐに忘れてしまった。
何か、すごく嫌な夢だったような気がする。
十分に二度寝が出来る時刻だったけれど、胡桃はすっかり目が覚めてしまったので散歩に出ることにした。
夏の夜明けは早い。まだ、四時半だというのに、外はぼんやりとした儚い明るさに包まれている。透き通った涼風が頬を撫でるけど、空は一面の灰鼠色だ。
太陽の射し込む隙間などないくらいには厚い雲なのに、どうして胡桃の目に映る景色は明るいのだろう。地上が明るいのなら、空はもっと明るくあって然るべきだと思う。
溜まった絵具が堆積し、上澄みが僅かに透ける水中とは真逆だと思った。だから、見慣れた景色のはずなのに酷い矛盾すら感じてしまう。
静けさに満ちた街並みを高台の公園から眺望し、眼前の柵にもたれかかる。
薄着の襯衣とズボンにサンダル。頬杖しながら仏頂面で黄昏る胡桃を知り合いが見たら、どう思うのだろう。
チチチッと鳴く小鳥の囀りに耳を傾け、深呼吸をしてみた。青臭い。朝露の滴る草木の不快な臭いに、思わず顔を顰める。
しばらく、ぼんやりと景色を眺め、ふと思う。今、何時なのだろう。つくづく、スマホがないと不便だ。朝早く起きたって、こうして無駄に時間を浪費するしかやることがない。
こういうのをデジタルデトックスと言うんだっけ?
あまりいいものじゃないな。当たり前にそう感じた。
少しずつ、耳をなぞる音が増えていく。自動車の走る音、蝉の鳴き声、コンビニ袋の揺すれる音。
こんな時間にコンビニに行く人って、どんな人なのだろう。朝ご飯を買いに? それとも、徹夜明けに栄養ドリンクを買いに?
そこまで考え、音のする方を窺うと、公園のベンチでサンドイッチを食べるスーツ姿の男性だった。背を丸め、サンドイッチを口に含んではお茶で流し込んでいく。とても作業的に思えた。
きっと、出社前の社会人、と普通は思う。胡桃だって、もちろんそう思う。だけど、実はリストラされていることを家族に言い出せないで、朝から公園で暇を潰しているとか、はたまた、スーツを着ているだけで社会人じゃないかもしれない。
結局、人は上っ面だけじゃ、何も分からない。
……馬鹿らしい。
「帰ろ……」
家に戻って時刻を確認すると、胡桃が予想していたよりも全然時間が経っていなかった。代わりに汗を流すシャワーの時間がすごく長かったらしい。結局、いつも通りの支度の時間だ。
「学校、行きたくないなぁ」
朝食をつくりながら零れた言葉は紛れもない本心だ。それでも、部活をサボるなんてことは微塵も考えなかった。だって、部長だし、胡桃がいないとみんなが困る。
……困るのだろうか。
横渕先生は絶対に困る。だって、先生は忙しいのに、部長の胡桃が休んだら手間が増える。
他のみんなはどうだろうか。
嫌なことを考えてしまい、慌てて頭を振る。ネクタイをいつもよりちょっときつく締め、最後に制服の袖ボタンを留めて家を出た。
本当、今年の夏休みは最悪だ。間違いなく、人生で一番最低な夏だ。
だから、今日くらいはせめて何も起きませんように。そんな希薄で、無意味な切望は、美術室のドアを開けた瞬間に勢いよく砕け散る。
鼻を衝く異臭に、思わず喉が締まった。生ごみのような腐臭と、鉄錆びのような血の臭い。咄嗟に息を止めたけれど、鼻の奥にこびりついた強烈な臭気に咳き込んだ。
一体、何の臭いだろうか。視線をさまよわせると、教室の最前列――教壇の上に織音がいた。そして、織音の手元の教卓を見て、
「――――ぃっ!?」
言葉にならない悲鳴が漏れる。
教卓の上に横たわるカラス――いや、カラスだったものと言うべきだろうか。瞳の色は失われ、裂けた腹から内臓が零れ落ちて、流れる鮮血が教卓から滴っている。力なく落ちた舌から吐しゃ物が零れ、背中を沿う真っ黒な毛並みには乾きかけの血がこびり付いていた。
胡桃はその場に立ち尽くし、何度も瞬きを繰り返す。これは夢だ。という思いを、胃から這いずり上がる気持ち悪さが即座に否定する。
籠った熱気と、全身を包み込む異臭が、現実の輪郭を胡桃に突き付けていた。
心臓の鼓動が耳の奥で爆ぜ、声を発しようにも喉が痙攣するだけで音が出ない。
天井越しに聞こえてくる吹奏楽の重厚な音色と、どんよりとした外から僅かに射し込む明かり。そして、何より、胡桃をまっすぐに見つめて立ち尽くす圧倒的な存在感の織音。それら全てが合わさって、この美術室という空間が一つの舞台のように感じた。
織音の虹彩が鈍く光り、ややあって彼女のきつく閉じられた口元が開かれる。
「――おはよう、胡桃」
見てはいけないものを見てしまったはずなのに。どうしても織音から目が離せない。織音の中に眠るおぞましい何かが、胡桃の意識を掴んで離してはくれなかった。
何か、すごく嫌な夢だったような気がする。
十分に二度寝が出来る時刻だったけれど、胡桃はすっかり目が覚めてしまったので散歩に出ることにした。
夏の夜明けは早い。まだ、四時半だというのに、外はぼんやりとした儚い明るさに包まれている。透き通った涼風が頬を撫でるけど、空は一面の灰鼠色だ。
太陽の射し込む隙間などないくらいには厚い雲なのに、どうして胡桃の目に映る景色は明るいのだろう。地上が明るいのなら、空はもっと明るくあって然るべきだと思う。
溜まった絵具が堆積し、上澄みが僅かに透ける水中とは真逆だと思った。だから、見慣れた景色のはずなのに酷い矛盾すら感じてしまう。
静けさに満ちた街並みを高台の公園から眺望し、眼前の柵にもたれかかる。
薄着の襯衣とズボンにサンダル。頬杖しながら仏頂面で黄昏る胡桃を知り合いが見たら、どう思うのだろう。
チチチッと鳴く小鳥の囀りに耳を傾け、深呼吸をしてみた。青臭い。朝露の滴る草木の不快な臭いに、思わず顔を顰める。
しばらく、ぼんやりと景色を眺め、ふと思う。今、何時なのだろう。つくづく、スマホがないと不便だ。朝早く起きたって、こうして無駄に時間を浪費するしかやることがない。
こういうのをデジタルデトックスと言うんだっけ?
あまりいいものじゃないな。当たり前にそう感じた。
少しずつ、耳をなぞる音が増えていく。自動車の走る音、蝉の鳴き声、コンビニ袋の揺すれる音。
こんな時間にコンビニに行く人って、どんな人なのだろう。朝ご飯を買いに? それとも、徹夜明けに栄養ドリンクを買いに?
そこまで考え、音のする方を窺うと、公園のベンチでサンドイッチを食べるスーツ姿の男性だった。背を丸め、サンドイッチを口に含んではお茶で流し込んでいく。とても作業的に思えた。
きっと、出社前の社会人、と普通は思う。胡桃だって、もちろんそう思う。だけど、実はリストラされていることを家族に言い出せないで、朝から公園で暇を潰しているとか、はたまた、スーツを着ているだけで社会人じゃないかもしれない。
結局、人は上っ面だけじゃ、何も分からない。
……馬鹿らしい。
「帰ろ……」
家に戻って時刻を確認すると、胡桃が予想していたよりも全然時間が経っていなかった。代わりに汗を流すシャワーの時間がすごく長かったらしい。結局、いつも通りの支度の時間だ。
「学校、行きたくないなぁ」
朝食をつくりながら零れた言葉は紛れもない本心だ。それでも、部活をサボるなんてことは微塵も考えなかった。だって、部長だし、胡桃がいないとみんなが困る。
……困るのだろうか。
横渕先生は絶対に困る。だって、先生は忙しいのに、部長の胡桃が休んだら手間が増える。
他のみんなはどうだろうか。
嫌なことを考えてしまい、慌てて頭を振る。ネクタイをいつもよりちょっときつく締め、最後に制服の袖ボタンを留めて家を出た。
本当、今年の夏休みは最悪だ。間違いなく、人生で一番最低な夏だ。
だから、今日くらいはせめて何も起きませんように。そんな希薄で、無意味な切望は、美術室のドアを開けた瞬間に勢いよく砕け散る。
鼻を衝く異臭に、思わず喉が締まった。生ごみのような腐臭と、鉄錆びのような血の臭い。咄嗟に息を止めたけれど、鼻の奥にこびりついた強烈な臭気に咳き込んだ。
一体、何の臭いだろうか。視線をさまよわせると、教室の最前列――教壇の上に織音がいた。そして、織音の手元の教卓を見て、
「――――ぃっ!?」
言葉にならない悲鳴が漏れる。
教卓の上に横たわるカラス――いや、カラスだったものと言うべきだろうか。瞳の色は失われ、裂けた腹から内臓が零れ落ちて、流れる鮮血が教卓から滴っている。力なく落ちた舌から吐しゃ物が零れ、背中を沿う真っ黒な毛並みには乾きかけの血がこびり付いていた。
胡桃はその場に立ち尽くし、何度も瞬きを繰り返す。これは夢だ。という思いを、胃から這いずり上がる気持ち悪さが即座に否定する。
籠った熱気と、全身を包み込む異臭が、現実の輪郭を胡桃に突き付けていた。
心臓の鼓動が耳の奥で爆ぜ、声を発しようにも喉が痙攣するだけで音が出ない。
天井越しに聞こえてくる吹奏楽の重厚な音色と、どんよりとした外から僅かに射し込む明かり。そして、何より、胡桃をまっすぐに見つめて立ち尽くす圧倒的な存在感の織音。それら全てが合わさって、この美術室という空間が一つの舞台のように感じた。
織音の虹彩が鈍く光り、ややあって彼女のきつく閉じられた口元が開かれる。
「――おはよう、胡桃」
見てはいけないものを見てしまったはずなのに。どうしても織音から目が離せない。織音の中に眠るおぞましい何かが、胡桃の意識を掴んで離してはくれなかった。