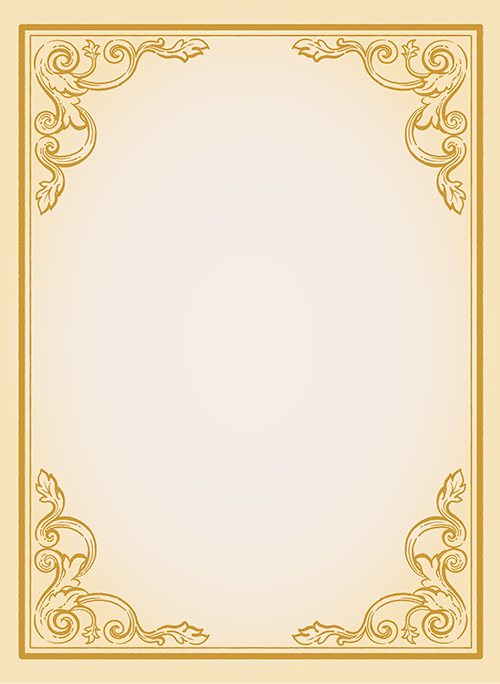「くそーっ、染井先輩も写真フォルダにパスワードかけてるのか。でもなぁ、凪先輩と違って予想付かないし……って、うわ、YouTubeの履歴エグ~。都市伝説に、害獣駆除に、心霊系って。怖いもの見たさってことかぁ」
燿は龍之介のスマホをいじりながら、ぶつぶつと一人で呟く。龍之介の端末だけど、もちろん中身は織音のものに入れ替わっている。
織音が出ていき、凪も気が付けばどこかへ行ってしまった。鞄がないし、帰ってしまったのだろう。
織音にあれだけの執着を見せていた凪だから、てっきり織音のスマホの中身が気になると思っていたのに。それどころではない心境なのか、彼なりの贖罪の意味なのか、胡桃には判断しかねる。だって、未だに凪はちゃんと話してくれないのだから。
「おい、スマホ返せよ」
龍之介が燿のいじるスマホに手を伸ばすが、燿はそれを見もせずに躱す。
「嫌でーす。スマホ置いていくって言ったの龍之介先輩じゃないっすか。あっ、僕のスマホ、持って帰っていいっすよ。また警察から電話かかってきたら困りますよね」
スマホに目を落としたまま、淡々と告げる燿の好奇心はもはや龍之介に向いていない。そんな燿に、龍之介は腹立たしそうに舌打ちをする。
「うは~、染井先輩、インスタのDMで荒木先輩に告られてる。告白に、織音呼びって、地雷踏み抜き過ぎでしょ。案の定、染井先輩ぶち切れてるし。告っただけでボロクソ言われてるのおもろっ」
まるで、子供がおもちゃを買ってもらった時のように目を輝かせる燿。
染井さんに悪いから、やめよう?
その言葉を胡桃は呑み込む。先程、織音に言われたことが頭の中でぐるぐると渦を巻いていた。
もう何を言っても、胡桃の言葉は誰にも届かない。意見をしたいのなら、同じ土俵に立たないと始まらない。客席から聞こえてくる不満の声に、誰が反応するというのだろうか。
それでも、見ているだけなんて出来っこない。
自らのスマホを諦めて、美術室を出た龍之介の後を追いかける。
「龍之介先輩、話をさせてください」
声をかけても、龍之介は何も返してくれないし、足も止めなかった。だから、胡桃は階段を降りる龍之介を追い越し、彼の前に立ちはだかる。そこまでして、ようやく龍之介はばつが悪そうな面持ちで胡桃に意識を向けた。
「俺、用事あんだけど」
数段上に立つ龍之介は、真横のステンドグラス窓から射し込む夏の陽射しを浴び、顔の半面を幾重もの色が編まれた光で照らされていた。赤、緑、金、砕けた光の破片は、胡桃を見下ろす龍之介の冷ややかな瞳を強調して引き立てる。
でも、きっと龍之介から見た胡桃も、同じなのだろう。
身体の半分をきらきらと艶やかな光が射し、影を伸ばして落とす。重たい色のステンドグラス窓ということもあって、昼間なのに仄かな暗さを漂わせるここでは、まるで夕暮れ時みたいに少し影が長い。
「その用事って、大事なものですか?」
「そうだけど?」
「……そうですか。引き留めて、すみませんでした」
結局、龍之介も胡桃には取り合ってくれなかった。
もっと、普段から話をしていたら龍之介は胡桃の味方をしてくれただろうか。
というか、味方って何だ。敵なんてどこにもいないのに。どうして、今そんな言葉が浮かんだのだろう。
零れ落ちた嘆息は、誰に対するものだろうか。無駄に煽って、一人だけ愉しそうにする燿に対する幻滅か、何も話してくれない凪に覚える歯がゆさか。それとも、どんなに胡桃が声をかけても、正面から取り合ってくれないみんなに感じる寂寞か。
きっと、胡桃も支え切れなくなっているのだ。
そもそも、支える必要ってあるのだろうか。誰も、胡桃のことなんて気にかけてくれない。むしろ、正義ぶってる邪魔者扱いになりつつある。綺麗ごとを並べて、具体策も出さない。よく考えてみれば、耳を傾けろと言う方が難しいのかもしれない。
自信のなさに、口を噤んだ。もう何も言えなかった。
そんな胡桃に、龍之介はため息を吐く。
「悪かったな、かき乱して」
「えっ……?」
予想外の謝罪に、思わず掠れた声が零れる。
「でもな、全部本当のことだ」
横を通り抜ける龍之介は、胡桃のことを見ていなかった。それが、これ以上会話をする気のない意思表示だった。
「嘘ですよね?」
「嘘は吐いてねぇよ。だから、あんま俺に構うな」
思わず、階段を降りていく龍之介の腕を掴む。
「せめて、燿くんの説得を一緒にしてもらえませんか……?」
龍之介の表情は見えないけれど、掴んだ彼の腕はじんわりと汗ばんでいた。
「きっと、誰かの秘密を暴きたいだなんて思ってるの、燿くんだけなんです。燿くんさえ止めることが出来たら、私たちはきっとまた、」
不意に視界がぼやける。瞼の裏から零れる熱いものを、胡桃は龍之介の腕を離して急いで拭う。
――泣くのはズルい人がすること。
母親に散々言われた言葉が楔となって、余計に涙が止まらなかった。
「なら、俺が燿に関わるのは逆効果だ」
「どうして……」
「燿がああなったのは、多分俺のせいだからよ」
結局、最後まで龍之介が振り返ることはなかった。
仄暗い校舎端の踊り場で、胡桃はしばらく立ち尽くした。ステンドグラスの弾けた光が、今ではうざったくて仕方がない。
「なんか、疲れちゃったなぁ……」
無駄なフィルターなんか通さずに、眩い光で焼かれたかった。
燿は龍之介のスマホをいじりながら、ぶつぶつと一人で呟く。龍之介の端末だけど、もちろん中身は織音のものに入れ替わっている。
織音が出ていき、凪も気が付けばどこかへ行ってしまった。鞄がないし、帰ってしまったのだろう。
織音にあれだけの執着を見せていた凪だから、てっきり織音のスマホの中身が気になると思っていたのに。それどころではない心境なのか、彼なりの贖罪の意味なのか、胡桃には判断しかねる。だって、未だに凪はちゃんと話してくれないのだから。
「おい、スマホ返せよ」
龍之介が燿のいじるスマホに手を伸ばすが、燿はそれを見もせずに躱す。
「嫌でーす。スマホ置いていくって言ったの龍之介先輩じゃないっすか。あっ、僕のスマホ、持って帰っていいっすよ。また警察から電話かかってきたら困りますよね」
スマホに目を落としたまま、淡々と告げる燿の好奇心はもはや龍之介に向いていない。そんな燿に、龍之介は腹立たしそうに舌打ちをする。
「うは~、染井先輩、インスタのDMで荒木先輩に告られてる。告白に、織音呼びって、地雷踏み抜き過ぎでしょ。案の定、染井先輩ぶち切れてるし。告っただけでボロクソ言われてるのおもろっ」
まるで、子供がおもちゃを買ってもらった時のように目を輝かせる燿。
染井さんに悪いから、やめよう?
その言葉を胡桃は呑み込む。先程、織音に言われたことが頭の中でぐるぐると渦を巻いていた。
もう何を言っても、胡桃の言葉は誰にも届かない。意見をしたいのなら、同じ土俵に立たないと始まらない。客席から聞こえてくる不満の声に、誰が反応するというのだろうか。
それでも、見ているだけなんて出来っこない。
自らのスマホを諦めて、美術室を出た龍之介の後を追いかける。
「龍之介先輩、話をさせてください」
声をかけても、龍之介は何も返してくれないし、足も止めなかった。だから、胡桃は階段を降りる龍之介を追い越し、彼の前に立ちはだかる。そこまでして、ようやく龍之介はばつが悪そうな面持ちで胡桃に意識を向けた。
「俺、用事あんだけど」
数段上に立つ龍之介は、真横のステンドグラス窓から射し込む夏の陽射しを浴び、顔の半面を幾重もの色が編まれた光で照らされていた。赤、緑、金、砕けた光の破片は、胡桃を見下ろす龍之介の冷ややかな瞳を強調して引き立てる。
でも、きっと龍之介から見た胡桃も、同じなのだろう。
身体の半分をきらきらと艶やかな光が射し、影を伸ばして落とす。重たい色のステンドグラス窓ということもあって、昼間なのに仄かな暗さを漂わせるここでは、まるで夕暮れ時みたいに少し影が長い。
「その用事って、大事なものですか?」
「そうだけど?」
「……そうですか。引き留めて、すみませんでした」
結局、龍之介も胡桃には取り合ってくれなかった。
もっと、普段から話をしていたら龍之介は胡桃の味方をしてくれただろうか。
というか、味方って何だ。敵なんてどこにもいないのに。どうして、今そんな言葉が浮かんだのだろう。
零れ落ちた嘆息は、誰に対するものだろうか。無駄に煽って、一人だけ愉しそうにする燿に対する幻滅か、何も話してくれない凪に覚える歯がゆさか。それとも、どんなに胡桃が声をかけても、正面から取り合ってくれないみんなに感じる寂寞か。
きっと、胡桃も支え切れなくなっているのだ。
そもそも、支える必要ってあるのだろうか。誰も、胡桃のことなんて気にかけてくれない。むしろ、正義ぶってる邪魔者扱いになりつつある。綺麗ごとを並べて、具体策も出さない。よく考えてみれば、耳を傾けろと言う方が難しいのかもしれない。
自信のなさに、口を噤んだ。もう何も言えなかった。
そんな胡桃に、龍之介はため息を吐く。
「悪かったな、かき乱して」
「えっ……?」
予想外の謝罪に、思わず掠れた声が零れる。
「でもな、全部本当のことだ」
横を通り抜ける龍之介は、胡桃のことを見ていなかった。それが、これ以上会話をする気のない意思表示だった。
「嘘ですよね?」
「嘘は吐いてねぇよ。だから、あんま俺に構うな」
思わず、階段を降りていく龍之介の腕を掴む。
「せめて、燿くんの説得を一緒にしてもらえませんか……?」
龍之介の表情は見えないけれど、掴んだ彼の腕はじんわりと汗ばんでいた。
「きっと、誰かの秘密を暴きたいだなんて思ってるの、燿くんだけなんです。燿くんさえ止めることが出来たら、私たちはきっとまた、」
不意に視界がぼやける。瞼の裏から零れる熱いものを、胡桃は龍之介の腕を離して急いで拭う。
――泣くのはズルい人がすること。
母親に散々言われた言葉が楔となって、余計に涙が止まらなかった。
「なら、俺が燿に関わるのは逆効果だ」
「どうして……」
「燿がああなったのは、多分俺のせいだからよ」
結局、最後まで龍之介が振り返ることはなかった。
仄暗い校舎端の踊り場で、胡桃はしばらく立ち尽くした。ステンドグラスの弾けた光が、今ではうざったくて仕方がない。
「なんか、疲れちゃったなぁ……」
無駄なフィルターなんか通さずに、眩い光で焼かれたかった。