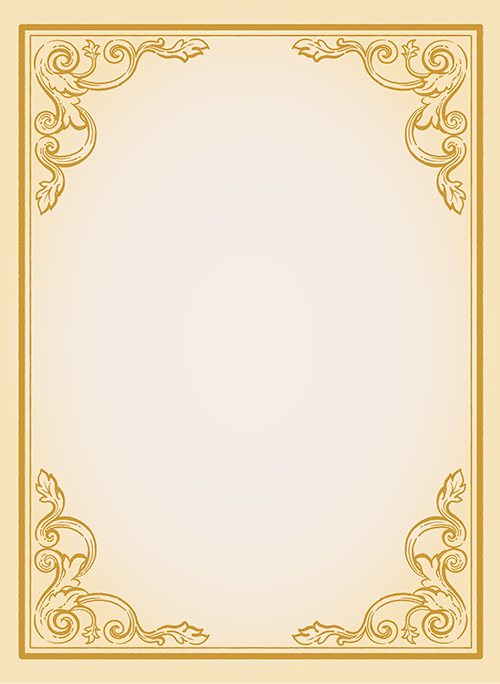◇
「はい……じゃあ、来週伺います……うす……」
電話が切れ、再び美術室に静けさが満ちる。
龍之介は誰とも目を合わせることなく、深いため息と共に椅子へ腰を下ろす。
今の美術室には、色々な感情が渦巻いている気がした。気まずそうな龍之介、悦に浸る燿、そして、安堵の息をそっと漏らした凪。
「なんだ、あの噂って本当だったんだ」
気が付けば、織音が戻っていた。どこから持ってきたのか、保冷剤と濡れタオルを燿の足元に置き、続ける。
「インスタのストーリーで誰かが呟いててさ、うちの学生が老人を階段から突き落として病院送りにさせたのを見たって。あれ、龍之介のことでしょ」
「えっ……?」
自然と言葉が零れ、慌てて噤む。この状況で口を挟むのは、流石に胡桃でも気が重くなる。
織音の見聞きした噂の真偽は不明だが、龍之介は依然として沈黙を貫いていた。しかし、その表情はどこか険しい。何かを迷っているように見える。
「龍之介先輩、説明してくださいよ」
正気を取り戻した燿が、椅子に座り直して龍之介を催促する。そして、保冷剤をあてがった左足を龍之介にわざとらしく向けた。その動作の意味を胡桃は理解できなかったが、足首に着けられたミサンガにどうしても目が行ってしまう。
「お前らには関係ない」
長い沈黙の後、龍之介はただそう答えた。
「じゃあ、本当なんすね? 老人に暴力を振るって、病院送りにしたってことでいいんすね?」
龍之介に詰問する燿を、胡桃は床にへたり込んだままぼんやりと眺めていた。
正直、驚けなかった。そのことがショックで、涙が出そうになる。これじゃまるで、龍之介が老人に暴力を振るってもおかしくない人と認識していたってことじゃないか。
そうじゃないと言葉では否定できても、心の奥底で疑いをかけることなく、受け入れようとしている自分がいる。凪と燿の裏の顔は再三否定し続けてきたというのに。
部員全員を平等に見つめてきたつもりだった。だけど、どうやら龍之介だけ、無意識に他の三人とは違う見方をしてしまっていたらしい。
龍之介が胡桃たちに関わろうとしていなかったことを踏まえたとしても、胡桃の本心はあまりにも醜い。
「うるせぇな。もう、それでいいよ」
結局、龍之介は否定することなく、事実として受け入れた。すると、今度は燿が口を閉ざす。
変な話だけど、すごい違和感だ。てっきり、燿はここぞとばかりに龍之介のことを責め立てるものだと思っていた。凪にしたように、誹り、嫌な正論を盾に傷付けるのだと、身構えてしまっていた。
しかし、燿の表情は複雑さを極め、先程とは一変して不機嫌そうなものだ。
「龍之介先輩、本当なんですか……?」
まっすぐ見つめる胡桃に、龍之介はやっぱり目を合わせてはくれない。
本当のことなのだとしたら、もう話すことはないということなのだろう。だけど、もしそうでないのなら、どうかたった一言でいいから否定してほしい。それだけで、胡桃はまだ龍之介のことを信じることが出来るのだから。
「何度も言わせんな」
だから、胡桃はもう何も言えなかった。
「さいってー」
窓の外に目を背け、織音が小さく呟く。もう、彼女は龍之介のことを見てもいなかった。
「まあ、やると思ってました、ってやつ?」
「染井さん……」
「……ごめん」
胡桃の呟きに、織音が小さな声で謝罪を述べて口を噤んだ。
正直、織音の気持ちも分かってしまう。もう全部受け入れてしまった方が楽だから、胡桃も不意に諦めそうになる。沢山の色の感情が渦巻く私たちは、もうどうやったって一色に戻れないのかもしれない。
いや、そうじゃない。きっと最初から、私たちは全員違う色をしていて、同じ色であろうと上から綺麗な色を塗りたくっていただけなんだ。
「帰るわ」
龍之介が鞄を片手に立ち上がる。
「えっ、でも、」
その後に続く言葉が出なかった。だって、部活はどうするの? なんて、あまりにも的外れなものだったから。こんな時ですら、頭のどこかでは優等生の自分がやるべきことをしようとしている。それがきっと、胡桃の原色だ。
自分がこんなにも薄情な人間だったなんて、初めて知った。
「俺のスマホ置いていくから、勝手にやっててくれよ。もう、うんざりだわ」
龍之介が自らのスマホを机の上に滑らせる。
真っ黒な画面の端末。それが、今となってはとても恐ろしい。人を傷付ける凶器みたいだ。ナイフよりも鋭く、鈍器よりも重い。他人と、自分すらも傷付ける諸刃の剣。
「何言ってるんすか。そんなの駄目に決まってるでしょ。まだ、事件のこともしっかり聞いてないのに」
胡桃が何かを言う前に、燿が調子を戻す。龍之介を睨み付ける燿の瞳は、もう胡桃たちを映してはいなかった。
「だから、何度も言わせんな。俺がやった。それでいいだろ」
「……凪先輩と龍之介先輩って、一緒っすわ。何も話してくれない。僕と同じ加害者の立場のくせに、今は被害者みたいな面してる」
燿が立ち上がり、左足を引きずりながら凪の元へ向かう。見下ろす燿に、凪は目を合わせない。
「ほら、またそうやって。染井先輩が言っていたこと、何にも分かってないじゃないですか。ちゃんと凪先輩の口から、本当の想いが知りたいって。伝わってないんすか? まさかそんなに馬鹿じゃないでしょ」
「ぼ、僕は……本当に悪いことをしたと思っていて……だから、」
虚ろな瞳を潤ませ、凪はそのまま口を閉ざした。その様子に、一段と燿の表情が曇る。
「だから、何すか? ……くっそウザい。どうして、こんな奴がのうのうと今まで生きていて、僕は……」
怒りに震える燿の歯ぎしりの音が、胡桃の耳にまで届いた。
「もうやめようよ……」
不意に力のない声が零れた。
「やめるって、何言ってるんですか? そりゃ、胡桃先輩には関係ないことばかりかもしれないですけど――」
「そうじゃなくて。一番壊れちゃいそうなの、燿くんだよ。気が付いてる? さっきから、怒ったり、悲しんだり。燿くんの感情が交錯し続けてる。きっと、一番混乱しているのはあなただよ。だから、もうやめよ? 私たち、あんなに仲良かったじゃん……」
こんなの現実逃避以外の何ものでもない。でも、燿以外は胡桃の意見に賛同してくれると思っていた。だから、目が合った織音が首を横に振ったことに愕然としてしまった。
「無理だよ。あたしと胡桃がそれを言っても」
「それって、どういう……」
刹那、小さな電子音が鳴り、龍之介のスマホが唐突に起動する。明るくなった画面に、全員の意識がすぐに集まる気配がした。
もちろん、胡桃も反射的に覗いてしまう。
見覚えのないホーム画面。だけど、画面に映るブレスレットには覚えがあった。
織音が小さくため息を吐く。
「あたしと胡桃がやめようって言ったって、それは秘密を知られたくないからそう言ってるってことでしょ?」
「そんなこと……」
それ以上、言葉が出てこなかった。
自分の言葉はもう誰にも届かない。そして、それは織音も一緒だ。
織音が荷物を持って立ち上がる。
「そんなこと言って、逃げるんすか?」
美術室のドアに手をかける織音の背中に、燿が叫ぶ。
「違うよ。あたしは別に誰に知られても構わない秘密しかないから」
けたたましい音と共に、織音がドアを開ける。
「それに、どうせ明日には分かるよ」
そう言い残し、織音の姿がドアの向こうへと消えていった。
「はい……じゃあ、来週伺います……うす……」
電話が切れ、再び美術室に静けさが満ちる。
龍之介は誰とも目を合わせることなく、深いため息と共に椅子へ腰を下ろす。
今の美術室には、色々な感情が渦巻いている気がした。気まずそうな龍之介、悦に浸る燿、そして、安堵の息をそっと漏らした凪。
「なんだ、あの噂って本当だったんだ」
気が付けば、織音が戻っていた。どこから持ってきたのか、保冷剤と濡れタオルを燿の足元に置き、続ける。
「インスタのストーリーで誰かが呟いててさ、うちの学生が老人を階段から突き落として病院送りにさせたのを見たって。あれ、龍之介のことでしょ」
「えっ……?」
自然と言葉が零れ、慌てて噤む。この状況で口を挟むのは、流石に胡桃でも気が重くなる。
織音の見聞きした噂の真偽は不明だが、龍之介は依然として沈黙を貫いていた。しかし、その表情はどこか険しい。何かを迷っているように見える。
「龍之介先輩、説明してくださいよ」
正気を取り戻した燿が、椅子に座り直して龍之介を催促する。そして、保冷剤をあてがった左足を龍之介にわざとらしく向けた。その動作の意味を胡桃は理解できなかったが、足首に着けられたミサンガにどうしても目が行ってしまう。
「お前らには関係ない」
長い沈黙の後、龍之介はただそう答えた。
「じゃあ、本当なんすね? 老人に暴力を振るって、病院送りにしたってことでいいんすね?」
龍之介に詰問する燿を、胡桃は床にへたり込んだままぼんやりと眺めていた。
正直、驚けなかった。そのことがショックで、涙が出そうになる。これじゃまるで、龍之介が老人に暴力を振るってもおかしくない人と認識していたってことじゃないか。
そうじゃないと言葉では否定できても、心の奥底で疑いをかけることなく、受け入れようとしている自分がいる。凪と燿の裏の顔は再三否定し続けてきたというのに。
部員全員を平等に見つめてきたつもりだった。だけど、どうやら龍之介だけ、無意識に他の三人とは違う見方をしてしまっていたらしい。
龍之介が胡桃たちに関わろうとしていなかったことを踏まえたとしても、胡桃の本心はあまりにも醜い。
「うるせぇな。もう、それでいいよ」
結局、龍之介は否定することなく、事実として受け入れた。すると、今度は燿が口を閉ざす。
変な話だけど、すごい違和感だ。てっきり、燿はここぞとばかりに龍之介のことを責め立てるものだと思っていた。凪にしたように、誹り、嫌な正論を盾に傷付けるのだと、身構えてしまっていた。
しかし、燿の表情は複雑さを極め、先程とは一変して不機嫌そうなものだ。
「龍之介先輩、本当なんですか……?」
まっすぐ見つめる胡桃に、龍之介はやっぱり目を合わせてはくれない。
本当のことなのだとしたら、もう話すことはないということなのだろう。だけど、もしそうでないのなら、どうかたった一言でいいから否定してほしい。それだけで、胡桃はまだ龍之介のことを信じることが出来るのだから。
「何度も言わせんな」
だから、胡桃はもう何も言えなかった。
「さいってー」
窓の外に目を背け、織音が小さく呟く。もう、彼女は龍之介のことを見てもいなかった。
「まあ、やると思ってました、ってやつ?」
「染井さん……」
「……ごめん」
胡桃の呟きに、織音が小さな声で謝罪を述べて口を噤んだ。
正直、織音の気持ちも分かってしまう。もう全部受け入れてしまった方が楽だから、胡桃も不意に諦めそうになる。沢山の色の感情が渦巻く私たちは、もうどうやったって一色に戻れないのかもしれない。
いや、そうじゃない。きっと最初から、私たちは全員違う色をしていて、同じ色であろうと上から綺麗な色を塗りたくっていただけなんだ。
「帰るわ」
龍之介が鞄を片手に立ち上がる。
「えっ、でも、」
その後に続く言葉が出なかった。だって、部活はどうするの? なんて、あまりにも的外れなものだったから。こんな時ですら、頭のどこかでは優等生の自分がやるべきことをしようとしている。それがきっと、胡桃の原色だ。
自分がこんなにも薄情な人間だったなんて、初めて知った。
「俺のスマホ置いていくから、勝手にやっててくれよ。もう、うんざりだわ」
龍之介が自らのスマホを机の上に滑らせる。
真っ黒な画面の端末。それが、今となってはとても恐ろしい。人を傷付ける凶器みたいだ。ナイフよりも鋭く、鈍器よりも重い。他人と、自分すらも傷付ける諸刃の剣。
「何言ってるんすか。そんなの駄目に決まってるでしょ。まだ、事件のこともしっかり聞いてないのに」
胡桃が何かを言う前に、燿が調子を戻す。龍之介を睨み付ける燿の瞳は、もう胡桃たちを映してはいなかった。
「だから、何度も言わせんな。俺がやった。それでいいだろ」
「……凪先輩と龍之介先輩って、一緒っすわ。何も話してくれない。僕と同じ加害者の立場のくせに、今は被害者みたいな面してる」
燿が立ち上がり、左足を引きずりながら凪の元へ向かう。見下ろす燿に、凪は目を合わせない。
「ほら、またそうやって。染井先輩が言っていたこと、何にも分かってないじゃないですか。ちゃんと凪先輩の口から、本当の想いが知りたいって。伝わってないんすか? まさかそんなに馬鹿じゃないでしょ」
「ぼ、僕は……本当に悪いことをしたと思っていて……だから、」
虚ろな瞳を潤ませ、凪はそのまま口を閉ざした。その様子に、一段と燿の表情が曇る。
「だから、何すか? ……くっそウザい。どうして、こんな奴がのうのうと今まで生きていて、僕は……」
怒りに震える燿の歯ぎしりの音が、胡桃の耳にまで届いた。
「もうやめようよ……」
不意に力のない声が零れた。
「やめるって、何言ってるんですか? そりゃ、胡桃先輩には関係ないことばかりかもしれないですけど――」
「そうじゃなくて。一番壊れちゃいそうなの、燿くんだよ。気が付いてる? さっきから、怒ったり、悲しんだり。燿くんの感情が交錯し続けてる。きっと、一番混乱しているのはあなただよ。だから、もうやめよ? 私たち、あんなに仲良かったじゃん……」
こんなの現実逃避以外の何ものでもない。でも、燿以外は胡桃の意見に賛同してくれると思っていた。だから、目が合った織音が首を横に振ったことに愕然としてしまった。
「無理だよ。あたしと胡桃がそれを言っても」
「それって、どういう……」
刹那、小さな電子音が鳴り、龍之介のスマホが唐突に起動する。明るくなった画面に、全員の意識がすぐに集まる気配がした。
もちろん、胡桃も反射的に覗いてしまう。
見覚えのないホーム画面。だけど、画面に映るブレスレットには覚えがあった。
織音が小さくため息を吐く。
「あたしと胡桃がやめようって言ったって、それは秘密を知られたくないからそう言ってるってことでしょ?」
「そんなこと……」
それ以上、言葉が出てこなかった。
自分の言葉はもう誰にも届かない。そして、それは織音も一緒だ。
織音が荷物を持って立ち上がる。
「そんなこと言って、逃げるんすか?」
美術室のドアに手をかける織音の背中に、燿が叫ぶ。
「違うよ。あたしは別に誰に知られても構わない秘密しかないから」
けたたましい音と共に、織音がドアを開ける。
「それに、どうせ明日には分かるよ」
そう言い残し、織音の姿がドアの向こうへと消えていった。