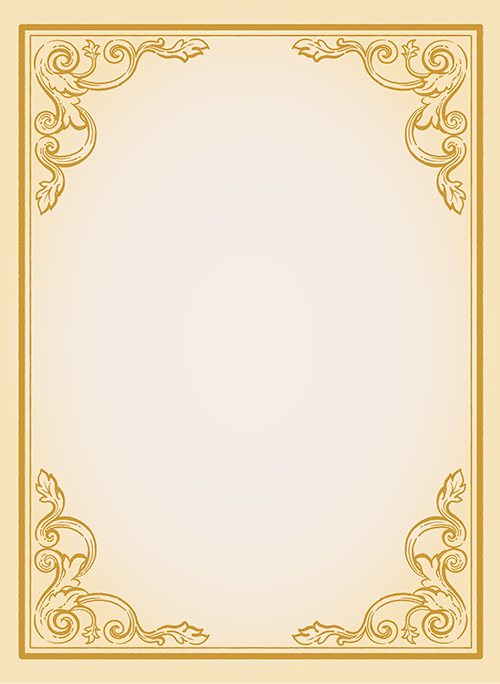結局、中学を卒業するまで、凪が自ら話しかけることが出来たのは織音だけだった。彼女もクラスでは少し浮いていた存在だったから、自ずと一緒にいることが増えた。
多分、織音を苦手としている人はクラスに一定数いる。でも、誰も織音の発言を妨げることも、否定することもなかった。きっとそれは、凪と同様、彼女に底抜けの魅力を感じ取っている人が多かったからだろう。
信頼を集めるわけでもなく、友達も決して多くはない。それでも、織音は隠し切れない強いカリスマ性のおかげで、クラス内のヒエラルキーは高かった。カースト上位の群れる陽キャたちに紛れ、孤独に輝く姿は、凪に言わせればまさに一等星のようだった。
そのおかげか、織音と関わるようになると、自然と凪への嫌がらせは減っていった。織音と対峙してまで、凪に対する執着を持つ必要が彼らにはなかったからだ。
凪と織音が互いに親友と認め合えるようになるまで、大して時間はいらなかった。
織音とは驚くくらい価値観が合う。だから、性格は全く違ったけど、喧嘩の一つだってしたことがない。親友だからこそ、何でも包み隠さず明け透けに話すことが出来た。
「あたし、恋愛ごとが本当に嫌いなの」
目の前を歩く男女が手を繋いだのを見て、織音は言った。足早に男女を追い抜かす彼女を凪は不思議に思いながらも追いかける。
「な、何かトラウマとか? 染井さん、モテそうだし」
「うーん、何から話したらいいのかな」
織音の瞳に、仄かな陰りが浮かんでいた。きらきらと夕照を滲ませ、炎のように揺らめいた虹彩に、確かな不満や怒りをくべているみたいだ。
「織音って名前、率直にどう思う?」
そう問われ、凪はすぐに答えることが出来なかった。どう反応をしても、彼女の求めている回答には辿り着けない気がする。
織音は以前、自分の名前が好きじゃないと言っていた。だから、下手に褒めるのは違うと思う。かといって、人の名前を否定するのはどうなんだろう。
色々な葛藤のせいで、沈黙が二人の間を漂う。
必死に正解を探す凪に、織音が「率直に、だよ」と念を押す。
「……星のように強く輝いていて、その、何て言うんだろうな。……染井さんにぴったりな名前だと思う、よ?」
織音がふっと小さく笑う。
「うん、正解」
そう言うものだから、凪は再び言葉を詰まらせた。絶対に織音の求める答えじゃないと思っていたのに、どうやら当たっていたらしい。
ただし、織音の瞳は依然として静かな怒りを抱えたままだった。
「でもね、あたしは昔からずっと嫌い。こんなきらきらした素敵な名前も、名付けた親も大っ嫌い」
感情の籠った強い言葉に、凪は思わず背筋を震わせた。
織音の両親は離婚していて、今は父親との二人暮らしのはず。今まで、織音は家族の話になると露骨に機嫌を悪くするのを凪は分かっていたから、意図的に避けていた話題だった。織音と両親の間には、何かしらの確執があるのだろう。
凪も自らの名前をあまり好ましく思わなかった時期がある。理由はよくあるもので、名前だけを見て女の子と間違えられることが恥ずかしかったからだ。そのせいで、面白がったクラスメートに〝ちゃん〟呼びされるのがすごく不愉快だった。
でも、織音の反応を見ていると、多分凪のような軽い原因ではないのだろう。もっと重たく、彼女を歪めた大きな理由がある。何となく、そう思った。
「そ、それで、恋愛と名前ってどう結びつくの……?」
「切り出しといてなんだけど、話すと長くなるんだよね。でも、端的にまとめるなら、あたしは両親のせいで愛してるとか、好きとかって感情が薄っぺらなんだ。なんなら、心の底から気持ち悪いと思ってる。……多分、つまらない人間なんだよ、あたしって。ほら、みんな恋愛で一喜一憂するでしょ? あたしはそれが出来ない。もったいない人間だよね」
振り返る。手を繋いだ男女は、確かに表情が明るい。幸せそうな雰囲気が漂って見える。
でも、凪も羨ましいとは思わなかった。自分が誰かに愛されるに値する人間だとは到底思っていないのだから。
本当に愛されるべきは、織音のような芯の通った人であるべきだ、と思ってしまうのは、彼女にとって酷いことなのだろうか。
織音はとにかく自分の世界が全て。自分が正しいと思ったことしか、受け入れられない人だ。彼女が、犬がにゃーと鳴くのが正解だと信じるのなら、他の誰もが間違っていると言っても、彼女には響かない。
凪が織音の横を歩けているのは、彼女の考える正義と凪の考える正義が、驚くくらい一緒だからだ。二人の違いは、そのことを表に出すのか、内に秘めるのかだけだ。
人によっては、織音のことを傲慢だと誹るのだろう。
しかし、織音はわざわざ自分の正義を他人に押し付けない。あくまでも、自分はこういう考えだという主張をするだけだ。自分の正義がマイノリティであると理解しているがゆえの考え方なのだろう。
そんな彼女が、唯一他者すらも目の敵にするのが、〝愛〟だ。
織音の根本すらも捻じ曲げるだけのトラウマって、一体何なんだろう。
「僕も好きとか、よく分からないよ」
本当のことだった。だって、好きになる程深く関わった人なんていない。両親や姉が自分に向けてくるような温かい感情を、凪は家族にもそれ以外の他者にも持ったことがなかった。自分のような人間がそういう感情を持つことは許しがたいことだとすら思う。
織音は凪を横目で見遣り、どこか安心したように笑みを零した。
「ねえ、あたしたち、ずっと友達でいようね」
凪が織音に感じていた羨望が、恋愛へと変形してしまったことに気が付いたのは、それからしばらくしてのことだった。
誰もかれも、生きるのが下手くそだ。
だから、僕はこの感情を一人で抱え込もうと思う。
思えば、一目惚れだったのだろう。そこに愛がなかったとしても、あの時、全てに不満を持ったような鮮烈とした雰囲気を漂わせる彼女に、凪は確かに堕ちていた。
だから、こうなってしまうことは必然だったのかもしれない。
凪が欲して止まないものを、織音は持ち合わせている。人の目を気にせず、敢然と自分の意思を打ち出す度胸に、凪はどうしようもなく憧れていた。
好きになってはいけない。友達のままでいなくてはいけない。そう思えば思う程、胸の奥で感情が膨らんでいく。排出路に溜まった汚い泡のような、あるべきではないそれが、コポッコポッと音を立てていた。
どこまでも、自分は愚かだ。
一人で立ち向かう勇気もないくせに、一緒にいてくれる人のタブーを犯そうとしている。織音の放つ強い光を浴びる程、凪の黒い感情がより色濃くなっていく。
光があるところに影があるって、こういうことじゃないような。
織音の傍にいたい。彼女に拒絶されたくない。でも、この膨らみ続ける感情はどうやって発散したらいい。抱え切れなくなって、溢れ出てしまうことが何よりも怖かった。
絶対に、織音にはバレちゃいけない。素直に打ち明けるなんて論外だ。彼女と違う価値観を提示すれば、今のままの関係じゃいられなくなることは、誰よりも織音と一緒にいる凪が一番よく分かっていた。
もしかしたら、織音は凪にほんの少し寄り添ってくれるかもしれない。この感情にも理解を見せてくれるかもしれない。
だとしても、凪のせいで織音が変わってしまうのは許しがたいことだ。
織音には完璧なままでいてほしい。あの日、凪を魅了してまんまと引きずり込んだ神様のままでいてほしい。
だから、このやましい想いはいらない。誰も望んでいない。凪も、もちろん望んでいない。勝手に膨らんでいくのだから、自分が一人で擦り潰していけばいいだけだ。織音にはバレないように、親友という関係が崩れないように。
でも、心のどこかでは分かっていたはずだ。一時的な気持ちの昇華のために愚かなことをしても、結局彼女のことを知れば知る程、底なしの沼に浸かっていくなんてことは。
ただ、それでも凪が織音に執着し続けたのは、やっぱりどこかで、彼女と親友じゃない新しい関係を夢見てしまっていたからだ。
勇気を出さなければ何も変わらないことは、十分過ぎるくらい分かっていたというのに――。
多分、織音を苦手としている人はクラスに一定数いる。でも、誰も織音の発言を妨げることも、否定することもなかった。きっとそれは、凪と同様、彼女に底抜けの魅力を感じ取っている人が多かったからだろう。
信頼を集めるわけでもなく、友達も決して多くはない。それでも、織音は隠し切れない強いカリスマ性のおかげで、クラス内のヒエラルキーは高かった。カースト上位の群れる陽キャたちに紛れ、孤独に輝く姿は、凪に言わせればまさに一等星のようだった。
そのおかげか、織音と関わるようになると、自然と凪への嫌がらせは減っていった。織音と対峙してまで、凪に対する執着を持つ必要が彼らにはなかったからだ。
凪と織音が互いに親友と認め合えるようになるまで、大して時間はいらなかった。
織音とは驚くくらい価値観が合う。だから、性格は全く違ったけど、喧嘩の一つだってしたことがない。親友だからこそ、何でも包み隠さず明け透けに話すことが出来た。
「あたし、恋愛ごとが本当に嫌いなの」
目の前を歩く男女が手を繋いだのを見て、織音は言った。足早に男女を追い抜かす彼女を凪は不思議に思いながらも追いかける。
「な、何かトラウマとか? 染井さん、モテそうだし」
「うーん、何から話したらいいのかな」
織音の瞳に、仄かな陰りが浮かんでいた。きらきらと夕照を滲ませ、炎のように揺らめいた虹彩に、確かな不満や怒りをくべているみたいだ。
「織音って名前、率直にどう思う?」
そう問われ、凪はすぐに答えることが出来なかった。どう反応をしても、彼女の求めている回答には辿り着けない気がする。
織音は以前、自分の名前が好きじゃないと言っていた。だから、下手に褒めるのは違うと思う。かといって、人の名前を否定するのはどうなんだろう。
色々な葛藤のせいで、沈黙が二人の間を漂う。
必死に正解を探す凪に、織音が「率直に、だよ」と念を押す。
「……星のように強く輝いていて、その、何て言うんだろうな。……染井さんにぴったりな名前だと思う、よ?」
織音がふっと小さく笑う。
「うん、正解」
そう言うものだから、凪は再び言葉を詰まらせた。絶対に織音の求める答えじゃないと思っていたのに、どうやら当たっていたらしい。
ただし、織音の瞳は依然として静かな怒りを抱えたままだった。
「でもね、あたしは昔からずっと嫌い。こんなきらきらした素敵な名前も、名付けた親も大っ嫌い」
感情の籠った強い言葉に、凪は思わず背筋を震わせた。
織音の両親は離婚していて、今は父親との二人暮らしのはず。今まで、織音は家族の話になると露骨に機嫌を悪くするのを凪は分かっていたから、意図的に避けていた話題だった。織音と両親の間には、何かしらの確執があるのだろう。
凪も自らの名前をあまり好ましく思わなかった時期がある。理由はよくあるもので、名前だけを見て女の子と間違えられることが恥ずかしかったからだ。そのせいで、面白がったクラスメートに〝ちゃん〟呼びされるのがすごく不愉快だった。
でも、織音の反応を見ていると、多分凪のような軽い原因ではないのだろう。もっと重たく、彼女を歪めた大きな理由がある。何となく、そう思った。
「そ、それで、恋愛と名前ってどう結びつくの……?」
「切り出しといてなんだけど、話すと長くなるんだよね。でも、端的にまとめるなら、あたしは両親のせいで愛してるとか、好きとかって感情が薄っぺらなんだ。なんなら、心の底から気持ち悪いと思ってる。……多分、つまらない人間なんだよ、あたしって。ほら、みんな恋愛で一喜一憂するでしょ? あたしはそれが出来ない。もったいない人間だよね」
振り返る。手を繋いだ男女は、確かに表情が明るい。幸せそうな雰囲気が漂って見える。
でも、凪も羨ましいとは思わなかった。自分が誰かに愛されるに値する人間だとは到底思っていないのだから。
本当に愛されるべきは、織音のような芯の通った人であるべきだ、と思ってしまうのは、彼女にとって酷いことなのだろうか。
織音はとにかく自分の世界が全て。自分が正しいと思ったことしか、受け入れられない人だ。彼女が、犬がにゃーと鳴くのが正解だと信じるのなら、他の誰もが間違っていると言っても、彼女には響かない。
凪が織音の横を歩けているのは、彼女の考える正義と凪の考える正義が、驚くくらい一緒だからだ。二人の違いは、そのことを表に出すのか、内に秘めるのかだけだ。
人によっては、織音のことを傲慢だと誹るのだろう。
しかし、織音はわざわざ自分の正義を他人に押し付けない。あくまでも、自分はこういう考えだという主張をするだけだ。自分の正義がマイノリティであると理解しているがゆえの考え方なのだろう。
そんな彼女が、唯一他者すらも目の敵にするのが、〝愛〟だ。
織音の根本すらも捻じ曲げるだけのトラウマって、一体何なんだろう。
「僕も好きとか、よく分からないよ」
本当のことだった。だって、好きになる程深く関わった人なんていない。両親や姉が自分に向けてくるような温かい感情を、凪は家族にもそれ以外の他者にも持ったことがなかった。自分のような人間がそういう感情を持つことは許しがたいことだとすら思う。
織音は凪を横目で見遣り、どこか安心したように笑みを零した。
「ねえ、あたしたち、ずっと友達でいようね」
凪が織音に感じていた羨望が、恋愛へと変形してしまったことに気が付いたのは、それからしばらくしてのことだった。
誰もかれも、生きるのが下手くそだ。
だから、僕はこの感情を一人で抱え込もうと思う。
思えば、一目惚れだったのだろう。そこに愛がなかったとしても、あの時、全てに不満を持ったような鮮烈とした雰囲気を漂わせる彼女に、凪は確かに堕ちていた。
だから、こうなってしまうことは必然だったのかもしれない。
凪が欲して止まないものを、織音は持ち合わせている。人の目を気にせず、敢然と自分の意思を打ち出す度胸に、凪はどうしようもなく憧れていた。
好きになってはいけない。友達のままでいなくてはいけない。そう思えば思う程、胸の奥で感情が膨らんでいく。排出路に溜まった汚い泡のような、あるべきではないそれが、コポッコポッと音を立てていた。
どこまでも、自分は愚かだ。
一人で立ち向かう勇気もないくせに、一緒にいてくれる人のタブーを犯そうとしている。織音の放つ強い光を浴びる程、凪の黒い感情がより色濃くなっていく。
光があるところに影があるって、こういうことじゃないような。
織音の傍にいたい。彼女に拒絶されたくない。でも、この膨らみ続ける感情はどうやって発散したらいい。抱え切れなくなって、溢れ出てしまうことが何よりも怖かった。
絶対に、織音にはバレちゃいけない。素直に打ち明けるなんて論外だ。彼女と違う価値観を提示すれば、今のままの関係じゃいられなくなることは、誰よりも織音と一緒にいる凪が一番よく分かっていた。
もしかしたら、織音は凪にほんの少し寄り添ってくれるかもしれない。この感情にも理解を見せてくれるかもしれない。
だとしても、凪のせいで織音が変わってしまうのは許しがたいことだ。
織音には完璧なままでいてほしい。あの日、凪を魅了してまんまと引きずり込んだ神様のままでいてほしい。
だから、このやましい想いはいらない。誰も望んでいない。凪も、もちろん望んでいない。勝手に膨らんでいくのだから、自分が一人で擦り潰していけばいいだけだ。織音にはバレないように、親友という関係が崩れないように。
でも、心のどこかでは分かっていたはずだ。一時的な気持ちの昇華のために愚かなことをしても、結局彼女のことを知れば知る程、底なしの沼に浸かっていくなんてことは。
ただ、それでも凪が織音に執着し続けたのは、やっぱりどこかで、彼女と親友じゃない新しい関係を夢見てしまっていたからだ。
勇気を出さなければ何も変わらないことは、十分過ぎるくらい分かっていたというのに――。