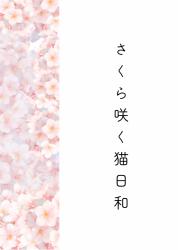文化祭までの日々は着々と過ぎていく。
基本的には放課後に同好会室で練習して、週末に紗蘭の家で、実際にピアノ伴奏と合わせて練習をする、といった感じだ。
紗蘭の家は、結構な豪邸だった。
広い庭はあるし、なんか高そうな車も停まってるし、スーツとか着てこなくて大丈夫だったのか?と最初は思ったが……
俺を出迎えてくれた紗蘭が中学のジャージを着ていたので、超安心した。
紗蘭は三歳のときからピアノを習っていたという。
でも、兄の方が上手すぎて、やる気をなくして中二でやめたらしい。
俺も兄ちゃんが頭いいから、勉強は昔から嫌いだった。
別に仲が悪いわけじゃないけど、生きてるだけで比較されるよな、なんて愚痴をこぼしたのも、紗蘭が初めてだった。
ただ、紗蘭が俺と違うのは、世間一般から見れば、十分ピアノが上手いと言われる部類に入る点だ。
実際、初めてそれを聴いたときは、歌を聴いたときと同じく、筆舌に尽くしがたい感動に飲み込まれた。
「……ぅか、響香、何ぼーっとしてるの」
「あ、わりぃ。なんだっけ」
紗蘭のピアノの余韻に浸っていたら、話が右から左へ抜けていってしまった。
「だから、ここ、もう少しボリューム大きくして。今のままだとバランスが悪いから」
「そうか?俺はそんな気になんなかったけど」
「僕は気になるよ。細かいところも妥協したくないんだけど」
「いや別に妥協ってわけじゃねーよ?俺だって本気だし」
「それならもう一回ちゃんと聴い……っ、ごめん……」
話し合いの途中、紗蘭が急に俯いて謝る。
いつもはグイグイ自分の意見を主張してくるのに、なんだ。
調子が狂う。
「え?マジでどうした?」
「中学のとき、部活で強く言いすぎて、揉めたことがあって……今、ふと、思い出したんだ」
意外だった。
周りの目なんか全く気にしないタイプかと思ってたのに。
「俺も結構強く言っちゃう方だし、お互い様だろ。あんまり遠慮してたらいいもんできねーし」
「響香……ありがとう」
「お、おう」
感謝の気持ちを向けられるのには慣れていない。
特に、こいつみたいな、普段はクールでツンツンとしたやつに関しては。
でも、否定されることの多かったありのままの俺を、ようやく認めてもらえたような気持ちになるから……照れくさいけど、純粋に嬉しい。
◇
文化祭前日の放課後。
俺たちは、全てのきっかけとも言える、あの河川敷の橋の下に来ていた。
「ここで二人で歌うのは初めてだよな」
「うん」
〜♪
夏の予感を感じさせる空気を思い切り吸い込んで、紗蘭と音を重ねる。
初めて話してからまだ三週間くらいしか経っていないのに、こんなにも気持ち良くデュエットできるなんて。
高校生ながらに、俺の人生の限界なんて知れてるって思ってたけど、予想外は案外起きるもんだな。
「……響香は、恋したことあるの?」
「え゙っ、なんで」
歌い終わったあと、紗蘭が変なことを聞いてくる。
まさか、これは、女子がよくやってる“恋バナ”ってやつか!?
「ちゅ、中学んときは、いたかも?しんねぇし、いないかも……」
「へぇ、好きな子いたんだ」
「ゔ……お前こそどーなんだよ!もしかして同じクラスとかにいんのか〜?」
「ううん。近所の歳上の人が好きだったけど、大学進学で遠くへ行っちゃったから、今はいない」
「歳上……」
こいつに好かれるって、一体どんな人間なんだ……!?
相当綺麗なモデルみたいなお姉さんなのか?
可愛くて、胸とか大きくて、肌がすべすべ……
「ねぇ、えっちなこと考えてない?」
「はぁ!?な、ななんでだよ!意味分かんねー!」
ドン引き〜とでも言いたげな目で見られて、顔がぼんっと熱くなる。
くそ、こいつだって健康な男子高校生のくせに。
絶対ちょっとくらい妄想とかすんだろ!……多分。
「そ、そもそも!なんで急に恋バナなんか……」
「僕たちが歌うの、ラブソングだから。響香はこんな気持ちになったことあるのかなって」
「……!そういうことかよ……それで言うと、まだないけど」
「ふふ、やっぱりね」
「おい」
くすくすと笑う紗蘭を軽く肘で突く。
こいつ、俺の前では結構笑うようになったと思う。
「……十年後、もしまた二人で歌えたらさ、同じ歌も違う風に聴こえるのかな」
「……かもな。ぜってぇに十年後までには彼女できるしー」
「ふーん、どうかな?」
憎たらしい返しをする紗蘭と、わーわー言い合いながら帰路につく。
西の空は雲ひとつなく、綺麗な夕焼け色に染まっていた。
◇
◇
◇
文化祭当日。
昼前の有志ステージ発表までは、俺も紗蘭も、自分のクラスの出し物の仕事で忙しくしていた。
本番前の緊張を、この忙しさで程よく誤魔化せたのは、好都合だったかもしれない。
「響香!」
「紗蘭、おつかれ」
体育館の近くで待ち合わせをして、いざステージ裏へと向かうと、同じく有志ステージに出る人たちが集まっているが……
蛍光色のスーツを着てる集団とか、いかにもマジシャンですって格好のやつとか、とにかく癖が強い。
対する俺たちは、めちゃくちゃ普通に制服だ。
「霞まないようにしないとな」
「ふふ、響香、緊張してる?」
「さあ、どうだろうな」
文化祭のプログラムが配布されてから、これまで話したことのなかったクラスメイトにも、有志出るんだって?と声をかけられることが増えた。
自ら一匹狼になって半端な不良をやってた俺に、よく話しかけてくれたよなぁとしみじみ思う。
中学のときと違って、歌を披露することを馬鹿にするやつは一人もいなかったし。
「行こ、響香」
「ああ」
俺を見つけてくれた人、俺を受け入れてくれた人。
今は、自分のためだけじゃなく、誰かのために歌いたいと思う。
「最初のパフォーマンスは、一年生の時雨紗蘭くんと五十嵐響香くんによるデュエット『点描の唄』です」
〜♪
しんと静まり返った体育館に、紗蘭が奏でる美しいピアノの音が響く。
そして、俺の発する一音目を待つ観客の視線が、この胸の真ん中にぎゅっと集まり、新鮮な高揚感を覚えた。
「―――」
ストレスを解消するための手段に過ぎなかった。
と、思っていたけど……そう言い聞かせるようになったのは、声を馬鹿にされてからだ。
それ以前の俺は、確かに歌が好きだった。
好きだという理由で、ただそれだけで、歌っていた。
そっか、本当はずっと、好きなんだ。
大好きなんだ。
歌を歌うことも、自分の歌声も。
紗蘭に出会って、心の底からそう思えた。
だから、紗蘭も……
♪〜――――――.
同じように思えていたらいいな。
……いや、
「響香……」
「紗蘭……」
歌い終わったお前の顔見れば、もう分かっちゃったよ。
「……楽しかったな!」
「……うん!」
紗蘭も、自分の“好き”を、思い出せたってこと!
◇
◇
◇
文化祭が無事に終わって、すっかり日常に戻った校舎の片隅。
俺たちは同好会室で、これからのことを話していた。
「で、紗蘭はどーしたいの」
「僕は……正直、とりあえず文化祭で響香と歌うことしか考えてなくて……」
「お前、それだけで同好会立ち上げるって、やっぱ行動力やべぇよな」
「だって、不良になり切れない孤立した生徒を引き込むには、そのくらいしないと無理かなって……」
「さらっと悪口言うな。事実だけど」
そのとき、コンコン、と扉を叩く音がする。
思わず紗蘭と顔を見合わせた。
この部屋に誰かが訪ねてくるなんて、初めてだから。
ガチャリと扉を開くと、そこには――。
「「入会希望です!!」」
新たに入会したいと言い出す者が数名。
なんと、俺たちのステージに感動して、ぜひ入りたいと思ったらしい。
もしかすると、合唱同好会が「部」に昇格する日は、あまり遠くないのかもしれない――?
基本的には放課後に同好会室で練習して、週末に紗蘭の家で、実際にピアノ伴奏と合わせて練習をする、といった感じだ。
紗蘭の家は、結構な豪邸だった。
広い庭はあるし、なんか高そうな車も停まってるし、スーツとか着てこなくて大丈夫だったのか?と最初は思ったが……
俺を出迎えてくれた紗蘭が中学のジャージを着ていたので、超安心した。
紗蘭は三歳のときからピアノを習っていたという。
でも、兄の方が上手すぎて、やる気をなくして中二でやめたらしい。
俺も兄ちゃんが頭いいから、勉強は昔から嫌いだった。
別に仲が悪いわけじゃないけど、生きてるだけで比較されるよな、なんて愚痴をこぼしたのも、紗蘭が初めてだった。
ただ、紗蘭が俺と違うのは、世間一般から見れば、十分ピアノが上手いと言われる部類に入る点だ。
実際、初めてそれを聴いたときは、歌を聴いたときと同じく、筆舌に尽くしがたい感動に飲み込まれた。
「……ぅか、響香、何ぼーっとしてるの」
「あ、わりぃ。なんだっけ」
紗蘭のピアノの余韻に浸っていたら、話が右から左へ抜けていってしまった。
「だから、ここ、もう少しボリューム大きくして。今のままだとバランスが悪いから」
「そうか?俺はそんな気になんなかったけど」
「僕は気になるよ。細かいところも妥協したくないんだけど」
「いや別に妥協ってわけじゃねーよ?俺だって本気だし」
「それならもう一回ちゃんと聴い……っ、ごめん……」
話し合いの途中、紗蘭が急に俯いて謝る。
いつもはグイグイ自分の意見を主張してくるのに、なんだ。
調子が狂う。
「え?マジでどうした?」
「中学のとき、部活で強く言いすぎて、揉めたことがあって……今、ふと、思い出したんだ」
意外だった。
周りの目なんか全く気にしないタイプかと思ってたのに。
「俺も結構強く言っちゃう方だし、お互い様だろ。あんまり遠慮してたらいいもんできねーし」
「響香……ありがとう」
「お、おう」
感謝の気持ちを向けられるのには慣れていない。
特に、こいつみたいな、普段はクールでツンツンとしたやつに関しては。
でも、否定されることの多かったありのままの俺を、ようやく認めてもらえたような気持ちになるから……照れくさいけど、純粋に嬉しい。
◇
文化祭前日の放課後。
俺たちは、全てのきっかけとも言える、あの河川敷の橋の下に来ていた。
「ここで二人で歌うのは初めてだよな」
「うん」
〜♪
夏の予感を感じさせる空気を思い切り吸い込んで、紗蘭と音を重ねる。
初めて話してからまだ三週間くらいしか経っていないのに、こんなにも気持ち良くデュエットできるなんて。
高校生ながらに、俺の人生の限界なんて知れてるって思ってたけど、予想外は案外起きるもんだな。
「……響香は、恋したことあるの?」
「え゙っ、なんで」
歌い終わったあと、紗蘭が変なことを聞いてくる。
まさか、これは、女子がよくやってる“恋バナ”ってやつか!?
「ちゅ、中学んときは、いたかも?しんねぇし、いないかも……」
「へぇ、好きな子いたんだ」
「ゔ……お前こそどーなんだよ!もしかして同じクラスとかにいんのか〜?」
「ううん。近所の歳上の人が好きだったけど、大学進学で遠くへ行っちゃったから、今はいない」
「歳上……」
こいつに好かれるって、一体どんな人間なんだ……!?
相当綺麗なモデルみたいなお姉さんなのか?
可愛くて、胸とか大きくて、肌がすべすべ……
「ねぇ、えっちなこと考えてない?」
「はぁ!?な、ななんでだよ!意味分かんねー!」
ドン引き〜とでも言いたげな目で見られて、顔がぼんっと熱くなる。
くそ、こいつだって健康な男子高校生のくせに。
絶対ちょっとくらい妄想とかすんだろ!……多分。
「そ、そもそも!なんで急に恋バナなんか……」
「僕たちが歌うの、ラブソングだから。響香はこんな気持ちになったことあるのかなって」
「……!そういうことかよ……それで言うと、まだないけど」
「ふふ、やっぱりね」
「おい」
くすくすと笑う紗蘭を軽く肘で突く。
こいつ、俺の前では結構笑うようになったと思う。
「……十年後、もしまた二人で歌えたらさ、同じ歌も違う風に聴こえるのかな」
「……かもな。ぜってぇに十年後までには彼女できるしー」
「ふーん、どうかな?」
憎たらしい返しをする紗蘭と、わーわー言い合いながら帰路につく。
西の空は雲ひとつなく、綺麗な夕焼け色に染まっていた。
◇
◇
◇
文化祭当日。
昼前の有志ステージ発表までは、俺も紗蘭も、自分のクラスの出し物の仕事で忙しくしていた。
本番前の緊張を、この忙しさで程よく誤魔化せたのは、好都合だったかもしれない。
「響香!」
「紗蘭、おつかれ」
体育館の近くで待ち合わせをして、いざステージ裏へと向かうと、同じく有志ステージに出る人たちが集まっているが……
蛍光色のスーツを着てる集団とか、いかにもマジシャンですって格好のやつとか、とにかく癖が強い。
対する俺たちは、めちゃくちゃ普通に制服だ。
「霞まないようにしないとな」
「ふふ、響香、緊張してる?」
「さあ、どうだろうな」
文化祭のプログラムが配布されてから、これまで話したことのなかったクラスメイトにも、有志出るんだって?と声をかけられることが増えた。
自ら一匹狼になって半端な不良をやってた俺に、よく話しかけてくれたよなぁとしみじみ思う。
中学のときと違って、歌を披露することを馬鹿にするやつは一人もいなかったし。
「行こ、響香」
「ああ」
俺を見つけてくれた人、俺を受け入れてくれた人。
今は、自分のためだけじゃなく、誰かのために歌いたいと思う。
「最初のパフォーマンスは、一年生の時雨紗蘭くんと五十嵐響香くんによるデュエット『点描の唄』です」
〜♪
しんと静まり返った体育館に、紗蘭が奏でる美しいピアノの音が響く。
そして、俺の発する一音目を待つ観客の視線が、この胸の真ん中にぎゅっと集まり、新鮮な高揚感を覚えた。
「―――」
ストレスを解消するための手段に過ぎなかった。
と、思っていたけど……そう言い聞かせるようになったのは、声を馬鹿にされてからだ。
それ以前の俺は、確かに歌が好きだった。
好きだという理由で、ただそれだけで、歌っていた。
そっか、本当はずっと、好きなんだ。
大好きなんだ。
歌を歌うことも、自分の歌声も。
紗蘭に出会って、心の底からそう思えた。
だから、紗蘭も……
♪〜――――――.
同じように思えていたらいいな。
……いや、
「響香……」
「紗蘭……」
歌い終わったお前の顔見れば、もう分かっちゃったよ。
「……楽しかったな!」
「……うん!」
紗蘭も、自分の“好き”を、思い出せたってこと!
◇
◇
◇
文化祭が無事に終わって、すっかり日常に戻った校舎の片隅。
俺たちは同好会室で、これからのことを話していた。
「で、紗蘭はどーしたいの」
「僕は……正直、とりあえず文化祭で響香と歌うことしか考えてなくて……」
「お前、それだけで同好会立ち上げるって、やっぱ行動力やべぇよな」
「だって、不良になり切れない孤立した生徒を引き込むには、そのくらいしないと無理かなって……」
「さらっと悪口言うな。事実だけど」
そのとき、コンコン、と扉を叩く音がする。
思わず紗蘭と顔を見合わせた。
この部屋に誰かが訪ねてくるなんて、初めてだから。
ガチャリと扉を開くと、そこには――。
「「入会希望です!!」」
新たに入会したいと言い出す者が数名。
なんと、俺たちのステージに感動して、ぜひ入りたいと思ったらしい。
もしかすると、合唱同好会が「部」に昇格する日は、あまり遠くないのかもしれない――?