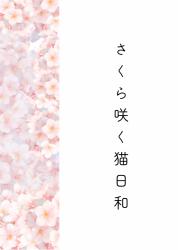「で、部員は何人いんの?てか、部室って音楽室じゃねぇの?」
合唱部に入ると決めた翌日。
早速、放課後に活動をすると言うからついてきたけど……
「……ここだよ」
「え?」
紗蘭が立ち止まったのは、明らかに使われていなさそうな空き教室の前。
ガチャガチャと古そうな鍵を開け、扉を開くと――
「っ!うわ!埃だらけじゃねーか!!」
「……そうだね」
「はぁ?ほんとにここで合ってんの?」
「うん。合ってるよ」
「掃除して使えってか?酷すぎんだろ!つーか、他の奴らはまだ来ねぇの?」
「……来ないよ、誰も」
「は?」
紗蘭の発言に耳を疑う。
こいつは、今、誰も来ないと言った?
え?何それ?急なホラー展開?
「……僕が作ったのは、『合唱部』じゃないんだ」
「っ、え、マジでホラー展開じゃん」
「僕が作ったのはね……」
紗蘭は意味深な視線を俺に向けたあと、ゆっくりと近づいてくる。
妙な緊張感に心臓がざわめいて、思わずごくりと唾を飲み込んだ。
紗蘭はそんな俺にお構いなく、耳元に口を寄せた。
「『同好会』だよ」
「……は……」
「僕が作ったの、合唱『部』じゃなくて『同好会』。部員は、僕と響香だけ」
「……え?」
呆然としている俺を見て、紗蘭は真顔で「てへぺろ」と軽やかに言ってみせた。
「なんじゃそりゃぁああ!!!」
◇
紗蘭による衝撃の告白から二時間。
ついに、最終チェックのときが来た。
「っ……」
俺は静かに跪き、部屋の隅を指で撫でる。
「……!」
それを確認するや否や、振り返って紗蘭を見つめた。
「……!」
紗蘭も確認を終えたあと、俺たちは同時にグッジョブポーズを天に掲げた――。
「……埃なし、掃除終了ォ!!!!!」
「あー疲れたー」
「てめぇほぼ何もやってねーだろ」
「酷いなぁ」
合唱同好会、活動初日。
記録・部屋の大掃除。以上。
「ったく、もうこんな時間。帰らなきゃじゃん」
「そうだね」
近くのホームセンターに掃除用品を買いに行き、超がつくほど集中して部室(同好会室?)を掃除して……
部屋が綺麗になる頃には、外はすっかり暗くなっていた。
ちなみに、紗蘭は掃除開始直後からくしゃみを連発したため、ほとんど見学させる羽目になり、実質俺が一人で掃除した……。
「そもそも、なんで部活って嘘ついたんだよ」
帰り道、隣を歩く紗蘭に尋ねる。
紗蘭とは背の高さがほとんど同じだから、そいつが少し気まずそうに目線を逸らしたのがすぐに分かった。
「……同好会って伝えたら、響香が『ショボい』って言うかなって」
「おいお前の中で俺はどんなイメージなんだよ鬼か?」
「ある意味?不良だし」
「正直だな……はぁ、不良なのは否定しねーけど、別にショボいなんて思わねーよ。好きなことやるのに、ショボいも何もあってたまるか」
「……!」
「え、何その顔」
なぜか、紗蘭が目をまん丸にして俺を見るから、若干居心地が悪い。
すぐにいつもの真顔に戻ったから、ちょっと安心したけど。
「ていうかさ、明日から何すんの俺たち」
「歌を歌うよ」
「いやまあそうだけど……合唱っていうから、てっきりコンクールか何かに出んのかと思ってたけど、二人だと無理だし」
「……明日、楽譜を持ってくるよ」
うむ、会話にならない。
しかし、何かしらの考えはあるみてぇだし、明日聞くのでも遅くはないだろう。
◇
「文化祭の有志ステージ、申し込んだから」
「はぁ!?」
「とりあえず、早く響香と歌いたい。直近で歌える場所って、文化祭じゃない?」
「そ、そうだけどお前、もう一ヶ月ないくらいだぞ!?一刻も早くやんねぇとやべぇじゃん!」
明日からでも遅くない……と思った昨日の自分を殴りたい。
活動二日目、紗蘭は涼しい顔で、来月の文化祭に出ると言い出した。
「僕と響香なら大丈夫でしょ。そんなに不安?」
「っ!べ、別に?不安とか?思ってねーし?」
紗蘭の発言にまんまと煽られて、五歳男児みたいな返しをしてしまった。
俺の精神年齢が低く見えるとしたら、それは兄ちゃんのせいだ。
あの日だって、彼女にフラれた兄ちゃんが、ちっちゃなことで八つ当たりしてきたから、俺までストレスが爆発して……
そんで、あの河川敷で歌ってたところを、紗蘭に見られていて……
だから俺は今、こいつと一緒に歌おうとしていて……
そう考えると、もしかすると俺は、兄ちゃんに感謝すべきなのかも……なんてな!
ムカつくからそんなこと思ってやんねーぞ。
「はいこれ、楽譜ね」
「おー」
脳内で調子に乗り始めた兄ちゃんを追い払って、紗蘭に手渡された楽譜を見る。
「……これって……」
そこには、俺もよく知る楽曲の名前が書いてあった。
「『点描の唄』……あの日、歌ってたよね」
そう、河川敷で歌っていたのは、まさにこの曲だった。
デュエットできる曲だけど、あのときは当然一人で歌っていたし、この先誰かと歌うことも考えていなかった。
「あのとき、響香の歌を聴いて、僕は……この歌声に音を重ねるのは、他の誰でもなく僕がいいと思ってしまった」
「……!」
紗蘭は、まるで恋をしているかのような声と言い方で、俺へ特大のアプローチをしてきた。
そんな切なげな顔で、そんな熱いことを言われてしまったら……
「……紗蘭」
「……?」
「ぜっったい成功させるぞ!!」
ボルテージも上がっちまうってもんだろ!!
「っしゃ、早速歌ってみ……あれ、これ誰がピアノ弾くん」
「あ、それは大丈夫。僕が弾くから」
「は!?ほんとに大丈夫!?」
「もう弾けるから。それに、響香は弾けないでしょ」
先ほど愛の告白(のようなもの)をしてくれた紗蘭はどこへやら、澄ました顔でスパッとそう言い切られる。
ぐぬぬ……と、悔しがる俺をよそに、紗蘭はスマホを取り出して、何やら再生ボタンをタップした。
〜♪
「……!」
流れてきたのは、点描の唄のイントロ。
美しいピアノの音は、紗蘭が演奏したものなのだろう。
「さ、歌って」
「!ああ……」
一番は、俺のソロパートから始まる。
改まって歌うのは少し緊張するが、それよりも今は……ワクワクの方が勝っている。
息を吸って、声帯を震わせる。
目を閉じれば、自分でも女みたいだと思う声だ。
何度もバカにされた高い声。
紗蘭は、本当に、この声を……?
チラリと紗蘭の顔を覗く。
表情は……いつもとあまり変わらない。
若干の不安を感じる中、まもなく紗蘭のパートが――。
「っ……!」
その歌声が鼓膜まで届いたとき、身体の芯に、すうっと撫でられたような感覚が走る。
感動という言葉では表しきれない心の震えが存在することを、俺は今、初めて知った。
「ちょっと響香、歌うのやめないでよ」
「ぁ……っ、わりぃ、いや、だって……」
じわじわと顔が熱くなるのが分かる。
この熱は、怒りでも闘争心でもない。
けど、ぴたりと当てはまる感情が見つからない。
でも、そうだな、例えるなら、それはまるで……
……ああ、そうか、だからさっき、紗蘭は――。
「……惚れたんだから仕方ねぇだろ」
「は?」
「俺も、紗蘭の歌に、惚れた!」
「っ!」
「だから早く歌いたい!ほら最初からやんぞ!」
再生時間を0:00までスライドして戻す。
胸の高鳴りが止まらない。
だって、お互い相手の歌に惚れたっていうならさ、それが重なったときは――。
重なる瞬間、紗蘭と視線を交えた。
言葉じゃ表せないものも、歌にしたら伝えられるのだと思えた。
俺たちは今、確かに、この歌を通して会話をしているから。
「……楽しかったな」
「うん……僕は、響香と歌うために、声変わりしたのかもしれない」
「……!俺も、そうかも」
コンプレックスが愛おしくなったこの日から、俺と紗蘭の合唱同好会は、本格的に始動した。
合唱部に入ると決めた翌日。
早速、放課後に活動をすると言うからついてきたけど……
「……ここだよ」
「え?」
紗蘭が立ち止まったのは、明らかに使われていなさそうな空き教室の前。
ガチャガチャと古そうな鍵を開け、扉を開くと――
「っ!うわ!埃だらけじゃねーか!!」
「……そうだね」
「はぁ?ほんとにここで合ってんの?」
「うん。合ってるよ」
「掃除して使えってか?酷すぎんだろ!つーか、他の奴らはまだ来ねぇの?」
「……来ないよ、誰も」
「は?」
紗蘭の発言に耳を疑う。
こいつは、今、誰も来ないと言った?
え?何それ?急なホラー展開?
「……僕が作ったのは、『合唱部』じゃないんだ」
「っ、え、マジでホラー展開じゃん」
「僕が作ったのはね……」
紗蘭は意味深な視線を俺に向けたあと、ゆっくりと近づいてくる。
妙な緊張感に心臓がざわめいて、思わずごくりと唾を飲み込んだ。
紗蘭はそんな俺にお構いなく、耳元に口を寄せた。
「『同好会』だよ」
「……は……」
「僕が作ったの、合唱『部』じゃなくて『同好会』。部員は、僕と響香だけ」
「……え?」
呆然としている俺を見て、紗蘭は真顔で「てへぺろ」と軽やかに言ってみせた。
「なんじゃそりゃぁああ!!!」
◇
紗蘭による衝撃の告白から二時間。
ついに、最終チェックのときが来た。
「っ……」
俺は静かに跪き、部屋の隅を指で撫でる。
「……!」
それを確認するや否や、振り返って紗蘭を見つめた。
「……!」
紗蘭も確認を終えたあと、俺たちは同時にグッジョブポーズを天に掲げた――。
「……埃なし、掃除終了ォ!!!!!」
「あー疲れたー」
「てめぇほぼ何もやってねーだろ」
「酷いなぁ」
合唱同好会、活動初日。
記録・部屋の大掃除。以上。
「ったく、もうこんな時間。帰らなきゃじゃん」
「そうだね」
近くのホームセンターに掃除用品を買いに行き、超がつくほど集中して部室(同好会室?)を掃除して……
部屋が綺麗になる頃には、外はすっかり暗くなっていた。
ちなみに、紗蘭は掃除開始直後からくしゃみを連発したため、ほとんど見学させる羽目になり、実質俺が一人で掃除した……。
「そもそも、なんで部活って嘘ついたんだよ」
帰り道、隣を歩く紗蘭に尋ねる。
紗蘭とは背の高さがほとんど同じだから、そいつが少し気まずそうに目線を逸らしたのがすぐに分かった。
「……同好会って伝えたら、響香が『ショボい』って言うかなって」
「おいお前の中で俺はどんなイメージなんだよ鬼か?」
「ある意味?不良だし」
「正直だな……はぁ、不良なのは否定しねーけど、別にショボいなんて思わねーよ。好きなことやるのに、ショボいも何もあってたまるか」
「……!」
「え、何その顔」
なぜか、紗蘭が目をまん丸にして俺を見るから、若干居心地が悪い。
すぐにいつもの真顔に戻ったから、ちょっと安心したけど。
「ていうかさ、明日から何すんの俺たち」
「歌を歌うよ」
「いやまあそうだけど……合唱っていうから、てっきりコンクールか何かに出んのかと思ってたけど、二人だと無理だし」
「……明日、楽譜を持ってくるよ」
うむ、会話にならない。
しかし、何かしらの考えはあるみてぇだし、明日聞くのでも遅くはないだろう。
◇
「文化祭の有志ステージ、申し込んだから」
「はぁ!?」
「とりあえず、早く響香と歌いたい。直近で歌える場所って、文化祭じゃない?」
「そ、そうだけどお前、もう一ヶ月ないくらいだぞ!?一刻も早くやんねぇとやべぇじゃん!」
明日からでも遅くない……と思った昨日の自分を殴りたい。
活動二日目、紗蘭は涼しい顔で、来月の文化祭に出ると言い出した。
「僕と響香なら大丈夫でしょ。そんなに不安?」
「っ!べ、別に?不安とか?思ってねーし?」
紗蘭の発言にまんまと煽られて、五歳男児みたいな返しをしてしまった。
俺の精神年齢が低く見えるとしたら、それは兄ちゃんのせいだ。
あの日だって、彼女にフラれた兄ちゃんが、ちっちゃなことで八つ当たりしてきたから、俺までストレスが爆発して……
そんで、あの河川敷で歌ってたところを、紗蘭に見られていて……
だから俺は今、こいつと一緒に歌おうとしていて……
そう考えると、もしかすると俺は、兄ちゃんに感謝すべきなのかも……なんてな!
ムカつくからそんなこと思ってやんねーぞ。
「はいこれ、楽譜ね」
「おー」
脳内で調子に乗り始めた兄ちゃんを追い払って、紗蘭に手渡された楽譜を見る。
「……これって……」
そこには、俺もよく知る楽曲の名前が書いてあった。
「『点描の唄』……あの日、歌ってたよね」
そう、河川敷で歌っていたのは、まさにこの曲だった。
デュエットできる曲だけど、あのときは当然一人で歌っていたし、この先誰かと歌うことも考えていなかった。
「あのとき、響香の歌を聴いて、僕は……この歌声に音を重ねるのは、他の誰でもなく僕がいいと思ってしまった」
「……!」
紗蘭は、まるで恋をしているかのような声と言い方で、俺へ特大のアプローチをしてきた。
そんな切なげな顔で、そんな熱いことを言われてしまったら……
「……紗蘭」
「……?」
「ぜっったい成功させるぞ!!」
ボルテージも上がっちまうってもんだろ!!
「っしゃ、早速歌ってみ……あれ、これ誰がピアノ弾くん」
「あ、それは大丈夫。僕が弾くから」
「は!?ほんとに大丈夫!?」
「もう弾けるから。それに、響香は弾けないでしょ」
先ほど愛の告白(のようなもの)をしてくれた紗蘭はどこへやら、澄ました顔でスパッとそう言い切られる。
ぐぬぬ……と、悔しがる俺をよそに、紗蘭はスマホを取り出して、何やら再生ボタンをタップした。
〜♪
「……!」
流れてきたのは、点描の唄のイントロ。
美しいピアノの音は、紗蘭が演奏したものなのだろう。
「さ、歌って」
「!ああ……」
一番は、俺のソロパートから始まる。
改まって歌うのは少し緊張するが、それよりも今は……ワクワクの方が勝っている。
息を吸って、声帯を震わせる。
目を閉じれば、自分でも女みたいだと思う声だ。
何度もバカにされた高い声。
紗蘭は、本当に、この声を……?
チラリと紗蘭の顔を覗く。
表情は……いつもとあまり変わらない。
若干の不安を感じる中、まもなく紗蘭のパートが――。
「っ……!」
その歌声が鼓膜まで届いたとき、身体の芯に、すうっと撫でられたような感覚が走る。
感動という言葉では表しきれない心の震えが存在することを、俺は今、初めて知った。
「ちょっと響香、歌うのやめないでよ」
「ぁ……っ、わりぃ、いや、だって……」
じわじわと顔が熱くなるのが分かる。
この熱は、怒りでも闘争心でもない。
けど、ぴたりと当てはまる感情が見つからない。
でも、そうだな、例えるなら、それはまるで……
……ああ、そうか、だからさっき、紗蘭は――。
「……惚れたんだから仕方ねぇだろ」
「は?」
「俺も、紗蘭の歌に、惚れた!」
「っ!」
「だから早く歌いたい!ほら最初からやんぞ!」
再生時間を0:00までスライドして戻す。
胸の高鳴りが止まらない。
だって、お互い相手の歌に惚れたっていうならさ、それが重なったときは――。
重なる瞬間、紗蘭と視線を交えた。
言葉じゃ表せないものも、歌にしたら伝えられるのだと思えた。
俺たちは今、確かに、この歌を通して会話をしているから。
「……楽しかったな」
「うん……僕は、響香と歌うために、声変わりしたのかもしれない」
「……!俺も、そうかも」
コンプレックスが愛おしくなったこの日から、俺と紗蘭の合唱同好会は、本格的に始動した。