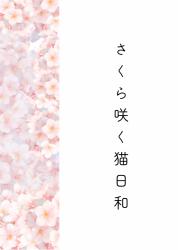「いってぇな……」
先ほど殴られた頬を押さえながら、校舎裏の壁にもたれかかり、ゆるゆるとしゃがむ。
ちょうど午後の授業の始まりを告げるチャイムが鳴ったが、不良の俺には関係ない。
俺にとっては、一日中昼休みみたいなものだ。
「ったく、しつけーんだよなー、あいつら」
今日俺を呼び出してきたのは、近隣の不良高校のやつら。
俺の高校じゃ不良は異分子だが、あそこは逆に不良ばかり集まっている。
先月から何度も俺に絡んでくるような、ネチネチとしつこい集団だ。
そもそも、喧嘩の発端はあいつらの――――
「あ、見つけた」
「あ゙?」
突然、柔らかい声が頭上から降ってきて、思わず威嚇するような目つきで顔を上げた。
「……誰だお前」
そこにいたのは、琥珀色の澄んだ瞳をした男子だった。
ネクタイの色からして、同じ一年か。
「へぇ、君、ほんとに不良みたいだね」
授業が行われている時間にも関わらず、のんびりとした口調で話すそいつは、不思議なものを見るような目で、俺の顔をまじまじと見つめる。
「なんだよマジで。授業中だろ」
「それは君もでしょ。今日は君に用があって」
「はぁ?なんの用?」
そいつはよいしょ、と俺の隣にしゃがんで、透明感のあるまっすぐな瞳で俺を捉え、口を開いた。
「合唱部に入って」
「……は?」
「だから、合唱部に入って」
一度目は、聞き間違えたかと思った。
しかし、こいつは二度も同じことを言った。
どうやら、聞き間違いの可能性はなさそうだ。
「合唱〜!?」
「そう。合唱部。入ってくれる?」
「いや待て待て、うちの高校に合唱部ねぇだろ」
「昨日、僕が作った」
「昨日〜!?」
「そう。昨日。入ってくれる?」
「お前なぁ……」
あまりにも強烈な勧誘内容とこいつのキャラクターに、少々頭が痛くなる。
「えーっと、合唱部があんのは分かったけど、なんで急に?なんで俺?」
入学して日も浅いし、俺はこいつと初対面のはずだ。
全く親しくない。名前すら知らない。
それなのになぜ、ピンポイントで俺を誘う?
普通の人間なら、純粋に疑問に思うだろ。
「だって……君、すごく声が綺麗で、歌も上手いでしょ」
「っ……!」
心臓がバクンと大きく跳ねた。
衝撃がビリビリと全身に走る。
「な、なんで、それ……」
驚きのあまり声が震える俺に対し、そいつは平然とした様子で話す。
「?この前、河川敷の橋の下で歌ってたでしょ」
「え……嘘だろ、聴いてたのか」
一ヶ月前、入学式の直前。
兄ちゃんと喧嘩して、むしゃくしゃした気持ちが限界に達していた俺は、気づけば橋の下へと駆け出していた。
俺は、昔から、ストレスが溜まりに溜まったとき、どうしようもなく歌いたくなる。
そういうときは、決まってあの河川敷の橋の下へ向かうんだ。
誰もいないあの場所で、思いっきりお腹から声を出して歌うと、胸に渦巻いていたモヤモヤが、すっきりと晴れていくような感覚になるから。
でも、あの日……
偶然通った不良高校の奴らが、俺が歌う様子を面白がって、からかってきたんだ。
まあ、そういうのには慣れてたから、最初は相手にしなかったんだけどさ……結局は手出しちゃって、そしたら今月になってもこの有様。
しつこいにも程があるだろ。
「ねぇ、無視しないでよ」
「はぁ?」
「合唱部に入ってくれる?」
「はぁ〜……やだね。合唱なんてまともにやったことねぇし。てかやる気ないし。俺以外をあたってくれー」
ひらひらと手を振って顔を背けたが、そいつは全く帰ろうとしない。
え、何、俺の方がどっか行かなきゃなんねぇの?
「……そっか、じゃあ、合唱部は廃部だね」
「は!?なんで!?昨日できたんだろ!?」
すん……と光のない目で遠くを見つめるそいつの肩を、ゆさゆさと強く揺さぶった。
「だって、君がいないなら意味ないよ」
「っ、はぁ……?俺より歌上手いやつは星の数ほどいるって」
「僕は君が入る前提で部活を作ったんだ。だから、君がいないなら廃部」
「だーかーら、なんで廃部なんだよ!もったいねぇだろ!」
「じゃあ入ってくれる?」
「っ……お前、そういう作戦か。廃部にするって脅せば入ると思ったか?俺は騙されないからな」
ふん、と今度こそ背中を向けて、そいつから離れることにした。
何を言われても俺は動じないぞ……と強い意志を持って……
「……」
何も言ってこないから、チラリと後ろを確認すると、
「なに?入る気になったの?」
と、迫られる。
「あーもー!うるさい!入らねーよ!じゃあな!」
三度目の正直で、俺はその場から走り去った。
もう絶対に振り返らない。
不良以外で頭がおかしいやつに絡まれると、本当に調子が狂う。
……あ、名前、聞くの忘れた……。
いや、別に、もう関わることないし、どうでもいいけど。
◇
「おはよう。合唱部、入ってくれる?」
「こんにちは。合唱部、入ってくれる?」
「お疲れ様。合唱部、入ってくれる?」
合唱部合唱部合唱部合唱部合唱部……
いよいよ、幻聴が聞こえてきそうだ。
初めて勧誘されたあの日から一週間。
あの頭がイカれた美人は、懲りることなく毎日、朝昼夕必ず一度ずつは俺を勧誘しにくる。
最初こそ軽く反応してやってたけど、三日目あたりからはガン無視しているというのに……めげずに話しかけてくるあたり、粘ればこっちが折れるとでも思っているのだろう。
「なぁ、時雨が放課後何してるか知ってる?」
そんなある日、帰り際に突然そんなことを聞いてきたのは、同じクラスで見たことあるやつ。
名前は覚えてない。
「時雨って誰?」
「えっ!時雨紗蘭だよ!最近いつも一緒にいるじゃん。俺、同じ中学だったんだよ」
「あー、あいつか。時雨って名前なんだ、初耳だわ」
「っ、それより!さっき偶然、時雨に会ったんだけど、なんか、珍しく急いでてさ。『河川敷に行って勝負をつける』とか言ってて、ちょっと心配なんだけど、」
そこまで聞いて、俺は急いで靴を履き、全力で駆け出した。
外は小雨が降っていた。
しとしとと静かに湿っていく制服が鬱陶しかった。
ひんやりと肌を滑る雨粒とは裏腹に、お腹の奥底では、何かが熱くメラメラと燃える感覚がある。
「っ!」
河川敷の橋の下に、時雨と不良高校の奴らを見つけた。
予感が現実になり、生まれて初めての焦燥感に襲われる。
そして同時に自覚する。
“俺は、時雨紗蘭を守りたい”と。
「おい、てめぇら」
「あ゙?」
時雨の腕を掴んでいた男が振り向いた瞬間、頬に一発。
「おいてめぇ!」
横からの蹴りをかわして、またまた一発。
次から次へと飛んでくる攻撃は、決して弱くないはずなのに、なぜか今日は……前よりずっと、遅く感じる。
「……二度とこいつに手ぇ出すんじゃねぇぞ」
見くびっていた相手に制圧され、呆気に取られた野郎どもの顔は、酷く情けないものだった。
失せろと言えば慌てて立ち上がり、ふらふらよろけながら去っていく。
「……おい、怪我は」
奴らに掴まれていた腕をそっと持ち上げて観察すると、
「五十嵐響香くん、ありがとう。大丈夫だよ」
「……!」
ふんわりとした声に名前を呼ばれた。
思わず顔を上げると、時雨紗蘭が……笑っていた。
「……なんで、俺の名前知ってんの」
「君と同じクラスの人に聞いた。僕の名前はね、」
「時雨紗蘭……だろ」
「あ、響香も知ってたんだ」
「……なんで、こんなとこで絡まれてたんだよ」
「昨日、ここで歌ってたんだ。あんなに綺麗な歌を歌う響香のお気に入りの場所って、どんなところなんだろうって気になって。そしたら、変な人たちに話しかけられた」
「はぁ……なに、俺のことなんか言われて、怒ってくれたわけ?」
「……僕はただ、自分が素敵だと思ったものを、素敵だと主張したかっただけだよ」
紗蘭は穏やかな瞳で、遠くを眺めながらそう言った。
凪のような雰囲気を纏いながら、内側では火傷しそうなほど熱い想いを燃やしている……時雨紗蘭はそういう人間なのだと、今初めて実感した気がする。
「……さっきの、同じ中学の奴ら。俺、こんな声だから、中学の頃は『女みたいな声だー』って馬鹿にされてたの。それから人前で歌うのが嫌になっちゃったってわけ」
あーあ。
こんなこと、誰かに話すつもりなかったのに。
紗蘭の横顔を見てたら、自然と口が動いてた。
「……僕は、中三のコンクール直前、声変わりしたんだ」
「……!」
「いつそうなってもおかしくなかったから、ソロパートの代役もいたし、本番も無事に終わったけどね」
紗蘭の過去を聞いた俺は、見事に何も言えなかった。
どんな言葉をかけたとしても、紗蘭の胸に刻まれた傷は、一生消えることがないと分かるから。
「もう歌はやらない。そう思ってたのに……響香のせいで、全部ひっくり返ったんだよ」
ふふ、と静かに微笑む紗蘭に、俺が言えること。
それは、「辛かったな」とか「悔しかったな」とか、そんな同情の言葉じゃなくて……
「紗蘭」
「?」
俺が、言うべきこと、言いたいことは――
「……俺と一緒に、歌ってくれ!」
「……!響香……」
雲の切れ間から差し込んだ光が、紗蘭の瞳を煌めかせたある春の日のこと。
俺は、紗蘭が作った合唱部に入部することを決めた。
先ほど殴られた頬を押さえながら、校舎裏の壁にもたれかかり、ゆるゆるとしゃがむ。
ちょうど午後の授業の始まりを告げるチャイムが鳴ったが、不良の俺には関係ない。
俺にとっては、一日中昼休みみたいなものだ。
「ったく、しつけーんだよなー、あいつら」
今日俺を呼び出してきたのは、近隣の不良高校のやつら。
俺の高校じゃ不良は異分子だが、あそこは逆に不良ばかり集まっている。
先月から何度も俺に絡んでくるような、ネチネチとしつこい集団だ。
そもそも、喧嘩の発端はあいつらの――――
「あ、見つけた」
「あ゙?」
突然、柔らかい声が頭上から降ってきて、思わず威嚇するような目つきで顔を上げた。
「……誰だお前」
そこにいたのは、琥珀色の澄んだ瞳をした男子だった。
ネクタイの色からして、同じ一年か。
「へぇ、君、ほんとに不良みたいだね」
授業が行われている時間にも関わらず、のんびりとした口調で話すそいつは、不思議なものを見るような目で、俺の顔をまじまじと見つめる。
「なんだよマジで。授業中だろ」
「それは君もでしょ。今日は君に用があって」
「はぁ?なんの用?」
そいつはよいしょ、と俺の隣にしゃがんで、透明感のあるまっすぐな瞳で俺を捉え、口を開いた。
「合唱部に入って」
「……は?」
「だから、合唱部に入って」
一度目は、聞き間違えたかと思った。
しかし、こいつは二度も同じことを言った。
どうやら、聞き間違いの可能性はなさそうだ。
「合唱〜!?」
「そう。合唱部。入ってくれる?」
「いや待て待て、うちの高校に合唱部ねぇだろ」
「昨日、僕が作った」
「昨日〜!?」
「そう。昨日。入ってくれる?」
「お前なぁ……」
あまりにも強烈な勧誘内容とこいつのキャラクターに、少々頭が痛くなる。
「えーっと、合唱部があんのは分かったけど、なんで急に?なんで俺?」
入学して日も浅いし、俺はこいつと初対面のはずだ。
全く親しくない。名前すら知らない。
それなのになぜ、ピンポイントで俺を誘う?
普通の人間なら、純粋に疑問に思うだろ。
「だって……君、すごく声が綺麗で、歌も上手いでしょ」
「っ……!」
心臓がバクンと大きく跳ねた。
衝撃がビリビリと全身に走る。
「な、なんで、それ……」
驚きのあまり声が震える俺に対し、そいつは平然とした様子で話す。
「?この前、河川敷の橋の下で歌ってたでしょ」
「え……嘘だろ、聴いてたのか」
一ヶ月前、入学式の直前。
兄ちゃんと喧嘩して、むしゃくしゃした気持ちが限界に達していた俺は、気づけば橋の下へと駆け出していた。
俺は、昔から、ストレスが溜まりに溜まったとき、どうしようもなく歌いたくなる。
そういうときは、決まってあの河川敷の橋の下へ向かうんだ。
誰もいないあの場所で、思いっきりお腹から声を出して歌うと、胸に渦巻いていたモヤモヤが、すっきりと晴れていくような感覚になるから。
でも、あの日……
偶然通った不良高校の奴らが、俺が歌う様子を面白がって、からかってきたんだ。
まあ、そういうのには慣れてたから、最初は相手にしなかったんだけどさ……結局は手出しちゃって、そしたら今月になってもこの有様。
しつこいにも程があるだろ。
「ねぇ、無視しないでよ」
「はぁ?」
「合唱部に入ってくれる?」
「はぁ〜……やだね。合唱なんてまともにやったことねぇし。てかやる気ないし。俺以外をあたってくれー」
ひらひらと手を振って顔を背けたが、そいつは全く帰ろうとしない。
え、何、俺の方がどっか行かなきゃなんねぇの?
「……そっか、じゃあ、合唱部は廃部だね」
「は!?なんで!?昨日できたんだろ!?」
すん……と光のない目で遠くを見つめるそいつの肩を、ゆさゆさと強く揺さぶった。
「だって、君がいないなら意味ないよ」
「っ、はぁ……?俺より歌上手いやつは星の数ほどいるって」
「僕は君が入る前提で部活を作ったんだ。だから、君がいないなら廃部」
「だーかーら、なんで廃部なんだよ!もったいねぇだろ!」
「じゃあ入ってくれる?」
「っ……お前、そういう作戦か。廃部にするって脅せば入ると思ったか?俺は騙されないからな」
ふん、と今度こそ背中を向けて、そいつから離れることにした。
何を言われても俺は動じないぞ……と強い意志を持って……
「……」
何も言ってこないから、チラリと後ろを確認すると、
「なに?入る気になったの?」
と、迫られる。
「あーもー!うるさい!入らねーよ!じゃあな!」
三度目の正直で、俺はその場から走り去った。
もう絶対に振り返らない。
不良以外で頭がおかしいやつに絡まれると、本当に調子が狂う。
……あ、名前、聞くの忘れた……。
いや、別に、もう関わることないし、どうでもいいけど。
◇
「おはよう。合唱部、入ってくれる?」
「こんにちは。合唱部、入ってくれる?」
「お疲れ様。合唱部、入ってくれる?」
合唱部合唱部合唱部合唱部合唱部……
いよいよ、幻聴が聞こえてきそうだ。
初めて勧誘されたあの日から一週間。
あの頭がイカれた美人は、懲りることなく毎日、朝昼夕必ず一度ずつは俺を勧誘しにくる。
最初こそ軽く反応してやってたけど、三日目あたりからはガン無視しているというのに……めげずに話しかけてくるあたり、粘ればこっちが折れるとでも思っているのだろう。
「なぁ、時雨が放課後何してるか知ってる?」
そんなある日、帰り際に突然そんなことを聞いてきたのは、同じクラスで見たことあるやつ。
名前は覚えてない。
「時雨って誰?」
「えっ!時雨紗蘭だよ!最近いつも一緒にいるじゃん。俺、同じ中学だったんだよ」
「あー、あいつか。時雨って名前なんだ、初耳だわ」
「っ、それより!さっき偶然、時雨に会ったんだけど、なんか、珍しく急いでてさ。『河川敷に行って勝負をつける』とか言ってて、ちょっと心配なんだけど、」
そこまで聞いて、俺は急いで靴を履き、全力で駆け出した。
外は小雨が降っていた。
しとしとと静かに湿っていく制服が鬱陶しかった。
ひんやりと肌を滑る雨粒とは裏腹に、お腹の奥底では、何かが熱くメラメラと燃える感覚がある。
「っ!」
河川敷の橋の下に、時雨と不良高校の奴らを見つけた。
予感が現実になり、生まれて初めての焦燥感に襲われる。
そして同時に自覚する。
“俺は、時雨紗蘭を守りたい”と。
「おい、てめぇら」
「あ゙?」
時雨の腕を掴んでいた男が振り向いた瞬間、頬に一発。
「おいてめぇ!」
横からの蹴りをかわして、またまた一発。
次から次へと飛んでくる攻撃は、決して弱くないはずなのに、なぜか今日は……前よりずっと、遅く感じる。
「……二度とこいつに手ぇ出すんじゃねぇぞ」
見くびっていた相手に制圧され、呆気に取られた野郎どもの顔は、酷く情けないものだった。
失せろと言えば慌てて立ち上がり、ふらふらよろけながら去っていく。
「……おい、怪我は」
奴らに掴まれていた腕をそっと持ち上げて観察すると、
「五十嵐響香くん、ありがとう。大丈夫だよ」
「……!」
ふんわりとした声に名前を呼ばれた。
思わず顔を上げると、時雨紗蘭が……笑っていた。
「……なんで、俺の名前知ってんの」
「君と同じクラスの人に聞いた。僕の名前はね、」
「時雨紗蘭……だろ」
「あ、響香も知ってたんだ」
「……なんで、こんなとこで絡まれてたんだよ」
「昨日、ここで歌ってたんだ。あんなに綺麗な歌を歌う響香のお気に入りの場所って、どんなところなんだろうって気になって。そしたら、変な人たちに話しかけられた」
「はぁ……なに、俺のことなんか言われて、怒ってくれたわけ?」
「……僕はただ、自分が素敵だと思ったものを、素敵だと主張したかっただけだよ」
紗蘭は穏やかな瞳で、遠くを眺めながらそう言った。
凪のような雰囲気を纏いながら、内側では火傷しそうなほど熱い想いを燃やしている……時雨紗蘭はそういう人間なのだと、今初めて実感した気がする。
「……さっきの、同じ中学の奴ら。俺、こんな声だから、中学の頃は『女みたいな声だー』って馬鹿にされてたの。それから人前で歌うのが嫌になっちゃったってわけ」
あーあ。
こんなこと、誰かに話すつもりなかったのに。
紗蘭の横顔を見てたら、自然と口が動いてた。
「……僕は、中三のコンクール直前、声変わりしたんだ」
「……!」
「いつそうなってもおかしくなかったから、ソロパートの代役もいたし、本番も無事に終わったけどね」
紗蘭の過去を聞いた俺は、見事に何も言えなかった。
どんな言葉をかけたとしても、紗蘭の胸に刻まれた傷は、一生消えることがないと分かるから。
「もう歌はやらない。そう思ってたのに……響香のせいで、全部ひっくり返ったんだよ」
ふふ、と静かに微笑む紗蘭に、俺が言えること。
それは、「辛かったな」とか「悔しかったな」とか、そんな同情の言葉じゃなくて……
「紗蘭」
「?」
俺が、言うべきこと、言いたいことは――
「……俺と一緒に、歌ってくれ!」
「……!響香……」
雲の切れ間から差し込んだ光が、紗蘭の瞳を煌めかせたある春の日のこと。
俺は、紗蘭が作った合唱部に入部することを決めた。