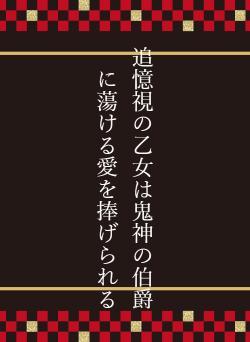風がどうっと吹いた。
木々のざわめきが夜空を震わせる。
今まで空を厚く覆っていた雲はいつしか消え失せ、隠されていた月が現れた。
月光に照らされ、花那の絹のような髪が艶やかに輝きを放った。
そんな花那の姿を真っ直ぐに見つめ、男――鬼道 豪は驚きと喜びで声を震わせながら言った。
「ようやく会えた。ずっと、ずっと君を探していたんだ」
そして次の瞬間、気づけば花那は豪の逞しい腕に閉じ込められていた。
その腕は決して花那を離さないという意志を表すように強いものであった。
突然のことに驚く花那をギュッと抱きしめた豪は、花那の耳元でしっかりとした言葉で囁いた。
「君を愛している」
少しだけ体を離した豪は、花那の瞳をじっと見つめた。
異能を持つ人間特有の青い目には、花那の泣きそうな顔が映っている。
「俺の運命。必ず君を幸せにすると誓おう」
柔らかく微笑む豪の表情は、花那に対する慈愛に満ちたもので、花那はその眼差しから豪の確かな愛を感じることができた。
豪と出会ったあの日。
そして結婚を申し込まれたあの日。
まさか花那にこのような幸福が訪れるとは思わなかった。
全てを受け入れてもらえた喜び、そして愛される喜びを噛みしめながら、豪の腕の中で、花那は全てが始まった日のことを思い返した。
※
大正十三年 卯月——
その日は風が強い日だった。
空は厚い雲に覆われ、今にも雨が降りそうだ。
(一雨くるかしら)
縁側の長い廊下を歩く足を止め、窓から空を見上げた花那はそう思った。
雨は嫌いだ。
両親が死んだ日を思い出すから。
だが、月夜はもっと嫌いだ。
自分の醜さが分かってしまうから。
花那は両親が亡くなった日のことを思い出して、ぼんやりとお盆に乗ったティーカップを見つめた。
琥珀色の紅茶には物憂げな自分の顔が映っている。
「ちょっと、ぼうっとしてないで早く彩様にお茶を運んでちょうだい!」
「は、はい」
「本当に使えない子ね。彩様の機嫌を損ねたら私まで怒られちゃうでしょ!」
「すみません」
花那は慌てて彩の部屋まで向かった。
その時、2人の女中が外出着や小間物を持って彩の部屋から出てきた。
「そういえば、聞いてる? 近所の森に禍牛が出たみたい。討伐隊が出ているらしいわよ」
「知らなかった! じゃ、夜は出歩かないようにしようかな」
禍牛とは人に禍をもたらす妖のことだが、軍からの討伐隊が来ているということなら、大事には至らないだろう。
花那がそんなことを考えているうちに、女中達は姦しく噂話を続けながら、花那の存在などいないかのように脇を通り過ぎて行った。
女中達の後ろ姿を見送った花那が彩の部屋に入ると、そこには薄紅色のワンピースを着た彩の姿があった。
上機嫌で姿見の前に立っていた彩は、花那の姿を鏡越しに見つけた途端、一気に顔を曇らせた。
「遅いわよ。紅茶を持ってくるだけでなんでこんなに時間かかるのよ!」
「も、申し訳ありません」
怒鳴られた花那は、その荒々しい言葉にびくりと肩を震わせた後、テーブルの上にティーカップをゆっくりと置いた。
その時ドアがノックされ、先ほどすれ違った女中の一人が部屋に入ってきた。
「どうぞ、お持ちいたしました」
「ありがとう」
彩が女中から受け取ったものを見て、花那は息を呑んだ。
それは、桜の花を模した摘まみ細工でできた髪飾りであり、母の形見だったからだ。
「そうそう、やっぱり髪飾りが無いと少し寂しいと思っていたのよね。ほら、この洋装にぴったりよね」
彩は女中から受け取った髪飾りを平然と自分の髪に挿し、満足そうに頷いた。
普段はなるべく息を潜めるようにして過ごしていた花那だったが、その髪飾りを見た瞬間思わず声を上げていた。
「そ、それは私の髪飾りです!」
父が亡くなり、叔父一家がこの家を相続した際、花那は私物のほとんどを取り上げられてしまっていた。
そのため形見という形見は手元に残っていない。
唯一手元に残った母の髪飾りが、何故彩の手元にあるのだろう。
「だってこの間あなたが持っているのを見て、気に入ったんだもの」
「……それは私の部屋に置いてあったはずです」
「ええ、そうよ。でもあなたの部屋は家主である私の部屋も同然。部屋に入って持ってきても問題ないわよね」
その答えに花那は驚きと困惑を隠せずにいると、彩はニヤリと意地の悪い笑みを浮かべた。
「この髪飾り、返してほしい?」
「もちろんです……。それはお母様の形見ですから」
花那は懇願するように答えた。何があってもこの髪飾りだけは返してほしい。
「でもこの洋装にこの髪飾りがぴったりなの。そうねぇ、この代わりがあれば返してあげてもいいわ」
「え……」
代わりと言われても、花那には髪飾り一つ持っていないのだ。
差し出したくても差し出せるものは無い。
答えられずに黙り込んでしまった花那を尻目に、彩は言葉を続けた。
「別の髪飾りはお父様に買ってもらっているの。今日店に取りに行く予定だったけど、取りに行けなかったのよ。だから、あなたが取りに行って」
「今から、ですか?」
「もちろん。だって明日のデエトに着けていくんだもの。当然でしょ?」
その時、花那の頭の中で女中達が先ほど言っていた言葉が蘇った。
彼女達はこの近辺で禍牛が出たと言っていた。
「あの……こんな夕方に出かけたら、帰りに禍牛に出会ってしまうかもしれません……」
「火狐を祖とする興津の人間ならば禍牛など倒せるはずでしょ? ああ、あなたはこの家の人間じゃないんだったわ。ふふふふ」
妖を祖とする一族の人間ならば、その異能の力で禍牛を退治することができる。
興津家は火狐の妖の血筋であり、彩を始めとして興津の人間は皆火を操る異能を持つ。
だが、花那は興津家の人間であるにも関わらずそれがない。
それを分かっていて彩はこのような無理難題を提案してきたのだ。
「行くならさっさと行きなさいよ!」
「……はい」
もし禍牛に襲われたら、無力な花那は死ぬ可能性もある。
それでも母の形見を諦めることはできなかった。
花那は意を決してそう言うと、夕闇迫る中、街へと向かうことにした。
※
曇りの日の夕暮れは、暗くなるのがいつも以上に早く感じる。
先ほどまで立ち込めていた雲は、更にその色を増し、風は湿り気を帯びてきていた。
薄暗くなる道を、花那は足早に歩く。
早くしなければ花飾りを受け取って帰る頃には、帰り道は暗闇に閉ざされてしまうだろう。
となると最悪の場合、夜に紛れて禍牛が現れるかもしれない。禍牛の姿を思い浮かべ、背中にゾクリと寒気が走った。
その時だった。
耳にざわりという葉音が聞こえてきて、花那は驚いて思わず足を止めた。
(もしかして……禍牛……?)
一瞬そう思った花那の耳に、今度は小さな呻き声が聞こえた。
花那は音がした草むらに目を凝らしつつ、恐る恐る近づいてみると、そこにいたのは一人の青年だった。
力なくうつ伏せに倒れている姿を認めた瞬間、花那は慌てて駆け寄った。
「大丈夫ですか!?」
「うっ……」
花那の呼びかけに、青年は小さく呻き声を漏らすだけだった。
見ると黒い服は土にまみれ、切り傷もあるようだった。
助けを呼ぶべきだろう。
だが周囲を見回しても夕暮れ時のせいか、人の姿は見えない。
(ど、どうしたらいいのかしら)
その一方で、花那は彩の命令で街に行かなければならない。
彩の言いつけを破れば、叔父である宏次郎から酷い折檻を受けるのは目に見えている上、母の形見も失ってしまう。
(でも……やっぱり、放ってはおけないわ)
人の命を救えるのであれば、自分が殴られるくらい平気だ。
痛みなどとうに慣れてしまっている。
母の形見を失うことは辛いが、それでも人が傷ついているのを見て見ぬふりは出来ない。
「大丈夫ですか? しっかりなさってください」
だが青年は苦悶の表情を浮かべたままで、花那の呼びかけには答えなかった。
そっと頬に触れると熱い。
「私の屋敷にお連れします。少し歩けますか?」
何度か青年の肩を揺すり、耳元で話しかけると、青年はようやくうっすらと目を開いた。
「すまな……い……」
花那は青年の腕を自らの肩に掛けると、青年を引きずるようにして屋敷へと戻った。
※
小さな体の花那が大の男を運ぶのは骨が折れた。少々雨に降られてしまったものの、本降りになる前に何とか屋敷に辿り着くことができた。
息を切らして玄関に駆け込むと、迎えた女中が目を丸くして驚いた。
「ま、まぁ! 何?」
「すみません、怪我人の手当てをしてくださいませんか?」
髪をしっとりと濡らし、息せき切らせながらそう言った花那に、女中は眉をひそめたかと思うと、そのまま屋敷の奥へと消えていった。
そしてすぐにその騒ぎを聞きつけた彩がやって来て開口一番に怒鳴った。
「ちょっと、髪飾りはどうしたのよ!」
「この方が怪我をされていて……」
「はぁ? そんな男より私の髪飾りの方が重要でしょ! 明日は正一郎様とのデエトなのよ!」
花那が懇願したが彩の怒りは収まらず、彩は手を振り上げた。
同時にパンという音がして花那の頬に痛みが走る。思わず倒れ込んだ花那を彩は怒りに満ちた目で見下ろした。それに対し、花那は土下座をして頼み込んだ。
「髪飾りは明日朝一番で取りに行きます。ですからこの方の手当てをさせてください」
「何があったんだ?」
そう言いながら奥からやって来たのは叔父の宏次郎だった。
花那はその姿を認めた瞬間、今度は宏次郎に向かって更に頭を下げて懇願を続けた。
「旦那様、どうかこの方の手当てをさせてください」
宏次郎は花那を一瞥した後、ぐったりとしたまま花那に寄りかかる青年に目を向け、そして冷たく言い放った。
「なんなんだこの男は」
「道で倒れていらっしゃったのです。怪我をされていて、熱もあるようなのです」
「どこの馬の骨か分からん男を拾って来たのか? 薬だってタダじゃない。こんな男など助けても一銭にもならんじゃないか。さっさと追い出せ」
「それでも、見捨てることはできません。お願いします!」
「〝色無し〟の分際で、当主の俺に意見するつもりか!」
雷のような大きな声で怒鳴られ、花那の肩がびくりと震える。
だが、人の命がかかっているのだ。ここで引き下がるわけにはいかない。
「ど、どんな罰も受けます。ですからお願いします……」
繰り返し花那が頼むと、突然宏次郎にグッと髪を掴まれて顔を上げさせられた。
かと思うと、先ほどよりも頬を思い切り殴られていた。
花那の体が吹き飛び、痛みと衝撃で目がちかちかした。
その様子を宏次郎は鼻を鳴らして一瞥したあと、鋭い口調で言った。
「ふん、介抱なら自分の部屋でしろ。部屋から一歩でも外に出すな。分かったな」
「……ありがとうございます」
花那は再び深く頭を下げて礼を言うと、苛立たし気に顔を歪めた彩も宏次朗に続いて、屋敷の奥へと消えていった。
それを見送った花那はほっと胸を撫で下ろすと、再び青年の肩を揺すって声を掛けた。
「すみません。もう少しで部屋なので、歩いていただけますか?」
相変わらず眉間に皺を寄せた青年は、小さく頷くだけの返事をした。
そうして花那は何とか青年を自室に運ぶことができたのだった。
※
外はすっかり夜の帳が下り、降りだした雨が容赦なく窓ガラスを叩いた。
花那の部屋にある灯りは蝋燭の灯だけ。
そのため布団に横たわる青年の顔色は良く分からないものの、眉間には深く皺が寄り、呼吸が乱れているところから熱があるのは一目瞭然だ。
体中にあった切り傷も手当をしたが、青年の綺麗な顔についた傷が痛々しく見える。
(なんとか手当は終わったけど、熱が下がらないのは心配だわ)
そう思いながら眉をひそめた花那は青年を見つめた。
青年は端正な顔立ちをしていた。
目の形は分からないが、高く通った鼻梁に薄い唇、前髪が少し長めの黒髪には艶がある。
部屋に運んで気づいたのは、青年が軍服を身に着けていたことだ。
推測ではあるが禍牛の討伐隊の一人で、禍牛と戦ったために傷を負ったのかもしれない。
(私の微弱な治癒の力じゃ、治せないかもしれないけど……)
花那は少しでも青年の傷が治り、熱が下がることを祈りつつ、そっと青年の手を握った。
そして目を閉じて、手に意識を集中する。
興津家には相応しくない程、微弱な異能の力。
花那はそれを使って青年の治癒を試みた。
すると少しだけ青年の呼吸の乱れが無くなり、眉間の皺が無くなったように見えるのは気のせいだろうか?
花那はそう思いつつ、青年の額にある濡らした手ぬぐいを取り替えた。
そうして、何度も手ぬぐいを取り換えているうち、外の雨は止み、窓からは朝日が差し込み始めた。
その頃には青年は穏やかな表情になっており、そっと額に触れると熱も下がったようだった。
(良かった)
花那が安堵していると、青年の睫毛がふるりと揺れ、ゆっくりと目を覚ました。
「ここは……」
「気づきましたか?」
青年は少しだけぼんやりと天井を見つめたあと、花那の言葉にゆっくりと体を起こした。
「無理なさらないでください」
「すまない……ここはどこだ?」
「ここは興津家の屋敷です。街に行く途中の道でお倒れになっていて、お連れしたのですが……」
花那が答えると、青年はふと何かに気づいたようだ。
「熱が引いている? ……まさか」
「まだ動かれては、傷が痛んでしまいます」
青年は慌てた様子で腕の包帯を解いたあと、ぽつりと呟くように言った。
「治っている……」
「え?」
青年が驚きのあまり、ぽつりと呟くように言った言葉に、花那も驚いて青年の腕を見た。
すると確かに昨日深々とあったはずの切り傷が無くなっていた。
「どういうことだ? ……君、私の手当てをした人間を呼んでくれ!」
「あの、私ですが……」
「君が?」
花那が小さく頷くと青年は居ずまいを正してから頭を下げた。
「そうか。助けてくれてありがとう。礼を言う。君、名前は?」
「興津花那と申します」
「興津? この屋敷の人間か?」
青年の問いに花那は言い淀んでしまった。
花那は興津の人間ではあるが、叔父達には興津家の人間とは認めてもらえていない。
むしろ、興津を名乗るなと言われ、使用人として扱われている。
だから胸を張って興津の人間だとは答えられなかったのだ。
口ごもった花那を見た青年はその態度の意味を捉えきれなかったようで、少しだけ訝し気な表情を浮かべた後、真っ直ぐに花那を見た。
「一つ聞きたい。君は俺の熱をどうやって鎮めたんだ?」
「あ……あの……普通に手ぬぐいで冷やしただけです」
「本当にそれだけか? その他に何かしたんじゃないのか?」
身を乗り出して尋ねられたが、青年は何故こんなにも必死に尋ねるのか分からない。
普通の手当てをしただけなのだ。
だが、その答えは青年が求めているそれとは違うものだったようで、更に花那に答えを促してきた。
あまりにも真剣に見つめられるので、他に自分がしたことをもう一度振り返って答えた。
「その……私には少しだけ治癒の力があるのでそれを使いました。微弱すぎて異能とは言えない程度なのですが……」
「治癒の力……」
青年は花那の答えに何か逡巡し、無言となる。
そんな青年の様子に花那が戸惑っていると、突然我に返ったように青年が花那に向き直った。
「ああ、すまなかった。まだ名乗っていなかったな。俺は」
青年が名乗ろうと口を開いた時だった。
何の音沙汰もなく、突然襖が乱暴に開かれた。
同時に声を荒げて入ってきたのは彩だった。
「ちょっと! 早く髪飾りを取ってきなさいよ! あなた、朝一番に行くって言ったわよね!」
眦を釣り上げた彩は不意に青年に目を留め、今度は息を呑んで目を丸くしたかと思うと、ほんのりと顔を赤らめた。
「あなたはこの屋敷の御息女か?」
青年の問いかけに、彩は先ほどの怒りの表情がすっかり消え去り、代わりに上品に微笑みながら答えた。
「え? ええそうですわ」
「俺の名前は鬼道豪と言う。この屋敷に電話があるのなら貸していただきたい」
「……鬼道? ま、まさか鬼道財閥の!? お、お父様、早くいらっしゃって!」
彩が驚きの声を上げたが、花那もまたその名前を聞いて息を呑んだ。
鬼道と言えば五大華族の財閥の一つだ。
妖を祖とする一族は社会的地位も高い。それゆえ興津家もそれなりに裕福な家だ。
だがその中でも最も力を持つのは五大華族であり、膨大な富を持ち、財閥を築いている。
しかも五大華族の中でも鬼道家は鬼神の力を有する最も力のある名家だ。
青年の正体に花那も驚いて声を出せずにいると、彩の声に宏次郎が面倒臭そうにやってきた。
「なんだ、彩。朝から騒々しい。またあの厄介者が粗相でもしたのか?」
「お父様、この方、鬼道豪様よ!」
「鬼道豪……鬼道家ご当主様でいらっしゃいますか!」
「ああ。介抱いただき感謝する」
「と、とんでもございません! こんな見窄らしいお部屋にお通しして申し訳ありません。ささ、こちらに」
慌てふためいた宏次郎は豪の手を引くと、部屋から出ていこうとする。そして、豪が何か言おうとする言葉を遮るように、宏次郎は花那を一瞥して鋭く命じた。
「おい、お前は早く茶を持ってくるんだ」
「は、はい。かしこまりました」
深く頭を下げて答えた花那が顔を上げた時には、宏次郎も彩も、そして豪の姿もなかった。
※
その後、豪とは再び顔を会わせることはなかった。
(傷が悪化していないといいのだけど……)
あれほどの高熱を出した後だ。
部屋を出る時には平気な様子であったが、やはり再度発熱していたらと、花那は心配していた。
だが、女中のような身分の花那が、鬼道財閥当主である豪と連絡を取ることなど不可能だ。ひっそりと無事を祈るほかないだろう。
そう思いながら花那が朝食の後片付けをしていると、台所の外がにわかに慌ただしくなった。
(どなたかいらっしゃったのかしら?)
首を傾げていると、女中の一人が花那に向かって鋭く命じた。
「手が離せないんだから、ぼうっとしてないで応接室にお茶を運びなさいよ」
「は、はい」
花那は慌ててお茶を用意して応接室に向かっていると、突然彩が横から現われ、出合い頭にぶつかってしまった。
「何やってるのよ! 危うくスカートが汚れるところだったじゃない!」
「も、申し訳ありません」
花那はいつものように慌てて土下座をすると、彩はその様子を上から見下した。
「まぁいいわ。今日は許してあげる。あなたなんかに構っている時間はないから」
彩は自慢気にそう言うと、優越感に満ちた笑みで花那を見た。
「ふふふ、鬼道様から縁談を申し込まれたのよ! 私が鬼道家に嫁入りしたら、あなたも下働きでついてきてもいいわよ」
「彩、準備ができたなら早く来なさい」
「はぁい、お父様!」
応接室から顔を覗かせた宏次郎が彩を急かした後、花那を一瞥する。
「お前はさっさと茶を持ってこい」
「……は、はい。畏まりました」
数日前に顔を合わせた豪が彩と婚姻を結ぶことに少々驚いたものの、花那は彩の追うように急いで応接室に向かった。
応接室に入ると、そこには既に豪の姿があった。
先日とは打って変わって顔色も良く、傷も無いように見え、花那は内心ほっと胸を撫で下ろした。
だが宏次郎からはさっさと出ていけという無言の圧を感じ、素早く部屋を出ようとした。
その時だった。
豪が花那を呼び止めた。
「君もここにいてくれ」
「……私、ですか?」
何故自分がこの場に残らねばならないのか戸惑いつつ、花那は小さく頷いてドアのところに控えた。
それを見た豪は一瞬眉をひそめたが、そんな豪の様子には気にも留めず、宏次郎はにこやかな笑顔で話を切り出した。
「いやぁ、この度は大変素晴らしいご縁をいただき、誠にありがとうございます。娘も鬼道様に見初められたことを、とても喜んでおりますよ」
宏次郎の言葉に、隣に座る彩がほんのりと頬を染めながら控えめに豪を見た。
突然の縁談に沸き立つ二人を見た豪は、二人とは対照的に硬い表情を浮かべていた。
その目はとても縁談を申し込みに来た人間とは思えない程冷たい色が宿っていた。
すると豪は静かに口を開いた。
「いや、婚姻を申し込みたいのは貴殿のご息女ではない」
「え?」
豪の言葉に宏次郎も、そして彩も驚きの表情を浮かべた。
理解が及ばなかったのか、宏次郎は一瞬言葉を失ったあと、慌てて豪に尋ねた。
「ど、どういうことでしょうか? 本日のご用件は彩へご縁談のお申し込みをいただけると思っておりましたが」
「私が結婚を申し込みたいのは彼女だ」
(私……?)
豪が視線を向けた先にいたのは花那だった。
「なっ……! この女は能無しですよ! あなた様のような高貴な方には相応しくありませんよ!」
豪の言葉の意味を理解した宏次郎は慌てふためいてそう言った。
彩もまた立ち上がって豪に訴えた。
「そうです。私はこの興津家の正当な血筋の人間ですわ。ですがこの女は異能の力もなく、興津の恥なのです!」
「彩の言う通りです。お考え直しください。こんな興津家の恥さらしを、鬼道様のようなお家柄に嫁がせるのは無理でございます」
慌てふためく宏次郎と彩を冷たく見据えた豪は、静かに、だが畏怖を覚えるような声で唐突に言った。
「貴殿は金が好きなのだろう?」
「え?」
「花那が俺を屋敷に運んだ時、貴殿は言ったな。『こんな男など助けても一銭にもならない』と」
「!」
「ならばこの金で彼女を買おう」
豪はそう言うと、花那が見たこともない数の札束を鞄から取り出すと、宏次郎の目の前でそれを宙に放り投げた。
お札は空中を舞い、ひらりひらりと宏次郎の前に落ちていく。
「金が不足するのなら屋敷まで来るといい」
あまりの展開に言葉を失っている宏次郎を豪は一瞥したかと思うと、花那の肩を抱きながら部屋を出た。
車に乗せられた花那は、そのまま大きな洋館に連れてこられた。
どうやらここは鬼道家の屋敷のようだった。
見たことのない異国の置物や、ダマスク柄が施された深い緑色の壁紙。
段通で出来た絨毯の敷かれた部屋に通されたのだが、花那は自分の身に起きていることが全く理解できずにいた。
目の前のソファに豪が腰を下ろすと、戸惑う花那を真っ直ぐに見つめた。
「さっきの話の通りだ。君に婚姻を申し込む」
豪は先ほど興津家で言った言葉を再度口にした。
どういう意味か理解できないでいる花那に、豪は言葉を続ける。
「介抱してくれた礼だと思ってくれ。俺の妻になれば誰にも文句を言われることなく贅沢が出来るだろう。あぁ、婚姻と言っても俺を愛する必要はない」
「あ、あの程度の事でそこまでのお礼は不要でございます。当然のことをしたまでですから」
「君の親戚はそうではないようだったがな」
豪は嘲笑を浮かべて吐き捨てるように言った。
その顔には宏次郎達に対する不快感が現われていた。
「それでも、私のような者と婚姻を結ぶなど……」
先程宏次郎が言ったのはもっともな話だった。
興津家の中でも異能の力がほとんどない花那が、鬼神の力を持つ由緒正しい鬼道家に嫁入りするなど、不相応すぎる。
固辞する花那を見た豪は、続きの言葉を口にした。
「実は代わりと言っては何だが一つ頼みたいことがある。その治癒の力で俺を癒してほしい」
「ですが私の治癒の力はあまりに弱くて、普通の人間のおまじない程度です。それなのに治癒の力を使っても、癒せるのは難しいと思います」
「いや、君なら出来る。今までで俺を治癒できた人間は君と、もう一人しか俺は知らない」
「え?」
「鬼道家は鬼神を祖とするが俺はその血を濃く受け継いでいる。だから、異能を使いすぎると器である体が力に耐えられない。俺が熱を出して倒れたのはそのためだ」
話を聞くと、女中達が噂していた禍牛の討伐隊というのは豪達のことだった。
禍牛の討伐に向かった討伐隊だったが、一個小隊がやられ、部下を退却させるために豪は足止めをしたせいで力を使いすぎて倒れたらしい。
「しかし普通の治癒師の力では鬼神の力が強すぎて、治癒させることができない。だが、君はそれができた」
まさか自分にそんな力があるとは思っていなかった。
「引き受けてくれないだろうか?」
それは花那にとって最良の提案であり、興津の家を出ることができる。
そしてこの微弱な異能の力でも人の役に立てるかもしれない。
だが、花那にはとある秘密がある。それが露見すればこの提案は無くなるだろう。
一抹の不安がよぎったが、その考えを振り切るように豪を真っ直ぐに見つめて答えた。
「分かりました。お引き受けいたします」
花那はそう答えると、窓を叩きつける雨音を聞きながら鬼道家で暮らす決心をした。
木々のざわめきが夜空を震わせる。
今まで空を厚く覆っていた雲はいつしか消え失せ、隠されていた月が現れた。
月光に照らされ、花那の絹のような髪が艶やかに輝きを放った。
そんな花那の姿を真っ直ぐに見つめ、男――鬼道 豪は驚きと喜びで声を震わせながら言った。
「ようやく会えた。ずっと、ずっと君を探していたんだ」
そして次の瞬間、気づけば花那は豪の逞しい腕に閉じ込められていた。
その腕は決して花那を離さないという意志を表すように強いものであった。
突然のことに驚く花那をギュッと抱きしめた豪は、花那の耳元でしっかりとした言葉で囁いた。
「君を愛している」
少しだけ体を離した豪は、花那の瞳をじっと見つめた。
異能を持つ人間特有の青い目には、花那の泣きそうな顔が映っている。
「俺の運命。必ず君を幸せにすると誓おう」
柔らかく微笑む豪の表情は、花那に対する慈愛に満ちたもので、花那はその眼差しから豪の確かな愛を感じることができた。
豪と出会ったあの日。
そして結婚を申し込まれたあの日。
まさか花那にこのような幸福が訪れるとは思わなかった。
全てを受け入れてもらえた喜び、そして愛される喜びを噛みしめながら、豪の腕の中で、花那は全てが始まった日のことを思い返した。
※
大正十三年 卯月——
その日は風が強い日だった。
空は厚い雲に覆われ、今にも雨が降りそうだ。
(一雨くるかしら)
縁側の長い廊下を歩く足を止め、窓から空を見上げた花那はそう思った。
雨は嫌いだ。
両親が死んだ日を思い出すから。
だが、月夜はもっと嫌いだ。
自分の醜さが分かってしまうから。
花那は両親が亡くなった日のことを思い出して、ぼんやりとお盆に乗ったティーカップを見つめた。
琥珀色の紅茶には物憂げな自分の顔が映っている。
「ちょっと、ぼうっとしてないで早く彩様にお茶を運んでちょうだい!」
「は、はい」
「本当に使えない子ね。彩様の機嫌を損ねたら私まで怒られちゃうでしょ!」
「すみません」
花那は慌てて彩の部屋まで向かった。
その時、2人の女中が外出着や小間物を持って彩の部屋から出てきた。
「そういえば、聞いてる? 近所の森に禍牛が出たみたい。討伐隊が出ているらしいわよ」
「知らなかった! じゃ、夜は出歩かないようにしようかな」
禍牛とは人に禍をもたらす妖のことだが、軍からの討伐隊が来ているということなら、大事には至らないだろう。
花那がそんなことを考えているうちに、女中達は姦しく噂話を続けながら、花那の存在などいないかのように脇を通り過ぎて行った。
女中達の後ろ姿を見送った花那が彩の部屋に入ると、そこには薄紅色のワンピースを着た彩の姿があった。
上機嫌で姿見の前に立っていた彩は、花那の姿を鏡越しに見つけた途端、一気に顔を曇らせた。
「遅いわよ。紅茶を持ってくるだけでなんでこんなに時間かかるのよ!」
「も、申し訳ありません」
怒鳴られた花那は、その荒々しい言葉にびくりと肩を震わせた後、テーブルの上にティーカップをゆっくりと置いた。
その時ドアがノックされ、先ほどすれ違った女中の一人が部屋に入ってきた。
「どうぞ、お持ちいたしました」
「ありがとう」
彩が女中から受け取ったものを見て、花那は息を呑んだ。
それは、桜の花を模した摘まみ細工でできた髪飾りであり、母の形見だったからだ。
「そうそう、やっぱり髪飾りが無いと少し寂しいと思っていたのよね。ほら、この洋装にぴったりよね」
彩は女中から受け取った髪飾りを平然と自分の髪に挿し、満足そうに頷いた。
普段はなるべく息を潜めるようにして過ごしていた花那だったが、その髪飾りを見た瞬間思わず声を上げていた。
「そ、それは私の髪飾りです!」
父が亡くなり、叔父一家がこの家を相続した際、花那は私物のほとんどを取り上げられてしまっていた。
そのため形見という形見は手元に残っていない。
唯一手元に残った母の髪飾りが、何故彩の手元にあるのだろう。
「だってこの間あなたが持っているのを見て、気に入ったんだもの」
「……それは私の部屋に置いてあったはずです」
「ええ、そうよ。でもあなたの部屋は家主である私の部屋も同然。部屋に入って持ってきても問題ないわよね」
その答えに花那は驚きと困惑を隠せずにいると、彩はニヤリと意地の悪い笑みを浮かべた。
「この髪飾り、返してほしい?」
「もちろんです……。それはお母様の形見ですから」
花那は懇願するように答えた。何があってもこの髪飾りだけは返してほしい。
「でもこの洋装にこの髪飾りがぴったりなの。そうねぇ、この代わりがあれば返してあげてもいいわ」
「え……」
代わりと言われても、花那には髪飾り一つ持っていないのだ。
差し出したくても差し出せるものは無い。
答えられずに黙り込んでしまった花那を尻目に、彩は言葉を続けた。
「別の髪飾りはお父様に買ってもらっているの。今日店に取りに行く予定だったけど、取りに行けなかったのよ。だから、あなたが取りに行って」
「今から、ですか?」
「もちろん。だって明日のデエトに着けていくんだもの。当然でしょ?」
その時、花那の頭の中で女中達が先ほど言っていた言葉が蘇った。
彼女達はこの近辺で禍牛が出たと言っていた。
「あの……こんな夕方に出かけたら、帰りに禍牛に出会ってしまうかもしれません……」
「火狐を祖とする興津の人間ならば禍牛など倒せるはずでしょ? ああ、あなたはこの家の人間じゃないんだったわ。ふふふふ」
妖を祖とする一族の人間ならば、その異能の力で禍牛を退治することができる。
興津家は火狐の妖の血筋であり、彩を始めとして興津の人間は皆火を操る異能を持つ。
だが、花那は興津家の人間であるにも関わらずそれがない。
それを分かっていて彩はこのような無理難題を提案してきたのだ。
「行くならさっさと行きなさいよ!」
「……はい」
もし禍牛に襲われたら、無力な花那は死ぬ可能性もある。
それでも母の形見を諦めることはできなかった。
花那は意を決してそう言うと、夕闇迫る中、街へと向かうことにした。
※
曇りの日の夕暮れは、暗くなるのがいつも以上に早く感じる。
先ほどまで立ち込めていた雲は、更にその色を増し、風は湿り気を帯びてきていた。
薄暗くなる道を、花那は足早に歩く。
早くしなければ花飾りを受け取って帰る頃には、帰り道は暗闇に閉ざされてしまうだろう。
となると最悪の場合、夜に紛れて禍牛が現れるかもしれない。禍牛の姿を思い浮かべ、背中にゾクリと寒気が走った。
その時だった。
耳にざわりという葉音が聞こえてきて、花那は驚いて思わず足を止めた。
(もしかして……禍牛……?)
一瞬そう思った花那の耳に、今度は小さな呻き声が聞こえた。
花那は音がした草むらに目を凝らしつつ、恐る恐る近づいてみると、そこにいたのは一人の青年だった。
力なくうつ伏せに倒れている姿を認めた瞬間、花那は慌てて駆け寄った。
「大丈夫ですか!?」
「うっ……」
花那の呼びかけに、青年は小さく呻き声を漏らすだけだった。
見ると黒い服は土にまみれ、切り傷もあるようだった。
助けを呼ぶべきだろう。
だが周囲を見回しても夕暮れ時のせいか、人の姿は見えない。
(ど、どうしたらいいのかしら)
その一方で、花那は彩の命令で街に行かなければならない。
彩の言いつけを破れば、叔父である宏次郎から酷い折檻を受けるのは目に見えている上、母の形見も失ってしまう。
(でも……やっぱり、放ってはおけないわ)
人の命を救えるのであれば、自分が殴られるくらい平気だ。
痛みなどとうに慣れてしまっている。
母の形見を失うことは辛いが、それでも人が傷ついているのを見て見ぬふりは出来ない。
「大丈夫ですか? しっかりなさってください」
だが青年は苦悶の表情を浮かべたままで、花那の呼びかけには答えなかった。
そっと頬に触れると熱い。
「私の屋敷にお連れします。少し歩けますか?」
何度か青年の肩を揺すり、耳元で話しかけると、青年はようやくうっすらと目を開いた。
「すまな……い……」
花那は青年の腕を自らの肩に掛けると、青年を引きずるようにして屋敷へと戻った。
※
小さな体の花那が大の男を運ぶのは骨が折れた。少々雨に降られてしまったものの、本降りになる前に何とか屋敷に辿り着くことができた。
息を切らして玄関に駆け込むと、迎えた女中が目を丸くして驚いた。
「ま、まぁ! 何?」
「すみません、怪我人の手当てをしてくださいませんか?」
髪をしっとりと濡らし、息せき切らせながらそう言った花那に、女中は眉をひそめたかと思うと、そのまま屋敷の奥へと消えていった。
そしてすぐにその騒ぎを聞きつけた彩がやって来て開口一番に怒鳴った。
「ちょっと、髪飾りはどうしたのよ!」
「この方が怪我をされていて……」
「はぁ? そんな男より私の髪飾りの方が重要でしょ! 明日は正一郎様とのデエトなのよ!」
花那が懇願したが彩の怒りは収まらず、彩は手を振り上げた。
同時にパンという音がして花那の頬に痛みが走る。思わず倒れ込んだ花那を彩は怒りに満ちた目で見下ろした。それに対し、花那は土下座をして頼み込んだ。
「髪飾りは明日朝一番で取りに行きます。ですからこの方の手当てをさせてください」
「何があったんだ?」
そう言いながら奥からやって来たのは叔父の宏次郎だった。
花那はその姿を認めた瞬間、今度は宏次郎に向かって更に頭を下げて懇願を続けた。
「旦那様、どうかこの方の手当てをさせてください」
宏次郎は花那を一瞥した後、ぐったりとしたまま花那に寄りかかる青年に目を向け、そして冷たく言い放った。
「なんなんだこの男は」
「道で倒れていらっしゃったのです。怪我をされていて、熱もあるようなのです」
「どこの馬の骨か分からん男を拾って来たのか? 薬だってタダじゃない。こんな男など助けても一銭にもならんじゃないか。さっさと追い出せ」
「それでも、見捨てることはできません。お願いします!」
「〝色無し〟の分際で、当主の俺に意見するつもりか!」
雷のような大きな声で怒鳴られ、花那の肩がびくりと震える。
だが、人の命がかかっているのだ。ここで引き下がるわけにはいかない。
「ど、どんな罰も受けます。ですからお願いします……」
繰り返し花那が頼むと、突然宏次郎にグッと髪を掴まれて顔を上げさせられた。
かと思うと、先ほどよりも頬を思い切り殴られていた。
花那の体が吹き飛び、痛みと衝撃で目がちかちかした。
その様子を宏次郎は鼻を鳴らして一瞥したあと、鋭い口調で言った。
「ふん、介抱なら自分の部屋でしろ。部屋から一歩でも外に出すな。分かったな」
「……ありがとうございます」
花那は再び深く頭を下げて礼を言うと、苛立たし気に顔を歪めた彩も宏次朗に続いて、屋敷の奥へと消えていった。
それを見送った花那はほっと胸を撫で下ろすと、再び青年の肩を揺すって声を掛けた。
「すみません。もう少しで部屋なので、歩いていただけますか?」
相変わらず眉間に皺を寄せた青年は、小さく頷くだけの返事をした。
そうして花那は何とか青年を自室に運ぶことができたのだった。
※
外はすっかり夜の帳が下り、降りだした雨が容赦なく窓ガラスを叩いた。
花那の部屋にある灯りは蝋燭の灯だけ。
そのため布団に横たわる青年の顔色は良く分からないものの、眉間には深く皺が寄り、呼吸が乱れているところから熱があるのは一目瞭然だ。
体中にあった切り傷も手当をしたが、青年の綺麗な顔についた傷が痛々しく見える。
(なんとか手当は終わったけど、熱が下がらないのは心配だわ)
そう思いながら眉をひそめた花那は青年を見つめた。
青年は端正な顔立ちをしていた。
目の形は分からないが、高く通った鼻梁に薄い唇、前髪が少し長めの黒髪には艶がある。
部屋に運んで気づいたのは、青年が軍服を身に着けていたことだ。
推測ではあるが禍牛の討伐隊の一人で、禍牛と戦ったために傷を負ったのかもしれない。
(私の微弱な治癒の力じゃ、治せないかもしれないけど……)
花那は少しでも青年の傷が治り、熱が下がることを祈りつつ、そっと青年の手を握った。
そして目を閉じて、手に意識を集中する。
興津家には相応しくない程、微弱な異能の力。
花那はそれを使って青年の治癒を試みた。
すると少しだけ青年の呼吸の乱れが無くなり、眉間の皺が無くなったように見えるのは気のせいだろうか?
花那はそう思いつつ、青年の額にある濡らした手ぬぐいを取り替えた。
そうして、何度も手ぬぐいを取り換えているうち、外の雨は止み、窓からは朝日が差し込み始めた。
その頃には青年は穏やかな表情になっており、そっと額に触れると熱も下がったようだった。
(良かった)
花那が安堵していると、青年の睫毛がふるりと揺れ、ゆっくりと目を覚ました。
「ここは……」
「気づきましたか?」
青年は少しだけぼんやりと天井を見つめたあと、花那の言葉にゆっくりと体を起こした。
「無理なさらないでください」
「すまない……ここはどこだ?」
「ここは興津家の屋敷です。街に行く途中の道でお倒れになっていて、お連れしたのですが……」
花那が答えると、青年はふと何かに気づいたようだ。
「熱が引いている? ……まさか」
「まだ動かれては、傷が痛んでしまいます」
青年は慌てた様子で腕の包帯を解いたあと、ぽつりと呟くように言った。
「治っている……」
「え?」
青年が驚きのあまり、ぽつりと呟くように言った言葉に、花那も驚いて青年の腕を見た。
すると確かに昨日深々とあったはずの切り傷が無くなっていた。
「どういうことだ? ……君、私の手当てをした人間を呼んでくれ!」
「あの、私ですが……」
「君が?」
花那が小さく頷くと青年は居ずまいを正してから頭を下げた。
「そうか。助けてくれてありがとう。礼を言う。君、名前は?」
「興津花那と申します」
「興津? この屋敷の人間か?」
青年の問いに花那は言い淀んでしまった。
花那は興津の人間ではあるが、叔父達には興津家の人間とは認めてもらえていない。
むしろ、興津を名乗るなと言われ、使用人として扱われている。
だから胸を張って興津の人間だとは答えられなかったのだ。
口ごもった花那を見た青年はその態度の意味を捉えきれなかったようで、少しだけ訝し気な表情を浮かべた後、真っ直ぐに花那を見た。
「一つ聞きたい。君は俺の熱をどうやって鎮めたんだ?」
「あ……あの……普通に手ぬぐいで冷やしただけです」
「本当にそれだけか? その他に何かしたんじゃないのか?」
身を乗り出して尋ねられたが、青年は何故こんなにも必死に尋ねるのか分からない。
普通の手当てをしただけなのだ。
だが、その答えは青年が求めているそれとは違うものだったようで、更に花那に答えを促してきた。
あまりにも真剣に見つめられるので、他に自分がしたことをもう一度振り返って答えた。
「その……私には少しだけ治癒の力があるのでそれを使いました。微弱すぎて異能とは言えない程度なのですが……」
「治癒の力……」
青年は花那の答えに何か逡巡し、無言となる。
そんな青年の様子に花那が戸惑っていると、突然我に返ったように青年が花那に向き直った。
「ああ、すまなかった。まだ名乗っていなかったな。俺は」
青年が名乗ろうと口を開いた時だった。
何の音沙汰もなく、突然襖が乱暴に開かれた。
同時に声を荒げて入ってきたのは彩だった。
「ちょっと! 早く髪飾りを取ってきなさいよ! あなた、朝一番に行くって言ったわよね!」
眦を釣り上げた彩は不意に青年に目を留め、今度は息を呑んで目を丸くしたかと思うと、ほんのりと顔を赤らめた。
「あなたはこの屋敷の御息女か?」
青年の問いかけに、彩は先ほどの怒りの表情がすっかり消え去り、代わりに上品に微笑みながら答えた。
「え? ええそうですわ」
「俺の名前は鬼道豪と言う。この屋敷に電話があるのなら貸していただきたい」
「……鬼道? ま、まさか鬼道財閥の!? お、お父様、早くいらっしゃって!」
彩が驚きの声を上げたが、花那もまたその名前を聞いて息を呑んだ。
鬼道と言えば五大華族の財閥の一つだ。
妖を祖とする一族は社会的地位も高い。それゆえ興津家もそれなりに裕福な家だ。
だがその中でも最も力を持つのは五大華族であり、膨大な富を持ち、財閥を築いている。
しかも五大華族の中でも鬼道家は鬼神の力を有する最も力のある名家だ。
青年の正体に花那も驚いて声を出せずにいると、彩の声に宏次郎が面倒臭そうにやってきた。
「なんだ、彩。朝から騒々しい。またあの厄介者が粗相でもしたのか?」
「お父様、この方、鬼道豪様よ!」
「鬼道豪……鬼道家ご当主様でいらっしゃいますか!」
「ああ。介抱いただき感謝する」
「と、とんでもございません! こんな見窄らしいお部屋にお通しして申し訳ありません。ささ、こちらに」
慌てふためいた宏次郎は豪の手を引くと、部屋から出ていこうとする。そして、豪が何か言おうとする言葉を遮るように、宏次郎は花那を一瞥して鋭く命じた。
「おい、お前は早く茶を持ってくるんだ」
「は、はい。かしこまりました」
深く頭を下げて答えた花那が顔を上げた時には、宏次郎も彩も、そして豪の姿もなかった。
※
その後、豪とは再び顔を会わせることはなかった。
(傷が悪化していないといいのだけど……)
あれほどの高熱を出した後だ。
部屋を出る時には平気な様子であったが、やはり再度発熱していたらと、花那は心配していた。
だが、女中のような身分の花那が、鬼道財閥当主である豪と連絡を取ることなど不可能だ。ひっそりと無事を祈るほかないだろう。
そう思いながら花那が朝食の後片付けをしていると、台所の外がにわかに慌ただしくなった。
(どなたかいらっしゃったのかしら?)
首を傾げていると、女中の一人が花那に向かって鋭く命じた。
「手が離せないんだから、ぼうっとしてないで応接室にお茶を運びなさいよ」
「は、はい」
花那は慌ててお茶を用意して応接室に向かっていると、突然彩が横から現われ、出合い頭にぶつかってしまった。
「何やってるのよ! 危うくスカートが汚れるところだったじゃない!」
「も、申し訳ありません」
花那はいつものように慌てて土下座をすると、彩はその様子を上から見下した。
「まぁいいわ。今日は許してあげる。あなたなんかに構っている時間はないから」
彩は自慢気にそう言うと、優越感に満ちた笑みで花那を見た。
「ふふふ、鬼道様から縁談を申し込まれたのよ! 私が鬼道家に嫁入りしたら、あなたも下働きでついてきてもいいわよ」
「彩、準備ができたなら早く来なさい」
「はぁい、お父様!」
応接室から顔を覗かせた宏次郎が彩を急かした後、花那を一瞥する。
「お前はさっさと茶を持ってこい」
「……は、はい。畏まりました」
数日前に顔を合わせた豪が彩と婚姻を結ぶことに少々驚いたものの、花那は彩の追うように急いで応接室に向かった。
応接室に入ると、そこには既に豪の姿があった。
先日とは打って変わって顔色も良く、傷も無いように見え、花那は内心ほっと胸を撫で下ろした。
だが宏次郎からはさっさと出ていけという無言の圧を感じ、素早く部屋を出ようとした。
その時だった。
豪が花那を呼び止めた。
「君もここにいてくれ」
「……私、ですか?」
何故自分がこの場に残らねばならないのか戸惑いつつ、花那は小さく頷いてドアのところに控えた。
それを見た豪は一瞬眉をひそめたが、そんな豪の様子には気にも留めず、宏次郎はにこやかな笑顔で話を切り出した。
「いやぁ、この度は大変素晴らしいご縁をいただき、誠にありがとうございます。娘も鬼道様に見初められたことを、とても喜んでおりますよ」
宏次郎の言葉に、隣に座る彩がほんのりと頬を染めながら控えめに豪を見た。
突然の縁談に沸き立つ二人を見た豪は、二人とは対照的に硬い表情を浮かべていた。
その目はとても縁談を申し込みに来た人間とは思えない程冷たい色が宿っていた。
すると豪は静かに口を開いた。
「いや、婚姻を申し込みたいのは貴殿のご息女ではない」
「え?」
豪の言葉に宏次郎も、そして彩も驚きの表情を浮かべた。
理解が及ばなかったのか、宏次郎は一瞬言葉を失ったあと、慌てて豪に尋ねた。
「ど、どういうことでしょうか? 本日のご用件は彩へご縁談のお申し込みをいただけると思っておりましたが」
「私が結婚を申し込みたいのは彼女だ」
(私……?)
豪が視線を向けた先にいたのは花那だった。
「なっ……! この女は能無しですよ! あなた様のような高貴な方には相応しくありませんよ!」
豪の言葉の意味を理解した宏次郎は慌てふためいてそう言った。
彩もまた立ち上がって豪に訴えた。
「そうです。私はこの興津家の正当な血筋の人間ですわ。ですがこの女は異能の力もなく、興津の恥なのです!」
「彩の言う通りです。お考え直しください。こんな興津家の恥さらしを、鬼道様のようなお家柄に嫁がせるのは無理でございます」
慌てふためく宏次郎と彩を冷たく見据えた豪は、静かに、だが畏怖を覚えるような声で唐突に言った。
「貴殿は金が好きなのだろう?」
「え?」
「花那が俺を屋敷に運んだ時、貴殿は言ったな。『こんな男など助けても一銭にもならない』と」
「!」
「ならばこの金で彼女を買おう」
豪はそう言うと、花那が見たこともない数の札束を鞄から取り出すと、宏次郎の目の前でそれを宙に放り投げた。
お札は空中を舞い、ひらりひらりと宏次郎の前に落ちていく。
「金が不足するのなら屋敷まで来るといい」
あまりの展開に言葉を失っている宏次郎を豪は一瞥したかと思うと、花那の肩を抱きながら部屋を出た。
車に乗せられた花那は、そのまま大きな洋館に連れてこられた。
どうやらここは鬼道家の屋敷のようだった。
見たことのない異国の置物や、ダマスク柄が施された深い緑色の壁紙。
段通で出来た絨毯の敷かれた部屋に通されたのだが、花那は自分の身に起きていることが全く理解できずにいた。
目の前のソファに豪が腰を下ろすと、戸惑う花那を真っ直ぐに見つめた。
「さっきの話の通りだ。君に婚姻を申し込む」
豪は先ほど興津家で言った言葉を再度口にした。
どういう意味か理解できないでいる花那に、豪は言葉を続ける。
「介抱してくれた礼だと思ってくれ。俺の妻になれば誰にも文句を言われることなく贅沢が出来るだろう。あぁ、婚姻と言っても俺を愛する必要はない」
「あ、あの程度の事でそこまでのお礼は不要でございます。当然のことをしたまでですから」
「君の親戚はそうではないようだったがな」
豪は嘲笑を浮かべて吐き捨てるように言った。
その顔には宏次郎達に対する不快感が現われていた。
「それでも、私のような者と婚姻を結ぶなど……」
先程宏次郎が言ったのはもっともな話だった。
興津家の中でも異能の力がほとんどない花那が、鬼神の力を持つ由緒正しい鬼道家に嫁入りするなど、不相応すぎる。
固辞する花那を見た豪は、続きの言葉を口にした。
「実は代わりと言っては何だが一つ頼みたいことがある。その治癒の力で俺を癒してほしい」
「ですが私の治癒の力はあまりに弱くて、普通の人間のおまじない程度です。それなのに治癒の力を使っても、癒せるのは難しいと思います」
「いや、君なら出来る。今までで俺を治癒できた人間は君と、もう一人しか俺は知らない」
「え?」
「鬼道家は鬼神を祖とするが俺はその血を濃く受け継いでいる。だから、異能を使いすぎると器である体が力に耐えられない。俺が熱を出して倒れたのはそのためだ」
話を聞くと、女中達が噂していた禍牛の討伐隊というのは豪達のことだった。
禍牛の討伐に向かった討伐隊だったが、一個小隊がやられ、部下を退却させるために豪は足止めをしたせいで力を使いすぎて倒れたらしい。
「しかし普通の治癒師の力では鬼神の力が強すぎて、治癒させることができない。だが、君はそれができた」
まさか自分にそんな力があるとは思っていなかった。
「引き受けてくれないだろうか?」
それは花那にとって最良の提案であり、興津の家を出ることができる。
そしてこの微弱な異能の力でも人の役に立てるかもしれない。
だが、花那にはとある秘密がある。それが露見すればこの提案は無くなるだろう。
一抹の不安がよぎったが、その考えを振り切るように豪を真っ直ぐに見つめて答えた。
「分かりました。お引き受けいたします」
花那はそう答えると、窓を叩きつける雨音を聞きながら鬼道家で暮らす決心をした。