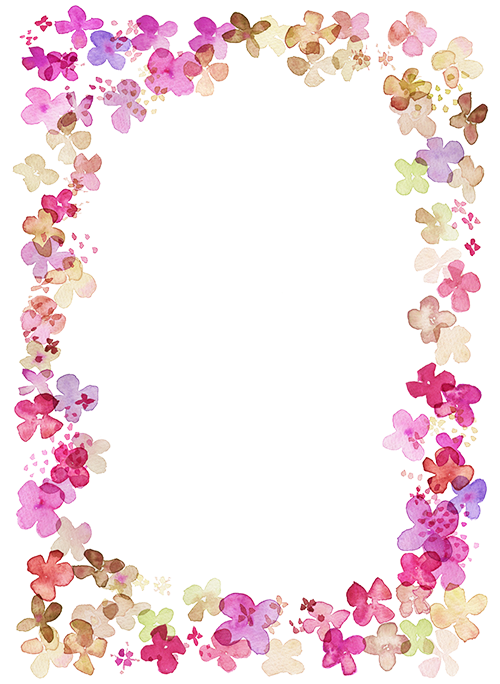***
俺は浮かれていたのだろう。人を好きになったのは初めてだった。それがいきなりの両想いだ。だから失敗した。
「え!? 俺、付き合ってって……言ってないね!」
時は流れクリスマスイブ。
遊園地にデートに来た俺は、彼女を前にして途方に暮れた。
思い返してみれば、ちゃんと「好きだ」とか「俺と付き合って欲しい」と言ったことはなかった。
まさか彼女が「付き合ってるかどうかはあやしいのでは」と思っていたとは。
それを知ったのが、クリスマスイブとか。
何ヶ月宙ぶらりんな状態だったんだよと、自分に呆れた。すっかり恋人気分だった。
いや。でも、普通男女二人きりで何度もデートしたらそれは彼氏彼女では。
そう思いはするものの、周りの友達にはいろんな女の子たちと遊び歩いている男もいるので、そこはしっかり口にすべきだったのかもしれない。
「えっと、俺、葉山のこと女の子として好きだし付き合ってると思ってたし今日もクリスマスデートだと思ってたけど」
早口になってしまったのは仕方がない。誤解を解かねば。
俺は冷や汗をかきながら彼女を見つめた。すると、葉山は満面の笑みで「あたしも秋山のこと大好き!」と言ってくれた。
ヤバイ。かわいい。
俺はつい顔を背けてしまった。赤くなっている顔を見られるのが恥ずかしかった。
「じゃあね、あたし、まずはあれ乗りたい!」
葉山が俺のジャケットの袖を引っ張った。
「うっわ、絶叫系」
「あ、秋山駄目だった?」
「いや、めっちゃ好き」
こうして、始まりはぎくしゃくしたものの、初めての「クリスマスデート」が始まった。
「あー、楽しかった!」
日が暮れてきた。まだ五時前だが一年で一番夜の長い季節だ。あたりは薄暗くなり始めていた。
「じゃあ俺、夜までに帰らないといけないから」
そう、親戚の法事を抜け出してきてしまったのだ。まだ一緒にいたいが仕方がない。夕食には間に合うように親に言われていた。
俺たちは駅に向かって歩き出した。すると、葉山が俺の袖をつんと引っ張った。
「何?」
俺が振り返ると、葉山はにこにことしている。
「な……」
「じゃーん!」
葉山はショルダーバッグの中から小さな包みを取り出した。
「クリスマスプレゼントだよ!」
「あ」
俺はその場に崩れ落ちそうになるのをなんとか堪えた。
俺はもう駄目だ……!
「ん? どしたの、秋山」
無言で立ちすくむ俺を、葉山は気遣わしげに見つめた。
プレゼント持ってくんの忘れた!
買ってはあった。何がいいのか全くわからなくて結局「気に入らない物をプレゼントしたらかえって迷惑では」「食べたらなくなるものにしておこう」と日和って、以前葉山が好きだと言っていたクッキーを用意したのだ。
が。急に幽体離脱できなくなったことで焦って持ってくるのを忘れてしまった。
ないだろう。クリスマスデートに彼女へのプレゼント持ってこない彼氏。いや、さすがにない。
だから! こういう俺の気遣いのなさが! 付き合ってないのではとか勘違いさせるんだろ!
そもそもクリスマスデートも葉山から誘われたのだった。
冬休みも会いたいなとは思っていた。が、「クリスマス」という最大のイベントは頭から抜け落ちていた。葉山の予定を聞いて、どこかの日に誘えるかなとかぼんやりと考えているうちにクリスマスデートに誘われたのだ。
「秋山……? ほら、開けてよ」
目の前の葉山が心配そうに首を傾げた。俺は焦りまくった。
「あ、うん。ありがとう!」
また葉山を泣かせてしまったら、俺はもう終わりだ。とにかく謝罪は後にして、プレゼントを笑顔で受け取らなくては。
俺は彼女の手の上にちょこんと乗る巾着を受け取ると、リボンをしゅっとほどいた。
「おおっ!」
俺は思わず声を上げた。ワイヤレスイヤホンだ。前を見ると、葉山は俺の反応に嬉しそうに頬を紅潮させた。
「冬休み入る前に壊れてたじゃん。お年玉入ったら買うって言ってたけどさ、秋山アニソンとかめっちゃ聴くから早いほうがいいかなって思って!」
俺はオタクだ。が、彼女もオタクで、というかそもそもオタク趣味があったことが親しくなったきっかけとも言えるのでそこは気にしない。
というか、めちゃくちゃ嬉しい。
イヤホンが、というより、俺のことを考えて選んでくれたのがわかるのが。それがめちゃくちゃ嬉しい。二度言う。
「ありがとう。すごく嬉しいよ」
その喜びをうまく言葉にできないのがもどかしい。が、彼女には伝わったようだ。嬉しそうに両手をぷらぷらさせた。かわいい。
が、いつまでもこうしているわけにはいかない。謝罪しなければ。
「で、あの、ごめん。実は俺、プレゼント持ってなくて。いや、買ってはあったんだ。葉山好きだって言ってただろ、『うさぎや』のクッキー。それを持ってこようと思ってて」
すっかり忘れてました。
俺はがくりと項垂れた。
そもそも彼女へのクリスマスプレゼントはアクセサリーとか記念になる残るものをあげるべきだったのではという気持ちもある。
「ごめん!」
俺はがばりと頭を下げた。すると、目の前の葉山が一歩前に近づいてきた。
「やだっ、頭なんか下げないでよ! うさぎやのクッキー嬉しい! あれ賞味期限長いから、今度会った時にちょうだい。そんでもって、一緒に食べようよ」
顔を上げると、葉山が拳を振るって力説している。俺は自分の情けなさに目眩を感じつつも、励まそうとしてくれている彼女にも目眩がしてきて。
ーーそんな彼女がまたかわいくて、どうしようもなくて。
「ふっ?」
目の前の葉山が大きく目を見開いた。それもそうだろう。
つい、キスをしてしまった。
唇がくっついたのはほんの一瞬。すぐに俺は顔を離した。そして目の前で呆然と立ち尽くす葉山を見て気付いた。
俺はまた、何をやってんだ!
初めてだった。キスをするのは。それもそうだ、付き合っているかどうかあやしいと思われるような仲だったのだから。
それを、ふいうちでキスとか。さすがにクリスマスなのにムードもへったくれもない。
「ごめんっ!」
俺は再び頭を下げた。
もう今日の俺はガタガタだ。誰か今日という日をこの世から消し去ってくれ。
冬だというのに額からは嫌な汗がだらだらと流れ出してくる。クリスマスの遊園地の楽しそうな喧噪の中、俺はこの世の終わりのような気持ちになっていた。
しばらく頭を下げていたが、葉山は何も言わない。勝手にキスしてさすがに怒ったのかとおそるおそる顔を上げた。
「え」
葉山は口を拳で押さえて真っ赤になっていた。
「あの、ごめん、はや……げふっ!」
言いかけた俺の胸に、彼女の拳が入った。
「殴るほど!?」
俺が咳き込みながら彼女を見ると、葉山は泣きそうな満面の笑みで俺に飛びついてきた。「びっくりした! けど、嬉しい! クリスマスプレゼントありがとう!」
葉山はしばらく俺の胸の中でひっくひっくと泣いていた。てか、また泣かせてしまった。
腕の中の彼女の髪を撫でながら、俺は思った。
よくわからんが、とにかくかわいい、と。