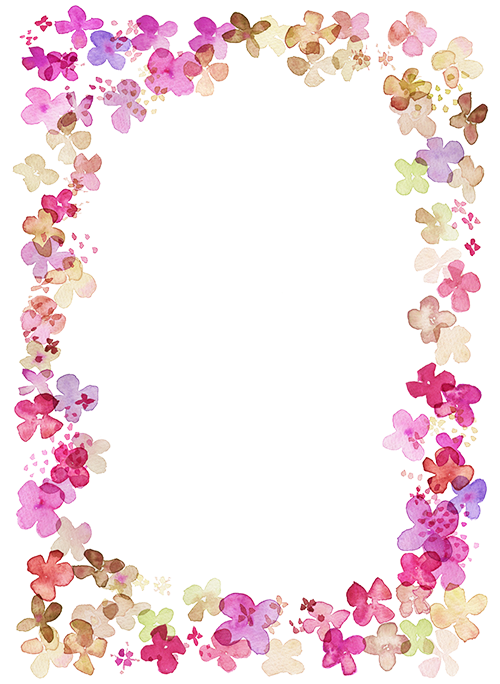俺の彼女は変わっている。
実は俺は幼い頃から何故か幽体離脱ができる。けれどそれは基本的に秘密だ。うっかり幼稚園でそれを言ってしまい、気味悪がられて転園騒ぎになったこともあるそうだ。小さい頃のことだからよく覚えていないが。
その秘密を彼女ーー葉山菜乃に知られてしまった。
「ほんと、俺の彼女変わってる」
夏休みが終わって新学期が始まった。俺が部活中にぼつりと呟くと、隣でラケットを振っていた安達が動きを止めてこちらを振り返った。
「あ!? 聞こえませーん。秋山くんのノロケなんて聞く耳ありませーん!」
「聞いてんじゃん」
俺は軽く安達の膝のあたりをキックした。
「あ! 折れた! 救急車! 救急車呼んで!」
「ホントに呼んでいいのかよ」
「よくありません!」
安達は俺が幽体離脱ができると知っている唯一の男だ。中学一年の時バドミントンクラブで知り合って、高一の今も一緒にバドミントンをやっている仲間だ。
俺はラケットを撫でながら首を傾げた。
「普通、気味悪いよな?」
そう、安達が家族以外で俺の秘密を知る唯一の男なら、夏休み中にできた彼女、葉山菜乃は唯一の女だった。
「何? もしかして秋山の彼女、お前の秘密知ってんの?」
ふっと安達は真面目な顔になった。俺は頷いた。
「うん。ていうか、初めて出会った時が幽体離脱中だった」
病気で一学期をほとんど休んでしまった俺は、手術が成功したのをいいことに、夏休みの補習に幽体離脱して参加してしまったのだ。勉強はわりと好きだったので「ばれやしない」とちょっと調子に乗ったことは否めない。そこで出会ったのが、葉山だった。
うっかりしていたのだ。補習最終日、勉強が好きだと言っても、終わった開放感からすぐに教室から元の体に戻ってしまった。そこを目撃されたらしい。葉山は、最初は俺が幽霊だと勘違いしたそうだ。
再会した時、彼女が誤解して泣いているので、なんとか誤解を解こうと幽体離脱のことを告げてしまった。泣いて欲しくなかったから。
こりゃまた気味悪がられるな。せっかく仲良くなれたのに……。
心臓がぎゅっと音を立てたが、気付かないふりをした。泣かせたくないから仕方がない。 それなのに。
「よ、良かった……。秋山が生きてて……」
「え? 泣き止んでよ」
泣き止んで欲しかったのに、彼女は余計にひっくひっくと泣き始めてしまった。「怖かった」とか「びっくりさせないでよ」とかぶつぶつ言っていた中に、確かにその言葉はあった。
「好きになっちゃ駄目なヒトだと思ったのに」
思ったのに。
体がカッと熱くなった。
「のに」。つまり、あれだ。駄目なヒトじゃなかったということだ。だからつまり、彼女は俺のことが好きだということだ。
ーーーーっしゃ!
俺は内心でガッツポーズをした。
「気付かないふり」を「して」いる時点で、もう気付いているということだ。
葉山も俺のこと、好きなんだ。
「で? 大丈夫なのか? もう別れ話とか?」
安達の声で我に返った。
「いや。なんというか、褒められた」
「は?」
「『すごーい! いいな! 便利だね!』って」
「やっぱり、ノロケかよ!」
今度は俺が膝裏に軽いケリを入れられた。
実は俺は幼い頃から何故か幽体離脱ができる。けれどそれは基本的に秘密だ。うっかり幼稚園でそれを言ってしまい、気味悪がられて転園騒ぎになったこともあるそうだ。小さい頃のことだからよく覚えていないが。
その秘密を彼女ーー葉山菜乃に知られてしまった。
「ほんと、俺の彼女変わってる」
夏休みが終わって新学期が始まった。俺が部活中にぼつりと呟くと、隣でラケットを振っていた安達が動きを止めてこちらを振り返った。
「あ!? 聞こえませーん。秋山くんのノロケなんて聞く耳ありませーん!」
「聞いてんじゃん」
俺は軽く安達の膝のあたりをキックした。
「あ! 折れた! 救急車! 救急車呼んで!」
「ホントに呼んでいいのかよ」
「よくありません!」
安達は俺が幽体離脱ができると知っている唯一の男だ。中学一年の時バドミントンクラブで知り合って、高一の今も一緒にバドミントンをやっている仲間だ。
俺はラケットを撫でながら首を傾げた。
「普通、気味悪いよな?」
そう、安達が家族以外で俺の秘密を知る唯一の男なら、夏休み中にできた彼女、葉山菜乃は唯一の女だった。
「何? もしかして秋山の彼女、お前の秘密知ってんの?」
ふっと安達は真面目な顔になった。俺は頷いた。
「うん。ていうか、初めて出会った時が幽体離脱中だった」
病気で一学期をほとんど休んでしまった俺は、手術が成功したのをいいことに、夏休みの補習に幽体離脱して参加してしまったのだ。勉強はわりと好きだったので「ばれやしない」とちょっと調子に乗ったことは否めない。そこで出会ったのが、葉山だった。
うっかりしていたのだ。補習最終日、勉強が好きだと言っても、終わった開放感からすぐに教室から元の体に戻ってしまった。そこを目撃されたらしい。葉山は、最初は俺が幽霊だと勘違いしたそうだ。
再会した時、彼女が誤解して泣いているので、なんとか誤解を解こうと幽体離脱のことを告げてしまった。泣いて欲しくなかったから。
こりゃまた気味悪がられるな。せっかく仲良くなれたのに……。
心臓がぎゅっと音を立てたが、気付かないふりをした。泣かせたくないから仕方がない。 それなのに。
「よ、良かった……。秋山が生きてて……」
「え? 泣き止んでよ」
泣き止んで欲しかったのに、彼女は余計にひっくひっくと泣き始めてしまった。「怖かった」とか「びっくりさせないでよ」とかぶつぶつ言っていた中に、確かにその言葉はあった。
「好きになっちゃ駄目なヒトだと思ったのに」
思ったのに。
体がカッと熱くなった。
「のに」。つまり、あれだ。駄目なヒトじゃなかったということだ。だからつまり、彼女は俺のことが好きだということだ。
ーーーーっしゃ!
俺は内心でガッツポーズをした。
「気付かないふり」を「して」いる時点で、もう気付いているということだ。
葉山も俺のこと、好きなんだ。
「で? 大丈夫なのか? もう別れ話とか?」
安達の声で我に返った。
「いや。なんというか、褒められた」
「は?」
「『すごーい! いいな! 便利だね!』って」
「やっぱり、ノロケかよ!」
今度は俺が膝裏に軽いケリを入れられた。