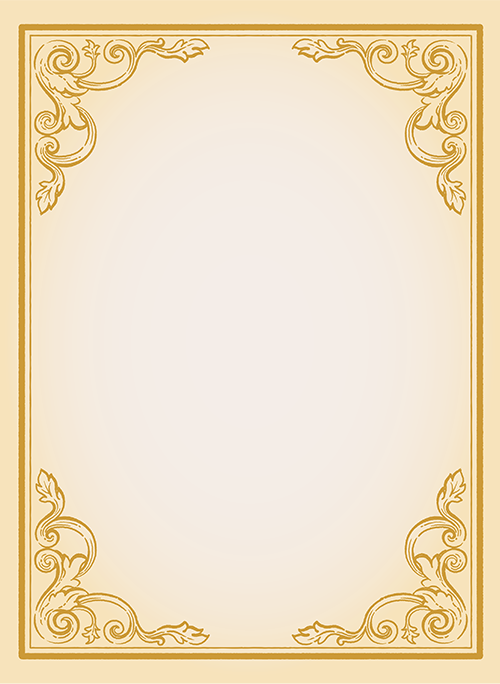大学生になって迎えた初めての冬。東京に出て来て八か月も経てば、流石に新しい生活にも慣れてきた。
ぼんやりとした意識の中、今日もいつも通りの時間に目が覚めたのだと何となく分かった。
目をこすりながら起き上がり、隣を見るとベッドの半分がぽっかりと空白になっている。そこに手を当てればまだ微かに温もりが残っている気がした。これもいつも通りだ。
また勝てなかったか、とよく分からないし、何度抱いたのか数えきれない温い敗北感を今日も覚える。
カーテンを開き、あれ? と首を傾げた。てっきり、今日もベランダから夜明けを待っているのだと思ったのに。
都内のどこにでもあるようなマンションの六階から覗く景色は、随分と寂しい。実家の自室からのオーシャンビューが懐かしく思えるほどに、背の高い灰色の建物から灯る橙色の寂しい明かりが暗闇にどこまでも浮かんでいた。
そっと窓に触れると、指先を伝う真冬の気配にすぐにその場を離れた。といっても、約十畳の1DK。二人では少し手狭なリビングとダイニングキッチンがあるだけの簡素な一室だ。東京は家賃も馬鹿にならない。寝室とリビングがある部屋を選ぶという選択肢は最初からなかった。
部屋の隅に置いたハンガーラックを見れば、隣り合わせでかけていたコートの一着がない。
「なら、あそこか……」
着替えてマンションを出る。肌を撫でる冷たい風に、手をコートのポケットに突っ込んで歩く。
東京の夜明け前はやけに賑やかで、明るさを帯びている。横の道路を車のヘッドライトが頻りに行き交い暗闇を蹴散らし、直線の一本道で何回か人とすれ違った。こんなこと、地元じゃ考えられない。
浅く息を吸い込めば、どこか空気が濁っているような気がする。どんなに夜更けに外に出ても、どこかで人の気配を感じる。街が眠ることを知らない。東京とはそういう場所だ。
電車に乗るのにほとんど待たなくていいし、欲しいものは何でも揃う。その利便性の中で、何か大切なものをじわじわとすり減らして生きているような錯覚を抱く。
少し前までは早くこちらに来たいと思っていたのに、実際に住んでみればどこか想像と乖離していることが多い。
結局、住めば都なんて場所は存在しないのかもしれない。
ふと、スマホが通知音を鳴らす。催促かなと確認すれば、意外なことに奏翔からだった。昨日、寝る前に送ったメッセージの返信だ。
こんな時間に奏翔から返信が届くのは珍しい。目覚ましの時間でも間違えたのだろうか。
マンションを出て裏手の道を数分歩くと、大きな公園がある。
街路樹がぐるりと公園を囲うように並び、公園内は芝生の広場になっている。大通りからは少し離れた場所にあるので車通りは少なく、陽の昇る前は人も園内の奥までは立ち入らない。園内の灯りも乏しく、ここだけは東京でもちゃんと夜明け前を感じることの出来る場所だ。
だから、僕たちはたまにこの公園で朝が来るのを待ちわびる。
公園の入り口の自販機でペットボトルの温かい紅茶を買う。場所が変わっても、この習慣は変わることはない。
園内に足を踏み入れると、一気に暗がりが押し寄せた。入り口付近にしか街灯がないのはちょっと不便だ。ずっと奥まで広がっているはずの芝生の広場は、少し先だってろくに見えなかった。
スマホのライトを点け、いつもの場所へ向かう。広場の奥手にある大きな木が僕たちの定位置だ。
本当にそこにいるのだろうか、なんて疑問は必要なく、遠くの方で小さなスマホの明かりが見えた。
今まで一人で行くことなんてなかったのに、今日は一体どういう気まぐれなのだろう。
明かりに向けて歩を進めると、あちらも僕に気が付いたのか、明かりが左右にせわしなく揺れる。
いつもの場所。大木を囲う丸形のベンチに彼女がいた。
「おはよう、奏汰くん!」
そんな彼女の第一声にいつの日かのことを思い出す。
「音子もおはよう」
軽いあくびを噛み殺し、彼女の隣に腰かける。
「思ったよりも早かったね。私も今来たところだよ」
「それなら、いつもみたいに一緒に来ればよかったのに。一人は心配になるよ」
「過保護な彼氏だなぁ」
彼女は傍らに置かれた缶コーヒーを手に取り、笑いながら言った。
ふと、再び奏翔からのメッセージを知らせる通知音が鳴る。
『そう言えば、正月は実家に帰る?』
その文面を見て、僕はしばし考える。横目で彼女を見遣れば、僕の顔を覗き込んで不思議そうに首を傾げていた。
「どした?」
「……何でもない」
おもむろにスマホの画面を消して、ポケットにしまう。
すると、彼女はむっと頬を膨らませた。
「浮気かぁ?」
「するわけないじゃん……」
「ふふっ、知ってるよ」
彼女は足をぱたぱたと揺らしながら、「冗談、冗談」と軽く言う。どうしてか上機嫌な彼女を眺め、やっぱり少し思案を巡らせる。
僕が実家に帰るとすれば、彼女はどうするのだろう。結局、彼女と彼女の母親の関係は何も変わっちゃいない。彼女が自分の実家に帰ることはないだろう。
とはいえ、一緒に僕の実家に行くのも……。
一緒に住むことになった時に、両親へ彼女のことは紹介したが、正月まで連れて帰るというのはかなり気恥ずかしい。
そもそも、彼女が地元に良い印象を持っていない可能性も考えられる。長く、彼女を苦しめて傷付けていた場所なのだ。帰りたくないと言われたら、僕も彼女と二人きりの正月を選ぶのだろう。
東の空がじんわりと燃え始め、園内の輪郭が次第にはっきりとしていく。朝が来るまで、もう少しだ。
結局、僕は悩んだ末に彼女に尋ねることにした。
「奏翔がさ、正月は向こうに帰るのかって。……音子はどうする? えっと、一緒に帰る?」
僕が歯切れ悪く言えば、彼女はぱっと表情を明るくした。
「えっ、いいじゃん! 奏汰くんたちのご両親優しいから好き! 一緒に行こ!」
ちょっぴり意外だった。
「そっか、じゃあ帰ろうかな」
「うんうん。まだ一年経ってないけど、何だかすっごく久しぶりに地元に帰る気分」
「こっちに来てから色々あったもんね。大学が始まって、二人で住みだして、アルバイトして」
「私が単位を落としかけて」
と彼女が続くから、二人でちょっと笑い合った。
「こんな未来、想像出来た?」
彼女がふと僕に尋ねる。
二人で明け行く空と海を眺めていたあの頃を振り返れば、答えはすぐに浮かんだ。
「思っていたよりいいかもね」
「私は想像の何倍も、何十倍もいいよ。毎日楽しい!」
彼女がそう思ってくれていることが、今の僕には何よりも嬉しいことだ。
「そうだ、あっち帰ったら、あの公園行こうね」
「構わないけど、音子はいいの?」
彼女の提案に思わず聞き返してしまう。
「ん? 何が?」
喉まで出かかった言葉を一度呑み込む。手元のペットボトルをぼんやり見つめ、ややあって言った。
「だって、あそこは音子にとって長い間一人を過ごしていた場所だからさ。あまり立ち寄りたくないんじゃないかって」
すると、彼女は呆気に取られたように目をしばたたかせ、ややあって大きなため息を吐いた。
「奏汰くんは相変わらずだなぁ」
「どういうこと?」
「あの公園も、あの灯台も、私は奏汰くんに大切な思い出に変えてもらったってことだよ。だから、とにかく一緒に行くの!」
ずいっと顔を僕に近付ける彼女に気圧され、小さく頷く。
「わ、分かったよ」
彼女が満足げに笑みを零す。
「でも、まだお正月気分は早いんじゃない?」
そう言い、彼女は僕とは反対側に置いてあった紙袋を持ち上げて見せた。
「何それ?」
「何って、今日はクリスマスだよ。そんなの一つしかないじゃないの」
弾んだ声と一緒に彼女が取り出した紙箱を開ければ、大きなホールケーキが姿を見せた。相変わらず白いクリームが少し歪なのを見れば、彼女の手作りだということが分かる。ただし、円型だったと思われるケーキは、真ん中で切り分けられて半分しか入っていなかった。
「何だかデジャブ……。いつの間につくったの?」
昨晩、冷蔵庫にこんな大きなものは入っていなかったはずだ。夜中に起きてつくっていたとしても、手狭な部屋で僕が起きないとは思えなかった。
「奏汰くんを驚かせようと思ってね。昨日、君がバイトに行ってる間につくって、奏翔くんの家に持って行って置かせてもらったの。今日はここに来る前に奏翔くんの家までこれを取りに行ってたんだ」
なるほど、これで色々疑問だったことが晴れた。奏翔が珍しく早い時間にメッセージを送って来たのは、彼女の訪問で早起きしたからだ。それにケーキが半分なのは、もう半分を奏翔に分けたからだろう。
それにしても、僕たちが住んでいるマンションから、奏翔が一人暮らしをしているマンションまでは十五分ほどかかる。わざわざ、僕へのサプライズのためにここまでする彼女の熱意には感心だ。
「確かに驚いた……。流石にこっちに来ても音子のケーキを朝から拝むことになるとは思わなかったよ」
「でしょ、でしょ~! これ、毎年やるからね。あっ、でも今日の夜はチキン食べようね」
「それは夜なんだね」
「もちろん」
相変わらず、彼女の基準はよく分からない。だけど、そんな彼女のペースにもすっかり慣れた自分がいる。
紙皿に切り分けられたケーキを受け取り、一口。十八歳の誕生日に初めて彼女のケーキを食べてからずっと、少し甘めにつくってくれている。きっと、あの時甘くし過ぎたと言った彼女に、僕がちょうど良いと言ったからだろう。
時間をかけたサプライズも、甘くつくってくれたケーキも、全部彼女が僕のためにしてくれたことだと思うと、
「幸せだなぁ」
そんな言葉が零れ落ちる。
「ふふっ」
彼女が嬉しそうに笑みを浮かべた。
「私の口癖、すっかりうつっちゃったね」
「あっ……」
少し、顔が熱くなった。本当に無意識に口を衝いて出た言葉だったので、なおさら恥ずかしい。
「あー、照れてる!」
「て、照れてないっ!」
「はいうそー。奏汰くんはうそを吐く時、目線が右下に行くんだよね~」
嬉々として僕の癖を暴く彼女に、余計に恥ずかしさが込み上がった。少し彼女と見つめ合い、二人同時に笑みを零す。彼女は嬉しそうに、僕は呆れたように。
ケーキを食べ終えた頃には、すっかり青空が広がっていた。
「そろそろ帰ろっか」
彼女の手を取り、立ち上がる。燦々と降り注ぐ陽射しが、僕たちを明るく照らしていた。
帰り道、ふと彼女に尋ねた。
「音子は今、幸せ?」
すると、隣の彼女は僕を見上げ、握った手にぎゅっと力を込めた。そして、晴れ晴れしい表情で、
「うん! とっても幸せ!」
そう言ったのだ。
「そっか、じゃあ、やっぱり僕も幸せだ」
平凡で、ちょっと特別な一日の夜明けが僕と彼女を迎えてくれていた。
(了)
ぼんやりとした意識の中、今日もいつも通りの時間に目が覚めたのだと何となく分かった。
目をこすりながら起き上がり、隣を見るとベッドの半分がぽっかりと空白になっている。そこに手を当てればまだ微かに温もりが残っている気がした。これもいつも通りだ。
また勝てなかったか、とよく分からないし、何度抱いたのか数えきれない温い敗北感を今日も覚える。
カーテンを開き、あれ? と首を傾げた。てっきり、今日もベランダから夜明けを待っているのだと思ったのに。
都内のどこにでもあるようなマンションの六階から覗く景色は、随分と寂しい。実家の自室からのオーシャンビューが懐かしく思えるほどに、背の高い灰色の建物から灯る橙色の寂しい明かりが暗闇にどこまでも浮かんでいた。
そっと窓に触れると、指先を伝う真冬の気配にすぐにその場を離れた。といっても、約十畳の1DK。二人では少し手狭なリビングとダイニングキッチンがあるだけの簡素な一室だ。東京は家賃も馬鹿にならない。寝室とリビングがある部屋を選ぶという選択肢は最初からなかった。
部屋の隅に置いたハンガーラックを見れば、隣り合わせでかけていたコートの一着がない。
「なら、あそこか……」
着替えてマンションを出る。肌を撫でる冷たい風に、手をコートのポケットに突っ込んで歩く。
東京の夜明け前はやけに賑やかで、明るさを帯びている。横の道路を車のヘッドライトが頻りに行き交い暗闇を蹴散らし、直線の一本道で何回か人とすれ違った。こんなこと、地元じゃ考えられない。
浅く息を吸い込めば、どこか空気が濁っているような気がする。どんなに夜更けに外に出ても、どこかで人の気配を感じる。街が眠ることを知らない。東京とはそういう場所だ。
電車に乗るのにほとんど待たなくていいし、欲しいものは何でも揃う。その利便性の中で、何か大切なものをじわじわとすり減らして生きているような錯覚を抱く。
少し前までは早くこちらに来たいと思っていたのに、実際に住んでみればどこか想像と乖離していることが多い。
結局、住めば都なんて場所は存在しないのかもしれない。
ふと、スマホが通知音を鳴らす。催促かなと確認すれば、意外なことに奏翔からだった。昨日、寝る前に送ったメッセージの返信だ。
こんな時間に奏翔から返信が届くのは珍しい。目覚ましの時間でも間違えたのだろうか。
マンションを出て裏手の道を数分歩くと、大きな公園がある。
街路樹がぐるりと公園を囲うように並び、公園内は芝生の広場になっている。大通りからは少し離れた場所にあるので車通りは少なく、陽の昇る前は人も園内の奥までは立ち入らない。園内の灯りも乏しく、ここだけは東京でもちゃんと夜明け前を感じることの出来る場所だ。
だから、僕たちはたまにこの公園で朝が来るのを待ちわびる。
公園の入り口の自販機でペットボトルの温かい紅茶を買う。場所が変わっても、この習慣は変わることはない。
園内に足を踏み入れると、一気に暗がりが押し寄せた。入り口付近にしか街灯がないのはちょっと不便だ。ずっと奥まで広がっているはずの芝生の広場は、少し先だってろくに見えなかった。
スマホのライトを点け、いつもの場所へ向かう。広場の奥手にある大きな木が僕たちの定位置だ。
本当にそこにいるのだろうか、なんて疑問は必要なく、遠くの方で小さなスマホの明かりが見えた。
今まで一人で行くことなんてなかったのに、今日は一体どういう気まぐれなのだろう。
明かりに向けて歩を進めると、あちらも僕に気が付いたのか、明かりが左右にせわしなく揺れる。
いつもの場所。大木を囲う丸形のベンチに彼女がいた。
「おはよう、奏汰くん!」
そんな彼女の第一声にいつの日かのことを思い出す。
「音子もおはよう」
軽いあくびを噛み殺し、彼女の隣に腰かける。
「思ったよりも早かったね。私も今来たところだよ」
「それなら、いつもみたいに一緒に来ればよかったのに。一人は心配になるよ」
「過保護な彼氏だなぁ」
彼女は傍らに置かれた缶コーヒーを手に取り、笑いながら言った。
ふと、再び奏翔からのメッセージを知らせる通知音が鳴る。
『そう言えば、正月は実家に帰る?』
その文面を見て、僕はしばし考える。横目で彼女を見遣れば、僕の顔を覗き込んで不思議そうに首を傾げていた。
「どした?」
「……何でもない」
おもむろにスマホの画面を消して、ポケットにしまう。
すると、彼女はむっと頬を膨らませた。
「浮気かぁ?」
「するわけないじゃん……」
「ふふっ、知ってるよ」
彼女は足をぱたぱたと揺らしながら、「冗談、冗談」と軽く言う。どうしてか上機嫌な彼女を眺め、やっぱり少し思案を巡らせる。
僕が実家に帰るとすれば、彼女はどうするのだろう。結局、彼女と彼女の母親の関係は何も変わっちゃいない。彼女が自分の実家に帰ることはないだろう。
とはいえ、一緒に僕の実家に行くのも……。
一緒に住むことになった時に、両親へ彼女のことは紹介したが、正月まで連れて帰るというのはかなり気恥ずかしい。
そもそも、彼女が地元に良い印象を持っていない可能性も考えられる。長く、彼女を苦しめて傷付けていた場所なのだ。帰りたくないと言われたら、僕も彼女と二人きりの正月を選ぶのだろう。
東の空がじんわりと燃え始め、園内の輪郭が次第にはっきりとしていく。朝が来るまで、もう少しだ。
結局、僕は悩んだ末に彼女に尋ねることにした。
「奏翔がさ、正月は向こうに帰るのかって。……音子はどうする? えっと、一緒に帰る?」
僕が歯切れ悪く言えば、彼女はぱっと表情を明るくした。
「えっ、いいじゃん! 奏汰くんたちのご両親優しいから好き! 一緒に行こ!」
ちょっぴり意外だった。
「そっか、じゃあ帰ろうかな」
「うんうん。まだ一年経ってないけど、何だかすっごく久しぶりに地元に帰る気分」
「こっちに来てから色々あったもんね。大学が始まって、二人で住みだして、アルバイトして」
「私が単位を落としかけて」
と彼女が続くから、二人でちょっと笑い合った。
「こんな未来、想像出来た?」
彼女がふと僕に尋ねる。
二人で明け行く空と海を眺めていたあの頃を振り返れば、答えはすぐに浮かんだ。
「思っていたよりいいかもね」
「私は想像の何倍も、何十倍もいいよ。毎日楽しい!」
彼女がそう思ってくれていることが、今の僕には何よりも嬉しいことだ。
「そうだ、あっち帰ったら、あの公園行こうね」
「構わないけど、音子はいいの?」
彼女の提案に思わず聞き返してしまう。
「ん? 何が?」
喉まで出かかった言葉を一度呑み込む。手元のペットボトルをぼんやり見つめ、ややあって言った。
「だって、あそこは音子にとって長い間一人を過ごしていた場所だからさ。あまり立ち寄りたくないんじゃないかって」
すると、彼女は呆気に取られたように目をしばたたかせ、ややあって大きなため息を吐いた。
「奏汰くんは相変わらずだなぁ」
「どういうこと?」
「あの公園も、あの灯台も、私は奏汰くんに大切な思い出に変えてもらったってことだよ。だから、とにかく一緒に行くの!」
ずいっと顔を僕に近付ける彼女に気圧され、小さく頷く。
「わ、分かったよ」
彼女が満足げに笑みを零す。
「でも、まだお正月気分は早いんじゃない?」
そう言い、彼女は僕とは反対側に置いてあった紙袋を持ち上げて見せた。
「何それ?」
「何って、今日はクリスマスだよ。そんなの一つしかないじゃないの」
弾んだ声と一緒に彼女が取り出した紙箱を開ければ、大きなホールケーキが姿を見せた。相変わらず白いクリームが少し歪なのを見れば、彼女の手作りだということが分かる。ただし、円型だったと思われるケーキは、真ん中で切り分けられて半分しか入っていなかった。
「何だかデジャブ……。いつの間につくったの?」
昨晩、冷蔵庫にこんな大きなものは入っていなかったはずだ。夜中に起きてつくっていたとしても、手狭な部屋で僕が起きないとは思えなかった。
「奏汰くんを驚かせようと思ってね。昨日、君がバイトに行ってる間につくって、奏翔くんの家に持って行って置かせてもらったの。今日はここに来る前に奏翔くんの家までこれを取りに行ってたんだ」
なるほど、これで色々疑問だったことが晴れた。奏翔が珍しく早い時間にメッセージを送って来たのは、彼女の訪問で早起きしたからだ。それにケーキが半分なのは、もう半分を奏翔に分けたからだろう。
それにしても、僕たちが住んでいるマンションから、奏翔が一人暮らしをしているマンションまでは十五分ほどかかる。わざわざ、僕へのサプライズのためにここまでする彼女の熱意には感心だ。
「確かに驚いた……。流石にこっちに来ても音子のケーキを朝から拝むことになるとは思わなかったよ」
「でしょ、でしょ~! これ、毎年やるからね。あっ、でも今日の夜はチキン食べようね」
「それは夜なんだね」
「もちろん」
相変わらず、彼女の基準はよく分からない。だけど、そんな彼女のペースにもすっかり慣れた自分がいる。
紙皿に切り分けられたケーキを受け取り、一口。十八歳の誕生日に初めて彼女のケーキを食べてからずっと、少し甘めにつくってくれている。きっと、あの時甘くし過ぎたと言った彼女に、僕がちょうど良いと言ったからだろう。
時間をかけたサプライズも、甘くつくってくれたケーキも、全部彼女が僕のためにしてくれたことだと思うと、
「幸せだなぁ」
そんな言葉が零れ落ちる。
「ふふっ」
彼女が嬉しそうに笑みを浮かべた。
「私の口癖、すっかりうつっちゃったね」
「あっ……」
少し、顔が熱くなった。本当に無意識に口を衝いて出た言葉だったので、なおさら恥ずかしい。
「あー、照れてる!」
「て、照れてないっ!」
「はいうそー。奏汰くんはうそを吐く時、目線が右下に行くんだよね~」
嬉々として僕の癖を暴く彼女に、余計に恥ずかしさが込み上がった。少し彼女と見つめ合い、二人同時に笑みを零す。彼女は嬉しそうに、僕は呆れたように。
ケーキを食べ終えた頃には、すっかり青空が広がっていた。
「そろそろ帰ろっか」
彼女の手を取り、立ち上がる。燦々と降り注ぐ陽射しが、僕たちを明るく照らしていた。
帰り道、ふと彼女に尋ねた。
「音子は今、幸せ?」
すると、隣の彼女は僕を見上げ、握った手にぎゅっと力を込めた。そして、晴れ晴れしい表情で、
「うん! とっても幸せ!」
そう言ったのだ。
「そっか、じゃあ、やっぱり僕も幸せだ」
平凡で、ちょっと特別な一日の夜明けが僕と彼女を迎えてくれていた。
(了)