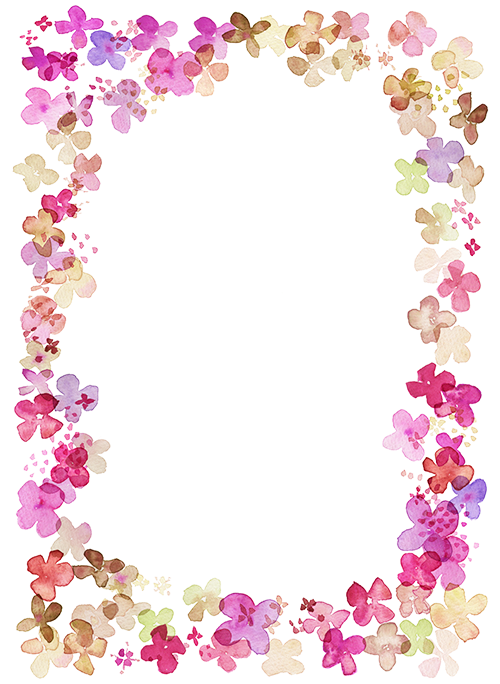封鎖令が出てから二十日目の朝、砂々の元に手紙が届いた。
部屋の前に置かれた盆に気づき、そっと腰を落として手紙を取ると、見覚えのある字で名前が記されていた。
(李澄さまの……)
胸が締めつけられて、急いで封を切る。
それは短い文章だった。書かれた文を追うごとに、砂々の呼吸は浅くなっていった。
『砂々へ
親類が私の借財を肩代わりしてくれた。お前に負担を背負わせることは、もうない。
ただ――お前との婚姻を破談にする条件で、私はそれを受け入れた。
おそらく、お前が手を回してくれたのだな?
どのような手段であったかは聞くまい。
家同士が決めた婚約ではあったが、お前を愛していたよ。
どうか幸せになってほしい』
たった数行で終わった手紙に、視界がぼやけた。
「……破談」
それも、おそらく砂々が身を差し出したのだろうと暗に含めている。
二人の婚約の誓いは幼い頃からの、家同士が決めたものだった。
砂々の気持ちは恋とは呼べない淡い情だったが、李澄と寄り添って生きていく未来を信じていた。
互いの貧しさも弱さも、知っていた。
いつか子を抱き、慎ましい幸せを得る――それが砂々の小さな夢だった。
(終わってしまった……)
自分は身を売っていないと訴えたい思いも、見る間にかき消えた。
深いところで何かがぽきりと折れる音が聞こえた。
辺りが閉塞していく心地で、全身から力が抜けるような虚無に覆われた。
夜になっても眠れず、何かに追われるように水瓶を運び、手を荒れさせながら床を磨き続けた。
(李澄さまに……見放された)
その事実が繰り返し心をえぐり、何かに打ち込んでいなければ倒れてしまいそうだった。
けれど砂々は弱い体を抱えていて、後宮の外で風に当たるような仕事はできないだろうと言われていた侍女だった。
翌朝、体と心をだますのも限界が来て、砂々は床にうずくまった。
三日間、昏く寒い水底に沈むような夢をさまよった。
心まで気弱になって、自分でも抑えられずに泣いたと思う。
けれどそんな夢うつつの状態で、不思議な光景を見た。いつもの侍女部屋の中に、見慣れぬ黒い衣の影がある。
そのひとは、砂々の額に触れ、柔らかい布で汗を拭き、「泣かなくていい」と言って砂々の手を包んでくれた。
(陛下……?)
そんなはずはないと、いくら頼りない心地でも信じなかった。
妃でもない自分の見舞いに、皇帝が来るなどありえない。
砂々はひどい羞恥心に襲われて、どこかに隠れたいような思いに駆られた。
(身の程知らず……。こんな、甘えた夢)
冷たい汗で寝具を濡らしたころ、ようやく熱が引いて砂々はまぶたを開いた。
「……あ」
側にいた侍女がそれをみとめて、足早に去っていく。
病の間、どうしてか同僚の侍女たちが片時も離れず側についていた。砂々の身分を考えるとそのように丁重に扱ってくれる理由がわからず、ただ困惑していた。
しばらくの後、房室の外に何人かの足音が近づいて来て、砂々の房室の前で止まる。
(これは……侍女の足音ではない……?)
戸が静かに開いて、そこには壮年の宦官長が宦官たちを従えて立っていた。
「砂々どの。お目覚めと伺って参りました」
宦官長は妃にさえ意見を言える存在で、砂々のような侍女は話しかけることさえできない雲の上の人だった。
砂々は恐縮で飛び起きて、慌てて床にひざまずこうとする。
「よい、まだ本調子ではないでしょう。横になっていてください」
ところが宦官長は柔和な表情で優しく言う。砂々はそれでもとても横になることはできず、寝台の上で正座をして頭を下げた。
「お越しいただき恐縮です。ですが……私は、どのような不届きをしてしまったのか、うかがってもよろしいでしょうか……?」
宦官長はそれを聞いて、穏やかに言葉を切り出す。
「この上ない慶事を申し上げに来ました」
そもそも砂々に話しかける口調が、侍女に対するものではない。砂々は震えながら、その沙汰を待つ。
宦官長は丁寧に巻物を取り出し、恭しく広げた。
「陛下からの勅書にございます」
砂々の胸が、高鳴りではなく驚愕で跳ねた。
(陛下……? どうして……?)
宦官はにこやかに、砂々が信じられないような内容を口にする。
「砂々どのを、「離宮・翠静宮」に住まわせること。さらに――妃として召し上げることを、陛下が正式にお決めになりました」
静かな声なのに、部屋の空気を一変させる宣告だった。
(妃……? 私、が……?)
それは大きな恐れに飲まれて、砂々は身じろぎもできなかった。
なぜ、どうして、周りの宦官たちに目で問いかけても、誰も彼もが微笑むばかりでその答えを拒絶する。
それは答えを禁じられているようにも見えた。微笑みの壁で砂々を包んで、砂々の知らないところに彼女を連れて行くように思えた。
砂々の喉は声を失い、唇だけが震えた。
宦官長は青ざめた砂々に気づいているだろうに、どこか誇らしげに告げた。
「砂々どのは、かねてより陛下のご恵愛を受けられていたとか。この度のこと、たいへんな栄誉とお察しします」
砂々の思考は、まるで千切れた糸のように散っていく。
(ご恵愛……栄誉……)
黒耀帝の、あの優しい瞳が脳裏に浮かぶ。
けれど同時に、後宮から逃げられなかった日々、官吏の処刑を思う。
――出られませんよ。とてもとても、名誉なことでございますから。
侍女たちの、微笑みとともに投げかけられた宣告が蘇る。
背筋がぞくりと震えて、それは全身に広がっていった。
砂々はいっそ病の見せた幻であればと願いながら、震え声で訴える。
「……ご辞退、ご辞退を……させて……」
「勅令に背くことはできません」
宦官長は、逃げ道を与えない声音で締めくくった。
「病が快癒されましたら、翠静宮にお迎えいたします。どうかそれまで……安らかにお休みいただきますよう」
宦官長が深く頭を下げるのは、もはや砂々を侍女と考えていない証だった。
その宮に向かった先にどんな運命があるのか、砂々にはもう想像することさえできなかった。
部屋の前に置かれた盆に気づき、そっと腰を落として手紙を取ると、見覚えのある字で名前が記されていた。
(李澄さまの……)
胸が締めつけられて、急いで封を切る。
それは短い文章だった。書かれた文を追うごとに、砂々の呼吸は浅くなっていった。
『砂々へ
親類が私の借財を肩代わりしてくれた。お前に負担を背負わせることは、もうない。
ただ――お前との婚姻を破談にする条件で、私はそれを受け入れた。
おそらく、お前が手を回してくれたのだな?
どのような手段であったかは聞くまい。
家同士が決めた婚約ではあったが、お前を愛していたよ。
どうか幸せになってほしい』
たった数行で終わった手紙に、視界がぼやけた。
「……破談」
それも、おそらく砂々が身を差し出したのだろうと暗に含めている。
二人の婚約の誓いは幼い頃からの、家同士が決めたものだった。
砂々の気持ちは恋とは呼べない淡い情だったが、李澄と寄り添って生きていく未来を信じていた。
互いの貧しさも弱さも、知っていた。
いつか子を抱き、慎ましい幸せを得る――それが砂々の小さな夢だった。
(終わってしまった……)
自分は身を売っていないと訴えたい思いも、見る間にかき消えた。
深いところで何かがぽきりと折れる音が聞こえた。
辺りが閉塞していく心地で、全身から力が抜けるような虚無に覆われた。
夜になっても眠れず、何かに追われるように水瓶を運び、手を荒れさせながら床を磨き続けた。
(李澄さまに……見放された)
その事実が繰り返し心をえぐり、何かに打ち込んでいなければ倒れてしまいそうだった。
けれど砂々は弱い体を抱えていて、後宮の外で風に当たるような仕事はできないだろうと言われていた侍女だった。
翌朝、体と心をだますのも限界が来て、砂々は床にうずくまった。
三日間、昏く寒い水底に沈むような夢をさまよった。
心まで気弱になって、自分でも抑えられずに泣いたと思う。
けれどそんな夢うつつの状態で、不思議な光景を見た。いつもの侍女部屋の中に、見慣れぬ黒い衣の影がある。
そのひとは、砂々の額に触れ、柔らかい布で汗を拭き、「泣かなくていい」と言って砂々の手を包んでくれた。
(陛下……?)
そんなはずはないと、いくら頼りない心地でも信じなかった。
妃でもない自分の見舞いに、皇帝が来るなどありえない。
砂々はひどい羞恥心に襲われて、どこかに隠れたいような思いに駆られた。
(身の程知らず……。こんな、甘えた夢)
冷たい汗で寝具を濡らしたころ、ようやく熱が引いて砂々はまぶたを開いた。
「……あ」
側にいた侍女がそれをみとめて、足早に去っていく。
病の間、どうしてか同僚の侍女たちが片時も離れず側についていた。砂々の身分を考えるとそのように丁重に扱ってくれる理由がわからず、ただ困惑していた。
しばらくの後、房室の外に何人かの足音が近づいて来て、砂々の房室の前で止まる。
(これは……侍女の足音ではない……?)
戸が静かに開いて、そこには壮年の宦官長が宦官たちを従えて立っていた。
「砂々どの。お目覚めと伺って参りました」
宦官長は妃にさえ意見を言える存在で、砂々のような侍女は話しかけることさえできない雲の上の人だった。
砂々は恐縮で飛び起きて、慌てて床にひざまずこうとする。
「よい、まだ本調子ではないでしょう。横になっていてください」
ところが宦官長は柔和な表情で優しく言う。砂々はそれでもとても横になることはできず、寝台の上で正座をして頭を下げた。
「お越しいただき恐縮です。ですが……私は、どのような不届きをしてしまったのか、うかがってもよろしいでしょうか……?」
宦官長はそれを聞いて、穏やかに言葉を切り出す。
「この上ない慶事を申し上げに来ました」
そもそも砂々に話しかける口調が、侍女に対するものではない。砂々は震えながら、その沙汰を待つ。
宦官長は丁寧に巻物を取り出し、恭しく広げた。
「陛下からの勅書にございます」
砂々の胸が、高鳴りではなく驚愕で跳ねた。
(陛下……? どうして……?)
宦官はにこやかに、砂々が信じられないような内容を口にする。
「砂々どのを、「離宮・翠静宮」に住まわせること。さらに――妃として召し上げることを、陛下が正式にお決めになりました」
静かな声なのに、部屋の空気を一変させる宣告だった。
(妃……? 私、が……?)
それは大きな恐れに飲まれて、砂々は身じろぎもできなかった。
なぜ、どうして、周りの宦官たちに目で問いかけても、誰も彼もが微笑むばかりでその答えを拒絶する。
それは答えを禁じられているようにも見えた。微笑みの壁で砂々を包んで、砂々の知らないところに彼女を連れて行くように思えた。
砂々の喉は声を失い、唇だけが震えた。
宦官長は青ざめた砂々に気づいているだろうに、どこか誇らしげに告げた。
「砂々どのは、かねてより陛下のご恵愛を受けられていたとか。この度のこと、たいへんな栄誉とお察しします」
砂々の思考は、まるで千切れた糸のように散っていく。
(ご恵愛……栄誉……)
黒耀帝の、あの優しい瞳が脳裏に浮かぶ。
けれど同時に、後宮から逃げられなかった日々、官吏の処刑を思う。
――出られませんよ。とてもとても、名誉なことでございますから。
侍女たちの、微笑みとともに投げかけられた宣告が蘇る。
背筋がぞくりと震えて、それは全身に広がっていった。
砂々はいっそ病の見せた幻であればと願いながら、震え声で訴える。
「……ご辞退、ご辞退を……させて……」
「勅令に背くことはできません」
宦官長は、逃げ道を与えない声音で締めくくった。
「病が快癒されましたら、翠静宮にお迎えいたします。どうかそれまで……安らかにお休みいただきますよう」
宦官長が深く頭を下げるのは、もはや砂々を侍女と考えていない証だった。
その宮に向かった先にどんな運命があるのか、砂々にはもう想像することさえできなかった。