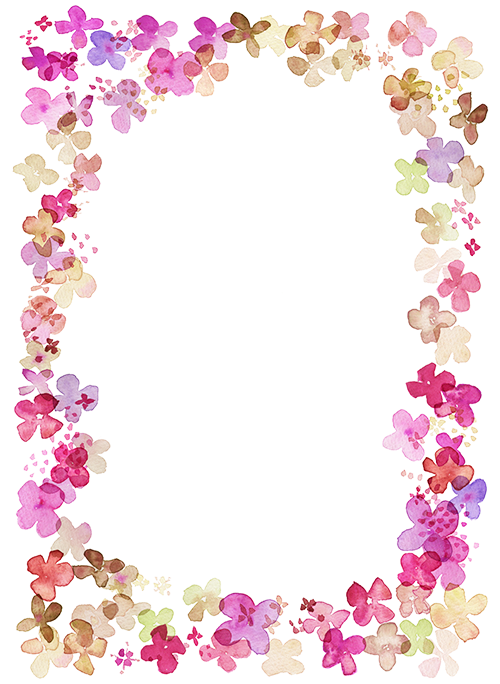その夜の空気は、一段と冷えて肌を突き刺すようだった。
この世界の容赦ない過酷さから守るように、私はさなを繰り返し抱いてはあやして、彼を温めていた。
やがて救護院の壁を伝って、隠しようもないざわめきが響いてくる。
蹄の音と、甲冑の触れ合う硬い音、命令に、短く返る兵たちの返事が重なる。
(……どうか、通り過ぎて)
そう願いながら、まるで私が縋るようにさなを抱きしめていた。
けれど儚い願いはむなしく裏切られて、看護人が青ざめた顔で駆け込んできた。
「砂々さま……っ、隠れてください! 皇帝の軍が、この救護院に――!」
胸が跳ねて、私はとっさにさなを胸に引き寄せる。
(来てしまった。やっぱり逃げ切れなかった……)
でも、恐怖よりも先に浮かんだのは抗えないほどの切望だった。
(黒耀さま……)
その腕の中に戻りたい。でも、戻ってはいけない。
その相反する想いが胸を裂くように暴れた。
「裏口から逃げましょう! 少しだけなら時間を稼ぎます!」
看護人が私の腕を取る。
私はさなを抱き直し、痛む足を床に下ろした。
そのときだった。
ギィ、と木の扉が低く軋む音がした。
救護院全体が怯えたように感じた。
ひとりの人間が静かにためらいなく押し開けた音だったのに、まるで嵐が到来したように辺りが静まり返った。
看護人の顔が蒼白になる。
「……ま、まさか。そんな……っ! 玉体が、御自ら……!」
看護人は倒れ込むように平伏して、喉を詰まらせた。
私も、姿を見るよりも先に悟ってしまった。
戸口から差し込む影は、月のように静かなのに、研ぎ澄ませた矛先のような力を持っていた。
それはこの国で唯一絶対の御方の、影だった。
闇に溶けた黒衣の裾が揺れる。
「……砂々」
その声は眠らず探し続けた者の、荒れた呼吸の重みを持っていた。
私は足が震えて、一歩も動けなかった。
黒耀さまは一歩、もう一歩と近づいてくる。
救護院の薄暗い灯りの下、私を見つけたその瞳は、狂気と安堵がないまぜになった光を宿していた。
「やっと……見つけた」
さなを抱く腕が、小刻みに震えていた。
この子を守らなければという思いと、黒耀さまの元に身を投げ出してしまいたいという衝動が胸の内でぶつかり合う。
「……近づかないでください」
やっとのことで告げた言葉は、弱弱しい一言だった。
それでも黒耀さまは、胸に短刀でも刺されたような顔をした。
まばたきさえ止めて、私を凝視していた。
「どうして……拒む? 私が、怖い?」
確かに、私は怖いのかもしれない。
黒耀さまが私に降り注いでくれた愛は、あまりに深かった。もう一度抱きしめられたら、私はきっとすべてを捨ててしまう。
「おそばに、いられない……。私が、黒耀さまのそばにいたら……だれかが死んでしまうの」
言った瞬間、黒耀さまの空気が変わった。
怒りでもなく、驚愕でもなく、息を呑むような痛みを浮かべた。
「……砂々。だから逃げたのか」
低く震える声だった。
黒耀さまはゆっくりと息を吸って、一歩だけ私の方に進む。
私は反射的に身を縮めた。それを見て、黒耀さまは立ち止まる。
まるで、私の怯えが鉄の鎖になって足を縛ったかのようだった。
「聞いてほしい。私の心を」
息を呑んだ私の前で、黒耀さまは迷わず床に片膝をついた。
帝が誰かに跪くなど、在位以来ただの一度もなかったはずだった。
それなのに今、黒耀さまは私を見上げている。
「君を愛している。出会ったときから少しも変わらず、君を想っている。君と寄り添い暮らしていくのが私の最大の幸せで、何にも替わらないたった一つの願いだ」
黒耀さまは私を狂ったような光を宿した目で見上げながらささやく。
「……ああ、そうだ。私は君のためなら誰を傷つけるのも厭わない。後宮を、王宮を、この世界を壊しても構わない。もちろん、君との子は至上の珠のように愛おしい。……皇位につけたくなる日も、来るのかもしれない」
びくりと震えた私に、黒耀さまはふいに甘い目をして言う。
「でも……君が恐れるのなら、妃たちも、他の子どもたちも、私は殺さない。君が望む、それだけですべての理由になる」
その言葉は優しくも力強く、私の胸の奥を衝いた。
「私は黒耀。君は私の妻で、私は君の夫だ。どうか……私の手を取ってくれないか」
その声音を聞いて、今すぐその手に触れたかった。
黒耀さまは、ただ静かに私を見つめていた。
追い詰めるでもなく、責めるでもなく、ただ、深い慈愛を湛えながら見上げていた。
「……砂々、帰ってきてほしい」
呼ばれた名に、涙がまたあふれそうになった。
「ふたりで、さなを守ろう。君がどうしたらいいかわからないなら……私が教える。君が怖がるなら、後宮も王宮も、私が全部変える。だから……おいで」
その言葉に、胸の奥が大きく揺れた。
黒耀さまは、一度だけまぶたを閉じた。
痛みでも悲しみでもなく、決意を噛みしめるように言った。
「たとえ拒まれても、連れ帰る。砂々。君が泣いていようと抵抗しようと……私は君なしでは、生きていけないから」
その声に、私はもう逃れられないのだと思った。
この人は私が拒んでも、世界が敵でも、必ず私とさなを奪い返す。
私は崩れ落ちるように膝をついて、黒耀さまに手を伸ばした。
「……さなは、男児、だったの……」
私が恐れている事実を告げると、黒耀さまは穏やかに微笑んだ。
「では、良い馬をたくさん用意しなければね」
黒耀さまは皇位のことなど一言も口にせず、ただ優しく未来を語った。
私がその声に安堵の息をつくと、黒耀さまはその呼吸に触れるように口づける。
「……つかまえた。二度と離さない」
黒耀さまはそっと、けれど閉じ込めるように私を腕に迎え入れた。
こうして私は、黒耀さまの作る優しい鳥籠のような世界の住民になった。
この世界の容赦ない過酷さから守るように、私はさなを繰り返し抱いてはあやして、彼を温めていた。
やがて救護院の壁を伝って、隠しようもないざわめきが響いてくる。
蹄の音と、甲冑の触れ合う硬い音、命令に、短く返る兵たちの返事が重なる。
(……どうか、通り過ぎて)
そう願いながら、まるで私が縋るようにさなを抱きしめていた。
けれど儚い願いはむなしく裏切られて、看護人が青ざめた顔で駆け込んできた。
「砂々さま……っ、隠れてください! 皇帝の軍が、この救護院に――!」
胸が跳ねて、私はとっさにさなを胸に引き寄せる。
(来てしまった。やっぱり逃げ切れなかった……)
でも、恐怖よりも先に浮かんだのは抗えないほどの切望だった。
(黒耀さま……)
その腕の中に戻りたい。でも、戻ってはいけない。
その相反する想いが胸を裂くように暴れた。
「裏口から逃げましょう! 少しだけなら時間を稼ぎます!」
看護人が私の腕を取る。
私はさなを抱き直し、痛む足を床に下ろした。
そのときだった。
ギィ、と木の扉が低く軋む音がした。
救護院全体が怯えたように感じた。
ひとりの人間が静かにためらいなく押し開けた音だったのに、まるで嵐が到来したように辺りが静まり返った。
看護人の顔が蒼白になる。
「……ま、まさか。そんな……っ! 玉体が、御自ら……!」
看護人は倒れ込むように平伏して、喉を詰まらせた。
私も、姿を見るよりも先に悟ってしまった。
戸口から差し込む影は、月のように静かなのに、研ぎ澄ませた矛先のような力を持っていた。
それはこの国で唯一絶対の御方の、影だった。
闇に溶けた黒衣の裾が揺れる。
「……砂々」
その声は眠らず探し続けた者の、荒れた呼吸の重みを持っていた。
私は足が震えて、一歩も動けなかった。
黒耀さまは一歩、もう一歩と近づいてくる。
救護院の薄暗い灯りの下、私を見つけたその瞳は、狂気と安堵がないまぜになった光を宿していた。
「やっと……見つけた」
さなを抱く腕が、小刻みに震えていた。
この子を守らなければという思いと、黒耀さまの元に身を投げ出してしまいたいという衝動が胸の内でぶつかり合う。
「……近づかないでください」
やっとのことで告げた言葉は、弱弱しい一言だった。
それでも黒耀さまは、胸に短刀でも刺されたような顔をした。
まばたきさえ止めて、私を凝視していた。
「どうして……拒む? 私が、怖い?」
確かに、私は怖いのかもしれない。
黒耀さまが私に降り注いでくれた愛は、あまりに深かった。もう一度抱きしめられたら、私はきっとすべてを捨ててしまう。
「おそばに、いられない……。私が、黒耀さまのそばにいたら……だれかが死んでしまうの」
言った瞬間、黒耀さまの空気が変わった。
怒りでもなく、驚愕でもなく、息を呑むような痛みを浮かべた。
「……砂々。だから逃げたのか」
低く震える声だった。
黒耀さまはゆっくりと息を吸って、一歩だけ私の方に進む。
私は反射的に身を縮めた。それを見て、黒耀さまは立ち止まる。
まるで、私の怯えが鉄の鎖になって足を縛ったかのようだった。
「聞いてほしい。私の心を」
息を呑んだ私の前で、黒耀さまは迷わず床に片膝をついた。
帝が誰かに跪くなど、在位以来ただの一度もなかったはずだった。
それなのに今、黒耀さまは私を見上げている。
「君を愛している。出会ったときから少しも変わらず、君を想っている。君と寄り添い暮らしていくのが私の最大の幸せで、何にも替わらないたった一つの願いだ」
黒耀さまは私を狂ったような光を宿した目で見上げながらささやく。
「……ああ、そうだ。私は君のためなら誰を傷つけるのも厭わない。後宮を、王宮を、この世界を壊しても構わない。もちろん、君との子は至上の珠のように愛おしい。……皇位につけたくなる日も、来るのかもしれない」
びくりと震えた私に、黒耀さまはふいに甘い目をして言う。
「でも……君が恐れるのなら、妃たちも、他の子どもたちも、私は殺さない。君が望む、それだけですべての理由になる」
その言葉は優しくも力強く、私の胸の奥を衝いた。
「私は黒耀。君は私の妻で、私は君の夫だ。どうか……私の手を取ってくれないか」
その声音を聞いて、今すぐその手に触れたかった。
黒耀さまは、ただ静かに私を見つめていた。
追い詰めるでもなく、責めるでもなく、ただ、深い慈愛を湛えながら見上げていた。
「……砂々、帰ってきてほしい」
呼ばれた名に、涙がまたあふれそうになった。
「ふたりで、さなを守ろう。君がどうしたらいいかわからないなら……私が教える。君が怖がるなら、後宮も王宮も、私が全部変える。だから……おいで」
その言葉に、胸の奥が大きく揺れた。
黒耀さまは、一度だけまぶたを閉じた。
痛みでも悲しみでもなく、決意を噛みしめるように言った。
「たとえ拒まれても、連れ帰る。砂々。君が泣いていようと抵抗しようと……私は君なしでは、生きていけないから」
その声に、私はもう逃れられないのだと思った。
この人は私が拒んでも、世界が敵でも、必ず私とさなを奪い返す。
私は崩れ落ちるように膝をついて、黒耀さまに手を伸ばした。
「……さなは、男児、だったの……」
私が恐れている事実を告げると、黒耀さまは穏やかに微笑んだ。
「では、良い馬をたくさん用意しなければね」
黒耀さまは皇位のことなど一言も口にせず、ただ優しく未来を語った。
私がその声に安堵の息をつくと、黒耀さまはその呼吸に触れるように口づける。
「……つかまえた。二度と離さない」
黒耀さまはそっと、けれど閉じ込めるように私を腕に迎え入れた。
こうして私は、黒耀さまの作る優しい鳥籠のような世界の住民になった。