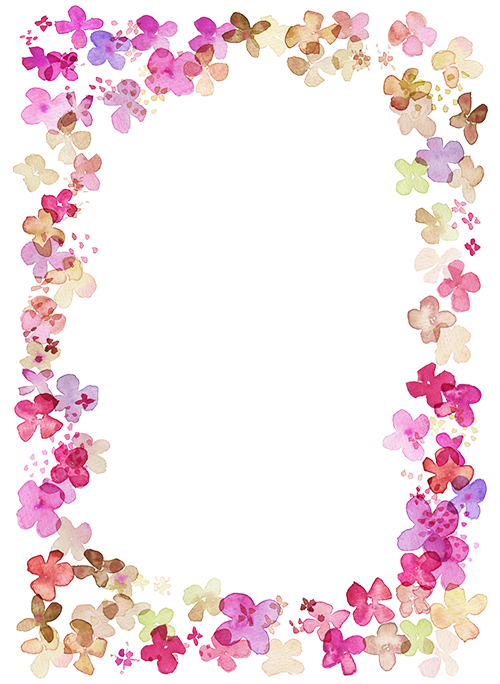翌朝、砂々はまだ暗い時間から荷をまとめて、後宮の自室を発った。
足元さえ見えない仄暗さであっても、子どもの頃から出入りしてきた場所だ。ただ今朝は重苦しく垂れこめた曇天で、砂々のこれからをなお見えなくしていた。
(道は……見えなくていい。李澄さまを裏切るような行いをしに行くのだもの)
昨日官吏に抵抗したときの恐れが蘇って、また逃げ出しそうになる。自分で決めたこととはいえ、獣の牙に噛まれに行くのが恐ろしくないはずはなかった。
けれど、門に向かった砂々は、門番の思わぬ言葉に足を止めた。
「……通れぬ。封鎖令が出ている」
砂々は目を見張ったものの、すぐに頭を下げて問いかける。
「なぜ……? いえ、侍女などに明かせないのは承知しています。せめて……いつになれば通れるか、教えていただけますか」
すがるように問いかけた砂々にも、門番はそれが厳命されているように無表情で答える。
「与えられた房室に戻れ。処罰されたいか」
脅しを含んだ言葉に、砂々はうつむいて首を横に振った。
(そんな……こうしているうちに、あの官吏が李澄さまを害してしまったら……)
砂々は諦めず、翌日も、その次の日も、裏門へ、正門へ、使用人門へと向かった。
侍女の姿をしていたら通してもらえないと思って、身をやつした下働きに姿も変えた。
だが封鎖令は解けないどころか、奇妙な事故が起こり始める。
ある日は、門へ続く廊下で突然天井瓦が落ちてきて通行止めになった。
ある日は、門の上から石壁が崩れ落ち、門自体が完全につぶれていた。
またある日は、ようやく砂々が門の前まで行くと、唐突に暴れ馬が走り出して官吏が殺到し、外へ出るどころではなくなった。
(どうして……どうして、こんなに……)
まるで後宮が、外へ出るものを柔らかい手で包んで阻んでいるようだった。優しく、子どもをあやすような仕草で、けれど決してその手から離さない。
砂々の背筋に、後宮の深淵に触れたような寒気が降りた。
後宮は美しい鳥籠。一度愛でられた鳥は、一生出られない……。
詩人がそう歌っていたのを、砂々は思い出した。
(でも……それは、後宮のお妃様たちのことで、私などが、決して……)
悪い想像を振り払うように、首を横に振る。
けれど砂々の願いとは裏腹に、後宮に敷かれた封鎖令は解けることなく、十日の月日が経とうとしていた。
あの官吏が処刑されたと知ったのは、夕陽が斜めに差し込む日暮れ時のことだった。
封鎖令に阻まれたまま無力感に肩を落としていた砂々に、水汲みをしていた侍女たちの声が耳に入った。
「……が、刑場に出されたそうよ」
砂々はそれを聞いたとき、肌が一斉に粟立つような心地がした。
名君と言われる黒耀帝の治世では、後宮は平穏な、守られた場所だった。けれど過去には日常だと言われていた、その血なまぐさい世界がにわかに近づいた気がした。
「聞いた……そう、金で……侍女に」
「悪い噂が……仕方ないこと……」
漏れ聞こえる声は途切れ途切れだが、その末路は問いただす必要もなかった。
(処刑……? あの人が……?)
自分に迫った恐ろしさのままに、いっそあの官吏がいなくなったらと思ったときはあった。
でも砂々は怪我を負ったわけではなく、命を奪うほどの咎があったとは思えない。
「離宮……鳥籠……」
それ以上の言葉を聞くことができずに、砂々はその場を後にしていた。
何度も呼吸を繰り返すけれど、うまく息が吸えない。
官吏の処刑が、自分に関わることだとは信じていない。ただ後宮がこの数日で、自分の知らないところに変わってしまったような恐ろしさを覚えた。
(出よう……ここは、人が命を奪われるところだから……!)
砂々は震える指で荷をまとめ、今度こそ逃げ出そうとした。
もう後宮のどこにも出口がなくとも、壁をよじ登ることも、下働きに紛れることも考えていた。
(もし……もしも、あの官吏の処刑が私に関わっていたとしたら)
自分にも、想像のつかない形で咎が襲うのではないか。
悪い未来だけが、頭の中で大きくなる。
使用人通路を足早に歩いていた砂々の元に、そっと声が降りてきた。
「砂々さま、どちらへ?」
振り返ると、侍女が三人、柔らかく微笑んでいる。
門番のように冷厳とした雰囲気はない。けれど目は油断なく砂々の挙動を見ていて、砂々は息を詰まらせた。
「実家に……里帰りを……」
苦し紛れに言う砂々に、侍女たちはふんわりと頷いた。
「後宮仕えの報酬はきちんと郷里に贈られていますよ」
「私たちは綺麗な衣を着て、微笑んで宮にお仕えしていればよいのです」
「さあ。そんな荷は、こちらにお預けになって」
左右から寄る手は、あくまで優しい。
けれど、逃げ道を与えない配置で砂々の腕を取った。
「ま、待って。私は帰らないと……!」
「どうして外などに興味を持たれるの?」
「もうじき、砂々さまのためのお住まいも完成するのに」
その言葉に、砂々の足がすくんだ。
(……私のための住まい?)
何か得体の知れない事態が動いているとわかっても、砂々は両脇を取られて侍女たちに部屋の奥へ戻されて行く。
元通りに砂々の部屋に戻ると、侍女たちは優しいようで残酷な言葉をかける。
「出られませんよ」
首筋に刃をあてられたような、ひやりとした感覚が走った。
「末永く愛でられませ。……とてもとても、名誉なことでございますから」
侍女たちは温かい茶を淹れて、半ば無理やり砂々に飲ませる。
砂々の体からはふっと力が抜けて、深い眠りに落ちていった。
足元さえ見えない仄暗さであっても、子どもの頃から出入りしてきた場所だ。ただ今朝は重苦しく垂れこめた曇天で、砂々のこれからをなお見えなくしていた。
(道は……見えなくていい。李澄さまを裏切るような行いをしに行くのだもの)
昨日官吏に抵抗したときの恐れが蘇って、また逃げ出しそうになる。自分で決めたこととはいえ、獣の牙に噛まれに行くのが恐ろしくないはずはなかった。
けれど、門に向かった砂々は、門番の思わぬ言葉に足を止めた。
「……通れぬ。封鎖令が出ている」
砂々は目を見張ったものの、すぐに頭を下げて問いかける。
「なぜ……? いえ、侍女などに明かせないのは承知しています。せめて……いつになれば通れるか、教えていただけますか」
すがるように問いかけた砂々にも、門番はそれが厳命されているように無表情で答える。
「与えられた房室に戻れ。処罰されたいか」
脅しを含んだ言葉に、砂々はうつむいて首を横に振った。
(そんな……こうしているうちに、あの官吏が李澄さまを害してしまったら……)
砂々は諦めず、翌日も、その次の日も、裏門へ、正門へ、使用人門へと向かった。
侍女の姿をしていたら通してもらえないと思って、身をやつした下働きに姿も変えた。
だが封鎖令は解けないどころか、奇妙な事故が起こり始める。
ある日は、門へ続く廊下で突然天井瓦が落ちてきて通行止めになった。
ある日は、門の上から石壁が崩れ落ち、門自体が完全につぶれていた。
またある日は、ようやく砂々が門の前まで行くと、唐突に暴れ馬が走り出して官吏が殺到し、外へ出るどころではなくなった。
(どうして……どうして、こんなに……)
まるで後宮が、外へ出るものを柔らかい手で包んで阻んでいるようだった。優しく、子どもをあやすような仕草で、けれど決してその手から離さない。
砂々の背筋に、後宮の深淵に触れたような寒気が降りた。
後宮は美しい鳥籠。一度愛でられた鳥は、一生出られない……。
詩人がそう歌っていたのを、砂々は思い出した。
(でも……それは、後宮のお妃様たちのことで、私などが、決して……)
悪い想像を振り払うように、首を横に振る。
けれど砂々の願いとは裏腹に、後宮に敷かれた封鎖令は解けることなく、十日の月日が経とうとしていた。
あの官吏が処刑されたと知ったのは、夕陽が斜めに差し込む日暮れ時のことだった。
封鎖令に阻まれたまま無力感に肩を落としていた砂々に、水汲みをしていた侍女たちの声が耳に入った。
「……が、刑場に出されたそうよ」
砂々はそれを聞いたとき、肌が一斉に粟立つような心地がした。
名君と言われる黒耀帝の治世では、後宮は平穏な、守られた場所だった。けれど過去には日常だと言われていた、その血なまぐさい世界がにわかに近づいた気がした。
「聞いた……そう、金で……侍女に」
「悪い噂が……仕方ないこと……」
漏れ聞こえる声は途切れ途切れだが、その末路は問いただす必要もなかった。
(処刑……? あの人が……?)
自分に迫った恐ろしさのままに、いっそあの官吏がいなくなったらと思ったときはあった。
でも砂々は怪我を負ったわけではなく、命を奪うほどの咎があったとは思えない。
「離宮……鳥籠……」
それ以上の言葉を聞くことができずに、砂々はその場を後にしていた。
何度も呼吸を繰り返すけれど、うまく息が吸えない。
官吏の処刑が、自分に関わることだとは信じていない。ただ後宮がこの数日で、自分の知らないところに変わってしまったような恐ろしさを覚えた。
(出よう……ここは、人が命を奪われるところだから……!)
砂々は震える指で荷をまとめ、今度こそ逃げ出そうとした。
もう後宮のどこにも出口がなくとも、壁をよじ登ることも、下働きに紛れることも考えていた。
(もし……もしも、あの官吏の処刑が私に関わっていたとしたら)
自分にも、想像のつかない形で咎が襲うのではないか。
悪い未来だけが、頭の中で大きくなる。
使用人通路を足早に歩いていた砂々の元に、そっと声が降りてきた。
「砂々さま、どちらへ?」
振り返ると、侍女が三人、柔らかく微笑んでいる。
門番のように冷厳とした雰囲気はない。けれど目は油断なく砂々の挙動を見ていて、砂々は息を詰まらせた。
「実家に……里帰りを……」
苦し紛れに言う砂々に、侍女たちはふんわりと頷いた。
「後宮仕えの報酬はきちんと郷里に贈られていますよ」
「私たちは綺麗な衣を着て、微笑んで宮にお仕えしていればよいのです」
「さあ。そんな荷は、こちらにお預けになって」
左右から寄る手は、あくまで優しい。
けれど、逃げ道を与えない配置で砂々の腕を取った。
「ま、待って。私は帰らないと……!」
「どうして外などに興味を持たれるの?」
「もうじき、砂々さまのためのお住まいも完成するのに」
その言葉に、砂々の足がすくんだ。
(……私のための住まい?)
何か得体の知れない事態が動いているとわかっても、砂々は両脇を取られて侍女たちに部屋の奥へ戻されて行く。
元通りに砂々の部屋に戻ると、侍女たちは優しいようで残酷な言葉をかける。
「出られませんよ」
首筋に刃をあてられたような、ひやりとした感覚が走った。
「末永く愛でられませ。……とてもとても、名誉なことでございますから」
侍女たちは温かい茶を淹れて、半ば無理やり砂々に飲ませる。
砂々の体からはふっと力が抜けて、深い眠りに落ちていった。