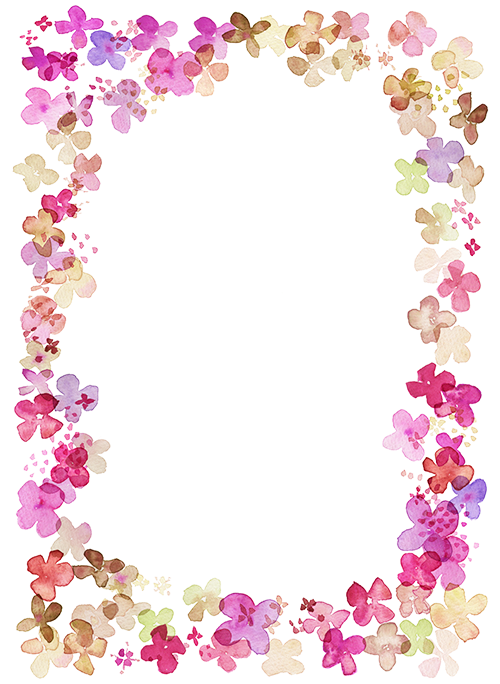砂々がお腹の子を「さな」と呼んだ日から、翠静宮にはたゆたう安息のような朝が戻り始めていた。
黒耀は毎朝のように、傍らの砂々が目覚めるまで見守ってきた。砂々が錯乱の中にあったときは、側にいる黒耀を目に映した途端に怯えて泣いた朝もあった。
けれど近頃の砂々は怯えではなく、ぼんやりとした明るさで黒耀をみつめ返す。それをみとめるたび、黒耀は胸が満たされるのを感じていた。
ゆるやかに目を開いた砂々を、甘く優しい声音で迎える。
「おはよう、砂々。……ああ、顔色がいいな。何よりだ」
以前の砂々は食事を運ばれても顔を背け、無理に匙を口に入れようとすると涙をこぼしていた。今ではほんの少しずつではあるが、自ら匙を持つようになった。
「これ、すき……」
「そうか、それが好きだったか。ではまた出すよう、料理長に伝えておこうな」
砂々がやせ細り、何も口に入れようとしなかったときは、自分も命がやせ細るような心地がしていた。それから時を超え、少しずつ砂々の好きなものを知るたび、蘇るような気持ちになれた。
「何でも食べたいものを言ってごらん。砂々の好きなものは、どんなささいなことでも知りたい」
黒耀が背を抱きながらささやくと、砂々はまだ眠たそうにうなずいた。
砂々が庭に出られるようになったのは昨日のことだ。
まだ足取りはおぼつかない。けれど初夏の野花が咲く中、そっと目を細めた砂々の横顔は、まるで陽だまりの中で息を吹き返した花そのものだった。
黒耀は時間が許す限り、自ら砂々の手を引いて歩くのを助けた。砂々はすぐに疲れて足を止めてしまうが、そうしたら抱き上げて砂々に庭を見せた。
庭の東屋で休憩をしていると、砂々はとろとろと眠りそうな顔でつぶやく。
「……風が、あったかい……ね」
「これから過ごしやすい時期になる。今、庭を整えさせているよ。砂々が毎日歩いても退屈しないように」
黒耀が言うと、砂々は黒耀の肩に寄りかかって、安心したように目を閉じる。
その甘えるような仕草に黒耀を怖がっていたときの名残はなくて、少年のように胸が弾んだ。
砂々の精神もまた、ゆっくりと育つように変わってきていた。
「こくようさま……は、ええと、陛……」
子どもが一生懸命習ったばかりの言葉を話そうとするような砂々に、黒耀は微笑んだ。
「黒耀でいいんだよ。砂々だけは、そう呼んでほしい」
砂々はきょとんと目を瞬かせ、それからたどたどしく言った。
「こくようさま……」
「うん、なぁに? 砂々」
とろけるように甘い声で問い返すと、砂々はほっとしたようにうなずいた。
砂々が「私」と口にするのを初めて聞いたときもそうだった。周囲の人々も、「お姉さま」「お医者さま」と認識できるようになる。
砂々が少しずつ、幼い世界から戻ってきている証だった。
黒耀はその成長を、誰よりも深く喜んでいた。
陽気がいつもよりも柔らかく、庭の葵が青々と茂る午後のことだった。
黒耀は砂々を小さな腰掛けに座らせると、懐から白く輝くものを取り出した。
それを見た砂々の瞳に、かすかな困惑が現れる。
「あ……」
吉祥鳥の意匠を施した、細く美しい指輪を、黒耀は苦い目で見下ろす。
「病に伏せっている間は、重荷になると思ってね。渡せなかった」
黒耀はそっと砂々の左手を取る。
その手首は細く、体力が戻ったとはいえ、まだ儚い小鳥のようだった。
「これを……君の指に与えたかった」
指輪をはめると、砂々は目を丸くして、それからぽつりと呟いた。
「きれい……。でも……これ、なんのもの、だったっけ……?」
その言葉は、まだ砂々の心が「婚姻」という概念を理解できないからでもあり……この指輪をきっかけに毒に侵された記憶が、どこかに残っているからかもしれなかった。
黒耀はそんな砂々の幼さも、弱さも愛おしかった。ただ微笑んで告げた。
「これはね、大切な証だよ。君と私が生涯寄り添うという約束」
「そう、なの……? こくようさまがうれしいなら……私も、うれしい」
その言葉に胸が衝かれた。
黒耀は思わず砂々の指を持ち上げて、性急に口づけた。
黒耀は熱を孕んだ瞳で砂々をみつめて言う。
「さなが生まれたら、もっと特別な贈り物をしよう。砂々が一生守られるもので……誰にも奪われないものを」
砂々は驚いたが、もう怯えたりはしなかった。とろりとまだ力が入らない目で柔く笑う。
「……ここは、あったかい……こわい夢、見ないの。だから、ほかに……なんにも、いらない」
砂々はあどけなく、たどたどしく答えた。
その無欲で無垢な笑顔を見つめながら、黒耀は静かに微笑み返した。
(砂々、砂々……なんて、可愛い。君がそう言うたび、私は底知れなく欲深くなるのだ)
自分の愛は、すでに取り返しのつかないほどこの小さな少女に絡まってしまっている。
「……君が望もうと望むまいと、私は君を離さないよ」
黒耀はその日、密かな決意を固めて砂々の頬に口づけた。
砂々が回復を始めてからというもの、一時はぞっとするような瞳をしていた皇帝は見る間に穏やかに変わり、臣下たちを安心させていた。
ところがその日朝議に姿を見せた黒耀は、その穏やかさとは違う気迫をまとっていた。
揺らぎのない絶対君主としての威容を放ち、黒耀は告げる。
「砂々を正妃に迎える」
ざわめきはあっという間に広間に満ち溢れた。
重臣たちは驚きと戸惑いを隠せなかった。その中でひとり、怜泉は目を伏せ、顔に影を落とす。
「もし余の正妃に砂々を迎えられないのなら」
黒耀の声は冷たく、しかし狂おしいほどの愛に満ちていた。
「……余は、砂々を連れて退位する」
その瞬間、朝議の空気は凍りついた。
黒耀はただ静かに、砂々のいる翠静宮の方に思いを馳せていた。
黒耀は毎朝のように、傍らの砂々が目覚めるまで見守ってきた。砂々が錯乱の中にあったときは、側にいる黒耀を目に映した途端に怯えて泣いた朝もあった。
けれど近頃の砂々は怯えではなく、ぼんやりとした明るさで黒耀をみつめ返す。それをみとめるたび、黒耀は胸が満たされるのを感じていた。
ゆるやかに目を開いた砂々を、甘く優しい声音で迎える。
「おはよう、砂々。……ああ、顔色がいいな。何よりだ」
以前の砂々は食事を運ばれても顔を背け、無理に匙を口に入れようとすると涙をこぼしていた。今ではほんの少しずつではあるが、自ら匙を持つようになった。
「これ、すき……」
「そうか、それが好きだったか。ではまた出すよう、料理長に伝えておこうな」
砂々がやせ細り、何も口に入れようとしなかったときは、自分も命がやせ細るような心地がしていた。それから時を超え、少しずつ砂々の好きなものを知るたび、蘇るような気持ちになれた。
「何でも食べたいものを言ってごらん。砂々の好きなものは、どんなささいなことでも知りたい」
黒耀が背を抱きながらささやくと、砂々はまだ眠たそうにうなずいた。
砂々が庭に出られるようになったのは昨日のことだ。
まだ足取りはおぼつかない。けれど初夏の野花が咲く中、そっと目を細めた砂々の横顔は、まるで陽だまりの中で息を吹き返した花そのものだった。
黒耀は時間が許す限り、自ら砂々の手を引いて歩くのを助けた。砂々はすぐに疲れて足を止めてしまうが、そうしたら抱き上げて砂々に庭を見せた。
庭の東屋で休憩をしていると、砂々はとろとろと眠りそうな顔でつぶやく。
「……風が、あったかい……ね」
「これから過ごしやすい時期になる。今、庭を整えさせているよ。砂々が毎日歩いても退屈しないように」
黒耀が言うと、砂々は黒耀の肩に寄りかかって、安心したように目を閉じる。
その甘えるような仕草に黒耀を怖がっていたときの名残はなくて、少年のように胸が弾んだ。
砂々の精神もまた、ゆっくりと育つように変わってきていた。
「こくようさま……は、ええと、陛……」
子どもが一生懸命習ったばかりの言葉を話そうとするような砂々に、黒耀は微笑んだ。
「黒耀でいいんだよ。砂々だけは、そう呼んでほしい」
砂々はきょとんと目を瞬かせ、それからたどたどしく言った。
「こくようさま……」
「うん、なぁに? 砂々」
とろけるように甘い声で問い返すと、砂々はほっとしたようにうなずいた。
砂々が「私」と口にするのを初めて聞いたときもそうだった。周囲の人々も、「お姉さま」「お医者さま」と認識できるようになる。
砂々が少しずつ、幼い世界から戻ってきている証だった。
黒耀はその成長を、誰よりも深く喜んでいた。
陽気がいつもよりも柔らかく、庭の葵が青々と茂る午後のことだった。
黒耀は砂々を小さな腰掛けに座らせると、懐から白く輝くものを取り出した。
それを見た砂々の瞳に、かすかな困惑が現れる。
「あ……」
吉祥鳥の意匠を施した、細く美しい指輪を、黒耀は苦い目で見下ろす。
「病に伏せっている間は、重荷になると思ってね。渡せなかった」
黒耀はそっと砂々の左手を取る。
その手首は細く、体力が戻ったとはいえ、まだ儚い小鳥のようだった。
「これを……君の指に与えたかった」
指輪をはめると、砂々は目を丸くして、それからぽつりと呟いた。
「きれい……。でも……これ、なんのもの、だったっけ……?」
その言葉は、まだ砂々の心が「婚姻」という概念を理解できないからでもあり……この指輪をきっかけに毒に侵された記憶が、どこかに残っているからかもしれなかった。
黒耀はそんな砂々の幼さも、弱さも愛おしかった。ただ微笑んで告げた。
「これはね、大切な証だよ。君と私が生涯寄り添うという約束」
「そう、なの……? こくようさまがうれしいなら……私も、うれしい」
その言葉に胸が衝かれた。
黒耀は思わず砂々の指を持ち上げて、性急に口づけた。
黒耀は熱を孕んだ瞳で砂々をみつめて言う。
「さなが生まれたら、もっと特別な贈り物をしよう。砂々が一生守られるもので……誰にも奪われないものを」
砂々は驚いたが、もう怯えたりはしなかった。とろりとまだ力が入らない目で柔く笑う。
「……ここは、あったかい……こわい夢、見ないの。だから、ほかに……なんにも、いらない」
砂々はあどけなく、たどたどしく答えた。
その無欲で無垢な笑顔を見つめながら、黒耀は静かに微笑み返した。
(砂々、砂々……なんて、可愛い。君がそう言うたび、私は底知れなく欲深くなるのだ)
自分の愛は、すでに取り返しのつかないほどこの小さな少女に絡まってしまっている。
「……君が望もうと望むまいと、私は君を離さないよ」
黒耀はその日、密かな決意を固めて砂々の頬に口づけた。
砂々が回復を始めてからというもの、一時はぞっとするような瞳をしていた皇帝は見る間に穏やかに変わり、臣下たちを安心させていた。
ところがその日朝議に姿を見せた黒耀は、その穏やかさとは違う気迫をまとっていた。
揺らぎのない絶対君主としての威容を放ち、黒耀は告げる。
「砂々を正妃に迎える」
ざわめきはあっという間に広間に満ち溢れた。
重臣たちは驚きと戸惑いを隠せなかった。その中でひとり、怜泉は目を伏せ、顔に影を落とす。
「もし余の正妃に砂々を迎えられないのなら」
黒耀の声は冷たく、しかし狂おしいほどの愛に満ちていた。
「……余は、砂々を連れて退位する」
その瞬間、朝議の空気は凍りついた。
黒耀はただ静かに、砂々のいる翠静宮の方に思いを馳せていた。