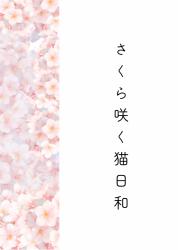「まあまあ、深刻に捉えすぎても良くないよ」
予備校の佐藤先生が、宥めるような声でそう言った。
両手で握りしめるのは、先週受けた高二東大本番レベル模試の結果。
その紙面に印刷されたのは、前回と変わらず「E」の文字。
「……夏休み、頑張ったんですけどね」
「ああ、知ってるよ。門田くんはよく頑張ってる。緊張感を持つのは大事なことだけど、今の判定に一喜一憂する必要はない」
「はい……でも、僕、不安なんです。このまま地道に努力をしていたら、東大との距離が縮まる……そんな確信が持てなくて」
「うむ……未来に絶対も百パーもないからねぇ」
「それは……そうですが……」
そんなことはもちろん分かっている。
この世には、「絶対に成績が伸びる勉強法」なんてものは存在しない。
ただ、着実に目標に近づいているときというのは、その実感が少なからずあるのだ。
今の僕にはそれがない。
勉強時間とこなした問題集のページが増えるだけで、「進んだ」という感覚がないのである。
「門田くんは……誰かに勉強を教えたことがあるかい?」
「え?」
佐藤先生は突然、僕にその質問を投げかけてきた。
素直に首を横に振ると、先生は再び口を開く。
「学んだことが身についているかどうか確認するのに、一番手っ取り早い方法はね、『教える』ことだよ」
「教える……」
「教えるっていうと、一見、教わる側にしかメリットがないようにも思えるけど……教える側も、自分の知識を整理して言葉にすることで、理解を深めることができる」
「なるほど……」
「門田くんも、誰かに『教える』勉強、試してみたらどうかな?」
……と、佐藤先生はアドバイスしてくれたけれど。
友達がいない陰キャの僕には、ハードルが高すぎる!!
特進コースのみんなは、基本的に他人と馴れ合わないし……僕のように特進コースの最下層にいる人間となれば、なおさら、仲良くするメリットもない。
一般コースにも、特別仲の良い友達はいないし。
スポーツ科に関しては、勉強には力を入れていないし。
やっぱり、無理ゲーじゃん……。
「はぁ」
ため息を吐いて、模試の結果を見つめる。
一喜一憂するなと言われても、でっかい「E」の文字は、それなりに心にダメージを与えてくる。
でも、どの教科でも、校内順位が最下位じゃないんだよな……。
教科によっては僕より点数が低くても、東大を目指している人が周りにいるんだ。
まだまだ、僕も周りも、これからだよな。
「ふー……」
「あーっ!!!!!」
「っ!?」
急に背後で叫び声がして、僕は一瞬、命の危機を感じた。
振り返らずに全力疾走して逃げるべきかどうか、一秒迷っている間に、声の主が僕の肩を叩いてきた。
「門田、啓杜くん?」
「ひっ!」
声の主は、持っていた模試の結果を覗き込んできた。
名前がバレてしまったということは、もう、オワリ?
何か、犯罪に巻き込まれ――
「俺、スポーツ科二年の赤城龍太朗!よろしく!」
「は!?」
恐怖でぎゅっと瞑っていた目をカッと開いた。
視線を横に向ければ、同じ制服を着た茶髪のチャラそうな男が、ニコニコ笑って僕を見ているではないか。
「だ、誰ですか……」
「え?だーかーら、スポーツ科二年の赤城龍太朗だって」
「はあ……えっと、どこかで話したことありましたっけ」
少なくとも僕の記憶には、彼の名前も顔も存在しないのだけど。
「ん?ないよ!はじめまして!」
「えっ」
頭が真っ白になる。
この男は、面識のない人間に、いきなりこんなテンションで話しかけたっていうのか……?
僕は著しく社交性が低いから、社交的な人のことは尊敬するけれど、ここまでグイグイ寄ってくるのは非常識なのでは……!?
「それより!」
それより!?
「啓ちゃんって、特進コースだよね?」
啓ちゃん!?
「んで、お願いがあるんだけど」
「はぁ……?」
やはり非常識だ。
距離の詰め方がどう考えても異常だ。
スポーツ科って、度が過ぎた陽キャしかいないのか?(※そんなことはありません)
「啓ちゃん!」
「っ、な、なに」
僕の手を取り、大きな瞳でまっすぐと僕を捉える赤城龍太朗が、次の瞬間放った言葉は―――。
「俺を東大に連れていってくれ!」
「は……?」
にわかには信じがたい内容。
日本語のリスニングで不安になるのは初めてだ。
今、こいつは、なんて……?
「俺、どうしても東大に行かなきゃなんだ!だから頼む!俺と一緒に勉強してくれないか!」
こいつが?東大?
スポーツ科の、いかにも勉強なんて興味なさそうなチャラ男が?
……正気か?
「あのー……これドッキリ?からかってる?」
「えぇ!?本気だよ本気!ガチのマジで本気!」
ぐっと顔を近づけて、その迫力で本気度を伝えようとしてくる赤城龍太朗。
普段、パーソナルスペースに人間が入ってこない僕は、思わず動揺する。
「っ、な、なんで東大行きたいの?スポーツ科なら、もっと他に活躍できる場所が、」
「俺、アーティストになりたいんだ」
「は?」
アーティスト?急にどうした。
論理的な会話ができないのか?
それとも、僕が何か間違ってる?
「バンドでデビューすんのが夢でさ。でも、父親が認めてくれなくて。音楽で食っていくなんて、東大入るより難しいぞって。そんな覚悟も積み重ねもないだろって」
「え……それで、東大?」
「ああ。東大に合格できたら、アーティスト活動を認めるって条件なんだ。音楽を続けるためなら、俺はなんだってやる」
ぶっ飛んでやがる。
こいつは頭がおかしい。
父親に言われたからって、それを真に受ける馬鹿がいるかよ。
「……諦めろ」
「えっ!?」
「あんたの父親は、暗に『絶対認めない』って言ってるんだよ。本気にするだけ無駄だ」
「そんな……」
スタスタと歩くスピードを速めても、赤城はめげずに着いてくる。
「待って待って!まだ話は終わってない!」
「終わったよ。諦めろって言ったじゃん」
「なんで俺の実力も見ずに、そんなことが言えるんだよっ!」
「っ……」
なるほど、そうか、その可能性があったか。
勉強苦手〜と見せかけて、実は結構頭いいってパターン。
さすがのこいつも、可能性がゼロに等しいことを他人に頼むほどはイかれてないのかもしれない。
「……分かったよ。じゃあ、明日の放課後、図書室に集合ってことで」
「マジ!?やったー!約束な!」
「はいはい……あ、これまでの模試の結果とか持ってきてね」
「今持ってるよ!」
「え?」
赤城はガサゴソとバッグを漁り、一部の冊子を取り出した。
僕はそれを見て、目を疑った。
「……それ……」
「先週、東大レベル模試?ってやつ受けてみたんだ〜。もしよかったら見てくれよ」
赤城の手から冊子を奪い、穴が開くほど凝視する。
こいつ……校内順位、全科目最下位じゃねーか!!
やっぱりそうですよねって感じだけど!!
なんだよ……ちょっとは期待したのに。
それに、僕より下の順位の一人がこいつって、当たり前すぎてガッカリなんだけど……特進でも僕よりできないやつがいるのかと思ってたのに……。
「……やっぱりなしだ。諦めた方がいい」
冊子を赤城の胸に押し付けて歩き出そうとすると、手首をガシッと掴まれる。
「明日の放課後、約束したろ。これだけで判断すんなよ〜」
「うっ……」
一度やると言ったことをやらないのは、僕の性格的にモヤモヤするのは確かだ。
それに、おそらく勢いだけで、ノー対策で挑んだであろう東大本番レベル模試だけでは、こいつの学力を正確に把握できないというのも、その通りで……。
「分かったよ。明日、約束通り放課後ね」
「っ!サンキュー啓ちゃん!」
「とりあえず今日は帰るね……バイバイ」
「また明日な!」
まあいい。
明日、いくつか問題を解かせてみて、あとは模試の結果も適当に見て、改めて無理だと断ればいいんだ。
一度真剣に向き合えば、あいつも素直に引いてくれるだろう。
◇
◇
◇
翌日の放課後、図書室。
僕は、想像以上に酷い現実を目の当たりにしていた。
「赤城……お前、よくこれで東大とか口にしたな……」
「ひぃ!そんな怖い顔しないで!」
「ターゲット1900の前半に載ってる単語すら抜けてるってどういうこと?数学も、チャートの典型的な解法で解ける問題を落としてるのは何?古典単語は一つも覚えてないの?」
「そ、それは〜、今までは勉強ほぼしてなかったし……」
現代文、古文漢文、英語、数学……一通り標準レベルの参考書の問題を解かせてみたが、結果はボロボロだった。
模試の方も散々だ。
基礎が固まっていないから、易しい模試ですらポロポロ点を落としている。
「……ちなみに、僕と一緒に勉強するっていうなら、物理と化学をやってもらうけど」
「ああ!確か授業でやったぜ!」
「それは基礎だろ。てか、理科何類に行きたいの?まさか三とか言わないよな」
「えーっと、そうそう、一とか二とか三とかあるんだよな!一が一番難しいんだっけ?調べ始めたばっかでさ……」
あはは……と笑う赤城を見て、堪忍袋の緒が切れる。
ふざけやがって、僕の時間を返せよ。
「……自分が行きたい場所のことを知らないなんて論外だ。試しに解かせた問題も、簡単な模試も、君の実力は東大とかけ離れすぎてる。僕は君にこれ以上の時間を割きたくない。さよなら」
「ちょっと、啓ちゃん!俺、これから色々調べるし、死ぬ気で頑張って、絶対成績伸びるから、」
「たとえ伸びるとしても!!」
「っ!」
「僕が……っ、僕が、幼稚園の頃から必死で得てきたものを、どうしてたった一年半で、君に全部あげなきゃならないんだよ……!」
「そ、れは……」
誰かにこんな風に声を荒げるのはいつぶりだろう。
もしかして、人生で初めてだろうか。
僕の人生は勉強で、勉強は僕の人生だ。
勉強を教えるということは、自分の全てを捧げるようなものなのだ。
「……そもそも、どうして僕なんだ。僕は、特進の底辺だ。僕だって東大なんか入れるか分からないのに」
「入れるよ」
「っ、は、なに?」
「啓ちゃんは、東大に入れるよ」
赤城はなぜか自信に満ちた瞳で、明瞭な声でそう言った。
ほんの少しの揺らぎもない真剣な表情で言い切るから、思いがけず心臓がドキリと音を立てる。
「っ……根拠のないことを簡単に言うなよ。とにかく、僕は君の面倒なんか見れない。これで本当に終わりだ。じゃあな」
荷物をまとめて足早に図書室を去ろうとすると、曇りのない声を背中にぶつけられた。
「俺!明日もここで待ってるから!ここで、勉強してるから!」
赤城の言葉には振り返らず、僕は図書室をあとにした。
根っから明るくて、楽観的で、容姿やスポーツの才能にも恵まれて、そんな奴が、音楽をやるために勉強して東大?
そんなの……そんなことあってたまるかよ。
神は平等なんて嘘っぱちだと、なぜ僕が自らの時間を割いてまで証明しなきゃならないんだ。
『啓ちゃんは、東大に入れるよ』
何の根拠も保証もない無責任な発言に、ほんの少しでも「嬉しい」と感じてしまった自分にも腹が立つ。
落ち込んでいる時期だからって、こんなに簡単に認められたような気分になって、情けないにもほどがある。
「ほんと調子狂う……」
赤城龍太朗。
奴は、僕の粛々とした人生に、稲妻の如く現れた。
◇
◇
◇
「じゃ、再来週の共通テスト模試に向けて、共テ対策もやっておくようにー」
担任の平坦な声を聞きつつ、わらわらと特進の生徒たちが教室を出てゆく。
僕もその波に乗って、目立たないように廊下を歩く。
共通テスト模試か……一日で全教科やるから、めちゃくちゃ疲れるんだよなぁ。
東工……科学大だったら、そんなに気にしなくていいけれど……僕が目指すのは東大だから。
共テ模試も、一回一回大切に受けなければ。
……そういや、あいつも受けるんだよな。
共テは特有の難しさがあるから、形式や時間配分について作戦を……っていやいやいや!
僕は関係ない!断じて関係ない!
僕があいつと関わることはない……。
『俺!明日もここで待ってるから!ここで、勉強してるから!』
……。
……ちょっと、覗くだけだからな。
どうせ、口だけだろ。
人間、言うだけならなんだって言えるんだ。
その場の勢いでデカいこと言うなんて、誰にでもでき……る……。
「……いるじゃん……」
図書室の扉の隙間からチラリと中を覗くと、昨日と同じ席に座り、真剣な顔で机に向かっている赤城がいた。
何を解いているのだろう。
数学か?
僕が昨日、基本的な解法を身につけろと言ったから。
横には英単語帳と古文単語帳もある。
いつまでに、どのくらい、どうやって覚えようとしているのだろうか。
きちんと計画を立てることはできているのか……
あ、眉間に皺が寄った。
赤ペンで何か書いている。
どの段階で躓いたのだろう。
何が分からなかったのか、しっかり理解できたのだろうか。
分からないポイントが分かるのは、決して当たり前のことではないから……
って何ぼーっと眺めているんだよ僕は!!
一刻も早く、予備校に行って勉強しなきゃいけないのに。
こんなところで突っ立っている暇はないんだ。
少しは感心したけれど、三日坊主という言葉もあるくらいだからな。
所詮は期間限定の気持ちの盛り上がりだ。
明日か明後日、粘っても一週間が相場だろ。
それ以上経てば、きっと何もかも嫌になって投げ出すさ。
きっと―――。
◇
◇
◇
あれから、一週間。
毎日、毎日、毎日。
僕は帰り際に図書室を覗いて、赤城の勉強する姿を見つけた。
明日には諦めるだろう、土日挟んだら気が変わるだろう。
そんな予想はことごとく外れ、今日も一生懸命に机に向かう赤城を眺めている。
「っ……」
本当は、分かっているんだ。
幼い頃から頑張った奴が偉いわけじゃない。
何歳から始めたっていい、ただ、二次試験を受けるその日に間に合えば、それでいいんだ。
受験とはずっと前からそういう世界で……そんな平等な世界で戦うと決めたのは、他でもない自分。
フライングという概念が存在しないなら、その逆だって存在しないのに、僕は赤城に強く当たった。
「……はぁ……」
こういうときにモヤモヤを放っておけない性格は、父と母のどちらに似たのだろう。
もっとテキトーな感じでゆるーく生きて、嫌なことはいつのまにか忘れちゃう♪……みたいな人間だったらなぁ。
「赤城」
「っ!啓ちゃん!」
ぱあっと顔を輝かせる赤城の向かいに座る。
なんとなく目を合わせるのは恥ずかしくて、机上の参考書などを眺めて尋ねる。
「何やってたの」
「え?ああ!そうそう、聞いてよ!ターゲット最後まで覚えたんだよ!」
「は!?」
思わず顔を上げて、がっつり赤城を見つめてしまったではないか。
「あ、最後って言っても、もちろん、ちょこちょこ抜けてるとこはあんだけどね」
「……数学は」
「とりあえず、これまでの模試とかで間違えたとこ中心に、基本問題から全部やってる。今まで、結構感覚でやってたんだな〜って思ったわ」
あ、古典はまだ単語帳半分だけ!と、赤城は続けた。
「どう、かな。俺なりにめっちゃ頑張ってるつもり、だけど……やっぱり啓ちゃんからしたら、そんなに、」
「赤城」
「っ!は、はい!」
ああ、僕は、どうして―――。
「僕と一緒に東大目指そう」
「……え……」
「今からだっていい。間に合えばそれでいいんだ……だが、あくまで僕は君を利用するというスタンスだ。自分が東大に受かるためにな。君の専属教師になるつもりはない。だから君も、僕を使え」
「……!」
「……どうだ、悪くないだろ」
安全な方を、波風の立たない方を選んできた人生だった。
地味に、静かに、勉強だけして生きてきた。
そんな僕が、一人の人間に懸けるんだ。
人生で一度か二度しかない、最大級の挑戦でな。
「……啓ちゃん」
「っ……」
俯いていた赤城が、パッと顔を上げて、
僕の隣まで来て、にこーっと笑って、
「ありがとう!大好き!」
「わっ!?」
勢いよく抱きついてきた。
「ちょ、っ、なに、」
「龍ちゃんって呼んでよ。親友の証!」
「い、いつから親友に、」
「ほら、『龍ちゃん』って!あ、俺の名前、龍太朗ね」
「それは知ってる……っ、けど……」
やっぱり、赤城龍太朗は距離感がおかしい。
そんな男の無茶な提案を受け入れた僕も、多分おかしい。
でも、こっから先の受験勉強なんて、おかしくならなきゃやってられないかもしれない。
「……やるからには本気でやるぞ、龍」
「おう!啓ちゃん!」
「よし、まずは離れろ、そして早速、」
「待って!なんか〜こうさ!気持ちアゲようぜ!部活みたいな感じで!」
「部活ぅ?」
首を傾げる僕に対し、龍は何かを閃いたような顔をして、机上のノートとマジックペンを手に取った。
「っしゃ!キタキタ!これだわ!」
「ん?」
バーンと突き出されたノートに書いてあったのは……
「赤門……同好会……?」
「そ!東大を目指す俺らにピッタリっしょ?」
「部活じゃなくて同好会じゃん……あと、そのまんまだな」
渋い反応をする僕に、龍はチッチッチッ、と人差し指をメトロノームのように揺らした。
「最後まで聞いてよ。この中にはさぁ……俺らの名前が入ってんの」
「名前……あ……!」
「ふふ、気づいた?赤城の『赤』と門田の『門』。合わせて赤門!なんか運命的!」
「運命……」
ああ、もう。
なぜ僕は、龍の発言に、あっさりと心を揺さぶられてしまうのか。
論理的根拠など皆無なのに……本当に、何かの運命みたいだって、思っちゃうじゃないか。
「ってことで。赤門同好会、ここに発足!」
「っ……」
「ほら!もっとテンション上げよう!」
「あーもう。ここ図書室だから……今は僕たちしかいないけど……」
「ならセーフだな!改めて、啓ちゃん、よろしくね!」
差し出された大きな手にそっと触れたら、すぐさまぎゅっと握られた。ちょっと痛い。
「……よろしく、龍」
こうして僕は、高二の九月、
赤城龍太朗という奇想天外な男と、
東大を目指す同好会・『赤門同好会』を発足したのだった。
ここから、青春と呼ぶには泥臭い、僕と龍のかけがえのない受験生活が始まる―――。
予備校の佐藤先生が、宥めるような声でそう言った。
両手で握りしめるのは、先週受けた高二東大本番レベル模試の結果。
その紙面に印刷されたのは、前回と変わらず「E」の文字。
「……夏休み、頑張ったんですけどね」
「ああ、知ってるよ。門田くんはよく頑張ってる。緊張感を持つのは大事なことだけど、今の判定に一喜一憂する必要はない」
「はい……でも、僕、不安なんです。このまま地道に努力をしていたら、東大との距離が縮まる……そんな確信が持てなくて」
「うむ……未来に絶対も百パーもないからねぇ」
「それは……そうですが……」
そんなことはもちろん分かっている。
この世には、「絶対に成績が伸びる勉強法」なんてものは存在しない。
ただ、着実に目標に近づいているときというのは、その実感が少なからずあるのだ。
今の僕にはそれがない。
勉強時間とこなした問題集のページが増えるだけで、「進んだ」という感覚がないのである。
「門田くんは……誰かに勉強を教えたことがあるかい?」
「え?」
佐藤先生は突然、僕にその質問を投げかけてきた。
素直に首を横に振ると、先生は再び口を開く。
「学んだことが身についているかどうか確認するのに、一番手っ取り早い方法はね、『教える』ことだよ」
「教える……」
「教えるっていうと、一見、教わる側にしかメリットがないようにも思えるけど……教える側も、自分の知識を整理して言葉にすることで、理解を深めることができる」
「なるほど……」
「門田くんも、誰かに『教える』勉強、試してみたらどうかな?」
……と、佐藤先生はアドバイスしてくれたけれど。
友達がいない陰キャの僕には、ハードルが高すぎる!!
特進コースのみんなは、基本的に他人と馴れ合わないし……僕のように特進コースの最下層にいる人間となれば、なおさら、仲良くするメリットもない。
一般コースにも、特別仲の良い友達はいないし。
スポーツ科に関しては、勉強には力を入れていないし。
やっぱり、無理ゲーじゃん……。
「はぁ」
ため息を吐いて、模試の結果を見つめる。
一喜一憂するなと言われても、でっかい「E」の文字は、それなりに心にダメージを与えてくる。
でも、どの教科でも、校内順位が最下位じゃないんだよな……。
教科によっては僕より点数が低くても、東大を目指している人が周りにいるんだ。
まだまだ、僕も周りも、これからだよな。
「ふー……」
「あーっ!!!!!」
「っ!?」
急に背後で叫び声がして、僕は一瞬、命の危機を感じた。
振り返らずに全力疾走して逃げるべきかどうか、一秒迷っている間に、声の主が僕の肩を叩いてきた。
「門田、啓杜くん?」
「ひっ!」
声の主は、持っていた模試の結果を覗き込んできた。
名前がバレてしまったということは、もう、オワリ?
何か、犯罪に巻き込まれ――
「俺、スポーツ科二年の赤城龍太朗!よろしく!」
「は!?」
恐怖でぎゅっと瞑っていた目をカッと開いた。
視線を横に向ければ、同じ制服を着た茶髪のチャラそうな男が、ニコニコ笑って僕を見ているではないか。
「だ、誰ですか……」
「え?だーかーら、スポーツ科二年の赤城龍太朗だって」
「はあ……えっと、どこかで話したことありましたっけ」
少なくとも僕の記憶には、彼の名前も顔も存在しないのだけど。
「ん?ないよ!はじめまして!」
「えっ」
頭が真っ白になる。
この男は、面識のない人間に、いきなりこんなテンションで話しかけたっていうのか……?
僕は著しく社交性が低いから、社交的な人のことは尊敬するけれど、ここまでグイグイ寄ってくるのは非常識なのでは……!?
「それより!」
それより!?
「啓ちゃんって、特進コースだよね?」
啓ちゃん!?
「んで、お願いがあるんだけど」
「はぁ……?」
やはり非常識だ。
距離の詰め方がどう考えても異常だ。
スポーツ科って、度が過ぎた陽キャしかいないのか?(※そんなことはありません)
「啓ちゃん!」
「っ、な、なに」
僕の手を取り、大きな瞳でまっすぐと僕を捉える赤城龍太朗が、次の瞬間放った言葉は―――。
「俺を東大に連れていってくれ!」
「は……?」
にわかには信じがたい内容。
日本語のリスニングで不安になるのは初めてだ。
今、こいつは、なんて……?
「俺、どうしても東大に行かなきゃなんだ!だから頼む!俺と一緒に勉強してくれないか!」
こいつが?東大?
スポーツ科の、いかにも勉強なんて興味なさそうなチャラ男が?
……正気か?
「あのー……これドッキリ?からかってる?」
「えぇ!?本気だよ本気!ガチのマジで本気!」
ぐっと顔を近づけて、その迫力で本気度を伝えようとしてくる赤城龍太朗。
普段、パーソナルスペースに人間が入ってこない僕は、思わず動揺する。
「っ、な、なんで東大行きたいの?スポーツ科なら、もっと他に活躍できる場所が、」
「俺、アーティストになりたいんだ」
「は?」
アーティスト?急にどうした。
論理的な会話ができないのか?
それとも、僕が何か間違ってる?
「バンドでデビューすんのが夢でさ。でも、父親が認めてくれなくて。音楽で食っていくなんて、東大入るより難しいぞって。そんな覚悟も積み重ねもないだろって」
「え……それで、東大?」
「ああ。東大に合格できたら、アーティスト活動を認めるって条件なんだ。音楽を続けるためなら、俺はなんだってやる」
ぶっ飛んでやがる。
こいつは頭がおかしい。
父親に言われたからって、それを真に受ける馬鹿がいるかよ。
「……諦めろ」
「えっ!?」
「あんたの父親は、暗に『絶対認めない』って言ってるんだよ。本気にするだけ無駄だ」
「そんな……」
スタスタと歩くスピードを速めても、赤城はめげずに着いてくる。
「待って待って!まだ話は終わってない!」
「終わったよ。諦めろって言ったじゃん」
「なんで俺の実力も見ずに、そんなことが言えるんだよっ!」
「っ……」
なるほど、そうか、その可能性があったか。
勉強苦手〜と見せかけて、実は結構頭いいってパターン。
さすがのこいつも、可能性がゼロに等しいことを他人に頼むほどはイかれてないのかもしれない。
「……分かったよ。じゃあ、明日の放課後、図書室に集合ってことで」
「マジ!?やったー!約束な!」
「はいはい……あ、これまでの模試の結果とか持ってきてね」
「今持ってるよ!」
「え?」
赤城はガサゴソとバッグを漁り、一部の冊子を取り出した。
僕はそれを見て、目を疑った。
「……それ……」
「先週、東大レベル模試?ってやつ受けてみたんだ〜。もしよかったら見てくれよ」
赤城の手から冊子を奪い、穴が開くほど凝視する。
こいつ……校内順位、全科目最下位じゃねーか!!
やっぱりそうですよねって感じだけど!!
なんだよ……ちょっとは期待したのに。
それに、僕より下の順位の一人がこいつって、当たり前すぎてガッカリなんだけど……特進でも僕よりできないやつがいるのかと思ってたのに……。
「……やっぱりなしだ。諦めた方がいい」
冊子を赤城の胸に押し付けて歩き出そうとすると、手首をガシッと掴まれる。
「明日の放課後、約束したろ。これだけで判断すんなよ〜」
「うっ……」
一度やると言ったことをやらないのは、僕の性格的にモヤモヤするのは確かだ。
それに、おそらく勢いだけで、ノー対策で挑んだであろう東大本番レベル模試だけでは、こいつの学力を正確に把握できないというのも、その通りで……。
「分かったよ。明日、約束通り放課後ね」
「っ!サンキュー啓ちゃん!」
「とりあえず今日は帰るね……バイバイ」
「また明日な!」
まあいい。
明日、いくつか問題を解かせてみて、あとは模試の結果も適当に見て、改めて無理だと断ればいいんだ。
一度真剣に向き合えば、あいつも素直に引いてくれるだろう。
◇
◇
◇
翌日の放課後、図書室。
僕は、想像以上に酷い現実を目の当たりにしていた。
「赤城……お前、よくこれで東大とか口にしたな……」
「ひぃ!そんな怖い顔しないで!」
「ターゲット1900の前半に載ってる単語すら抜けてるってどういうこと?数学も、チャートの典型的な解法で解ける問題を落としてるのは何?古典単語は一つも覚えてないの?」
「そ、それは〜、今までは勉強ほぼしてなかったし……」
現代文、古文漢文、英語、数学……一通り標準レベルの参考書の問題を解かせてみたが、結果はボロボロだった。
模試の方も散々だ。
基礎が固まっていないから、易しい模試ですらポロポロ点を落としている。
「……ちなみに、僕と一緒に勉強するっていうなら、物理と化学をやってもらうけど」
「ああ!確か授業でやったぜ!」
「それは基礎だろ。てか、理科何類に行きたいの?まさか三とか言わないよな」
「えーっと、そうそう、一とか二とか三とかあるんだよな!一が一番難しいんだっけ?調べ始めたばっかでさ……」
あはは……と笑う赤城を見て、堪忍袋の緒が切れる。
ふざけやがって、僕の時間を返せよ。
「……自分が行きたい場所のことを知らないなんて論外だ。試しに解かせた問題も、簡単な模試も、君の実力は東大とかけ離れすぎてる。僕は君にこれ以上の時間を割きたくない。さよなら」
「ちょっと、啓ちゃん!俺、これから色々調べるし、死ぬ気で頑張って、絶対成績伸びるから、」
「たとえ伸びるとしても!!」
「っ!」
「僕が……っ、僕が、幼稚園の頃から必死で得てきたものを、どうしてたった一年半で、君に全部あげなきゃならないんだよ……!」
「そ、れは……」
誰かにこんな風に声を荒げるのはいつぶりだろう。
もしかして、人生で初めてだろうか。
僕の人生は勉強で、勉強は僕の人生だ。
勉強を教えるということは、自分の全てを捧げるようなものなのだ。
「……そもそも、どうして僕なんだ。僕は、特進の底辺だ。僕だって東大なんか入れるか分からないのに」
「入れるよ」
「っ、は、なに?」
「啓ちゃんは、東大に入れるよ」
赤城はなぜか自信に満ちた瞳で、明瞭な声でそう言った。
ほんの少しの揺らぎもない真剣な表情で言い切るから、思いがけず心臓がドキリと音を立てる。
「っ……根拠のないことを簡単に言うなよ。とにかく、僕は君の面倒なんか見れない。これで本当に終わりだ。じゃあな」
荷物をまとめて足早に図書室を去ろうとすると、曇りのない声を背中にぶつけられた。
「俺!明日もここで待ってるから!ここで、勉強してるから!」
赤城の言葉には振り返らず、僕は図書室をあとにした。
根っから明るくて、楽観的で、容姿やスポーツの才能にも恵まれて、そんな奴が、音楽をやるために勉強して東大?
そんなの……そんなことあってたまるかよ。
神は平等なんて嘘っぱちだと、なぜ僕が自らの時間を割いてまで証明しなきゃならないんだ。
『啓ちゃんは、東大に入れるよ』
何の根拠も保証もない無責任な発言に、ほんの少しでも「嬉しい」と感じてしまった自分にも腹が立つ。
落ち込んでいる時期だからって、こんなに簡単に認められたような気分になって、情けないにもほどがある。
「ほんと調子狂う……」
赤城龍太朗。
奴は、僕の粛々とした人生に、稲妻の如く現れた。
◇
◇
◇
「じゃ、再来週の共通テスト模試に向けて、共テ対策もやっておくようにー」
担任の平坦な声を聞きつつ、わらわらと特進の生徒たちが教室を出てゆく。
僕もその波に乗って、目立たないように廊下を歩く。
共通テスト模試か……一日で全教科やるから、めちゃくちゃ疲れるんだよなぁ。
東工……科学大だったら、そんなに気にしなくていいけれど……僕が目指すのは東大だから。
共テ模試も、一回一回大切に受けなければ。
……そういや、あいつも受けるんだよな。
共テは特有の難しさがあるから、形式や時間配分について作戦を……っていやいやいや!
僕は関係ない!断じて関係ない!
僕があいつと関わることはない……。
『俺!明日もここで待ってるから!ここで、勉強してるから!』
……。
……ちょっと、覗くだけだからな。
どうせ、口だけだろ。
人間、言うだけならなんだって言えるんだ。
その場の勢いでデカいこと言うなんて、誰にでもでき……る……。
「……いるじゃん……」
図書室の扉の隙間からチラリと中を覗くと、昨日と同じ席に座り、真剣な顔で机に向かっている赤城がいた。
何を解いているのだろう。
数学か?
僕が昨日、基本的な解法を身につけろと言ったから。
横には英単語帳と古文単語帳もある。
いつまでに、どのくらい、どうやって覚えようとしているのだろうか。
きちんと計画を立てることはできているのか……
あ、眉間に皺が寄った。
赤ペンで何か書いている。
どの段階で躓いたのだろう。
何が分からなかったのか、しっかり理解できたのだろうか。
分からないポイントが分かるのは、決して当たり前のことではないから……
って何ぼーっと眺めているんだよ僕は!!
一刻も早く、予備校に行って勉強しなきゃいけないのに。
こんなところで突っ立っている暇はないんだ。
少しは感心したけれど、三日坊主という言葉もあるくらいだからな。
所詮は期間限定の気持ちの盛り上がりだ。
明日か明後日、粘っても一週間が相場だろ。
それ以上経てば、きっと何もかも嫌になって投げ出すさ。
きっと―――。
◇
◇
◇
あれから、一週間。
毎日、毎日、毎日。
僕は帰り際に図書室を覗いて、赤城の勉強する姿を見つけた。
明日には諦めるだろう、土日挟んだら気が変わるだろう。
そんな予想はことごとく外れ、今日も一生懸命に机に向かう赤城を眺めている。
「っ……」
本当は、分かっているんだ。
幼い頃から頑張った奴が偉いわけじゃない。
何歳から始めたっていい、ただ、二次試験を受けるその日に間に合えば、それでいいんだ。
受験とはずっと前からそういう世界で……そんな平等な世界で戦うと決めたのは、他でもない自分。
フライングという概念が存在しないなら、その逆だって存在しないのに、僕は赤城に強く当たった。
「……はぁ……」
こういうときにモヤモヤを放っておけない性格は、父と母のどちらに似たのだろう。
もっとテキトーな感じでゆるーく生きて、嫌なことはいつのまにか忘れちゃう♪……みたいな人間だったらなぁ。
「赤城」
「っ!啓ちゃん!」
ぱあっと顔を輝かせる赤城の向かいに座る。
なんとなく目を合わせるのは恥ずかしくて、机上の参考書などを眺めて尋ねる。
「何やってたの」
「え?ああ!そうそう、聞いてよ!ターゲット最後まで覚えたんだよ!」
「は!?」
思わず顔を上げて、がっつり赤城を見つめてしまったではないか。
「あ、最後って言っても、もちろん、ちょこちょこ抜けてるとこはあんだけどね」
「……数学は」
「とりあえず、これまでの模試とかで間違えたとこ中心に、基本問題から全部やってる。今まで、結構感覚でやってたんだな〜って思ったわ」
あ、古典はまだ単語帳半分だけ!と、赤城は続けた。
「どう、かな。俺なりにめっちゃ頑張ってるつもり、だけど……やっぱり啓ちゃんからしたら、そんなに、」
「赤城」
「っ!は、はい!」
ああ、僕は、どうして―――。
「僕と一緒に東大目指そう」
「……え……」
「今からだっていい。間に合えばそれでいいんだ……だが、あくまで僕は君を利用するというスタンスだ。自分が東大に受かるためにな。君の専属教師になるつもりはない。だから君も、僕を使え」
「……!」
「……どうだ、悪くないだろ」
安全な方を、波風の立たない方を選んできた人生だった。
地味に、静かに、勉強だけして生きてきた。
そんな僕が、一人の人間に懸けるんだ。
人生で一度か二度しかない、最大級の挑戦でな。
「……啓ちゃん」
「っ……」
俯いていた赤城が、パッと顔を上げて、
僕の隣まで来て、にこーっと笑って、
「ありがとう!大好き!」
「わっ!?」
勢いよく抱きついてきた。
「ちょ、っ、なに、」
「龍ちゃんって呼んでよ。親友の証!」
「い、いつから親友に、」
「ほら、『龍ちゃん』って!あ、俺の名前、龍太朗ね」
「それは知ってる……っ、けど……」
やっぱり、赤城龍太朗は距離感がおかしい。
そんな男の無茶な提案を受け入れた僕も、多分おかしい。
でも、こっから先の受験勉強なんて、おかしくならなきゃやってられないかもしれない。
「……やるからには本気でやるぞ、龍」
「おう!啓ちゃん!」
「よし、まずは離れろ、そして早速、」
「待って!なんか〜こうさ!気持ちアゲようぜ!部活みたいな感じで!」
「部活ぅ?」
首を傾げる僕に対し、龍は何かを閃いたような顔をして、机上のノートとマジックペンを手に取った。
「っしゃ!キタキタ!これだわ!」
「ん?」
バーンと突き出されたノートに書いてあったのは……
「赤門……同好会……?」
「そ!東大を目指す俺らにピッタリっしょ?」
「部活じゃなくて同好会じゃん……あと、そのまんまだな」
渋い反応をする僕に、龍はチッチッチッ、と人差し指をメトロノームのように揺らした。
「最後まで聞いてよ。この中にはさぁ……俺らの名前が入ってんの」
「名前……あ……!」
「ふふ、気づいた?赤城の『赤』と門田の『門』。合わせて赤門!なんか運命的!」
「運命……」
ああ、もう。
なぜ僕は、龍の発言に、あっさりと心を揺さぶられてしまうのか。
論理的根拠など皆無なのに……本当に、何かの運命みたいだって、思っちゃうじゃないか。
「ってことで。赤門同好会、ここに発足!」
「っ……」
「ほら!もっとテンション上げよう!」
「あーもう。ここ図書室だから……今は僕たちしかいないけど……」
「ならセーフだな!改めて、啓ちゃん、よろしくね!」
差し出された大きな手にそっと触れたら、すぐさまぎゅっと握られた。ちょっと痛い。
「……よろしく、龍」
こうして僕は、高二の九月、
赤城龍太朗という奇想天外な男と、
東大を目指す同好会・『赤門同好会』を発足したのだった。
ここから、青春と呼ぶには泥臭い、僕と龍のかけがえのない受験生活が始まる―――。