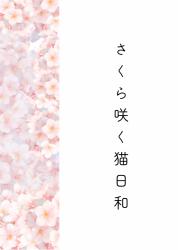日が沈み、あたりが薄暗くなってきた頃。
俺は心臓をドキドキさせながら、花火大会の会場へ向かう電車に乗っていた。
一つ、また一つと最寄駅に近づくたび、車内はどんどん混んでいく。
次の駅で、やっと賢人くんが乗ってきてくれると思うと、緊張するのに安心するという、甘酸っぱい矛盾のような感覚が生じた。
「わ、っ、」
停車して、扉が開き、一気に乗車する人々に押し流されそうになる俺の手首を、ガシッと掴んでくれる温かい手。
「先輩」
「賢人くん!ありがと……」
「こっち来て」
「っ……」
ぐい、と体を引き寄せられる。
片手で吊り革を掴む彼に、もう片方の手で抱きしめられた状態で身動きが取れなくなる。
恥ずかしくて賢人くんの首元に顔を埋めたら、くらりとするような甘い香水の匂いに鼻腔をくすぐられた。
密着した俺たちを乗せ、電車はしばらく走り、漸く目的地に到着する。
勢いよく降りていく人々の波に乗って、俺たちも改札を出た。
「先輩、混んでたけど大丈夫でしたか?気分悪くなったり、何かされたりしてませんか?」
「うん、大丈夫だよ。賢人くんのおかげで」
大丈夫、だけど、ずっとくっついていた身体が離れてしまって、その体温が既に恋しい。
「……先輩、あの、嫌じゃなければ、なんですけど」
「?」
賢人くんは頬を赤らめながら、そっと俺の手を握る。
手のひらから、指先から、熱い温度がドクドクと伝わってきて、この心を満たす。
「は、はぐれちゃ、困るので」
「……嫌じゃないよ。嬉しい」
「……!良かった……」
ああ、俺、賢人くんのこと、本当に―――。
「じゃ、花火始まる前に、屋台行きましょう」
「うん!」
笑顔で大きく頷いて、繋がれた手をぎゅっと握り返した。
◇
◇
◇
花火の打ち上げ開始時刻が少しずつ近づく。
賢人くんの両腕には、二人で挑戦した射的の景品や、美味しそうな屋台の食べ物が入った袋が提げられている。
「先輩、ちょっと持っててもらえますか?シート敷きますね」
「うん、ありがとう、何から何まで」
賢人くんは荷物を俺に預けて、コンパクトに収納されていたレジャーシートを取り出し、サッと広げて場所を確保してくれる。
「よし、食べましょうか」
「うん!」
シートの上に座れば、自然と身体の距離は近くなって、胸がキュンと高鳴る。
こんなに蒸し暑いのに近づきたいと思うのは、隣にいるのが賢人くんだからだよ。
「あ、先輩、ここ蚊に刺されてる」
「え」
賢人くんの指がふくらはぎに触れて、ビクッと肩が跳ねる。
「あ、ここも」
「ひぁ、っ、!」
今度は、すう、と太ももの赤くなったところを撫でられて、ゾクっとくすぐったくて、自分でも聞いたことのない声が出て、咄嗟に口を覆ったけれど……もう遅い。
「い、今のは、聞かなかったことに……」
湯気が出そうなほどあっつい顔を手で扇ぎながら、チラリと賢人くんを見ると、その瞳はなぜかぼーっと熱っぽく揺れている。
「……先輩、可愛い……」
「か!?け、賢人くん!?」
「っ!あれ、俺、待って、今、声に……うわ〜……」
大きな大きなため息を吐きながら、俺より恥ずかしそうにする賢人くんを見て、思わずぷはっと吹き出してしまう。
「先輩、笑いすぎ……」
「ふふ、ごめんごめん」
「もー、ほら、たこ焼き食べますよ」
割り箸を押し付けてくる賢人くんに、ほっぺたがタコみたいに赤いよって教えてあげようかと思ったけど、もし自分の方が真っ赤だったら恥ずかしいのでやめておいた。
たこ焼きを食べ終わった後はフライドポテトをシェアして、その後は賢人くんが「ゴミを捨てるついでに買ってきました」と言って、ふわふわのかき氷をくれた。
いちごとブルーハワイを半分こすれば、口の中はひんやりするのに、胸はどんどん熱くなって。
賢人くんと過ごす時間が長くなるほど、「心がちゃんと動いてる」って実感する。
同時に、この二年間、知らず知らずのうちに、自分がどれだけ自分自身の心を抑えつけていたのか、よく分かった。
「そろそろ始まりますね」
みんなそれぞれ、大切な人と一緒に夜空を見上げてる。
これから咲く光の花への期待に満ちた瞳で。
「……」
横を見れば、俺にとってのかけがえのない人もまた、学校では見せない表情で夜空を眺めている。
君との距離。
たった十数センチ、されど十数センチ。
……ブレーキを放り出して動き出した恋心は、思った以上に欲張りで大胆みたいだ。
「っ、先輩……」
「あ、暑い、かな」
勇気を出してぴったりとくっついたけれど、目を合わせるほどの余裕はない。
「……暑くても、こっちがいいです」
「……!」
賢人くんがそう答え終わると同時、大きな花火が夜空に咲いた。
きらきら光って、静かに夜に溶けていく。
「……綺麗……」
少し前まで、俺はもう一生、花火を見ることなんて、ましてやそれを綺麗だと思うことなんて、できないんじゃないかと思っていた。
それなのに、今、内側から無意識に言葉が零れ落ちるほどに、この景色を綺麗だと感じている。
今、この時間を、楽しいと、感じることができているんだ。
「……賢人くん」
「っ、先輩、なんで泣いて、」
「花火大会、誘ってくれてありがとう」
「……!」
「俺をここに連れてきてくれて、ありがとう」
賢人くんの肩に頭を寄せたら、彼は俺の涙を優しく拭ってから、同じように頭を寄せてくれた。
次々と夜空を彩る花火を見つめながら、この時間がずっと続けばいいのに、なんて、ラブソングの歌詞みたいなことをぼんやりと考えていた。
◇
◇
◇
「……先輩、今日、楽しかったですか?」
「うん……楽しかった、本当に」
「ふふ、良かった」
なんとなく繋いだ手を離せないまま帰路につく。
人混みに紛れたら、絡めた指もきっとバレない。
「……賢人くんも、楽しかった?」
「そんなの……楽しかったに決まってるじゃないですか」
「ふふ、そっかぁ」
帰りたくないなぁ。
もう少しだけ、一緒にいたいな。
そんな思いから、歩くスピードが随分とゆっくりになってしまったせいだろうか。
見つけてしまった。
「……あ……」
「?先輩、どうかしました?」
たくさんの人が行き交う中で、その人の輪郭だけが、くっきりと浮かび上がる。
ドクン、ドクン、と心臓が大きく収縮と拡張を繰り返す。
「……先輩?あの人、お知り合いですか?」
「……俺が、好きだった子」
「っ……!」
今、このとき、この場所で、あの子に再会すること。
この出来事がどんな意味を持つのか、いや、この出来事にどんな意味を持たせたいのか、神様に問われているような気がした。
「……賢人くん、あの、」
「聞きたく、ないです」
「っ!」
「っ、行かせたく、ないです……でも、でも……」
苦しそうに唇を噛む彼を見て、俺の決心は揺るがないものになる。
そっと手を伸ばして、頬に触れた。
君が、何度も俺にしてくれたように。
「賢人くん……俺はね、これからも賢人くんの隣にいるために、行くんだよ」
「……!」
「賢人くんと対等に向き合える自分になって、必ず、戻ってくるから……あの子と話す時間を、もらえないかな」
「先輩……」
「……わがまま言って、ごめんね……」
「っ……分かりました。先輩のわがままなら、聞きます」
賢人くんは少し潤んだ瞳で俺をまっすぐに見つめ、繋がれていた手を解いた。
そしてその手を、背中に優しく添えてくれる。
「先輩なら、大丈夫。ちゃんと、話したいこと話せるように、応援してます」
「賢人くん……本当にありがとう」
「俺……待ってますから」
「うん……!」
賢人くんに背中を押してもらったら、なんだってできそうな気分になれる。
最初で最後、あの夏に向き合うチャンスから、目を逸らさずに走れる。
「あの、すみません!」
二年前に比べてかなり身長が伸びたその子に、勇気を出して声をぶつけた。
彼の隣には、恋人らしき男の子もいる。
「はい……?」
「っ!やっぱり、篠崎、夏くん、だよね?」
目をまん丸にして驚くその子は、確かに、俺の初恋の相手―――篠崎夏くんだった。
「……!瑞稀先輩……?どう、して、」
「高校の友達が、こっちの方に住んでて……夏くん、今は、このあたりの高校に通ってるの?」
「……なんで、今更」
今更、という言葉に胸を締めつけられる。
そうだよね、もっともっと早く、君に謝るべきだった。
「っ、俺、ずっと、夏くんと……ちゃんと、話したかったんだ。だけど、全然、高校もどこに行ったか、分からなかったから……」
「……もう、あのときのことは、気にしてないので」
「今更……確かに、そうだと思う。だけど、あの日のこと、本当はずっと謝りたかった……もう、二度と会えないかもしれないと思ってたんだ……どうか、一度でいいから、俺に話す時間を、もらえないかな?」
必死で訴える俺の言葉に、夏くんは動揺していた。
隣の男の子は、そんな夏くんに寄り添うように、肩に手を添えて何か声をかけているようだった。
恋人らしき人からの言葉を受けた夏くんは、覚悟を決めたような瞳で口を開く。
「……分かりました。話しましょう」
「……!ありがとう……」
人通りが多く時間も遅いから、と夏くんは改めて会う機会を作ろうと提案してくれた。
こうして謝る機会をもらえたこと、そして、今の夏くんには、隣にいてくれる人がいるということ、この二つの事実に胸がいっぱいになった。
賢人くんは駅で待っていてくれた。
夏くんと後日話すことになったと伝えると、一瞬顔を曇らせながらも、いつもの優しい瞳で「分かりました」と微笑んでくれた。
この微笑みを、何の躊躇いもなく受け取れるような俺に、きっとなるから……どうか、待ってて、賢人くん。
俺は心臓をドキドキさせながら、花火大会の会場へ向かう電車に乗っていた。
一つ、また一つと最寄駅に近づくたび、車内はどんどん混んでいく。
次の駅で、やっと賢人くんが乗ってきてくれると思うと、緊張するのに安心するという、甘酸っぱい矛盾のような感覚が生じた。
「わ、っ、」
停車して、扉が開き、一気に乗車する人々に押し流されそうになる俺の手首を、ガシッと掴んでくれる温かい手。
「先輩」
「賢人くん!ありがと……」
「こっち来て」
「っ……」
ぐい、と体を引き寄せられる。
片手で吊り革を掴む彼に、もう片方の手で抱きしめられた状態で身動きが取れなくなる。
恥ずかしくて賢人くんの首元に顔を埋めたら、くらりとするような甘い香水の匂いに鼻腔をくすぐられた。
密着した俺たちを乗せ、電車はしばらく走り、漸く目的地に到着する。
勢いよく降りていく人々の波に乗って、俺たちも改札を出た。
「先輩、混んでたけど大丈夫でしたか?気分悪くなったり、何かされたりしてませんか?」
「うん、大丈夫だよ。賢人くんのおかげで」
大丈夫、だけど、ずっとくっついていた身体が離れてしまって、その体温が既に恋しい。
「……先輩、あの、嫌じゃなければ、なんですけど」
「?」
賢人くんは頬を赤らめながら、そっと俺の手を握る。
手のひらから、指先から、熱い温度がドクドクと伝わってきて、この心を満たす。
「は、はぐれちゃ、困るので」
「……嫌じゃないよ。嬉しい」
「……!良かった……」
ああ、俺、賢人くんのこと、本当に―――。
「じゃ、花火始まる前に、屋台行きましょう」
「うん!」
笑顔で大きく頷いて、繋がれた手をぎゅっと握り返した。
◇
◇
◇
花火の打ち上げ開始時刻が少しずつ近づく。
賢人くんの両腕には、二人で挑戦した射的の景品や、美味しそうな屋台の食べ物が入った袋が提げられている。
「先輩、ちょっと持っててもらえますか?シート敷きますね」
「うん、ありがとう、何から何まで」
賢人くんは荷物を俺に預けて、コンパクトに収納されていたレジャーシートを取り出し、サッと広げて場所を確保してくれる。
「よし、食べましょうか」
「うん!」
シートの上に座れば、自然と身体の距離は近くなって、胸がキュンと高鳴る。
こんなに蒸し暑いのに近づきたいと思うのは、隣にいるのが賢人くんだからだよ。
「あ、先輩、ここ蚊に刺されてる」
「え」
賢人くんの指がふくらはぎに触れて、ビクッと肩が跳ねる。
「あ、ここも」
「ひぁ、っ、!」
今度は、すう、と太ももの赤くなったところを撫でられて、ゾクっとくすぐったくて、自分でも聞いたことのない声が出て、咄嗟に口を覆ったけれど……もう遅い。
「い、今のは、聞かなかったことに……」
湯気が出そうなほどあっつい顔を手で扇ぎながら、チラリと賢人くんを見ると、その瞳はなぜかぼーっと熱っぽく揺れている。
「……先輩、可愛い……」
「か!?け、賢人くん!?」
「っ!あれ、俺、待って、今、声に……うわ〜……」
大きな大きなため息を吐きながら、俺より恥ずかしそうにする賢人くんを見て、思わずぷはっと吹き出してしまう。
「先輩、笑いすぎ……」
「ふふ、ごめんごめん」
「もー、ほら、たこ焼き食べますよ」
割り箸を押し付けてくる賢人くんに、ほっぺたがタコみたいに赤いよって教えてあげようかと思ったけど、もし自分の方が真っ赤だったら恥ずかしいのでやめておいた。
たこ焼きを食べ終わった後はフライドポテトをシェアして、その後は賢人くんが「ゴミを捨てるついでに買ってきました」と言って、ふわふわのかき氷をくれた。
いちごとブルーハワイを半分こすれば、口の中はひんやりするのに、胸はどんどん熱くなって。
賢人くんと過ごす時間が長くなるほど、「心がちゃんと動いてる」って実感する。
同時に、この二年間、知らず知らずのうちに、自分がどれだけ自分自身の心を抑えつけていたのか、よく分かった。
「そろそろ始まりますね」
みんなそれぞれ、大切な人と一緒に夜空を見上げてる。
これから咲く光の花への期待に満ちた瞳で。
「……」
横を見れば、俺にとってのかけがえのない人もまた、学校では見せない表情で夜空を眺めている。
君との距離。
たった十数センチ、されど十数センチ。
……ブレーキを放り出して動き出した恋心は、思った以上に欲張りで大胆みたいだ。
「っ、先輩……」
「あ、暑い、かな」
勇気を出してぴったりとくっついたけれど、目を合わせるほどの余裕はない。
「……暑くても、こっちがいいです」
「……!」
賢人くんがそう答え終わると同時、大きな花火が夜空に咲いた。
きらきら光って、静かに夜に溶けていく。
「……綺麗……」
少し前まで、俺はもう一生、花火を見ることなんて、ましてやそれを綺麗だと思うことなんて、できないんじゃないかと思っていた。
それなのに、今、内側から無意識に言葉が零れ落ちるほどに、この景色を綺麗だと感じている。
今、この時間を、楽しいと、感じることができているんだ。
「……賢人くん」
「っ、先輩、なんで泣いて、」
「花火大会、誘ってくれてありがとう」
「……!」
「俺をここに連れてきてくれて、ありがとう」
賢人くんの肩に頭を寄せたら、彼は俺の涙を優しく拭ってから、同じように頭を寄せてくれた。
次々と夜空を彩る花火を見つめながら、この時間がずっと続けばいいのに、なんて、ラブソングの歌詞みたいなことをぼんやりと考えていた。
◇
◇
◇
「……先輩、今日、楽しかったですか?」
「うん……楽しかった、本当に」
「ふふ、良かった」
なんとなく繋いだ手を離せないまま帰路につく。
人混みに紛れたら、絡めた指もきっとバレない。
「……賢人くんも、楽しかった?」
「そんなの……楽しかったに決まってるじゃないですか」
「ふふ、そっかぁ」
帰りたくないなぁ。
もう少しだけ、一緒にいたいな。
そんな思いから、歩くスピードが随分とゆっくりになってしまったせいだろうか。
見つけてしまった。
「……あ……」
「?先輩、どうかしました?」
たくさんの人が行き交う中で、その人の輪郭だけが、くっきりと浮かび上がる。
ドクン、ドクン、と心臓が大きく収縮と拡張を繰り返す。
「……先輩?あの人、お知り合いですか?」
「……俺が、好きだった子」
「っ……!」
今、このとき、この場所で、あの子に再会すること。
この出来事がどんな意味を持つのか、いや、この出来事にどんな意味を持たせたいのか、神様に問われているような気がした。
「……賢人くん、あの、」
「聞きたく、ないです」
「っ!」
「っ、行かせたく、ないです……でも、でも……」
苦しそうに唇を噛む彼を見て、俺の決心は揺るがないものになる。
そっと手を伸ばして、頬に触れた。
君が、何度も俺にしてくれたように。
「賢人くん……俺はね、これからも賢人くんの隣にいるために、行くんだよ」
「……!」
「賢人くんと対等に向き合える自分になって、必ず、戻ってくるから……あの子と話す時間を、もらえないかな」
「先輩……」
「……わがまま言って、ごめんね……」
「っ……分かりました。先輩のわがままなら、聞きます」
賢人くんは少し潤んだ瞳で俺をまっすぐに見つめ、繋がれていた手を解いた。
そしてその手を、背中に優しく添えてくれる。
「先輩なら、大丈夫。ちゃんと、話したいこと話せるように、応援してます」
「賢人くん……本当にありがとう」
「俺……待ってますから」
「うん……!」
賢人くんに背中を押してもらったら、なんだってできそうな気分になれる。
最初で最後、あの夏に向き合うチャンスから、目を逸らさずに走れる。
「あの、すみません!」
二年前に比べてかなり身長が伸びたその子に、勇気を出して声をぶつけた。
彼の隣には、恋人らしき男の子もいる。
「はい……?」
「っ!やっぱり、篠崎、夏くん、だよね?」
目をまん丸にして驚くその子は、確かに、俺の初恋の相手―――篠崎夏くんだった。
「……!瑞稀先輩……?どう、して、」
「高校の友達が、こっちの方に住んでて……夏くん、今は、このあたりの高校に通ってるの?」
「……なんで、今更」
今更、という言葉に胸を締めつけられる。
そうだよね、もっともっと早く、君に謝るべきだった。
「っ、俺、ずっと、夏くんと……ちゃんと、話したかったんだ。だけど、全然、高校もどこに行ったか、分からなかったから……」
「……もう、あのときのことは、気にしてないので」
「今更……確かに、そうだと思う。だけど、あの日のこと、本当はずっと謝りたかった……もう、二度と会えないかもしれないと思ってたんだ……どうか、一度でいいから、俺に話す時間を、もらえないかな?」
必死で訴える俺の言葉に、夏くんは動揺していた。
隣の男の子は、そんな夏くんに寄り添うように、肩に手を添えて何か声をかけているようだった。
恋人らしき人からの言葉を受けた夏くんは、覚悟を決めたような瞳で口を開く。
「……分かりました。話しましょう」
「……!ありがとう……」
人通りが多く時間も遅いから、と夏くんは改めて会う機会を作ろうと提案してくれた。
こうして謝る機会をもらえたこと、そして、今の夏くんには、隣にいてくれる人がいるということ、この二つの事実に胸がいっぱいになった。
賢人くんは駅で待っていてくれた。
夏くんと後日話すことになったと伝えると、一瞬顔を曇らせながらも、いつもの優しい瞳で「分かりました」と微笑んでくれた。
この微笑みを、何の躊躇いもなく受け取れるような俺に、きっとなるから……どうか、待ってて、賢人くん。