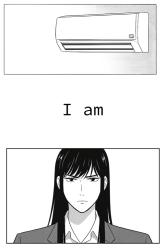「こんなモビルスーツがあってもいいじゃない」
ユキがそう言ったとき、コウヤは思わず笑ってしまった。彼女のノートには、見たことのない機体のスケッチが描かれていたからだ。
肩にセーラー服の襟のような翼端板を背負い、脚部はまるで長い靴下のようなスラスターを実装している。武器は、先端にマイク型の鉄球を装着した箒。
「…それ、戦えるの?」
「戦わなくてもいいじゃない。これを振り回して踊ればいいのよ」
「踊る…!」
ユキの言葉は、どこかピロティの4人組に似ていた。制服を着崩さず、ふざけたように舞っていた彼女たち。あれは、戦いではなくて、表現だった。
コウヤは、自分のノートを開いた。そこには、ずっと頭の中にあった“もしも”の機体が描かれていた。「ガンダム・カオス・フレーム」変形機構を持たず、ただ“美しい”ことだけを追求した設計。武器は持たない。代わりに、光の軌跡を残す。
アキラとケンスケもそれを覗き込みながら、思わぬ提案を誰ともなく発した。
「…これ、文化祭で出そうか」
それにユキが頷いて言った。「勝手同好会ってことで。部室もないし、顧問もいないけど、いいじゃない」
否定をしない。肯定してきた。
翌日の日曜日、4人は、近くの青果店から譲り受けた段ボールをコウヤの部屋に持ち込んで、学校の工作室から借りてきたカッターや大きな鋏で裁断し始めた。
そしてフリップ芸の練習も始めた。「ボクたちの考えたガンダム」それは、誰にも求められていないけれど、誰よりも自分たちが欲しかったもの。あっという間に日曜日は費やされた。
文化祭が次第に近づくとともに、すっかり秋の訪れが加速してきた。
放課後のピロティ。フェンスの向こうで、また風が吹いた。踊って、肩車をし、髪を振り回し、舌を出して歌っている4人組が、コウヤは作業をしているときに感じた。
コウヤは、その彼女たちの動きが、どこか自分たちのやりたいことの“設計図”に似ていることに気づいていた。それはまだ誰も知らない“可能性”のかたちなのかもしれない。
「自由って、設計できるんだな」
そう呟いたコウヤの声は、ピロティの柱に吸い込まれていった。
ユキがそう言ったとき、コウヤは思わず笑ってしまった。彼女のノートには、見たことのない機体のスケッチが描かれていたからだ。
肩にセーラー服の襟のような翼端板を背負い、脚部はまるで長い靴下のようなスラスターを実装している。武器は、先端にマイク型の鉄球を装着した箒。
「…それ、戦えるの?」
「戦わなくてもいいじゃない。これを振り回して踊ればいいのよ」
「踊る…!」
ユキの言葉は、どこかピロティの4人組に似ていた。制服を着崩さず、ふざけたように舞っていた彼女たち。あれは、戦いではなくて、表現だった。
コウヤは、自分のノートを開いた。そこには、ずっと頭の中にあった“もしも”の機体が描かれていた。「ガンダム・カオス・フレーム」変形機構を持たず、ただ“美しい”ことだけを追求した設計。武器は持たない。代わりに、光の軌跡を残す。
アキラとケンスケもそれを覗き込みながら、思わぬ提案を誰ともなく発した。
「…これ、文化祭で出そうか」
それにユキが頷いて言った。「勝手同好会ってことで。部室もないし、顧問もいないけど、いいじゃない」
否定をしない。肯定してきた。
翌日の日曜日、4人は、近くの青果店から譲り受けた段ボールをコウヤの部屋に持ち込んで、学校の工作室から借りてきたカッターや大きな鋏で裁断し始めた。
そしてフリップ芸の練習も始めた。「ボクたちの考えたガンダム」それは、誰にも求められていないけれど、誰よりも自分たちが欲しかったもの。あっという間に日曜日は費やされた。
文化祭が次第に近づくとともに、すっかり秋の訪れが加速してきた。
放課後のピロティ。フェンスの向こうで、また風が吹いた。踊って、肩車をし、髪を振り回し、舌を出して歌っている4人組が、コウヤは作業をしているときに感じた。
コウヤは、その彼女たちの動きが、どこか自分たちのやりたいことの“設計図”に似ていることに気づいていた。それはまだ誰も知らない“可能性”のかたちなのかもしれない。
「自由って、設計できるんだな」
そう呟いたコウヤの声は、ピロティの柱に吸い込まれていった。