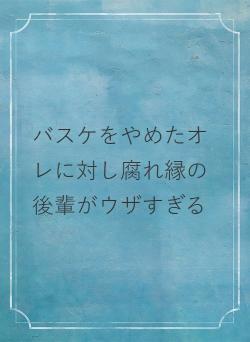「もう、将棋指しに行きたくないな」
そう、勇人君が言ったのは、それから三か月後のことだった。
勇人君は、げんなりとした顔をしている。
最近手加減して指すことが多くなっていると感じていた。
そう、もう限界に近い状態であることは気づいていた。
ついにその爆弾が爆発しちゃったのだろうか。
この三か月間。私は勇人君を楽しませるために、様々な事をしていた。
だけど、そんなものはただの気晴らし。
それどころか、将棋以外の楽しみを得てしまったからこそ、将棋を指したくないのだろう。
「葵さえいれば僕は後はどうでもいいよ」
続いてそう言う勇人君。
幸せすぎたのか、五月病の学生っぽいことを言っている。
後は私をゲームなどにしたら『ゲームさえあれば後はどうでもいいよ』うん、完璧だ。
冗談は置いといて……
彼はもう、本当に将棋を指しに行きたくない様子だ。
実際最近将棋の研究などをしている様子はほとんど見ていない。だが、それでも彼は全勝レベルで勝ち進んでいた。
過去最高勝率は八割くらいだったと記憶しているが、それをはるかに超える九割五分もの勝率を保っている。
結婚後の半年、手加減を常にしていたが、負けたのは一回だけ。あの熱の日だ。
でもその時も勇人君はうなっていた。
負けても悔しくないって言ってたあの言葉は忘れられない。
もはや。将棋の勝敗なんてどうでもいいのかなと。
勇人君は、対局日の前日。
ベッドに入るのを拒み続けた。
理由はおそらくただ一つ。
明日を、明日の対局日を迎えたくないからだと、思う。
こんなことほとんど初めてだ。
勇人君は、行きたくなくても、責任感で向かって行ってるのに。
「僕は本当に将棋をしてていいのか? 僕に負けた人が泣いたことがあった。普通将棋は終局後涙を流さないものだ。だが、そんな中、対局相手の矢司馬八段は泣いていた。初タイトルを目指してたのにって、なんでこんな悪魔みたいなやつに、戦ったら即負けのやつなんているんだって。だけど、僕は勝ってしまった。僕はただ、将棋界の富を独占しているだけのくずだ」
夜だから気持ちが落ちてるのだろうか。
あの出来事は覚えている。
三週間前に、勇人君が勝った相手、その相手は矢司馬八段だった。
彼は、不遇の時代を生き、ついにタイトル戦に手が届いた。
そんな中、タイトルを持ってるのは当然勇人君。
勇人君と対局をすることになったが、当然ながら、勇人君が圧巻の将棋で、四連勝をした。
事件はその矢先だった。
矢司馬八段が泣き出したのだ。
普通プロ棋士がなくケースは多くはない。
感情を矢面に出すことは失礼だと思われるからだ。
むろんそれは逆のケースも同様で、勝った時にもガッツポーズなんてほとんどしないらしい。
その時に、暴言を吐いた。
普通、暴言を吐けばネット上で炎上するのが世の常だ。
しかし――
それが炎上ではなく絶賛されることになった。
もう、勇人君はスターじゃなく、エネミー、敵だという事になったのだ。
あの時の悔しさは半端じゃなかった。
勇人君だって、一人の人間であることを皆忘れてしまっている。
傷つかない人間なんて、この世に誰一人としていないというのに。
「そんなことはないよ。ただルールにのっとって将棋をしているだけじゃん」
勇人君は決して悪くない。
「いや、ネットで言われているんだ。僕は将棋なんて指したらいけないって、カンニングしてるんじゃないかって、将棋界を面白くなくしてるんだって。数年前はそう言われていてもまだ耐えれた。でも、僕でも今そう思ってしまっているんだ。僕は……」
やはり、あの件がとどめとなったのかと、私は軽くため息をつく。
どちらにしろ、今の勇人君を慰めうる言葉を私は持っていない。
「とりあえず、私が許すよ。明日は休んで」
そう言うと勇人君はただ頷いた。
基本、私が休んだらと言っても、絶対に指しに行くと言い出す癖に。
今日はよほど行きたくなかったのだろうか。
そして、私は彼を行かせられないと判断して、彼を病欠という事で将棋連盟に連絡をした。
不戦敗にはなってしまうが、勇人君にはあまり関係が無いだろう。
勇人君にはもはや、将棋の勝ち負けなんてどうでもいいと思うから。
ただ、それもまたいけなかったのかもしれない。
「勇人君?」
部屋の片隅で、暗い中、彼は座っている。
呟いている言葉を聞くと、「僕はだめだ」とか、「僕は生きてたらいけないんだ」とか、そう言った自分を責める言葉ばかりだ。
私がいくら言っても無駄だ。
仮病で休んでしまったこと。それが、勇人君の自己肯定感を大幅に下げる結果となってしまったのかもしれない。
もはや私が何と言おうか、勇人君が立ち直ることはなかった。
ここは、私が何とかしなければならない。
そう、勇人君が言ったのは、それから三か月後のことだった。
勇人君は、げんなりとした顔をしている。
最近手加減して指すことが多くなっていると感じていた。
そう、もう限界に近い状態であることは気づいていた。
ついにその爆弾が爆発しちゃったのだろうか。
この三か月間。私は勇人君を楽しませるために、様々な事をしていた。
だけど、そんなものはただの気晴らし。
それどころか、将棋以外の楽しみを得てしまったからこそ、将棋を指したくないのだろう。
「葵さえいれば僕は後はどうでもいいよ」
続いてそう言う勇人君。
幸せすぎたのか、五月病の学生っぽいことを言っている。
後は私をゲームなどにしたら『ゲームさえあれば後はどうでもいいよ』うん、完璧だ。
冗談は置いといて……
彼はもう、本当に将棋を指しに行きたくない様子だ。
実際最近将棋の研究などをしている様子はほとんど見ていない。だが、それでも彼は全勝レベルで勝ち進んでいた。
過去最高勝率は八割くらいだったと記憶しているが、それをはるかに超える九割五分もの勝率を保っている。
結婚後の半年、手加減を常にしていたが、負けたのは一回だけ。あの熱の日だ。
でもその時も勇人君はうなっていた。
負けても悔しくないって言ってたあの言葉は忘れられない。
もはや。将棋の勝敗なんてどうでもいいのかなと。
勇人君は、対局日の前日。
ベッドに入るのを拒み続けた。
理由はおそらくただ一つ。
明日を、明日の対局日を迎えたくないからだと、思う。
こんなことほとんど初めてだ。
勇人君は、行きたくなくても、責任感で向かって行ってるのに。
「僕は本当に将棋をしてていいのか? 僕に負けた人が泣いたことがあった。普通将棋は終局後涙を流さないものだ。だが、そんな中、対局相手の矢司馬八段は泣いていた。初タイトルを目指してたのにって、なんでこんな悪魔みたいなやつに、戦ったら即負けのやつなんているんだって。だけど、僕は勝ってしまった。僕はただ、将棋界の富を独占しているだけのくずだ」
夜だから気持ちが落ちてるのだろうか。
あの出来事は覚えている。
三週間前に、勇人君が勝った相手、その相手は矢司馬八段だった。
彼は、不遇の時代を生き、ついにタイトル戦に手が届いた。
そんな中、タイトルを持ってるのは当然勇人君。
勇人君と対局をすることになったが、当然ながら、勇人君が圧巻の将棋で、四連勝をした。
事件はその矢先だった。
矢司馬八段が泣き出したのだ。
普通プロ棋士がなくケースは多くはない。
感情を矢面に出すことは失礼だと思われるからだ。
むろんそれは逆のケースも同様で、勝った時にもガッツポーズなんてほとんどしないらしい。
その時に、暴言を吐いた。
普通、暴言を吐けばネット上で炎上するのが世の常だ。
しかし――
それが炎上ではなく絶賛されることになった。
もう、勇人君はスターじゃなく、エネミー、敵だという事になったのだ。
あの時の悔しさは半端じゃなかった。
勇人君だって、一人の人間であることを皆忘れてしまっている。
傷つかない人間なんて、この世に誰一人としていないというのに。
「そんなことはないよ。ただルールにのっとって将棋をしているだけじゃん」
勇人君は決して悪くない。
「いや、ネットで言われているんだ。僕は将棋なんて指したらいけないって、カンニングしてるんじゃないかって、将棋界を面白くなくしてるんだって。数年前はそう言われていてもまだ耐えれた。でも、僕でも今そう思ってしまっているんだ。僕は……」
やはり、あの件がとどめとなったのかと、私は軽くため息をつく。
どちらにしろ、今の勇人君を慰めうる言葉を私は持っていない。
「とりあえず、私が許すよ。明日は休んで」
そう言うと勇人君はただ頷いた。
基本、私が休んだらと言っても、絶対に指しに行くと言い出す癖に。
今日はよほど行きたくなかったのだろうか。
そして、私は彼を行かせられないと判断して、彼を病欠という事で将棋連盟に連絡をした。
不戦敗にはなってしまうが、勇人君にはあまり関係が無いだろう。
勇人君にはもはや、将棋の勝ち負けなんてどうでもいいと思うから。
ただ、それもまたいけなかったのかもしれない。
「勇人君?」
部屋の片隅で、暗い中、彼は座っている。
呟いている言葉を聞くと、「僕はだめだ」とか、「僕は生きてたらいけないんだ」とか、そう言った自分を責める言葉ばかりだ。
私がいくら言っても無駄だ。
仮病で休んでしまったこと。それが、勇人君の自己肯定感を大幅に下げる結果となってしまったのかもしれない。
もはや私が何と言おうか、勇人君が立ち直ることはなかった。
ここは、私が何とかしなければならない。