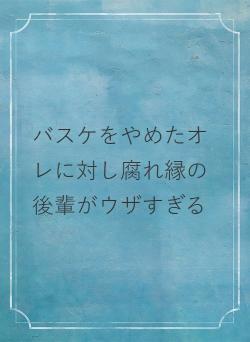「ねえ、勇人君」
日本に戻ってきてから一週間ほど経ったある日、勇人君に話しかけた。
「私達って結婚したのよね」
「うん。僕たちは結婚したな」
「でも、なんだか普通じゃない?」
結婚してからも、いつもの日常は変わらずにいる。
それは良い事なのかもしれないけれど、でも、結婚という人生の一番大事ともいえるイベントを得てもなお、何も変わらなかった。
唯一変わったと言えば、私の苗字が渡部に変わったという、まさにその一点だけだ。
「正直、もっと変わると思ってたのよね」
「なら、何かする?」
「何か……」
カップルなら出来なくて、夫婦なら出来る事。
正直何も分からない。
「私達って今思ったら結婚前から結婚しているような生活をしているんだね」
今思ったら。私って結構大胆だったのかもしれない。
事情があったとはいえ、出会ってから数日の異性である渡部君の家に、お邪魔してたし。
そして、すぐさま同棲もしてたし。
「なら、葵。ちょっと今日出かけないか?」
「え?」
急にどうしたんだろ。
「ちょっと連れていきたい場所があるんだ」
そして、その日の夜。
私は今豪華なレストランにいる。
「えっと、勇人君、これは?」
今の状況が理解できていない。
なぜ、あの会話の流れでこうなったんだろう。
「思えば二人であまり一緒にご飯を食べに行くことなんて無かったけど、結婚した今なら出来るだろ」
「そ、そうだけど」
確かに私と勇人君はそこまで二人で外食したことは無い。
理由はそこまでで複雑なものはない。ただ、行ってなかっただけだ。
ちなみに勇人君は渡部勇人だとばれないようにか、変装をしている。
「それに、結婚した今、葵に思う存分お金を使える」
「私、別にお金のために結婚したんじゃないんだけど」
「それは知ってる。でも、葵のためにお金を使いたいだけだ」
「お金を……」
別にいいのにと言いたいところだが、勇人君はお金をたくさん持っている。
確か、所持金が5億円を超えていたような気がする。
だからこんなもの、はした金なのだろう。
なんだろう、この言い方。これから私にジャンジャンと、お金を貢いでいく気なのだろうか。
「勇人君ありがとう」
別に私は、勇人君にお金を使ってもらうほどたいそうな人間ではない。
ただ、勇人君の優しさは、甘んじて受け取っていきたい。
勇人君に取って私は大事な人なんだから。
そしてメニュー表を開く。
すると、全部の値段が高いな、と思った。
パスタは二千円を超えていて、サブメニューのはずのアヒージョなども1200円もしている。
こんなの、勇人君と結婚しなかったら永遠に食べられてなかっただろうな、と思う。
別にお金のために結婚したわけでは無いけれど、それでも嬉しい。
「僕は何を食べようか」
そう言ってメニュー表を開く勇人君。
「僕は、何が食べたいんだろう」
勇人君は悩み始めた。
「もしかして勇人君って、自由だと逆に何を食べるか迷うタイプ?」
「そうかもしれない。葵が来てからは葵の作ってくれたご飯ばかり食べていたし、葵が来る前は、適当に目についたものを食べてた。正直、食欲なんて無かったし」
「そう……」
そう言えば、勇人君は私が来る前、ご飯をあまり食べていなかった。
勇人君に関する問題は正直解決したわけでは無かったのだ。
最近明るいけれど。
「じゃあ、私が決めてあげる」
そう、私は言った。
勇人君が好きなのは、きっと。
「これかな」
勇人君が一番美味しいと言っていたご飯。それは、しょうゆで味付けをしたものだ。
という事は、カルボナーラよりも、バター炒めパスタとか、キノコパスタの方が好きだろう。
そうなれば、決めるのも簡単になってくる。
「そうか、なら僕はこの二択で選べばいいのか」
「そうね」
「なら、気楽になって来た」
勇人君は、基本食事にはこだわらない。
だけど、このレストランの食事はきっと私の作った料理よりも美味しいだろう。
食材も豪華で、一流の料理人たちが作ってるのだ。
「楽しみだね」
勇人君が頼み終わった後、私はそう言った。
勇人君はその言葉にただ頷いて見せた。
「そう言えばこの前の話なんだけど」
私は言葉を紡ぐ。
「結婚式場で言った話」
「そう言えば言ってたな」
「私は今は正直気にしてないけど、なんか気を使わないで欲しい」
「気を使ってなんか……」
いや、勇人君は優しい。少しだけ、気にしてるのをたびたび感じる。
私も勇人君の尊敬する人を殺してしまった。
その事を気にしてた私が言える事ではないけれど。
「私は過去の事は過去の事って割り切ってるから、本当に今まで通りでいいよ」
「そうか、でも辛いのは分かってるから甘えてもいいよ」
「まあ、甘えるけど。……というか、今までも結構甘えてない?」
私は結構勇人君に支えられてきている。
勇人君がいるから支えられていると言っても過言ではない。
「それを言ったら僕も支えられてるよ」
「ふふ、だったらお互い様だね」
ワインが届いた。
私はそれを少しづつ飲む。
普段はあまりお酒を飲まないが、レストランだと、雰囲気も良く、ワインが美味しい。
「そう言えば、勇人君ってお酒飲まないんだね」
私は酒をくびっと飲みながら言った。
「そりゃ僕は酒があまり得意じゃないから。もしかして、こういう場ってお酒を飲むのがマナーだったりするのか?」
「ううん、そんなことない。ただ、私が思っただけ」
「そっか」
そして、私たちが楽しく話していると、ようやく食事が運ばれてきた。
見るからにおいしそうだ。
まず具材が沢山入っており見た目がインスタ映えしそうな感じがする。しかも、香ってくる匂いも中々鼻を刺激して、食欲を増してくる。
「勇人君」
「ああ、中々美味しそうだ」
「きっと、私の作るパスタよりも美味しいよ」
「それ、肯定しにくいからやめてくれないか」
確かに、勇人君が私のパスタよりも美味しいと言ったら少しもやもやするけれど。
でも、ここのパスタが、私の作るパスタよりも美味しくないなんてことは無いだろう。
何しろ、高級レストランなのだから。
「いただきます」
「いただきます」
私たちは互いにそう言って、フォークでパスタを巻いて口に入れる。
人か見すると一気にパスタの風味が口の中に広がる。
「美味しい」
「美味しいな」
私たちの言葉が重なる。
実際に美味しい。
私たちは顔を見合わせる。
すると、なんだか不思議な気持ちになって、思わず笑ってしまった。
「なんだよ」
「私よ勇人の声が重なった」
「確かに」
そうぼそっと呟くと、勇人君は一気に顔を赤くした。
私はこういう場合、どのような反応をしたらいいんだろう。
笑ったらいいのか、私も顔を赤くしたらいいのだろうか。
困った私はとりあえずパスタを食べる。
その後暫く私たちは無言でパスタを食べる。
そして、半分程度食べた後、私はとあるものを勇人君に見せた。
「これ、見に行こうかなって思ってるの」
私が見せた画面。それは、棋戦の後悔対局のチケットだった。
将棋の対局場には普通、対局者と、記録係。それくらいしかいない。
だけど、例外的に、プロが戦う姿を間近で見られる棋戦があるのだ。
それがこの棋戦だ。
私は勇人君が対局している姿を、ネット配信くらいでしか見たことが無い。
だからこそ、間近で見たいなと前々から思っていたのだ。
そしてそんな棋戦が存在すると聞いて、私は嬉しく思っているのだ。
是非とも見てみたいとは思うけど、勇人君の許可がないとね。
夫である。
そう、考えると少し照れてきた。
そうだ。私はもう奥さんであり、勇人君は私の夫だ。
結婚したから、何かが変わったことは無い。とは思っていたけども、私たちは互いが番になったことで称号を手に入れられているじゃないの。
「葵、どうしたんだ?」
「は、勇人君、何でもないよ」
「なんか、話の続きが一向にないから」
確かに。私よく考えれば一分くらい硬直してたかも。
「ごめんね。それで、これで勇人君の対局を見ようと思ってるの」
「その対局は、皆川四段との」
「そう、見に行きたいと思ってるの。夫の対局を」
最後の方は呂律が回らなくなったかもしれない。なんだか言ってる途中で恥ずかしくなってしまったのだ。
夫のというあたりで。
「ごめんね。急に恥ずかしくなっちゃって。勇人君の夫である私が」
「大丈夫だよ。葵は僕の奥さんなんだから自信持ってくれよ」
「それが恥ずかしいの。それで、見に行ってもいい?」
「もちろん。僕の許可なく見に行っていいよ。でも、少し恥ずかしいけど」
「恥ずかしいんだ」
「そりゃ。僕だって恥ずかしいよ」
そう言う勇人君の顔はワインのアルコールのせいか、恥ずかしいからなのか、軽く紅潮していた。
「ふふ、じゃあ見に行くね」
「うん、ぜひ」
そして私たちは軽く笑った。
日本に戻ってきてから一週間ほど経ったある日、勇人君に話しかけた。
「私達って結婚したのよね」
「うん。僕たちは結婚したな」
「でも、なんだか普通じゃない?」
結婚してからも、いつもの日常は変わらずにいる。
それは良い事なのかもしれないけれど、でも、結婚という人生の一番大事ともいえるイベントを得てもなお、何も変わらなかった。
唯一変わったと言えば、私の苗字が渡部に変わったという、まさにその一点だけだ。
「正直、もっと変わると思ってたのよね」
「なら、何かする?」
「何か……」
カップルなら出来なくて、夫婦なら出来る事。
正直何も分からない。
「私達って今思ったら結婚前から結婚しているような生活をしているんだね」
今思ったら。私って結構大胆だったのかもしれない。
事情があったとはいえ、出会ってから数日の異性である渡部君の家に、お邪魔してたし。
そして、すぐさま同棲もしてたし。
「なら、葵。ちょっと今日出かけないか?」
「え?」
急にどうしたんだろ。
「ちょっと連れていきたい場所があるんだ」
そして、その日の夜。
私は今豪華なレストランにいる。
「えっと、勇人君、これは?」
今の状況が理解できていない。
なぜ、あの会話の流れでこうなったんだろう。
「思えば二人であまり一緒にご飯を食べに行くことなんて無かったけど、結婚した今なら出来るだろ」
「そ、そうだけど」
確かに私と勇人君はそこまで二人で外食したことは無い。
理由はそこまでで複雑なものはない。ただ、行ってなかっただけだ。
ちなみに勇人君は渡部勇人だとばれないようにか、変装をしている。
「それに、結婚した今、葵に思う存分お金を使える」
「私、別にお金のために結婚したんじゃないんだけど」
「それは知ってる。でも、葵のためにお金を使いたいだけだ」
「お金を……」
別にいいのにと言いたいところだが、勇人君はお金をたくさん持っている。
確か、所持金が5億円を超えていたような気がする。
だからこんなもの、はした金なのだろう。
なんだろう、この言い方。これから私にジャンジャンと、お金を貢いでいく気なのだろうか。
「勇人君ありがとう」
別に私は、勇人君にお金を使ってもらうほどたいそうな人間ではない。
ただ、勇人君の優しさは、甘んじて受け取っていきたい。
勇人君に取って私は大事な人なんだから。
そしてメニュー表を開く。
すると、全部の値段が高いな、と思った。
パスタは二千円を超えていて、サブメニューのはずのアヒージョなども1200円もしている。
こんなの、勇人君と結婚しなかったら永遠に食べられてなかっただろうな、と思う。
別にお金のために結婚したわけでは無いけれど、それでも嬉しい。
「僕は何を食べようか」
そう言ってメニュー表を開く勇人君。
「僕は、何が食べたいんだろう」
勇人君は悩み始めた。
「もしかして勇人君って、自由だと逆に何を食べるか迷うタイプ?」
「そうかもしれない。葵が来てからは葵の作ってくれたご飯ばかり食べていたし、葵が来る前は、適当に目についたものを食べてた。正直、食欲なんて無かったし」
「そう……」
そう言えば、勇人君は私が来る前、ご飯をあまり食べていなかった。
勇人君に関する問題は正直解決したわけでは無かったのだ。
最近明るいけれど。
「じゃあ、私が決めてあげる」
そう、私は言った。
勇人君が好きなのは、きっと。
「これかな」
勇人君が一番美味しいと言っていたご飯。それは、しょうゆで味付けをしたものだ。
という事は、カルボナーラよりも、バター炒めパスタとか、キノコパスタの方が好きだろう。
そうなれば、決めるのも簡単になってくる。
「そうか、なら僕はこの二択で選べばいいのか」
「そうね」
「なら、気楽になって来た」
勇人君は、基本食事にはこだわらない。
だけど、このレストランの食事はきっと私の作った料理よりも美味しいだろう。
食材も豪華で、一流の料理人たちが作ってるのだ。
「楽しみだね」
勇人君が頼み終わった後、私はそう言った。
勇人君はその言葉にただ頷いて見せた。
「そう言えばこの前の話なんだけど」
私は言葉を紡ぐ。
「結婚式場で言った話」
「そう言えば言ってたな」
「私は今は正直気にしてないけど、なんか気を使わないで欲しい」
「気を使ってなんか……」
いや、勇人君は優しい。少しだけ、気にしてるのをたびたび感じる。
私も勇人君の尊敬する人を殺してしまった。
その事を気にしてた私が言える事ではないけれど。
「私は過去の事は過去の事って割り切ってるから、本当に今まで通りでいいよ」
「そうか、でも辛いのは分かってるから甘えてもいいよ」
「まあ、甘えるけど。……というか、今までも結構甘えてない?」
私は結構勇人君に支えられてきている。
勇人君がいるから支えられていると言っても過言ではない。
「それを言ったら僕も支えられてるよ」
「ふふ、だったらお互い様だね」
ワインが届いた。
私はそれを少しづつ飲む。
普段はあまりお酒を飲まないが、レストランだと、雰囲気も良く、ワインが美味しい。
「そう言えば、勇人君ってお酒飲まないんだね」
私は酒をくびっと飲みながら言った。
「そりゃ僕は酒があまり得意じゃないから。もしかして、こういう場ってお酒を飲むのがマナーだったりするのか?」
「ううん、そんなことない。ただ、私が思っただけ」
「そっか」
そして、私たちが楽しく話していると、ようやく食事が運ばれてきた。
見るからにおいしそうだ。
まず具材が沢山入っており見た目がインスタ映えしそうな感じがする。しかも、香ってくる匂いも中々鼻を刺激して、食欲を増してくる。
「勇人君」
「ああ、中々美味しそうだ」
「きっと、私の作るパスタよりも美味しいよ」
「それ、肯定しにくいからやめてくれないか」
確かに、勇人君が私のパスタよりも美味しいと言ったら少しもやもやするけれど。
でも、ここのパスタが、私の作るパスタよりも美味しくないなんてことは無いだろう。
何しろ、高級レストランなのだから。
「いただきます」
「いただきます」
私たちは互いにそう言って、フォークでパスタを巻いて口に入れる。
人か見すると一気にパスタの風味が口の中に広がる。
「美味しい」
「美味しいな」
私たちの言葉が重なる。
実際に美味しい。
私たちは顔を見合わせる。
すると、なんだか不思議な気持ちになって、思わず笑ってしまった。
「なんだよ」
「私よ勇人の声が重なった」
「確かに」
そうぼそっと呟くと、勇人君は一気に顔を赤くした。
私はこういう場合、どのような反応をしたらいいんだろう。
笑ったらいいのか、私も顔を赤くしたらいいのだろうか。
困った私はとりあえずパスタを食べる。
その後暫く私たちは無言でパスタを食べる。
そして、半分程度食べた後、私はとあるものを勇人君に見せた。
「これ、見に行こうかなって思ってるの」
私が見せた画面。それは、棋戦の後悔対局のチケットだった。
将棋の対局場には普通、対局者と、記録係。それくらいしかいない。
だけど、例外的に、プロが戦う姿を間近で見られる棋戦があるのだ。
それがこの棋戦だ。
私は勇人君が対局している姿を、ネット配信くらいでしか見たことが無い。
だからこそ、間近で見たいなと前々から思っていたのだ。
そしてそんな棋戦が存在すると聞いて、私は嬉しく思っているのだ。
是非とも見てみたいとは思うけど、勇人君の許可がないとね。
夫である。
そう、考えると少し照れてきた。
そうだ。私はもう奥さんであり、勇人君は私の夫だ。
結婚したから、何かが変わったことは無い。とは思っていたけども、私たちは互いが番になったことで称号を手に入れられているじゃないの。
「葵、どうしたんだ?」
「は、勇人君、何でもないよ」
「なんか、話の続きが一向にないから」
確かに。私よく考えれば一分くらい硬直してたかも。
「ごめんね。それで、これで勇人君の対局を見ようと思ってるの」
「その対局は、皆川四段との」
「そう、見に行きたいと思ってるの。夫の対局を」
最後の方は呂律が回らなくなったかもしれない。なんだか言ってる途中で恥ずかしくなってしまったのだ。
夫のというあたりで。
「ごめんね。急に恥ずかしくなっちゃって。勇人君の夫である私が」
「大丈夫だよ。葵は僕の奥さんなんだから自信持ってくれよ」
「それが恥ずかしいの。それで、見に行ってもいい?」
「もちろん。僕の許可なく見に行っていいよ。でも、少し恥ずかしいけど」
「恥ずかしいんだ」
「そりゃ。僕だって恥ずかしいよ」
そう言う勇人君の顔はワインのアルコールのせいか、恥ずかしいからなのか、軽く紅潮していた。
「ふふ、じゃあ見に行くね」
「うん、ぜひ」
そして私たちは軽く笑った。