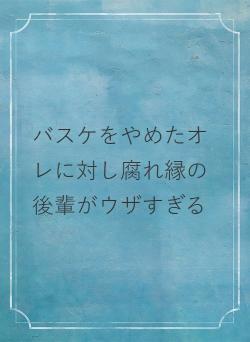その後、その男が依馬家からの依頼で来た者だとわかった。
「そんな」
成花は嘆く。
自分を連れ戻そうだなんて思っているとは思っていなかった。
きっと、清美の逆燐に振れたのだろう。
「きっと逆上したんだろう。自分の選ばれていない方の娘が、僕に選ばれたんだから」
「あの」
成花はおずおずと訊く。
「どういう事ですか?」
「どういう、とは?」
「私が実の娘だって言うのは」
その言葉を聞いた凛が、白斗に耳打ちをする。
「なるほどそういう事か」
そして、そう頷いて見せた。
「僕の調べによると君は彼らの娘だ。何しろ、彼らの召使の中に君の苗字の依馬を名乗る物はいなかった。それに出生記録も異なっていた証拠が残っている」
「そこまで調べてたのですね」
感心したように成花は言う。
「でも、理解が追い付きません」
「まあ、簡単な話だ。その……」
白斗は言いにくそうにしている。
それを見て、成花は即座に理解した。
「私が醜いから……」
「そういう事らしい」
そう言って、白斗は息をこぼす。
「実際、そんな事はないけどな」
「そう言ってもらえて、嬉しいです」
「まあでも、お前は絶対に守ってやる」
「ありがとうございます」
そう、素直にうれしいのだ。自分なんかのためにここまでしてくれるという行為自体が。
自分をほめてくれる事が。
それこそ今知った、実の娘だというのに、使用人として育てられたその事実を踏まえても嬉しさの方が勝つ。
(私、依存してるのかも)
そう、成花は思った。
この新しい環境。その中で、自分は受け入れられつつある。
「私、白斗さんと、凛さんがいたら他には何もいりません」
「なら、僕の婚約を受けてくれるってことかな」
「それは、違うかもしれないけど……」
「ええ!?」
その言葉に成花はくすくすと笑う。
「私は大丈夫です。もう未練は晴れましたから」
未練。勿論あの家に対してだ。
「それならよかった。僕の婚約に対してはじっくり考えて欲しい」
「ありがとうございます。でも一つだけ」
そして息を吸う。
「かっこよかったです」
その言葉で白斗が軽く顔を赤くしたのを見て、また成花はふふと笑った。
「それじゃあ、私部屋に戻っていますね」
「ああ」
そして、部屋に戻り、寝転がった後、成花は顔を抑えた。
ドキドキが今も止まらない。
吊り橋効果という言葉がある。
危機に陥った場合、死の間際のドキドキを恋愛のどきどきと勘違いしてしまうという事だ。
しかし、それにしても心身がおかしい。
きっと、やっぱり彼に恋し始めているからだ。
こんな感情は初めてだ。
今まで味わったことがない。
あの瞬間、部屋へと戻っていなければ、きっとドキドキで死んでいただろう。
戻ってよかった。
こんな恥ずかしい姿をさらけ出さなくて済んだのだから。
そう言えば、
(白斗様は私の姿をどうおもっているのでしょう)
ふと思った疑問だ。
成花は自他ともに認める醜い姿だ。
火傷後や片目の光を失っているのだ。
今日のあの男もそう言って成花を嘲り笑っていた。
それが私なのだ。
「もし、私の存在意義が予言だけだったらどうしよう……」
同様に不安に陥る。
自分はそれくらいしか必要とされてなかったとしたら。
それを考え出すと不安な自分が出てきてしまう。
今までのやさしさも、全ては自分の体調がよくなるためだとしたら。
そんなよからぬ考えが脳内を巡る。
「成花様」
ふすまがノックされる。
「はい」
成花は少し間を置き、返事を返した。
「成花様、料理の時間ですが、今日は一緒に食べませんかと、主様が」
昨日は部屋に運んでもらっていた。勿論今日の朝も。
だから一緒にご飯を食べるというのは初めてだ。
だけど、わくわくする。
「はい!」
成花は元気よく答えた。
その席で真意を訊こう。きっと彼なら答えてくれるはずだ。
そして、向かう道の途中。
「そう言えば凛さん」
「何ですか?」
「貴方は狐だったのですね」
先程の騒動で新たに知った事実だ。
「ええ。幻滅した?」
「幻滅というか……」
幻滅なんてものはしていない。
むしろ、
「感謝してます。私を見つけてくれて」
そう頭を下げた。
「こちらこそ、あの時助けてくれてありがとう。実は、あの時人間の姿に上手く慣れなくて、焦ってたのよ」
「そうだったんですね」
そして、あっという間に食事場へとついた。
席に着く。
「あの、白斗様」
早速成花は訊く。
「どうしたんだい」
料理を前に白斗がほほ笑む。
「流石にこれは多すぎませんか?」
そこにあった料理はかなりの量で、この場にいる三人だけでは食べきれないだろう。
「一応多くつくらせたんだ。君が満足いく量が食べられるように」
「ありがとうございます。でも、私小食ですよ」
そこまでの量は食べない、というよりも食べられない。
体が細いのもあるが、毎日そこまでの量を食べられない環境に身を置いていたため、ほとんど食べられないのだ。
「そうだったのか」
「落ち込まないでください。私頑張って食べますから」
「いや、無理はしないで欲しいんだが」
そして、料理を少しづつ食べ始める。
その料理の前に、凛は出て行った。
(凛さん……)
二人きりにさせたいのだろう。でも、そんな気遣いは困る。
成花は今激しく緊張しているのだ。
「美味しいかい?」
その優しさが嬉しい。
「美味しいです」
「それは良かった」
その笑顔がまぶしい。
自分がどうにでもなってしまいそうだ。
でも、そうだ。自分の訊きたいことを訊いておかなくちゃ。
そう思い、口を開く。
「あの、少しいいですか?」
「何だい?」
「私のこの顔をどう思いますか?」
そう発した後、極度の緊張に襲われた。
もし、この人まで否定されたらその時はもうどうなるか分からない。
発狂してしまうかもしれない。
それほどまでに、好きになっているのだから。
「その顔は……」
言葉が濁った。
それを見て、少し顔を背ける。
「もしかして、私が運命の人じゃなかったら、私の事を妻に迎え入れようとは思いますか?」
「それは……迎えるさ」
その言葉には安心感を覚えられない。
「っごめんなさい。変なことを訊いてしまって」
そう言った瞬間、白斗様は成花を抱きしめた。
「へ?」
「もしも本当に僕が君の事を愛さなかったらこんなことできるかい?」
「……出来ないと思います」
少なくとも打算込みであれ、清美が成花を抱きしめるなんてことはしないだろう。
「だから、安心して欲しい。君を不安にさせたのはたぶん、僕の求愛行動が足りなかったのだろう。でも、僕は君の事を愛らしいと思ってるよ」
「こんな見た目でも?」
「ああ。それに、それは僕のせいでもあるんだから」
生まれつき、この顔だと聞いた。
たしかにそれは生まれつきの伴侶として生まれたという事なら納得できる。
「これは、君を傷つけるかもしれないと思って言っていなかったんだけど。君が自分に自信が持てる顔に生まれていたら良かったなと思う。君は苦しみ続けていたんだから」
「なんで、私が傷つくと?」
「君の顔を全否定してしまうかもしれないと思ったからだ」
確かに成花の事を何かいう時、毎回言いにくそうな顔をしていた。
それは成花が傷つくのを避けようとしていたのだろうか。
「ありがとうございます」
成花は静かにお礼を告げた。
「おかげで、今私は幸せです」
そして笑顔で、そう告げるのであった。