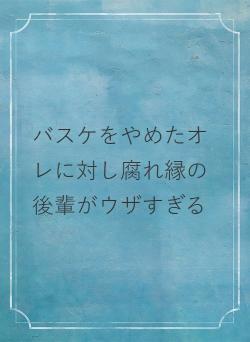「今日は遅かったじゃないの」
帰って早々に清美にそう睨まれた。
その剣幕にうぅ、と成花は軽く怯む。
「それで、今日は疲れたの。肩をもんでくれないかしら」
「かしこまりました、お嬢様」
感情を捨て、姉の肩を揉む。
強くもみ過ぎても弱くもみ過ぎても文句は言われる。
気を使いながらちょうどいい強さを心掛けながら揉んでいく。
「清美」
そこに母親、和美が来た。
「縁談の申し込みが来ているわ」
と母。
「縁談ですって、どこから?」
「矢代木家です」
その母が告げた家は名門も名門。
それこそ、この国の支配層と言ってもいいお方だった。
かつて帝が国を踏破した際に、その右腕として帝を支えた褒章としてこの国の第二位の権力を与えられているのだ。
「そんな方がどうして」
清美は呟く。たがが一村の領主の家。格が違いすぎる、
まるでシンデレラストーリーだ。
「でも、嬉しいわ。私の事を見てくださったのね。まるで、物語の主人公みたいだわ」
だが、清美には関係が無かった。
自分の人間性が認められたという証拠なのだから。
「ここには明後日に使いの者が来るらしいわ」
「じゃあ、それまでにおめかししていかなきゃ」
その会話を成花は無心で訊いていた。
どうせ自分には関係のない事だ。
それよりもこれからしばらく振り回されるのかと思うと、ため息が止まらなかった。
その予想は案の定当たってしまった。
その翌日、お付きの者として成花は清美の買い物に付き合わされることとなった。
一応立場上成花は使用人という事になっているが、その職務内容は家のために働く事、だけだ。
そのために、こういった日によって用事が増えてしまうのだ。
正直成花にとってはこの姉は苦手そのものであった。
いつも高圧的で、自分の我儘を常に聞いているしかない。
仕事だから仕方ないと割り切るしかない、というのも分かっている。
しかし、いつまでこうして命令に従わないといけないのか。
しかし、この姉がいなくなってくれるなら好都合だ。
もう、振り回されなくて済むのかもしれないのだから。
「私はねー、翌日からこの国を掌握するの。素敵だと思わない?」
買い物中にふと、清美がそう言葉を放つ。
「素敵だと思います」
自分には関係ないと思いつつ、そう言葉を返す。
「私があなたを連れて行ってあげる。そしてあなたを私の僕として永遠に可愛がってあげるわ」
その言葉は高圧的であり、絶望的な物だった。
「貴方は一生私の物よ」
その言葉に、成花は何も返すことが出来なかった。
(なぜこんなに傲慢な清美様に、惹かれたのでしょう)
成花にとってはそれが不思議でたまらなかった。
そしてその翌日。ついに使いの者がやってきた。
清美は緊張した様子だ。
「お嬢様、頑張ってきてください」
そう、成花は頭を下げた。
「私が行くだけよ」
先日床屋で髪の毛を整えてもらい、新たな衣服を仕立て上げた清美。
その顔には自身の二文字しか見えない。
そして、成花は部屋で待機だ。いつでも行けるように。
★★★★★
「初めまして。私は主の命で参りました、凛と申します」
そう言って使いの者、凛は頭を下げた。
「それで、訊きますが」
そう言って凛は清美を見る。
そして次の瞬間に、清美を睨む。
「君がこの家の娘か?」
その眼光は鋭い物だった。
しかし、清美は臆さずに言う。
「ええ、わたくしがこの家の一人娘依馬清美でございます」
そして清美は頭を下げた。
そして凛はその顔をじっと見る。
清美はその見定めるような視線にじっと耐える。
その視線は正直気色悪かったが、それでも、清美は確信していた。
自分が家の奥様になれることを。
しかし――
「違うな」
凛は非常にもそう吐き捨てた。
その目は軽蔑の目だった。
「もう一人娘がいるはずです」
そう、和美の方を見て、問う。
「我が家には一人しか娘はおりませぬが」
和美が怯えながら言った。
「もう一人娘がいるはずだ。それを主のために連れてこねばならぬ」
「そうは言いましても」
「連れてこい!!」
怒号が鳴り響く。
権力的にはかなわないお相手。
和美と父親、清治は互いに顔を合わせ、清美はその場で只うずくまった。
数秒の間の後、
「分かりました」
そう、清治が言う。
そして、「連れてきます」と言って部屋を経った。
そして取り残された清美は、
「なんで、なんでよ」
その場でそう、ぶつぶつと呟いた。
★★★★★
「成花」
「はい、何でしょうか」
「来てもらいたい」
腕を強引に引っ張られる。
「なんでしょうか」
「お前に会いたいとご所望だ」
「え?」
思わず声を漏らす。
なぜ自分をご所望しているのか。その理由が分からない。自分はただの使用人だというのに。
そして、部屋に入り正座座りをする。
その面前には凛。
成花には緊張の色が走る。
「それで、私に何の用でしょうか」
おずおずと訊く。ただ、顔は正面じゃなくて、軽く下を向く。
あまり顔を見られたくない。
火傷後の残る、片目のない自分の顔なんて。
「君だ」
その瞬間、そう発された。
「え?」
とぼけたような顔で、唖然と凛の方を見る。
「探してたのは君だよ。主人が待っている。来てもらいたいわ」
「しかしっ!!」
和美が叫ぶ。
「その子は使用人の子どもです」
「本当にか?」
凛は睨む。
「この子は本当に貴様の娘ではないというのですか?」
その言葉に母はした唇をかむ。
「まあいい、調べればわかる事。それよりも我が主のために着いて来てくれないか?」
その言葉に成花は二人の顔を見た後、
「いいのであれば」と続けた。
この環境から早く逃れたい。逃れたい。そう、ずっと思い続けてきた。
その願いがようやく叶う。
こんなにうれしいことなど他にはなかった。
「待て、お前は私の使用人じゃないの?」
清美が立ち上がり叫ぶ。
「行ったらだめよ!!」
その言葉に成花は動きを止める。
「いいのです。我々が彼女に従う義務はありません。何かあれば我々が権力でつぶしますので」
権力でつぶす。恐ろしい言葉だ。
しかし、その言葉が成花にとっては心地良い物に聞こえた。
自分はもう従わなくてもいいのだという安心感。
この地獄のような日々から逃れられるという安ど感。
「行きましょう」
成花はそう答えた。
★★★★★
「何なのよ一体」
清美は床を拳で殴った。淑女であれば取ってはいけない行動だ。
しかし、激情している彼女にとっては関係なかった。
その後、その場に力を失ったかのようにへたり込んだ。
「これは何かの間違いだわ」
和美が叫ぶ。
「そうよ間違いよ」
「そうだな」
清治も首肯した。
「こんなことがあってはいけない。お前じゃなくてあんな汚らわしい子が選ばれるなんて。きっとすぐに勘違いだと気づくはずだ」
「そう、そうよね!!」
「そうだわ。私が最後には勝つのよ。あの子に比べて全然美しいもの」
「その意気よ。私の血を引くあなたが、選ばれないなんてことありえないのだから」
母は、昔はその美貌を武器に何人ものおおt子を虜にしてきていた。
その結果領主の息子であった現夫の妻という地位を得たのだ。
その血を被気づいている娘が美しくないわけがない。
むろん、成花もその血を引き継いでいるのだが。
「でも、念には念を入れるわ」
和美がそう呟く。
「依頼するのよ」
「依頼?」
「あの子を取り戻す」
そして、和美はにやりと笑った。
★★★★★
馬車の後部座席に座ってる間、成花の緊張は中々ほどけなかった。
理由を聞きたいと思ったが、それは主の口から直接言いたいそうですと言われ、教えてもらえなかった。
ただの、使用人の子ども。
両親が借金と共に消えたことにより、下働きを開始した身。
決して美しくも、きれいでもない。それどころか、汚い容姿である事は自他ともに認めている。
清美に何度も言われているのだ。汚らわしい容姿だと。
自分を卑下することは簡単すぎるのだ。
外の景色を見る。
どんどんと景色が移り変わっていき、都会らしくなる。
あの家は帝都にある。
体とどころか、自分の生まれ育った村からすら出たことも無い。
わくわくと緊張が共に湧き上がる。
「着きました」
それは、おおよそ3時間後の事だった。
「長旅お疲れでしょう。寝床を用意してあります。どうぞ」
「はい……」
遣いの者の手を借り、地面へと降りる。
足で踏みしめている大地の感覚が違う。
成花は一気に前を見た。
「これが帝都……」
その景色は今まで見たことも無いような荘厳なものだった。
とにかく建物がずらりと並んでおり、人の数も多い。
村の市場にも人が多くいたが、これはスケールが違う。
「すごいでしょう」
凛が言う。
「これからここで暮らすのですよ」
「それはこちらが決める事だと思いますが」
「ふふ、そうよね。勝手に決めてごめんね」
凛は謝罪の言葉を口にする。
「……いえ、謝る事では」
「じゃあ、行くわね」
「はい」
凛の手を握りながら真っ直ぐ歩んでいく。
成花は目が不自由だ。だから慣れてない道を歩くのには苦労する。
凛さんの手を借りられてよかった、と思いながら歩いていく。
そして、三分ほど歩いてたどり着いた建物も素晴らしい物だった。
ここが、今日から住む場所だ。
勿論それはこれから会うその主に気に入られればの話だが。
「どう?」
凛が静かに言う。
「ここに来てから驚きっぱなしです」
「そりゃそうよね。この建物は凄いからね」
そこにあるのは人が百人は住めるであろう木製建物だ。
経てるのに、どれだけのお金がかかるのか、想像しただけで恐ろしい。
そしてその日は建物に入り、食事をとったのち、直ぐに寝床に着いた。
長旅の疲れが出ていたのだ。
肝心の矢代木様と会うのは翌日だ。今日は体を休めて欲しいらしい。
大きな空間で布団で一人眠るのも、少し怖かった。
しかし、今まで味わったことも無いような寝やすい布団の力を借り、眠りについた。
流石は最高級の布団。今までで一番の眠りにつくことが出来た。