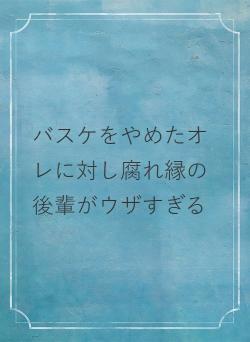依馬家には二人の娘がいた。
姉の名を清美、妹の名を成花と言った。
姉よりも三年遅れて生まれた妹は早産だった。
普通よりも早く生まれたのだ。
そのため、生まれつき体も弱く、生まれつき片目の光を失っていた。またその一方の目の視力も弱かった。
また生まれつき体中に火傷後のようなあざがあり、家の者はとにかく嫌うようになった。
この子は、忌み子だ。呪われた子供だと。
そのため、彼女は生まれたことを秘匿された。
こんな子供がいたとなれば、一族の恥だから。
子どもは、流産したことにして、成花は使用人の子どもという事にしたのだ。
とは言っても、亡くなった使用人のだが。
それが成花の地獄の日々の始まりだった。
小さな古小屋の窓から太陽の日差しが舞い降りる。
それを、視力の弱い右目で見て呟いた。
「朝か」
と。
朝は憂鬱だ。朝早く起きて朝食の準備をしなくてはならない。
ぐっと重たい体を気合で起き上がらせ、建物から出る。
そして10分程度歩いた先に成家があった。
今成花は使用人として依馬家に仕えている。
彼女は自分がまさにその依馬家の血を引いているという事を知られていない。
皮肉なものだ。自分の家族であるはずの人達にへりくだらなければ、ならないのだから。
家に着いた後は兎に角調理だ。朝ごはん、また夜ご飯を作る事は彼女の担当なのだ。
早速彼女は鍋に山菜を入れ炒め始めた。
そして、鍋でいため、すぐに完成だ。
「お嬢様、ご主人様、奥様、料理でございます」
そう言って、成花はさらに盛りつけられている料理を出した。
「ご苦労」
「では、失礼します」
そう言って奥へと下がった。
家族の食事の場は汚してはならないのだ。
そして、自分の食事をとる。勿論、先ほどよりも質素なものだ。
その後も仕事も多にわたる。
部屋の掃除などの家事が残っている。
それらが終わってからようやく自由時間。
既に時計の針は12を回っていた。
そして、仕事が終われば、町へ出るのが日課だ。
食料調達ももちろんだが、それと同様に、家から出られるのが嬉しい。
息が詰まるのだ。
何かあれば、職務時間外でも、清美に雑用を言い渡される。
それに、勤務時間内とは言っても、そこまで厳密に仕事のみに取り掛からなくてもいい。
夕食の用意を行わねばならぬ時間までに戻れば何ら問題はない。
店に向かう。上質な野菜が売ってある。
「これください」
そう、静かに成花が言う。
「まいど」
そう言って店員は粗雑に接客をする。お金を強引に奪い去り、成花の前に野菜を置いた。
関わりたくない、とでもいいだけだ。
知っている。
肌が焼け焦がれ、片目の視力が失われている成花に対して愛想をよくする人はほとんどいない。心で分かっている。
それに、こんなのはもう慣れている。
いちいち腹が立っていては無駄に疲れてしまう。
体力は温存しておきたい。
どうせ、もう希望はないのだ。
それが自分の運命だと知っている。
野菜を手に持ちながら色々と見て回る。
成花には、自由に使えるお金が支給されている。しかし、それは主に食料調達に使われる。
それを除けばほとんど使えるお金はない。
精々余りをお小遣いに加えるくらいだ。
「あら」
その帰り道、通りかかる清美の姿を目にした。
それを見て成花はそっと、前髪をたらした。
今日も華美な着物を着て歩いている。
その肌は雪のように白く、美しい。
実際に、清美はいくつも縁談が来るほど、美人なのだ。
その母、和美の血をまっとうに引いているからだろう。
母も、実際に巷で有名な美女だったのだ。
清美の美貌を見ると嫌になってしまう。
この自分のコンプレックスである肌を意識してしまって。
今すぐにでもこの場から離れたい。ここにいれば自分の惨めさに心が蝕まれてしまう。
足を翻し、そのまま歩いてその場を離れようとする――
しかし、その瞬間清美が成花を見た。
「あら、成花じゃない?」
話しかけられてしまった。
無視して去っていけば後に折檻されることは間違いないだろう。
清美の気に障ることをする訳にはいかない。
「はい」
成花は頷いた。
「外に歩いていいと思ってるのかしら?」
「それはいったい」
「そんな汚い面を周りに見せびらかして。周りの目の毒になると辞任しなさい」
「そんなことを言われましても」
自分は買い物をしに来てるのだ。
必要だから、出かけているだけで。それをさせているのはご主人側の清美たちなのだ。
勿論自身の肌が焼け肌れ、誰が見ても汚らしいと思うだろうことは知っているが、だから外に出かけてはいけない派、理不尽だ。
「もう、外に出ないで頂戴」
「なら、ご飯はどう作れば」
「山で山菜でも詰めばいいんじゃないの? もしくは山でクマを狩るとかね。そしたら人に会わないでしょ」
「そう言われても……」
山菜摘みならまだしも、狩猟などの経験はない。そもそも猟銃などないのにどうやって狩ればいいのだろうか。
それに、そう言う訳があるなら他の人に頼めばいい。
おそらく、無理な命令を出しておちょくってるのだろう。
「ご主人様の命令よ」
そう吐き捨て去っていく。
「こんなごみと喋っていたら移ってしまうわ」
その場で、数秒間ただ、立ちふけった。
そして、去ったのを確認すると軽くため息をついた。
その後、もう少し市場を見回るのも飽きたので、山の上へと向かった。
そう、山の風を浴びるために。
実のところ成花は今まで精神が落ち込んだ時には毎度山の上へとやって来ていた。
今日で四度目くらいになるだろうか。
草木をかき分け兎に角上へと上がって行く。
行き路に狐を見かけた。
可愛らしいと、一目してからそのまま歩みを進める。
この山は頂上がそこまで高くはない。だからこそ、すぐに頂上へとたどり着いた。
山の上から街を見下ろすとなんとなく気分が安らぐ気がするのだ。
その時だった。山の上から狼の咆哮のようなものが聴こえた。
「狼?」
静かに叫ぶ。
その音を聞き、急いで山を下りる。
狼は危険な存在だ。人に飼いならされていない犬。
出会えば最期死の危険性がある。
人間がかなう相手ではない。
今までもこのようなケースは極まれにあった。しかし、ここまで近くで咆哮を感じたのは初めてだった。
街中へと降りれば大丈夫だ。
野生とはいえ、そこまで野蛮な生き物ではないだろう。
山をもの凄い勢いで駆け降りていく。
だが、その時、近くで狐が動けなくなっている事に気が付いた。
挟まった木々が挟まっていたのだ。
「狐?」
成花は叫んだ。
最初に見かけた狐と同じだろう。
一瞬その場に立ち止まり、狐を手に抱える。
見逃しても良かったのだ。このまま放置しても死ぬとは限らない。
だけど、ほっておけなかった。
だけど、それがいけなかったのかもしれない。
それにより、体のバランスが乱れてしまった。
その結果、地面に転がりゆく。
(痛い痛い)
でも、成花は狐の事は決して離さなかった。
手でギュっと抱きしめる。
「いててて」
底まで転がり落ちた後、成花は立ち上がる。
気が付けば衣服がはだけていた。
さらに元から酷かった肌がさらに荒れている。
人に見られなくてよかった、と思いつつ衣服を直す。
するとキツネはすぐに成花の腕の中から抜け出し、走って去って行った。
成花はその後を見て、軽く手を振った。
「ばいばい」
そして、衣服を整え、
その日、無事に山から下りる事の出来た成花はその足で依馬家へと戻った。
もう、狼の気配もない。
ゆったりと戻ることが出来る。
姉の名を清美、妹の名を成花と言った。
姉よりも三年遅れて生まれた妹は早産だった。
普通よりも早く生まれたのだ。
そのため、生まれつき体も弱く、生まれつき片目の光を失っていた。またその一方の目の視力も弱かった。
また生まれつき体中に火傷後のようなあざがあり、家の者はとにかく嫌うようになった。
この子は、忌み子だ。呪われた子供だと。
そのため、彼女は生まれたことを秘匿された。
こんな子供がいたとなれば、一族の恥だから。
子どもは、流産したことにして、成花は使用人の子どもという事にしたのだ。
とは言っても、亡くなった使用人のだが。
それが成花の地獄の日々の始まりだった。
小さな古小屋の窓から太陽の日差しが舞い降りる。
それを、視力の弱い右目で見て呟いた。
「朝か」
と。
朝は憂鬱だ。朝早く起きて朝食の準備をしなくてはならない。
ぐっと重たい体を気合で起き上がらせ、建物から出る。
そして10分程度歩いた先に成家があった。
今成花は使用人として依馬家に仕えている。
彼女は自分がまさにその依馬家の血を引いているという事を知られていない。
皮肉なものだ。自分の家族であるはずの人達にへりくだらなければ、ならないのだから。
家に着いた後は兎に角調理だ。朝ごはん、また夜ご飯を作る事は彼女の担当なのだ。
早速彼女は鍋に山菜を入れ炒め始めた。
そして、鍋でいため、すぐに完成だ。
「お嬢様、ご主人様、奥様、料理でございます」
そう言って、成花はさらに盛りつけられている料理を出した。
「ご苦労」
「では、失礼します」
そう言って奥へと下がった。
家族の食事の場は汚してはならないのだ。
そして、自分の食事をとる。勿論、先ほどよりも質素なものだ。
その後も仕事も多にわたる。
部屋の掃除などの家事が残っている。
それらが終わってからようやく自由時間。
既に時計の針は12を回っていた。
そして、仕事が終われば、町へ出るのが日課だ。
食料調達ももちろんだが、それと同様に、家から出られるのが嬉しい。
息が詰まるのだ。
何かあれば、職務時間外でも、清美に雑用を言い渡される。
それに、勤務時間内とは言っても、そこまで厳密に仕事のみに取り掛からなくてもいい。
夕食の用意を行わねばならぬ時間までに戻れば何ら問題はない。
店に向かう。上質な野菜が売ってある。
「これください」
そう、静かに成花が言う。
「まいど」
そう言って店員は粗雑に接客をする。お金を強引に奪い去り、成花の前に野菜を置いた。
関わりたくない、とでもいいだけだ。
知っている。
肌が焼け焦がれ、片目の視力が失われている成花に対して愛想をよくする人はほとんどいない。心で分かっている。
それに、こんなのはもう慣れている。
いちいち腹が立っていては無駄に疲れてしまう。
体力は温存しておきたい。
どうせ、もう希望はないのだ。
それが自分の運命だと知っている。
野菜を手に持ちながら色々と見て回る。
成花には、自由に使えるお金が支給されている。しかし、それは主に食料調達に使われる。
それを除けばほとんど使えるお金はない。
精々余りをお小遣いに加えるくらいだ。
「あら」
その帰り道、通りかかる清美の姿を目にした。
それを見て成花はそっと、前髪をたらした。
今日も華美な着物を着て歩いている。
その肌は雪のように白く、美しい。
実際に、清美はいくつも縁談が来るほど、美人なのだ。
その母、和美の血をまっとうに引いているからだろう。
母も、実際に巷で有名な美女だったのだ。
清美の美貌を見ると嫌になってしまう。
この自分のコンプレックスである肌を意識してしまって。
今すぐにでもこの場から離れたい。ここにいれば自分の惨めさに心が蝕まれてしまう。
足を翻し、そのまま歩いてその場を離れようとする――
しかし、その瞬間清美が成花を見た。
「あら、成花じゃない?」
話しかけられてしまった。
無視して去っていけば後に折檻されることは間違いないだろう。
清美の気に障ることをする訳にはいかない。
「はい」
成花は頷いた。
「外に歩いていいと思ってるのかしら?」
「それはいったい」
「そんな汚い面を周りに見せびらかして。周りの目の毒になると辞任しなさい」
「そんなことを言われましても」
自分は買い物をしに来てるのだ。
必要だから、出かけているだけで。それをさせているのはご主人側の清美たちなのだ。
勿論自身の肌が焼け肌れ、誰が見ても汚らしいと思うだろうことは知っているが、だから外に出かけてはいけない派、理不尽だ。
「もう、外に出ないで頂戴」
「なら、ご飯はどう作れば」
「山で山菜でも詰めばいいんじゃないの? もしくは山でクマを狩るとかね。そしたら人に会わないでしょ」
「そう言われても……」
山菜摘みならまだしも、狩猟などの経験はない。そもそも猟銃などないのにどうやって狩ればいいのだろうか。
それに、そう言う訳があるなら他の人に頼めばいい。
おそらく、無理な命令を出しておちょくってるのだろう。
「ご主人様の命令よ」
そう吐き捨て去っていく。
「こんなごみと喋っていたら移ってしまうわ」
その場で、数秒間ただ、立ちふけった。
そして、去ったのを確認すると軽くため息をついた。
その後、もう少し市場を見回るのも飽きたので、山の上へと向かった。
そう、山の風を浴びるために。
実のところ成花は今まで精神が落ち込んだ時には毎度山の上へとやって来ていた。
今日で四度目くらいになるだろうか。
草木をかき分け兎に角上へと上がって行く。
行き路に狐を見かけた。
可愛らしいと、一目してからそのまま歩みを進める。
この山は頂上がそこまで高くはない。だからこそ、すぐに頂上へとたどり着いた。
山の上から街を見下ろすとなんとなく気分が安らぐ気がするのだ。
その時だった。山の上から狼の咆哮のようなものが聴こえた。
「狼?」
静かに叫ぶ。
その音を聞き、急いで山を下りる。
狼は危険な存在だ。人に飼いならされていない犬。
出会えば最期死の危険性がある。
人間がかなう相手ではない。
今までもこのようなケースは極まれにあった。しかし、ここまで近くで咆哮を感じたのは初めてだった。
街中へと降りれば大丈夫だ。
野生とはいえ、そこまで野蛮な生き物ではないだろう。
山をもの凄い勢いで駆け降りていく。
だが、その時、近くで狐が動けなくなっている事に気が付いた。
挟まった木々が挟まっていたのだ。
「狐?」
成花は叫んだ。
最初に見かけた狐と同じだろう。
一瞬その場に立ち止まり、狐を手に抱える。
見逃しても良かったのだ。このまま放置しても死ぬとは限らない。
だけど、ほっておけなかった。
だけど、それがいけなかったのかもしれない。
それにより、体のバランスが乱れてしまった。
その結果、地面に転がりゆく。
(痛い痛い)
でも、成花は狐の事は決して離さなかった。
手でギュっと抱きしめる。
「いててて」
底まで転がり落ちた後、成花は立ち上がる。
気が付けば衣服がはだけていた。
さらに元から酷かった肌がさらに荒れている。
人に見られなくてよかった、と思いつつ衣服を直す。
するとキツネはすぐに成花の腕の中から抜け出し、走って去って行った。
成花はその後を見て、軽く手を振った。
「ばいばい」
そして、衣服を整え、
その日、無事に山から下りる事の出来た成花はその足で依馬家へと戻った。
もう、狼の気配もない。
ゆったりと戻ることが出来る。