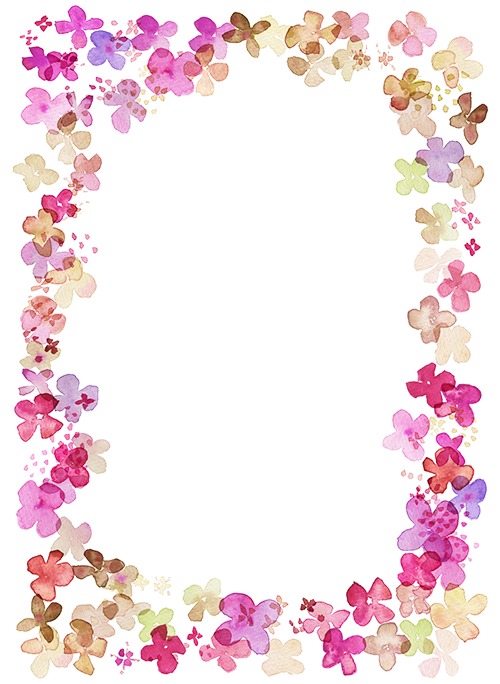茜色の雲が空に浮かぶ頃、咲希は離れの庭を歩いていた。
咲希の宮での仕事は元から穏やかな日々だったが、懐妊がわかってからはより宮様が過保護になって、咲希は体調を崩すこともなく過ごしていた。
空をよくみつめたのは、子どもの頃以来かもしれない。子どもの頃、咲希の思い描いた未来はいくつかが叶って、叶わないものは意図的に忘れてしまった。
一番大きなこと、生業はまだ続けていられるから、そのときの自分は満足してくれるだろう。けれどそのときの自分が想像もしていなかったこともある。
赤い陽を仰いで、咲希はそっと腹部を押さえた。
咲希は妊婦となって、宿った命に愛おしさを抱きながら、同じくらいに不安も抱いている。
宮様は咲希の分まで咲希の体を労わってくれている。咲希には妊娠した実感が薄く、気づかず今までのように立ち仕事をしてしまって、宮様に止められる。
妊娠は不意の出来事だったからかもしれない。自分であって自分でないものに傾ける心が、つかめないでいる。
大切なひとが自分を労わってくれているのに、咲希はお腹の子をどうにも生み出す自信がない。
赤い陽をみつめたまま、咲希は呼吸がうまくできないでいた。たまらなく愛おしいのにどうしようもなく不安で、自分が自分の中で分離してしまって、動けない。
自分は母親になれないのだろうか。昨年亡くした母に縋りたい思いで、立ちすくんだ。
けれどもちろん母は現れることなく、咲希に声をかけたのは宮様だった。
「こんなところにいると冷えてしまうよ」
宮様は咲希の背を羽織で包むと、その前に立って言った。
「咲希、不安は全部僕に預けてみないか」
宮様は咲希の揺れた瞳をみつめ返して、そっと咲希の手を取る。
「僕は一回り君より年上だし、この宮での暮らしのことをよく知っているよ。赤子を産むのは君しかできないけれど、他のことは僕に託してほしい」
「宮様……」
「青慈と呼んでほしいな。君は僕と共に人生を歩んでいく人なんだから」
咲希はそろそろと、青慈さま、と口にする。
咲希はいつも彼に頼っている。出会ったときから彼が咲希に差し伸べてきた慈愛の手は、あまりに温かい。
咲希が喉を詰まらせると、宮様……青慈は優しくその頬に触れた。
「咲希が側にいることが、僕の人生で最良の出来事なんだ。僕は今からわくわくしているんだよ。親子三人で、どんなことをして過ごしていこうかと」
見上げれば柔らかい茜色がまぶしかった。咲希は青慈に手を取られて歩き始めながら、彼に声をかける。
「桜を見せてあげたいです。赤子に、白嶺領の美しい白い桜を」
咲希の言葉に、彼は微笑んでうなずいた。
「僕もだ。ここの桜はどこより美しいからね。……さあ、帰ろう」
伸びた影を踏みながら二人、庭を渡り始める。
また夜になれば不安はやって来るかもしれないが、咲希は青慈が側にいればそれを乗り越えていける気がしていた。
咲希の宮での仕事は元から穏やかな日々だったが、懐妊がわかってからはより宮様が過保護になって、咲希は体調を崩すこともなく過ごしていた。
空をよくみつめたのは、子どもの頃以来かもしれない。子どもの頃、咲希の思い描いた未来はいくつかが叶って、叶わないものは意図的に忘れてしまった。
一番大きなこと、生業はまだ続けていられるから、そのときの自分は満足してくれるだろう。けれどそのときの自分が想像もしていなかったこともある。
赤い陽を仰いで、咲希はそっと腹部を押さえた。
咲希は妊婦となって、宿った命に愛おしさを抱きながら、同じくらいに不安も抱いている。
宮様は咲希の分まで咲希の体を労わってくれている。咲希には妊娠した実感が薄く、気づかず今までのように立ち仕事をしてしまって、宮様に止められる。
妊娠は不意の出来事だったからかもしれない。自分であって自分でないものに傾ける心が、つかめないでいる。
大切なひとが自分を労わってくれているのに、咲希はお腹の子をどうにも生み出す自信がない。
赤い陽をみつめたまま、咲希は呼吸がうまくできないでいた。たまらなく愛おしいのにどうしようもなく不安で、自分が自分の中で分離してしまって、動けない。
自分は母親になれないのだろうか。昨年亡くした母に縋りたい思いで、立ちすくんだ。
けれどもちろん母は現れることなく、咲希に声をかけたのは宮様だった。
「こんなところにいると冷えてしまうよ」
宮様は咲希の背を羽織で包むと、その前に立って言った。
「咲希、不安は全部僕に預けてみないか」
宮様は咲希の揺れた瞳をみつめ返して、そっと咲希の手を取る。
「僕は一回り君より年上だし、この宮での暮らしのことをよく知っているよ。赤子を産むのは君しかできないけれど、他のことは僕に託してほしい」
「宮様……」
「青慈と呼んでほしいな。君は僕と共に人生を歩んでいく人なんだから」
咲希はそろそろと、青慈さま、と口にする。
咲希はいつも彼に頼っている。出会ったときから彼が咲希に差し伸べてきた慈愛の手は、あまりに温かい。
咲希が喉を詰まらせると、宮様……青慈は優しくその頬に触れた。
「咲希が側にいることが、僕の人生で最良の出来事なんだ。僕は今からわくわくしているんだよ。親子三人で、どんなことをして過ごしていこうかと」
見上げれば柔らかい茜色がまぶしかった。咲希は青慈に手を取られて歩き始めながら、彼に声をかける。
「桜を見せてあげたいです。赤子に、白嶺領の美しい白い桜を」
咲希の言葉に、彼は微笑んでうなずいた。
「僕もだ。ここの桜はどこより美しいからね。……さあ、帰ろう」
伸びた影を踏みながら二人、庭を渡り始める。
また夜になれば不安はやって来るかもしれないが、咲希は青慈が側にいればそれを乗り越えていける気がしていた。