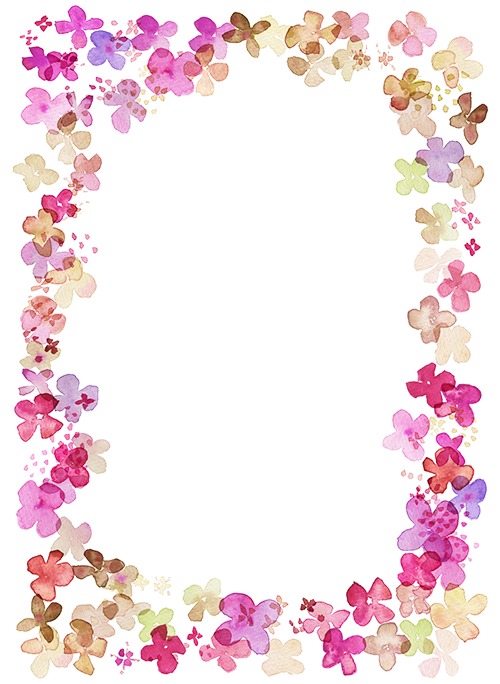咲希が染料に使う桜の実を見て、周りの音も忘れるほど集中しているとき、森の中にいるような気分になる。
実際、多くの人々が行き交う宮の中で働いているのだから、それは人波の中の一人になっている一体感だろうか。
顔を上げて辺りを見回すと、天から金色の陽光が差し込んできていた。咲希が育てている桜たちは、季節柄、花こそ咲いてはいないが健やかに枝を伸ばしていて、悠々と過ごしているように見えた。
森を思わせる桜の園の中で一人、それは真夜中であれば恐ろしいのかもしれないが、真昼にここにいて咲希が感じるのはただ安息感だ。
昼下がりになれば宮様がやって来て、居室で茶をたしなむ。その他愛ない時間が愛おしい。
そう思いながら居室に戻って来て、咲希はふと隣室から聞こえた声に耳を澄ませた。
隣室は宮様の衣装合わせの部屋だが、そこに立ち入る侍女や侍従は限られている。戸も普段は閉じていて、近頃は宮様と咲希の二人だけの空間だった。
そこから聞こえてきたのは、宮様の声だった。誰かと話しているようだが、相手の声は聞こえない。
宮様と恋人のような関係になって少し経ったが、咲希は周りから冷たい扱いを受けたことがない。もちろん妻になるというのは、恋人とはずいぶん違うことだと、咲希は畏れているけれど。
今、宮様の声は強張っているようだった。彼は侍従たちの前でも、咲希の前でも、声を荒らげたことがない人だが、今は何かの感情に押し流されていた。
宮様は誰かに対して、かみつくように告げる。
「彼女に過去など要らない。つらい思いをさせた者たちなど、滅びればいい!」
開け放った扉から冷気が流れ込むように、咲希はひどくそちら側に身を固くしながら、目を伏せて縫物の手仕事に集中しようとした。皮肉にもそれはますます咲希の耳を鋭敏にして、耳に届くか届かないかの微かな声に全身を傾けてしまった。
そのとき、相手の声が聞こえた。不思議なことに、それは宮様にそっくりの声だった。
「そう、宮の言う通り、因果応報というものだろう……」
宮様の声とその声がぴたりと重なったとき、咲希は目の前が暗くなった。
肩を叩かれて振り向くと、そこに宮様の心配そうなまなざしがあった。彼の視線の先を追うと、咲希の頬に涙が流れた跡があった。
……あれは、夢だったのだろうか。でも、白昼夢のように鮮明だった。
彼はそっと咲希の頬を拭って言う。
「どうしたの、咲希」
「……私は病気なんでしょうか」
宮様が聞き手ということを忘れて、咲希は不安を口にしていた。
「幻のような光景を、見ることがあるんです」
時々見る夢、どうしてか途切れる意識は、この上なく穏やかな日常に小さな風穴を空けている。
宮様は彼らしく、その落ち着きで咲希を宥めて言った。
「咲希は繊細な子だから。そこが愛おしくもあるのだけど」
宮様は咲希の背をさすって、考えた後に告げる。
「少し仕事を休みなさい。それと……医師に診せよう。一緒についているよ」
「そんな、ご迷惑をおかけするようなこと」
抵抗した咲希に、宮様は優しく目をのぞきこんだ。
「君は永く共に歩んでいく人なんだよ。僕に寄りかかって構わない」
宮様は咲希の肩を引き寄せて自分にもたれさせた。
咲希はその温もりに泣きたくなるような思いで、彼の肩を拠り所に瞳を揺らした。
実際、多くの人々が行き交う宮の中で働いているのだから、それは人波の中の一人になっている一体感だろうか。
顔を上げて辺りを見回すと、天から金色の陽光が差し込んできていた。咲希が育てている桜たちは、季節柄、花こそ咲いてはいないが健やかに枝を伸ばしていて、悠々と過ごしているように見えた。
森を思わせる桜の園の中で一人、それは真夜中であれば恐ろしいのかもしれないが、真昼にここにいて咲希が感じるのはただ安息感だ。
昼下がりになれば宮様がやって来て、居室で茶をたしなむ。その他愛ない時間が愛おしい。
そう思いながら居室に戻って来て、咲希はふと隣室から聞こえた声に耳を澄ませた。
隣室は宮様の衣装合わせの部屋だが、そこに立ち入る侍女や侍従は限られている。戸も普段は閉じていて、近頃は宮様と咲希の二人だけの空間だった。
そこから聞こえてきたのは、宮様の声だった。誰かと話しているようだが、相手の声は聞こえない。
宮様と恋人のような関係になって少し経ったが、咲希は周りから冷たい扱いを受けたことがない。もちろん妻になるというのは、恋人とはずいぶん違うことだと、咲希は畏れているけれど。
今、宮様の声は強張っているようだった。彼は侍従たちの前でも、咲希の前でも、声を荒らげたことがない人だが、今は何かの感情に押し流されていた。
宮様は誰かに対して、かみつくように告げる。
「彼女に過去など要らない。つらい思いをさせた者たちなど、滅びればいい!」
開け放った扉から冷気が流れ込むように、咲希はひどくそちら側に身を固くしながら、目を伏せて縫物の手仕事に集中しようとした。皮肉にもそれはますます咲希の耳を鋭敏にして、耳に届くか届かないかの微かな声に全身を傾けてしまった。
そのとき、相手の声が聞こえた。不思議なことに、それは宮様にそっくりの声だった。
「そう、宮の言う通り、因果応報というものだろう……」
宮様の声とその声がぴたりと重なったとき、咲希は目の前が暗くなった。
肩を叩かれて振り向くと、そこに宮様の心配そうなまなざしがあった。彼の視線の先を追うと、咲希の頬に涙が流れた跡があった。
……あれは、夢だったのだろうか。でも、白昼夢のように鮮明だった。
彼はそっと咲希の頬を拭って言う。
「どうしたの、咲希」
「……私は病気なんでしょうか」
宮様が聞き手ということを忘れて、咲希は不安を口にしていた。
「幻のような光景を、見ることがあるんです」
時々見る夢、どうしてか途切れる意識は、この上なく穏やかな日常に小さな風穴を空けている。
宮様は彼らしく、その落ち着きで咲希を宥めて言った。
「咲希は繊細な子だから。そこが愛おしくもあるのだけど」
宮様は咲希の背をさすって、考えた後に告げる。
「少し仕事を休みなさい。それと……医師に診せよう。一緒についているよ」
「そんな、ご迷惑をおかけするようなこと」
抵抗した咲希に、宮様は優しく目をのぞきこんだ。
「君は永く共に歩んでいく人なんだよ。僕に寄りかかって構わない」
宮様は咲希の肩を引き寄せて自分にもたれさせた。
咲希はその温もりに泣きたくなるような思いで、彼の肩を拠り所に瞳を揺らした。