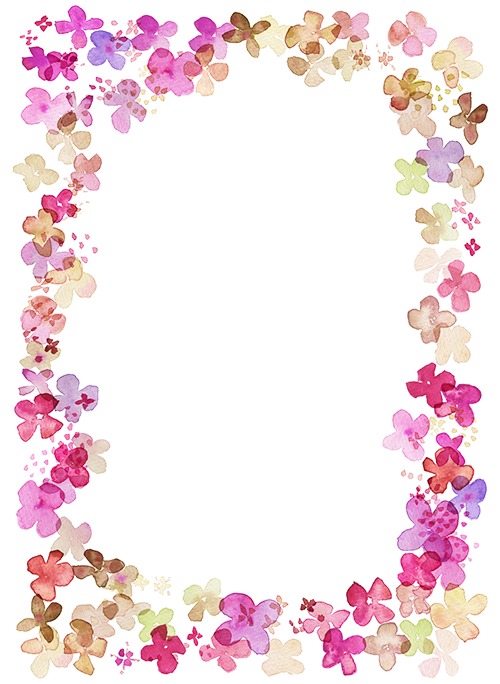咲希は時々、夢を見る。どこか遠い街に嫁いで日々を送っている。
そこでの咲希は手荒い扱いを受けている。寒い土地柄でもある。夫となった人は、咲希を愛していない。
けれど咲希は生まれてから白嶺領を離れたことがない。だからそれはたぶんただの夢で、今の咲希は他愛ない機織りだ。
宮様の住まう屋敷で一晩を過ごした後、咲希はまだ家に帰ることができずにいた。
咲希が宮様に提案された、巫女として仕える仕事は、とても恵まれているように思う。
姫のような衣装も調度も与えられ、広く日当たりのいい居室も与えてもらっている。
ただいつからかその居室の隣で、宮様が過ごすことが多くなっていた。
咲希は居室の隣、淡い朝陽が差し込む寝所で、宮様の膝枕をしていた。
宮様は普段着の直衣を解き、無防備に寝息を立てていた。
陶器のような白い肌に細くしなやかな眉、男性としては華奢な体。宮様は咲希より一回り年上とは思えないような、柔い雰囲気をまとう人だ。
いつまでもその面差しをみつめていたい。そう思っていたら、まぶたが開く。
薄い唇が咲希と動いて笑みを作ったのを見て、咲希は慌てて言う。
「失礼いたしました。朝餉をお持ちしますか?」
「いや……もう少し、このまま」
少年のようにうなずいて、宮様は手を伸ばす。咲希は反射的にその手を取ってしまったが、気恥ずかしさにぱっと手を離した。
宮様は微笑んで咲希に言う。
「夢を見ていた」
「夢?」
「咲希は夢を見る?」
咲希はそう問われて、ふと言葉を口にした。
「時々……悪い夢を見ますけれど」
「悪い夢は忘れてしまっていいんだよ」
宮様はそう言ってから、慈しむように咲希を見る。
「僕の夢はいい夢だから、いつまでも覚えてる。咲希が来たときだよ。まだ女童の他愛ない頃だったね」
首を傾けて宮様がうれしそうに語るのは、何度か彼が口にする咲希の子どもの頃の話だ。
咲希は幼い頃、何かの儀式のとき宮様に会ったことがあるらしい。でも咲希には思い出せなくてもどかしい。
宮様はうれしそうにつぶやく。
「僕の袖をつかむと、宝物みたいに笑った」
宮様はふいに咲希の袖を引いた。思っていたより強い力に、咲希は宮様の方に身を傾ける格好になる。
「……今は君自体が宝のような女人になった」
耳元でささやかれた言葉に、咲希の心がざわめいた。
咲希と宮様は隠れた恋人同士、ということなのだろう。突然それを意識させられて、気恥ずかしくなる。
「ね?」
いたずらっぽく告げた宮様は、恋人というよりずっとまぶしい御方として咲希の心に存在している。
宮様は伸びをして、他の誰よりも似合う直衣をさっとまとう。
「さて、仕事をしようかな。君の夫はちゃんと日々執務を行っているよ」
夫など、まだ口にするのも恐れ多くて。そう宮様に言ったら、笑って、「慣れて」と言われてしまった。
彼が瞳で咲希をなだめた気配を感じながら、咲希は苦笑してうなずいた。
そこでの咲希は手荒い扱いを受けている。寒い土地柄でもある。夫となった人は、咲希を愛していない。
けれど咲希は生まれてから白嶺領を離れたことがない。だからそれはたぶんただの夢で、今の咲希は他愛ない機織りだ。
宮様の住まう屋敷で一晩を過ごした後、咲希はまだ家に帰ることができずにいた。
咲希が宮様に提案された、巫女として仕える仕事は、とても恵まれているように思う。
姫のような衣装も調度も与えられ、広く日当たりのいい居室も与えてもらっている。
ただいつからかその居室の隣で、宮様が過ごすことが多くなっていた。
咲希は居室の隣、淡い朝陽が差し込む寝所で、宮様の膝枕をしていた。
宮様は普段着の直衣を解き、無防備に寝息を立てていた。
陶器のような白い肌に細くしなやかな眉、男性としては華奢な体。宮様は咲希より一回り年上とは思えないような、柔い雰囲気をまとう人だ。
いつまでもその面差しをみつめていたい。そう思っていたら、まぶたが開く。
薄い唇が咲希と動いて笑みを作ったのを見て、咲希は慌てて言う。
「失礼いたしました。朝餉をお持ちしますか?」
「いや……もう少し、このまま」
少年のようにうなずいて、宮様は手を伸ばす。咲希は反射的にその手を取ってしまったが、気恥ずかしさにぱっと手を離した。
宮様は微笑んで咲希に言う。
「夢を見ていた」
「夢?」
「咲希は夢を見る?」
咲希はそう問われて、ふと言葉を口にした。
「時々……悪い夢を見ますけれど」
「悪い夢は忘れてしまっていいんだよ」
宮様はそう言ってから、慈しむように咲希を見る。
「僕の夢はいい夢だから、いつまでも覚えてる。咲希が来たときだよ。まだ女童の他愛ない頃だったね」
首を傾けて宮様がうれしそうに語るのは、何度か彼が口にする咲希の子どもの頃の話だ。
咲希は幼い頃、何かの儀式のとき宮様に会ったことがあるらしい。でも咲希には思い出せなくてもどかしい。
宮様はうれしそうにつぶやく。
「僕の袖をつかむと、宝物みたいに笑った」
宮様はふいに咲希の袖を引いた。思っていたより強い力に、咲希は宮様の方に身を傾ける格好になる。
「……今は君自体が宝のような女人になった」
耳元でささやかれた言葉に、咲希の心がざわめいた。
咲希と宮様は隠れた恋人同士、ということなのだろう。突然それを意識させられて、気恥ずかしくなる。
「ね?」
いたずらっぽく告げた宮様は、恋人というよりずっとまぶしい御方として咲希の心に存在している。
宮様は伸びをして、他の誰よりも似合う直衣をさっとまとう。
「さて、仕事をしようかな。君の夫はちゃんと日々執務を行っているよ」
夫など、まだ口にするのも恐れ多くて。そう宮様に言ったら、笑って、「慣れて」と言われてしまった。
彼が瞳で咲希をなだめた気配を感じながら、咲希は苦笑してうなずいた。