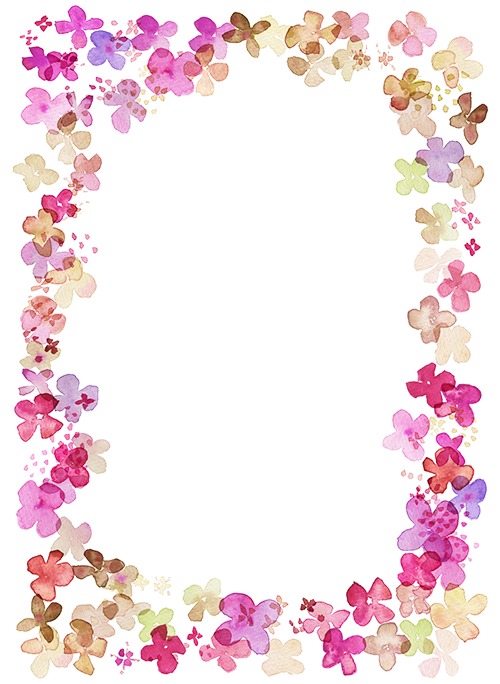咲希は白嶺領で生まれて育った。
白嶺領は帝のおわす神領からは遠く離れているが、穏やかな気候と豊かな土壌に恵まれたところだった。咲希はそこで商家を営む母の元、機織りをして暮らしていた。
特別なことは何もない暮らしの中、春の豊穣祭で舞う機会があった。そのとき、領主である宮様からお声がけがあった。
「重畳。天女のような舞だ」
そう告げた宮様は、目を細めてまぶしいものを見る目で咲希を見た。
後で御前に呼ばれたとき、宮様は優しい声音で咲希に声をかけた。
「君のことを、遠い昔から知っていたような気がする。ずっと離れ離れだった人にようやく再会したようだ」
「とんでもない。私は白嶺領で生まれた機織りに過ぎません」
咲希は緊張してなかなか顔も上げられずにいたが、促されてようやく宮様の顔を見た。
宮様は白い直衣の似合う長い手足と、切れ長の綺麗な目をしていた。咲希より一回り年上の落ち着いた雰囲気の人で、慈しむような目で咲希を見て言った。
「じゃあ笑って聞いてほしい。……おかえり。待っていた」
咲希の心はことんと音を立てて、淡い心地で彼を見上げた。
けれどそれは儀式の後にたまわった言葉で、明日からは元の日常に戻るのだと思っていた。
ただそれはひとときでは終わらなかった。宮様は翌日には母の元に使者を送り、咲希を自分の元に出仕させるように促した。母が恐縮して辞退しようとしても、引かなかった。
何度か咲希が宮を訪れて舞い、その際に食事を共にし、その間隔が次第に狭くなっていった。
ある日、宮様と庭を歩いていたとき、宮様はそっと首を傾けて言った。
「また帰ってしまうの?」
咲希はずっと昔から宮様といたのに、長く離れていたような、切ない気持ちに襲われた。
咲希は畏れ多いと思って、慌てて返した。
「それが私の暮らしですから」
そう言いながら、また寂しいような思いになっていた。
咲希は幼い日に父を、昨年母を亡くしていて、一人きりの春は初めてだった。
ちゃんとしないと。そう自分に言い聞かせて、前を見ようとした。
咲希の暮らしはきちんと働けば、ひどく貧しくはない。それで十分なのだからと思って、じきにやって来る静かな夜をみつめた。
北の橋を渡れば門戸があって、そこからは歩いて帰るつもりだった。儀式も橋のこちら側で開かれたから、ここは本来咲希のような者がいる場所ではない。
振り返ると、夜の灯りで照らされた白嶺宮が立っていた。
大きな鳥が羽を休ませているような優雅な建物に、白い桜が夜に枝葉を広げている光景を見ているうちに、どこにも行き難い気持ちにさせられた。
歩き出そうとした咲希の手、そこに優しく指が重なったのは、そのときだった。
後ろから伸ばされた手が自分の手に重なっているのに気づいて、咲希は振り向いた。
風に乗って白い桜の花びらが降りてくる。その最中に宮様が立っていて、咲希に言った。
「僕の元に嫁がないか」
咲希が息を呑んで立ちすくむと、宮様は優しく告げた。
「君が覚えていないずっと前から、僕は君を想ってきた。これからは側で、君を守りたい」
宵闇に座す桜から目を逸らせないように、咲希は彼をみつめ返した。
庶民の自分と宮様の彼、結ばれるはずもないと言おうとしたのに、喉が詰まった。
言いよどんだ咲希を、宮様は後ろから腕に包み込んだ。
夜の橋の上、一つの樹になったように、二人は互いに身を寄せていた。
白嶺領は帝のおわす神領からは遠く離れているが、穏やかな気候と豊かな土壌に恵まれたところだった。咲希はそこで商家を営む母の元、機織りをして暮らしていた。
特別なことは何もない暮らしの中、春の豊穣祭で舞う機会があった。そのとき、領主である宮様からお声がけがあった。
「重畳。天女のような舞だ」
そう告げた宮様は、目を細めてまぶしいものを見る目で咲希を見た。
後で御前に呼ばれたとき、宮様は優しい声音で咲希に声をかけた。
「君のことを、遠い昔から知っていたような気がする。ずっと離れ離れだった人にようやく再会したようだ」
「とんでもない。私は白嶺領で生まれた機織りに過ぎません」
咲希は緊張してなかなか顔も上げられずにいたが、促されてようやく宮様の顔を見た。
宮様は白い直衣の似合う長い手足と、切れ長の綺麗な目をしていた。咲希より一回り年上の落ち着いた雰囲気の人で、慈しむような目で咲希を見て言った。
「じゃあ笑って聞いてほしい。……おかえり。待っていた」
咲希の心はことんと音を立てて、淡い心地で彼を見上げた。
けれどそれは儀式の後にたまわった言葉で、明日からは元の日常に戻るのだと思っていた。
ただそれはひとときでは終わらなかった。宮様は翌日には母の元に使者を送り、咲希を自分の元に出仕させるように促した。母が恐縮して辞退しようとしても、引かなかった。
何度か咲希が宮を訪れて舞い、その際に食事を共にし、その間隔が次第に狭くなっていった。
ある日、宮様と庭を歩いていたとき、宮様はそっと首を傾けて言った。
「また帰ってしまうの?」
咲希はずっと昔から宮様といたのに、長く離れていたような、切ない気持ちに襲われた。
咲希は畏れ多いと思って、慌てて返した。
「それが私の暮らしですから」
そう言いながら、また寂しいような思いになっていた。
咲希は幼い日に父を、昨年母を亡くしていて、一人きりの春は初めてだった。
ちゃんとしないと。そう自分に言い聞かせて、前を見ようとした。
咲希の暮らしはきちんと働けば、ひどく貧しくはない。それで十分なのだからと思って、じきにやって来る静かな夜をみつめた。
北の橋を渡れば門戸があって、そこからは歩いて帰るつもりだった。儀式も橋のこちら側で開かれたから、ここは本来咲希のような者がいる場所ではない。
振り返ると、夜の灯りで照らされた白嶺宮が立っていた。
大きな鳥が羽を休ませているような優雅な建物に、白い桜が夜に枝葉を広げている光景を見ているうちに、どこにも行き難い気持ちにさせられた。
歩き出そうとした咲希の手、そこに優しく指が重なったのは、そのときだった。
後ろから伸ばされた手が自分の手に重なっているのに気づいて、咲希は振り向いた。
風に乗って白い桜の花びらが降りてくる。その最中に宮様が立っていて、咲希に言った。
「僕の元に嫁がないか」
咲希が息を呑んで立ちすくむと、宮様は優しく告げた。
「君が覚えていないずっと前から、僕は君を想ってきた。これからは側で、君を守りたい」
宵闇に座す桜から目を逸らせないように、咲希は彼をみつめ返した。
庶民の自分と宮様の彼、結ばれるはずもないと言おうとしたのに、喉が詰まった。
言いよどんだ咲希を、宮様は後ろから腕に包み込んだ。
夜の橋の上、一つの樹になったように、二人は互いに身を寄せていた。