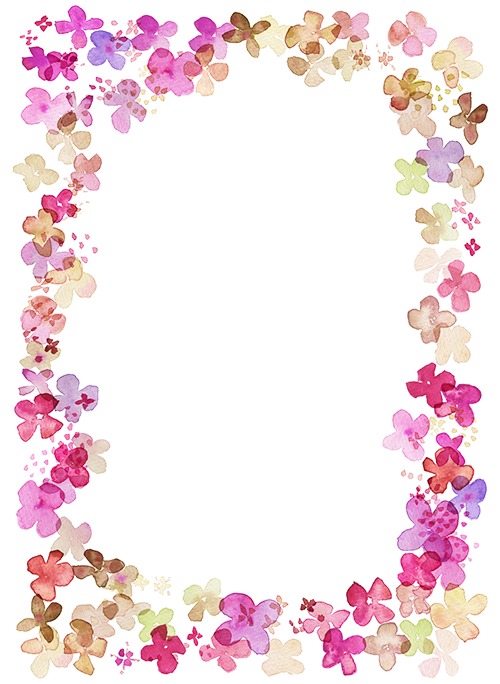咲希の出産から数か月が経ち、青慈と咲希は婚儀を挙げた。
都からも地方の豪族からも盛大な祝いの品が届き、華やかなりし宴が開かれた。
そんな夜、ひととき青慈は月見台に出て風を感じていた。
ふと欄干の下を見れば、暗黒が煙るようにうごめいていた。青慈はそれに冷ややかな笑みを向ける。
青慈はかつて、咲希を手酷く扱っていた婚家に術をほどこした。咲希が亡くなってまもなく病気を流行らせ、霧が散るように家系を途絶えさせた。
それでも亡者たちは呪詛を送り、子の命をついえさせようとした。到底許せるものではなく、青慈は再び術をかけた。
「……その地獄は、お前たちでは解けないよ。神の呪いだからね」
青慈が舞を舞うように虚空を撫でれば、暗黒は蓋を閉じるように静かになった。
ふいに青慈は顔を上げて、目を細めた。
軽やかな足音が近づいて来る。青慈が振り向いてほほえむと、その声は言った。
「父上、月を見ていらしたのですか」
青慈を見上げて弾んだ声を上げたのは、利発そうな男児だった。青慈によく似た涼しげな目元に、子どもらしい色づいた頬をしていた。
青慈はその手を取ってうなずく。
「月のしらべを聞いていた。お前にもじきに、その音色の聞き方を教えてあげよう」
「はい。楽しみです」
彼ははつらつと言葉を話し、咲希に似た淡い笑顔を浮かべた。その優しい表情に、青慈は思わず微笑み返す。
咲希が彼を産んだのは数か月前のこと。普通の子どもの成長と違ったとしても、咲希は彼を慈しんで育ててくれている。
青慈はまぶしそうに少年の頬に手を触れて言う。
「父様にとっては、お前に会えたのが二つ目の奇跡だ」
「一つ目は?」
「もちろん、母上をみつけたことだよ」
青慈が淀みなく答えると、彼は聡明な瞳で父を見返す。
「母上は、一度人の世界に呼ばれて、それで戻っていらしたそうですね」
青慈たちは神とも精霊とも呼ばれる、境界の外の存在だ。
青慈はうなずいて、その心を告げる。
「父様と母様は深い縁で結ばれているから。……さあ、今夜はもうお休み。今日は父様と母様の、大切な夜だから」
少年は敬意を払うように頭を下げて、月見台を後にした。
青慈はもう一度月を仰いで、咲希との婚儀の部屋に向かう。
回廊を渡れば、風の匂いは淡く、木々の揺れる音が子守歌のように聞こえる。白嶺宮の春は生命の彩り豊かで、動植物が生き生きと伸びていく。
桜から生を受けた自分たちが、そのように白嶺領を守っている。
「咲希」
寝所に入ると、咲希が待っていた。儀式の名残で少し緊張した様子で、そんな彼女の背をそっと包む。
その隣に身を横たえながら、青慈はたずねる。
「最近は、古い夢を見る?」
「夢?」
咲希はそう問い返して、少女のように屈託なく笑った。
「いいえ。未来のことで、今は心がいっぱいなのです」
その答えを聞いて、青慈はそれが何よりだと微笑み返す。
咲希が白嶺領の桜の神族に戻った証だった。青慈という樹に抱きしめられて、花を咲かせた。
青慈は幸せそうに笑って、首を傾ける。
「今夜も君の御業に包まれて眠っていいか? ……良い夢が見れそうだ」
咲希も笑い返して、夫を自らの桜の衣で包んだ。
都からも地方の豪族からも盛大な祝いの品が届き、華やかなりし宴が開かれた。
そんな夜、ひととき青慈は月見台に出て風を感じていた。
ふと欄干の下を見れば、暗黒が煙るようにうごめいていた。青慈はそれに冷ややかな笑みを向ける。
青慈はかつて、咲希を手酷く扱っていた婚家に術をほどこした。咲希が亡くなってまもなく病気を流行らせ、霧が散るように家系を途絶えさせた。
それでも亡者たちは呪詛を送り、子の命をついえさせようとした。到底許せるものではなく、青慈は再び術をかけた。
「……その地獄は、お前たちでは解けないよ。神の呪いだからね」
青慈が舞を舞うように虚空を撫でれば、暗黒は蓋を閉じるように静かになった。
ふいに青慈は顔を上げて、目を細めた。
軽やかな足音が近づいて来る。青慈が振り向いてほほえむと、その声は言った。
「父上、月を見ていらしたのですか」
青慈を見上げて弾んだ声を上げたのは、利発そうな男児だった。青慈によく似た涼しげな目元に、子どもらしい色づいた頬をしていた。
青慈はその手を取ってうなずく。
「月のしらべを聞いていた。お前にもじきに、その音色の聞き方を教えてあげよう」
「はい。楽しみです」
彼ははつらつと言葉を話し、咲希に似た淡い笑顔を浮かべた。その優しい表情に、青慈は思わず微笑み返す。
咲希が彼を産んだのは数か月前のこと。普通の子どもの成長と違ったとしても、咲希は彼を慈しんで育ててくれている。
青慈はまぶしそうに少年の頬に手を触れて言う。
「父様にとっては、お前に会えたのが二つ目の奇跡だ」
「一つ目は?」
「もちろん、母上をみつけたことだよ」
青慈が淀みなく答えると、彼は聡明な瞳で父を見返す。
「母上は、一度人の世界に呼ばれて、それで戻っていらしたそうですね」
青慈たちは神とも精霊とも呼ばれる、境界の外の存在だ。
青慈はうなずいて、その心を告げる。
「父様と母様は深い縁で結ばれているから。……さあ、今夜はもうお休み。今日は父様と母様の、大切な夜だから」
少年は敬意を払うように頭を下げて、月見台を後にした。
青慈はもう一度月を仰いで、咲希との婚儀の部屋に向かう。
回廊を渡れば、風の匂いは淡く、木々の揺れる音が子守歌のように聞こえる。白嶺宮の春は生命の彩り豊かで、動植物が生き生きと伸びていく。
桜から生を受けた自分たちが、そのように白嶺領を守っている。
「咲希」
寝所に入ると、咲希が待っていた。儀式の名残で少し緊張した様子で、そんな彼女の背をそっと包む。
その隣に身を横たえながら、青慈はたずねる。
「最近は、古い夢を見る?」
「夢?」
咲希はそう問い返して、少女のように屈託なく笑った。
「いいえ。未来のことで、今は心がいっぱいなのです」
その答えを聞いて、青慈はそれが何よりだと微笑み返す。
咲希が白嶺領の桜の神族に戻った証だった。青慈という樹に抱きしめられて、花を咲かせた。
青慈は幸せそうに笑って、首を傾ける。
「今夜も君の御業に包まれて眠っていいか? ……良い夢が見れそうだ」
咲希も笑い返して、夫を自らの桜の衣で包んだ。