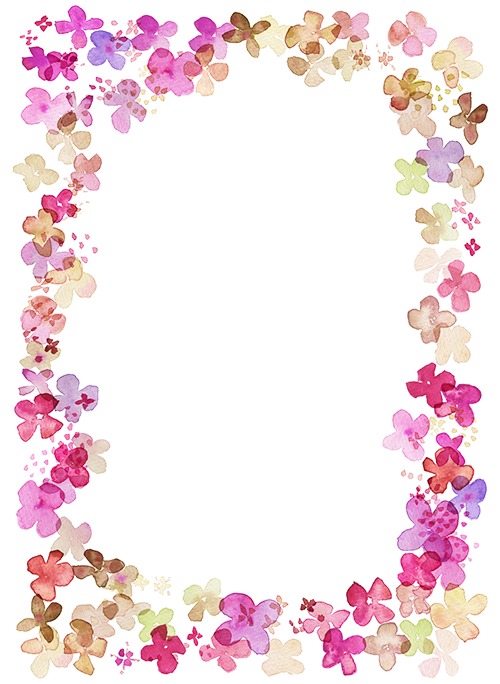底に沈むような長い夢は、咲希が白嶺領に帰って来た日につながっていた。
咲希は婚家で夫や使用人たちに手酷く扱われ、息を引き取った。けれど目が覚めれば白い桜吹雪の舞う街を、母に手を引かれて歩いていた。
白嶺領は、婚家で暮らしていたところとは何もかもが違った。薫る風と木々に囲まれたところに住処があった。咲希はそこで、父と母に愛されて育った。
咲希が女童の頃、父が亡くなった。咲希にとって父との別れは悲しみには違いなかったが、それは永遠ではないような不思議な気持ちがしていた。
ある日、咲希に白嶺宮への誘いの使者が来た。そこの領主たる宮様は、どこか懐かしい人のように感じた。
母は寂しそうに笑っていた。母は、今思えば咲希がその行き先に心を奪われるのをわかっていたのかもしれなかった。
咲希は一人、その桜の園を訪れた。
そこで、咲希は青慈に出会った。
「おかえり、咲希」
青慈は屈みこんで優しく告げて、咲希はきょとんと首を傾げた。
青慈は柔く微笑んで続けた。
「ここは咲希が生まれる前にいたところなんだ。でも忘れてしまっても構わない。今世でまた出会えたのだから」
それで、青慈は桜の園の中を案内してくれた。
そこで目にした桜の木々は、育てた人たちの愛情がわかるような健やかな木々だった。咲希は目を輝かせて口々に質問をして、青慈はそんな咲希の問いに愛おしそうに答えてくれた。
やがて青慈は咲希にそっと問いかけた。
「桜は好き?」
はい、好きですと、咲希は答えた。桜が散るたびに涙が出てくるくらいだった。それは染め物への関心にもつながって、いつか機織りになるのだと願っていた。
そのとき、青慈は一つの秘密を教えてくれた。
「白嶺領の植物は、みんな一本の桜から分かれているんだ。……それは桜の神様なんだよ」
青慈は時間をかけて咲希を案内してくれた。まだ探検をしたがっていた咲希に、彼はなだめるように言った。
「時間が来たから、今日はお帰り」
青慈の言葉に、咲希はわがままな子どものように口をへの字にして返した。
「ずっといてはいけないのですか?」
「大人になったときにここに仕えてくれれば、いいよ」
「ほんとう?」
目を輝かせた咲希に、青慈は柔く笑って言った。
「いいよ。ただ……そのときは僕のお嫁さんにもなってほしいな」
咲希は成長して、青慈に恋をした。青慈はその気持ちを受け止めて咲希を包んでくれた。
ふいに過去にはない言葉を、青慈は告げた。
「おいで。今日だけ、僕のもう一つの姿を見せよう」
咲希が足を踏み出したとき、夢ではない場所に立ち入るような錯覚があった。
丘を下って、どこか深いところまでやって来た。先に下りた青慈に続くと、そこに青慈はいなかった。
代わりにそこには緑の楽園が広がっていて、花は咲き乱れ、果実が実っていた。太陽はさんさんと差し込み、甘い香りが漂っていた。
そこに、白い桜が立っていた。
舞うように花びらを落としながら、咲希を見下ろして優しく微笑んでいるようだった。これが彼のもう一つの姿なのだと、咲希は呼吸をするように受け入れた。
相反するように、意識の向こう側で青慈の声が耳を叩く。
誰か、咲希を助けよ。咲希が側にいなければ僕の人生はつまらない。咲希と一緒だと思ったから、この世で形を取ったのだから。
「……咲希を死なせるくらいなら、子どもを殺せ」
禁断の一言を青慈が放ったとき、咲希は初めて母親になった気がした。
ずっと彼の庇護の元にいた。彼に守られて、彼に反対しようともしなかった。
でも今、咲希は一人の女性として青慈に向き合う。
咲希は意識の戸を叩くようにして言った。
「そんなことを言ってはだめです。青慈さま」
彼に二度とそんなことを言わせない。今、心臓より近いところに抱いている存在にも、二度と不安にさせたりしない。
「私、強くなりますから。あなたも子どもも守りますから。……一緒に育てましょう」
咲希は桜の幹を抱きしめて、誓うように告げた。
咲希は婚家で夫や使用人たちに手酷く扱われ、息を引き取った。けれど目が覚めれば白い桜吹雪の舞う街を、母に手を引かれて歩いていた。
白嶺領は、婚家で暮らしていたところとは何もかもが違った。薫る風と木々に囲まれたところに住処があった。咲希はそこで、父と母に愛されて育った。
咲希が女童の頃、父が亡くなった。咲希にとって父との別れは悲しみには違いなかったが、それは永遠ではないような不思議な気持ちがしていた。
ある日、咲希に白嶺宮への誘いの使者が来た。そこの領主たる宮様は、どこか懐かしい人のように感じた。
母は寂しそうに笑っていた。母は、今思えば咲希がその行き先に心を奪われるのをわかっていたのかもしれなかった。
咲希は一人、その桜の園を訪れた。
そこで、咲希は青慈に出会った。
「おかえり、咲希」
青慈は屈みこんで優しく告げて、咲希はきょとんと首を傾げた。
青慈は柔く微笑んで続けた。
「ここは咲希が生まれる前にいたところなんだ。でも忘れてしまっても構わない。今世でまた出会えたのだから」
それで、青慈は桜の園の中を案内してくれた。
そこで目にした桜の木々は、育てた人たちの愛情がわかるような健やかな木々だった。咲希は目を輝かせて口々に質問をして、青慈はそんな咲希の問いに愛おしそうに答えてくれた。
やがて青慈は咲希にそっと問いかけた。
「桜は好き?」
はい、好きですと、咲希は答えた。桜が散るたびに涙が出てくるくらいだった。それは染め物への関心にもつながって、いつか機織りになるのだと願っていた。
そのとき、青慈は一つの秘密を教えてくれた。
「白嶺領の植物は、みんな一本の桜から分かれているんだ。……それは桜の神様なんだよ」
青慈は時間をかけて咲希を案内してくれた。まだ探検をしたがっていた咲希に、彼はなだめるように言った。
「時間が来たから、今日はお帰り」
青慈の言葉に、咲希はわがままな子どものように口をへの字にして返した。
「ずっといてはいけないのですか?」
「大人になったときにここに仕えてくれれば、いいよ」
「ほんとう?」
目を輝かせた咲希に、青慈は柔く笑って言った。
「いいよ。ただ……そのときは僕のお嫁さんにもなってほしいな」
咲希は成長して、青慈に恋をした。青慈はその気持ちを受け止めて咲希を包んでくれた。
ふいに過去にはない言葉を、青慈は告げた。
「おいで。今日だけ、僕のもう一つの姿を見せよう」
咲希が足を踏み出したとき、夢ではない場所に立ち入るような錯覚があった。
丘を下って、どこか深いところまでやって来た。先に下りた青慈に続くと、そこに青慈はいなかった。
代わりにそこには緑の楽園が広がっていて、花は咲き乱れ、果実が実っていた。太陽はさんさんと差し込み、甘い香りが漂っていた。
そこに、白い桜が立っていた。
舞うように花びらを落としながら、咲希を見下ろして優しく微笑んでいるようだった。これが彼のもう一つの姿なのだと、咲希は呼吸をするように受け入れた。
相反するように、意識の向こう側で青慈の声が耳を叩く。
誰か、咲希を助けよ。咲希が側にいなければ僕の人生はつまらない。咲希と一緒だと思ったから、この世で形を取ったのだから。
「……咲希を死なせるくらいなら、子どもを殺せ」
禁断の一言を青慈が放ったとき、咲希は初めて母親になった気がした。
ずっと彼の庇護の元にいた。彼に守られて、彼に反対しようともしなかった。
でも今、咲希は一人の女性として青慈に向き合う。
咲希は意識の戸を叩くようにして言った。
「そんなことを言ってはだめです。青慈さま」
彼に二度とそんなことを言わせない。今、心臓より近いところに抱いている存在にも、二度と不安にさせたりしない。
「私、強くなりますから。あなたも子どもも守りますから。……一緒に育てましょう」
咲希は桜の幹を抱きしめて、誓うように告げた。