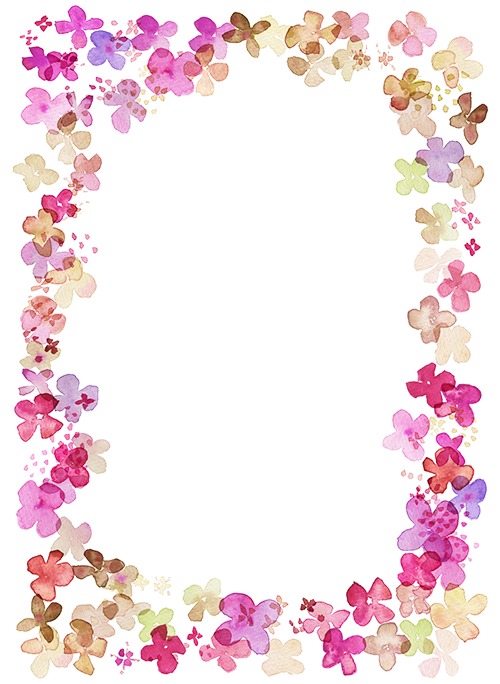泉のそばで休んだ後、咲希は自分の足で立ち上がることができなかった。
行きは歩めた廊下が帰りは歩けず、青慈が腕に抱えて咲希を居室に連れ帰った。
居室で泥のような眠りに落ちて……目覚めたときには多くの侍従たちに囲まれていた。
寝所の脇に座る青慈が、咲希の手をつかんでいた。いつも咲希の手を包むように彼は手をつなぐのに、今は縋るように堅く握りしめていた。
咲希は青慈を見上げてつぶやく。
「赤子に、何か」
悪い想像を口にしようとした咲希に、青慈は無理に笑った。
「心配要らない。赤子は元気だよ」
咲希は少し笑い返して、それならよかったと胸を撫でおろした。
けれど青慈がまとう緊張は咲希にも伝わっていた。彼が「元気」という言葉を告げたときの陰を、肌で感じていた。
毎日のように腹を撫でて、咲希は赤子の成長を確かめてきた。咲希の出産の知識はそう多くはないが……赤子の成長は速すぎるように思った。
青慈は咲希の体を起こして彼女の背中に枕を入れると、侍従たちを下がらせて切り出した。
「……近く、生まれるのだそうだ」
咲希はそれを聞いて、やっぱりと思った。
十月十日を待つ前に赤子は成長する。それが意味するところを、咲希は察してしまった。
咲希の体は、穴が空いたように力が入らない。お腹の赤子はそれくらい元気なのだった。
咲希は青慈に頼んで体を横たえてもらうと、彼を見上げた。
いつも咲希を守り、過保護に労わる彼は、予想していなかった事態に混乱しているようには見えなかった。咲希の手をつかんで、離すまいとしているように見えた。
咲希はふと微笑んだ。なぜだか彼に会えるのが最後のような気がして、それなら言葉にして伝えようと思った。
「青慈さま。まだ伝えていませんでした。ずっと、お慕いしています」
咲希が心を告げると、青慈は息を呑んで、言葉を覆うように返した。
「不安なのか? 大丈夫だ。子も君も、僕は手放したりしない」
咲希は次第に混濁していく意識の中でうなずいた。
青慈は嘘を言っていないと思う。きっと彼は手を尽くしてくれる。宮の中という、一番安全なところに自分はいる。
でも咲希はそろそろ彼と、この領の秘密に気づいている。この領は清浄で、穏やかで、どこにも汚れがない。
……まるで人の住まうところではないみたいに。
青慈は強い調子で言葉をかける。
「咲希、君は僕と歩いていく人なんだ。どこにも行かせない」
彼がそう言ったとき、それは海の底で響くように聞こえた。
咲希はもう声が出ないのをもどかしく思いながら、心で思う。
……二度目の嫁入りは、これ以上なく幸せでした。あなたのおかげです。
咲希は闇の中にぽっかりと空いた穴のような意識の濁りへ、さかさまに落ちていった。
行きは歩めた廊下が帰りは歩けず、青慈が腕に抱えて咲希を居室に連れ帰った。
居室で泥のような眠りに落ちて……目覚めたときには多くの侍従たちに囲まれていた。
寝所の脇に座る青慈が、咲希の手をつかんでいた。いつも咲希の手を包むように彼は手をつなぐのに、今は縋るように堅く握りしめていた。
咲希は青慈を見上げてつぶやく。
「赤子に、何か」
悪い想像を口にしようとした咲希に、青慈は無理に笑った。
「心配要らない。赤子は元気だよ」
咲希は少し笑い返して、それならよかったと胸を撫でおろした。
けれど青慈がまとう緊張は咲希にも伝わっていた。彼が「元気」という言葉を告げたときの陰を、肌で感じていた。
毎日のように腹を撫でて、咲希は赤子の成長を確かめてきた。咲希の出産の知識はそう多くはないが……赤子の成長は速すぎるように思った。
青慈は咲希の体を起こして彼女の背中に枕を入れると、侍従たちを下がらせて切り出した。
「……近く、生まれるのだそうだ」
咲希はそれを聞いて、やっぱりと思った。
十月十日を待つ前に赤子は成長する。それが意味するところを、咲希は察してしまった。
咲希の体は、穴が空いたように力が入らない。お腹の赤子はそれくらい元気なのだった。
咲希は青慈に頼んで体を横たえてもらうと、彼を見上げた。
いつも咲希を守り、過保護に労わる彼は、予想していなかった事態に混乱しているようには見えなかった。咲希の手をつかんで、離すまいとしているように見えた。
咲希はふと微笑んだ。なぜだか彼に会えるのが最後のような気がして、それなら言葉にして伝えようと思った。
「青慈さま。まだ伝えていませんでした。ずっと、お慕いしています」
咲希が心を告げると、青慈は息を呑んで、言葉を覆うように返した。
「不安なのか? 大丈夫だ。子も君も、僕は手放したりしない」
咲希は次第に混濁していく意識の中でうなずいた。
青慈は嘘を言っていないと思う。きっと彼は手を尽くしてくれる。宮の中という、一番安全なところに自分はいる。
でも咲希はそろそろ彼と、この領の秘密に気づいている。この領は清浄で、穏やかで、どこにも汚れがない。
……まるで人の住まうところではないみたいに。
青慈は強い調子で言葉をかける。
「咲希、君は僕と歩いていく人なんだ。どこにも行かせない」
彼がそう言ったとき、それは海の底で響くように聞こえた。
咲希はもう声が出ないのをもどかしく思いながら、心で思う。
……二度目の嫁入りは、これ以上なく幸せでした。あなたのおかげです。
咲希は闇の中にぽっかりと空いた穴のような意識の濁りへ、さかさまに落ちていった。