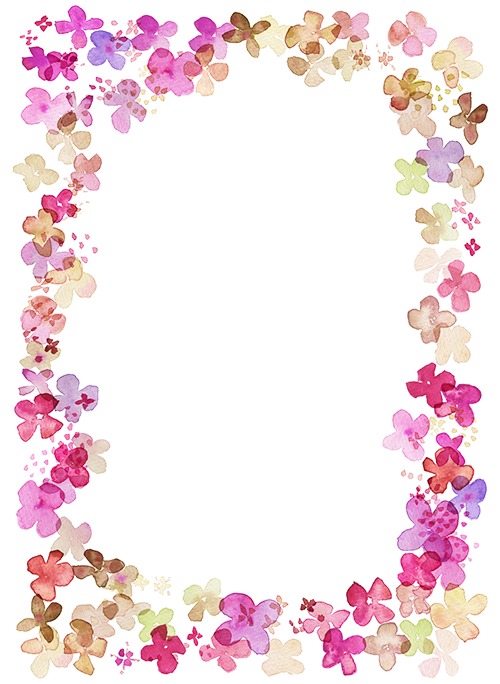青慈が過剰にも思えるほど心配した咲希の不調は、色のない毒霧のようにまもなく咲希の日常を覆いつくした。
夜に何度も起きる日が続いたかと思うと、どうしても朝起きることができず、痛むほど体が重くなった。夜に奇妙なほど体が冷えて、震えながら朝まで起きていることもあった。
深夜の寝所の中、医師が呼ばれていた。咲希は子どものように青慈に背中をさすってもらいながら、その言葉を受ける。
「呪詛です。……何者かが、咲希様の流産を図っています」
青慈は咲希の体を守るように抱きながら、厳しく言葉を返した。
「相手は心当たりがある。すぐに術返しを」
「は」
医師は侍従に何か言いつけて、準備のために一度御前を去った。
青慈は咲希の体を横たえてその隣に添いながら、暗闇の中で咲希の髪をなでた。
「よく聞いて。咲希の優しさが、呪詛に引っ張られようとしている。咲希は一度触れたものに対する愛情がとても深いんだ。遠くに去った樹たちに対するように、咲希はまだそれに思いを馳せようとしている。……けど」
暗がりの中で青慈の表情はよく見えないが、心配そうなまなざしが向けられているのは感じていた。
青慈は彼にしては強い調子で咲希にさとす。
「それは形のない夢だ。咲希を怯えさせるほどの価値がないものだ。咲希はそんなものに震えなくていい」
青慈は咲希の手を取って、大樹を抱きしめるように自分に腕をからませた。
「不安になったら僕にしがみついて。僕がここにいる。……僕が必ず咲希を未来まで、僕らの子どもたちが待っているところまで連れて行くから」
まもなく神事を行う侍従たちが入ってきて、夜を徹して呪詛返しがなされた。
朝、咲希はどうにか起き上がることができるようになった。そんな咲希の手を取って、青慈は欄干の元まで連れ出した。
泉をゆっくりと泳ぐ魚を見ながら、ひだまりに座を置いて青慈と過ごした。空が澄んで緑も青く空に映えていたから、咲希の気持ちも少し晴れた。
青慈は侍従が運んできた皿を手に取って、咲希に声をかける。
「もなかを食べたことはある?」
咲希が首を傾げると、青慈は皿の上の菓子を手に取って二つに割ってくれる。
庶民の咲希は菓子を食べたことはほとんどない。ただ見たことがあったのは、儀式の中で配られていたからだった。
この桜の領は、それほど平和で、穏やかな土地だった。そんな土地に生まれたこと自体が、奇跡のようだった。
「食べてごらん。甘いよ」
咲希は手を伸ばそうとして、くらりとめまいに襲われた。
でもきゅっとお腹が空く。お腹の子どもが、もなかを欲しがっている気がした。不安に負けそうな咲希を、優しく励ましてくれているようだった。
咲希は微笑んで、青慈からもなかを受け取る。
「ありがとうございます」
咲希が青慈を見上げると、彼は労わるように咲希に言った。
「咲希に元気でいてほしいんだ。僕も、その子も」
咲希はうなずいて、もなかを一口含んだ。
喉を通っていく菓子は甘く甘く、咲希の体に浸っていった。
夜に何度も起きる日が続いたかと思うと、どうしても朝起きることができず、痛むほど体が重くなった。夜に奇妙なほど体が冷えて、震えながら朝まで起きていることもあった。
深夜の寝所の中、医師が呼ばれていた。咲希は子どものように青慈に背中をさすってもらいながら、その言葉を受ける。
「呪詛です。……何者かが、咲希様の流産を図っています」
青慈は咲希の体を守るように抱きながら、厳しく言葉を返した。
「相手は心当たりがある。すぐに術返しを」
「は」
医師は侍従に何か言いつけて、準備のために一度御前を去った。
青慈は咲希の体を横たえてその隣に添いながら、暗闇の中で咲希の髪をなでた。
「よく聞いて。咲希の優しさが、呪詛に引っ張られようとしている。咲希は一度触れたものに対する愛情がとても深いんだ。遠くに去った樹たちに対するように、咲希はまだそれに思いを馳せようとしている。……けど」
暗がりの中で青慈の表情はよく見えないが、心配そうなまなざしが向けられているのは感じていた。
青慈は彼にしては強い調子で咲希にさとす。
「それは形のない夢だ。咲希を怯えさせるほどの価値がないものだ。咲希はそんなものに震えなくていい」
青慈は咲希の手を取って、大樹を抱きしめるように自分に腕をからませた。
「不安になったら僕にしがみついて。僕がここにいる。……僕が必ず咲希を未来まで、僕らの子どもたちが待っているところまで連れて行くから」
まもなく神事を行う侍従たちが入ってきて、夜を徹して呪詛返しがなされた。
朝、咲希はどうにか起き上がることができるようになった。そんな咲希の手を取って、青慈は欄干の元まで連れ出した。
泉をゆっくりと泳ぐ魚を見ながら、ひだまりに座を置いて青慈と過ごした。空が澄んで緑も青く空に映えていたから、咲希の気持ちも少し晴れた。
青慈は侍従が運んできた皿を手に取って、咲希に声をかける。
「もなかを食べたことはある?」
咲希が首を傾げると、青慈は皿の上の菓子を手に取って二つに割ってくれる。
庶民の咲希は菓子を食べたことはほとんどない。ただ見たことがあったのは、儀式の中で配られていたからだった。
この桜の領は、それほど平和で、穏やかな土地だった。そんな土地に生まれたこと自体が、奇跡のようだった。
「食べてごらん。甘いよ」
咲希は手を伸ばそうとして、くらりとめまいに襲われた。
でもきゅっとお腹が空く。お腹の子どもが、もなかを欲しがっている気がした。不安に負けそうな咲希を、優しく励ましてくれているようだった。
咲希は微笑んで、青慈からもなかを受け取る。
「ありがとうございます」
咲希が青慈を見上げると、彼は労わるように咲希に言った。
「咲希に元気でいてほしいんだ。僕も、その子も」
咲希はうなずいて、もなかを一口含んだ。
喉を通っていく菓子は甘く甘く、咲希の体に浸っていった。