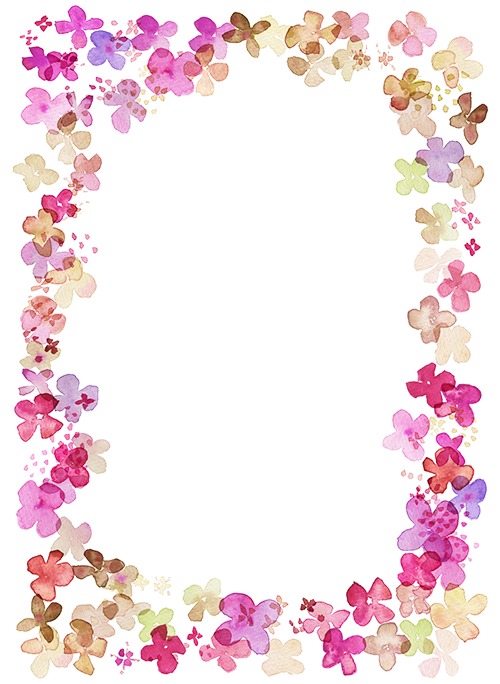咲希は、元々植物の世話をすることが好きで、しかも勤勉だった。だから街にいたときも、一日文句の一つもなく畑仕事をこなしていた。
だがこの宮に来てからは、青慈がそれをさせなかった。
特に懐妊がわかってからは、咲希を真綿で包むようだった。桜の樹の世話もしなくていいと言ったが、咲希は街にいたときから、毎日染料の植物の様子を見に行くのが日課だった。
だから青慈は、咲希が外に出るときは一緒に付き添うようになっていた。
咲希は桜の樹を見上げながらつぶやく。
「明日、実がつきます」
「そうだね。咲希もわかるようになったか」
桜の世話を続けるうちに、咲希にも実をつける時期がわかるようになっていた。確かめるように青慈に告げる声が、少し頼りなく響くのも気づいていた。
青慈はそっと咲希の肩に触れて言う。
「子どものように思っているの?」
咲希は迷って、こくんとうなずいた。
実をつけると、桜の世話は咲希の手から離れる。それが咲希には寂しくてたまらなかった。相手は植物だと自分に言い聞かせるのは、もうだいぶ前にやめた。
「咲希が愛したから育ったんだ。大丈夫、これからも永く生きていくよ」
咲希は白嶺宮の桜を人のように思っているところがある。青慈はそんな咲希を愛おしむようにして言う。
「咲希がそういう子だから、ここに戻ってこられたんだよ」
「私が女童だったときに、ここに来た話ですか?」
離れがたいように桜の樹をみつめながら答えた咲希に、青慈は優しく言う。
「それもある。……それだけではないけど。そうだな」
青慈は咲希に手を差し伸べる。
「行ってみる?」
咲希は青慈の手を取ると、不思議そうに首を傾げた。
青慈が咲希を連れて行ったのは、白嶺宮の表の方にある小さな庭園だった。咲希の住まうところは内宮で一般の立ち入りが禁止されているが、その辺りは街の人々もやって来ることがある。
白嶺領は樹の街、それも宮の中では白い桜が至るところに枝葉を広げる。だからなのか、いつもそこには街の人々たちがいた。
今日もそこでは数人、小さな子らが植物を見ていた。大人たちに手を引かれて、子どもたちは憧れるように桜を見ていた。
その気持ちは、咲希も覚えがある。咲希も女童の頃、ここを訪れた。どういう経緯だったかは知らないが、咲希は一人で来たのを覚えている。
青慈は咲希の手を取って歩きながら言う。
「この辺りの木はずっと変わりがないのだけど」
青慈が見上げる先には、そろそろ冬に至るというのに生き生きと枝を広げる桜の樹があった。白嶺領は土壌が豊かで気候も穏やかだから、樹にとって楽園のようなところだった。
青慈はふと咲希を見下ろしてつぶやく。
「咲希の背はずいぶん伸びた」
「ふふ。大人ですから」
咲希が微笑んで答えると、青慈はふと感慨深そうにため息をついた。
「青慈さま?」
「君が知るずっと前から君を見守ってきた。こうして並んで歩ける日が来るなんて、夢みたいだ」
青慈は咲希とつないだ手を持ち上げて、その手に頬を寄せる。
「……いや、夢じゃないんだ。君は僕の妻で、もうじき子も産まれるんだ」
瞬間、咲希には切ないような気持ちがこみ上げた。
幼い日、咲希はやっと出会えたというような気持ちで青慈の袖をつかんだ。そのときの咲希に向けた青慈の表情は、泣きそうな、切ないような笑顔だった。
咲希と青慈は、ずっと離れ離れだったような気がする。どうしてそんな思いを抱くのかは、わからないけれど。
青慈は手をつなぎ直すと、いつものように優しく言った。
「ずっと側にいてほしい」
咲希は笑い返したが、ただどこか迷う心があるのも事実だった。
もうじき大切な子がやって来る。咲希はどうにかして無事に産みたいと願っている。
……けれどこんな幸せな日々がずっと続くはずがないとも、思っていた。
だがこの宮に来てからは、青慈がそれをさせなかった。
特に懐妊がわかってからは、咲希を真綿で包むようだった。桜の樹の世話もしなくていいと言ったが、咲希は街にいたときから、毎日染料の植物の様子を見に行くのが日課だった。
だから青慈は、咲希が外に出るときは一緒に付き添うようになっていた。
咲希は桜の樹を見上げながらつぶやく。
「明日、実がつきます」
「そうだね。咲希もわかるようになったか」
桜の世話を続けるうちに、咲希にも実をつける時期がわかるようになっていた。確かめるように青慈に告げる声が、少し頼りなく響くのも気づいていた。
青慈はそっと咲希の肩に触れて言う。
「子どものように思っているの?」
咲希は迷って、こくんとうなずいた。
実をつけると、桜の世話は咲希の手から離れる。それが咲希には寂しくてたまらなかった。相手は植物だと自分に言い聞かせるのは、もうだいぶ前にやめた。
「咲希が愛したから育ったんだ。大丈夫、これからも永く生きていくよ」
咲希は白嶺宮の桜を人のように思っているところがある。青慈はそんな咲希を愛おしむようにして言う。
「咲希がそういう子だから、ここに戻ってこられたんだよ」
「私が女童だったときに、ここに来た話ですか?」
離れがたいように桜の樹をみつめながら答えた咲希に、青慈は優しく言う。
「それもある。……それだけではないけど。そうだな」
青慈は咲希に手を差し伸べる。
「行ってみる?」
咲希は青慈の手を取ると、不思議そうに首を傾げた。
青慈が咲希を連れて行ったのは、白嶺宮の表の方にある小さな庭園だった。咲希の住まうところは内宮で一般の立ち入りが禁止されているが、その辺りは街の人々もやって来ることがある。
白嶺領は樹の街、それも宮の中では白い桜が至るところに枝葉を広げる。だからなのか、いつもそこには街の人々たちがいた。
今日もそこでは数人、小さな子らが植物を見ていた。大人たちに手を引かれて、子どもたちは憧れるように桜を見ていた。
その気持ちは、咲希も覚えがある。咲希も女童の頃、ここを訪れた。どういう経緯だったかは知らないが、咲希は一人で来たのを覚えている。
青慈は咲希の手を取って歩きながら言う。
「この辺りの木はずっと変わりがないのだけど」
青慈が見上げる先には、そろそろ冬に至るというのに生き生きと枝を広げる桜の樹があった。白嶺領は土壌が豊かで気候も穏やかだから、樹にとって楽園のようなところだった。
青慈はふと咲希を見下ろしてつぶやく。
「咲希の背はずいぶん伸びた」
「ふふ。大人ですから」
咲希が微笑んで答えると、青慈はふと感慨深そうにため息をついた。
「青慈さま?」
「君が知るずっと前から君を見守ってきた。こうして並んで歩ける日が来るなんて、夢みたいだ」
青慈は咲希とつないだ手を持ち上げて、その手に頬を寄せる。
「……いや、夢じゃないんだ。君は僕の妻で、もうじき子も産まれるんだ」
瞬間、咲希には切ないような気持ちがこみ上げた。
幼い日、咲希はやっと出会えたというような気持ちで青慈の袖をつかんだ。そのときの咲希に向けた青慈の表情は、泣きそうな、切ないような笑顔だった。
咲希と青慈は、ずっと離れ離れだったような気がする。どうしてそんな思いを抱くのかは、わからないけれど。
青慈は手をつなぎ直すと、いつものように優しく言った。
「ずっと側にいてほしい」
咲希は笑い返したが、ただどこか迷う心があるのも事実だった。
もうじき大切な子がやって来る。咲希はどうにかして無事に産みたいと願っている。
……けれどこんな幸せな日々がずっと続くはずがないとも、思っていた。