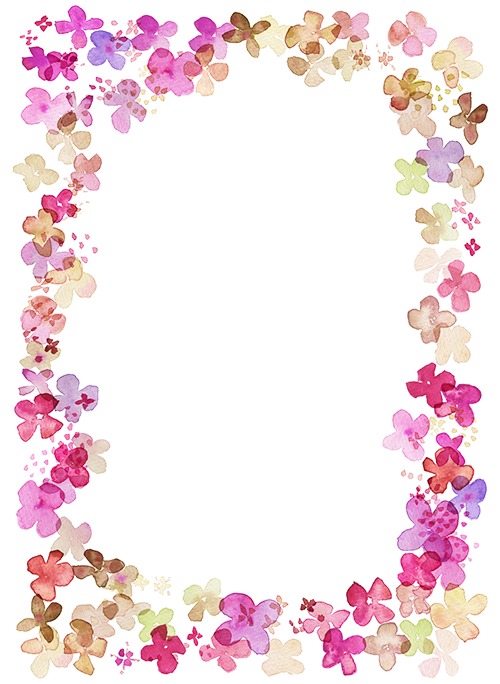咲希の懐妊は、無事に御子が産まれるまでは公にしないと決められたらしい。
ただ、咲希はずいぶん前から宮の中では妃としての扱いを受けていた。
侍従や侍女たちは仰々しく騒ぐことなく、まして汚い言葉をかけることもなかった。咲希の体に負担にならないように気を遣って、甲斐甲斐しく咲希を助けてくれた。
咲希にとって大きかった心遣いが一つある。青慈は、咲希が育てていた桜をいつもうかがうことのできる、東屋を新たに作ってくれた。
そこは緑の紗のような蔓が伸びて、心地よい薄暗がりを作っていた。いつも木々の音や小鳥の声が、優しい音楽のように聞こえていた。
ある日咲希は、東屋をのぞいた青慈に声をかけられた。
「ここにいた方が咲希は顔色がいいみたいだね」
咲希はすぐにうなずいたが、少し考えた後に言葉を返した。
「過分なほどのことをしていただいています。こんなに守られていていいんでしょうか。時々あった貧血も、ここではないんです」
その言葉に青慈はとても満足なようで、うなずいて笑う。
「何よりだ。それでいいんだよ。……咲希」
ふいに青慈は東屋に座って咲希を呼ぶと、彼女を抱え上げて膝に座らせた。
咲希は不思議そうに彼を見上げて、問い返そうとする。
「青慈さ……」
声を塞ぐように、青慈は咲希にそっと口づけた。
まだ真昼で、人目もある。咲希が驚くと、青慈は顔を離していたずらっぽく言った。
「ほら、僕の方がよほど障りのあることをしている。でも誰にも詫びないよ。今の咲希に、何が一番大事か教えるためだから」
青慈は咲希の目をのぞきこんで、その頬を包んだ。
「咲希、安心しておいで。今は二人分、体を大事にして。……大丈夫、ここは僕たちの世界だ」
咲希がまだ不安の目で青慈を見上げると、彼は安心させるように笑う。咲希の頭を胸に抱いてそっとなでた。
そのまま咲希の背を撫でて、青慈は咲希の中にいる子にも語り掛けるように言う。
「季節のしらべが聴こえる? ここは穏やかなところ。つらいことは夢の中に置いて、ここにおいで」
咲希はつと目を閉じた。木々のさざめきと鳥の声が残響のように耳に届き、息を吸えば森の香りに包まれている。
「愛してるんだ。……呼吸するみたいに、それを受け入れてほしいな」
子どもの頃、どこか遠いところで聞いた音楽に青慈の声が重なって、咲希は少しずつ記憶を取り戻していった。
ただ、咲希はずいぶん前から宮の中では妃としての扱いを受けていた。
侍従や侍女たちは仰々しく騒ぐことなく、まして汚い言葉をかけることもなかった。咲希の体に負担にならないように気を遣って、甲斐甲斐しく咲希を助けてくれた。
咲希にとって大きかった心遣いが一つある。青慈は、咲希が育てていた桜をいつもうかがうことのできる、東屋を新たに作ってくれた。
そこは緑の紗のような蔓が伸びて、心地よい薄暗がりを作っていた。いつも木々の音や小鳥の声が、優しい音楽のように聞こえていた。
ある日咲希は、東屋をのぞいた青慈に声をかけられた。
「ここにいた方が咲希は顔色がいいみたいだね」
咲希はすぐにうなずいたが、少し考えた後に言葉を返した。
「過分なほどのことをしていただいています。こんなに守られていていいんでしょうか。時々あった貧血も、ここではないんです」
その言葉に青慈はとても満足なようで、うなずいて笑う。
「何よりだ。それでいいんだよ。……咲希」
ふいに青慈は東屋に座って咲希を呼ぶと、彼女を抱え上げて膝に座らせた。
咲希は不思議そうに彼を見上げて、問い返そうとする。
「青慈さ……」
声を塞ぐように、青慈は咲希にそっと口づけた。
まだ真昼で、人目もある。咲希が驚くと、青慈は顔を離していたずらっぽく言った。
「ほら、僕の方がよほど障りのあることをしている。でも誰にも詫びないよ。今の咲希に、何が一番大事か教えるためだから」
青慈は咲希の目をのぞきこんで、その頬を包んだ。
「咲希、安心しておいで。今は二人分、体を大事にして。……大丈夫、ここは僕たちの世界だ」
咲希がまだ不安の目で青慈を見上げると、彼は安心させるように笑う。咲希の頭を胸に抱いてそっとなでた。
そのまま咲希の背を撫でて、青慈は咲希の中にいる子にも語り掛けるように言う。
「季節のしらべが聴こえる? ここは穏やかなところ。つらいことは夢の中に置いて、ここにおいで」
咲希はつと目を閉じた。木々のさざめきと鳥の声が残響のように耳に届き、息を吸えば森の香りに包まれている。
「愛してるんだ。……呼吸するみたいに、それを受け入れてほしいな」
子どもの頃、どこか遠いところで聞いた音楽に青慈の声が重なって、咲希は少しずつ記憶を取り戻していった。