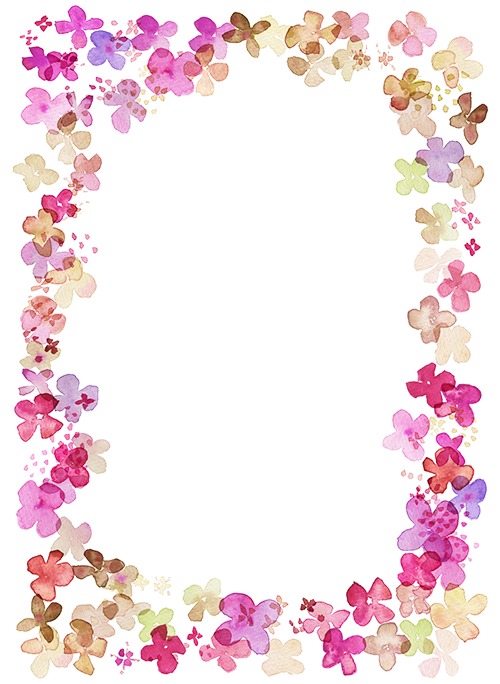咲希が青慈の住まう居室の向かいに住まいを移したのは、それから間もなくのことだった。
青慈はすぐにでも結婚の儀を執り行いたがったが、臣下たちは万が一にも御子に障りがあっては大事だと、青慈をいさめたと聞く。
咲希もそれには賛成だった。自分が宮様の妃というのは、まだ実感がわかない。自分は確かに御子を授かった身ではあるが、それだけで宮の生涯の伴侶として過ごしていいのか、畏れをもっていた。
ただその日から青慈が咲希に与えてくれたのは、濁らない水の中で漂っているような穏やかな日々だった。
青慈は執務を執り行う以外、ほとんど咲希を側から離したがらない。朝目覚めてから執務に向かうまでは、いつも本当に惜しそうな顔をしていた。
「咲希、具合は?」
「私は健やかです。何もご心配はありません……」
「何かあったらすぐに呼ぶんだよ」
青慈はいつも出かけにそっと咲希を包んで、咲希にそう言うのを忘れなかった。
青慈のその静かな慈愛に咲希は助けられていて、身重の体を抱えていても普段通りの生活ができていた。
こちらに越してきてわかったこともある。青慈は咲希より大人で、優しさと労わりに満ちた人柄を尊敬しているけれど、ちょっと可愛いと思うところもある。
青慈は体を離して、苦笑いしてつぶやく。
「僕が離れたくないだけかもしれないね。咲希のぬくもりが、いつも心地よくて」
青慈は朝が弱いようで、寝所の中でねぼけているときがある。咲希が先に起きようとしても、腕をからませて一緒に寝坊させてしまうこともある。
咲希は困ったように言う。
「困った方。執務に遅れてしまいますよ」
「そうしたら、その日は咲希の言うことを何でも聞くよ」
「……もう、甘やかしてほしいわけじゃないです」
普段でも、青慈は咲希の言うことをほとんど叶えてくれる。咲希より恵まれた身分も立場も、咲希を導くために使ってくれていた。
咲希は怒ろうとしても、青慈に対してそんな感情は長く続かない。代わりに、咲希は素朴な言葉をつぶやいた。
「青慈さまは夜だって遅くないのに、とてもよく眠りますね」
「体質なんだよ。水や呼吸と同じくらい眠りが大事なんだ。……あ、いけない」
急ぎ足で執務に向かう彼も、微笑ましいと思いながら見上げていた。
日中も青慈はたびたび咲希の元を訪れ、共に食事を取ったり庭を歩く。彼と同じ時間を過ごすのは心地よかった。青慈の膝元なら、どこも安心していられる。たまに彼の目から離れるだけで、頼りない気持ちになるくらいだった。
一日は早くも遅くもなく一定の速さで過ぎて、やがては二人とも仕事を終える。
その日、青慈は珍しくお抱えの商人を屋敷に呼んだ。
「見てもらいたいものがあるんだ」
青慈が咲希に見せたのは、子ども用の服だった。色も生地も彼の中でほとんど決めているようで、熱をもって検分する。
咲希は苦笑して青慈に言う。
「まだそんなに大きくなるのはだいぶ先です」
咲希が言葉をかけると、彼はそうだねと照れたように笑った。
「待ち遠しくてね。笑ってくれていいよ。咲希との子だと思うと、何でも与えてやりたいんだ」
青慈は愛おしげに服をなでて、それは子どもにそっと触れる仕草にも見えた。
彼はどこにも乱暴さがないから、きっと子どもを大切に扱って、愛してくれるのだろう。
彼の腕の中で育つ子どもはきっと幸せだ。そう思いながら、咲希はそっと自分の腹部をさすった。
青慈もその仕草に気づいたのか、彼もそっと咲希の腹部をなでた。
「早く出ておいで。待っているよ」
青慈は赤子にそう告げて、咲希の手の上に自分の手を重ねた。
青慈はすぐにでも結婚の儀を執り行いたがったが、臣下たちは万が一にも御子に障りがあっては大事だと、青慈をいさめたと聞く。
咲希もそれには賛成だった。自分が宮様の妃というのは、まだ実感がわかない。自分は確かに御子を授かった身ではあるが、それだけで宮の生涯の伴侶として過ごしていいのか、畏れをもっていた。
ただその日から青慈が咲希に与えてくれたのは、濁らない水の中で漂っているような穏やかな日々だった。
青慈は執務を執り行う以外、ほとんど咲希を側から離したがらない。朝目覚めてから執務に向かうまでは、いつも本当に惜しそうな顔をしていた。
「咲希、具合は?」
「私は健やかです。何もご心配はありません……」
「何かあったらすぐに呼ぶんだよ」
青慈はいつも出かけにそっと咲希を包んで、咲希にそう言うのを忘れなかった。
青慈のその静かな慈愛に咲希は助けられていて、身重の体を抱えていても普段通りの生活ができていた。
こちらに越してきてわかったこともある。青慈は咲希より大人で、優しさと労わりに満ちた人柄を尊敬しているけれど、ちょっと可愛いと思うところもある。
青慈は体を離して、苦笑いしてつぶやく。
「僕が離れたくないだけかもしれないね。咲希のぬくもりが、いつも心地よくて」
青慈は朝が弱いようで、寝所の中でねぼけているときがある。咲希が先に起きようとしても、腕をからませて一緒に寝坊させてしまうこともある。
咲希は困ったように言う。
「困った方。執務に遅れてしまいますよ」
「そうしたら、その日は咲希の言うことを何でも聞くよ」
「……もう、甘やかしてほしいわけじゃないです」
普段でも、青慈は咲希の言うことをほとんど叶えてくれる。咲希より恵まれた身分も立場も、咲希を導くために使ってくれていた。
咲希は怒ろうとしても、青慈に対してそんな感情は長く続かない。代わりに、咲希は素朴な言葉をつぶやいた。
「青慈さまは夜だって遅くないのに、とてもよく眠りますね」
「体質なんだよ。水や呼吸と同じくらい眠りが大事なんだ。……あ、いけない」
急ぎ足で執務に向かう彼も、微笑ましいと思いながら見上げていた。
日中も青慈はたびたび咲希の元を訪れ、共に食事を取ったり庭を歩く。彼と同じ時間を過ごすのは心地よかった。青慈の膝元なら、どこも安心していられる。たまに彼の目から離れるだけで、頼りない気持ちになるくらいだった。
一日は早くも遅くもなく一定の速さで過ぎて、やがては二人とも仕事を終える。
その日、青慈は珍しくお抱えの商人を屋敷に呼んだ。
「見てもらいたいものがあるんだ」
青慈が咲希に見せたのは、子ども用の服だった。色も生地も彼の中でほとんど決めているようで、熱をもって検分する。
咲希は苦笑して青慈に言う。
「まだそんなに大きくなるのはだいぶ先です」
咲希が言葉をかけると、彼はそうだねと照れたように笑った。
「待ち遠しくてね。笑ってくれていいよ。咲希との子だと思うと、何でも与えてやりたいんだ」
青慈は愛おしげに服をなでて、それは子どもにそっと触れる仕草にも見えた。
彼はどこにも乱暴さがないから、きっと子どもを大切に扱って、愛してくれるのだろう。
彼の腕の中で育つ子どもはきっと幸せだ。そう思いながら、咲希はそっと自分の腹部をさすった。
青慈もその仕草に気づいたのか、彼もそっと咲希の腹部をなでた。
「早く出ておいで。待っているよ」
青慈は赤子にそう告げて、咲希の手の上に自分の手を重ねた。