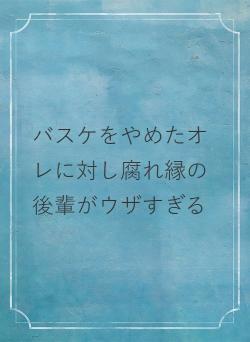そして翌日また二人で登校した。流石にもう慣れられたようで俺たちが二人で登校してもいつものことと把握されている。だが、時々、「ラブラブだなー」なんてことを言われるからその弁明が大変なだけだ。
とにかくだ! 俺は席に座りいつもと同じように授業を受ける。いくらあいつと一緒にいたって学校に行けば、それはいつもと同じ日々だ。休み時間以外は。
「えーつまり、このXを移行させれば、解が求まるわけですね」
そんな先生の説明と式を必死でノートに写す。そういえばあいつはノート取ってるんだろうか? と思い、鈴奈のノートを見る。すると、真面目では到底なさそうだった。それどころか、ちゃんと授業を聴いているのかすら怪しい。
てか、よくよく見たらあれ、隠れてスマホでマンガ読んでるだろ。
とりあえず彼女は余命四ヶ月、ノートを取る理由なんてない。
だからこそ俺もとやかく言うつもりはないが……流石に漫画に熱中しすぎな気がする。
ここまで露骨にやられたらバレるんじゃないか?
「榊原さん、ちゃんと授業を聴いてください。後スマホは没収です」
ほら怒られた。
「なんで。謝りますから返してください」
「お前は俺を馬鹿にしてるのか!!」
鈴奈が助けを乞うように俺の方を見る。だが、これは完全なる自業自得だ。俺には助けてやることは出来ん。
そして休み時間
「浩二君、助けてよ!」
早速泣きついてきた。
「いや、あれは助けられないだろ」
「何よ、冷たいじゃん」
そして、
「そういやさ、」
気になったことがあった。
「何?」
「なんでちゃんと学校は、行ってるんだ?」
それが俺が感じだ疑問だ。
どうせ死ぬのが分かっているのに知識を蓄えとく意味がない。俺たちは吉田松陰ではないのだ。
それに、漫画を読みながら授業出てるし。
「それはねー、ふふん! 最期の瞬間まで普通の生活をしたいからです!」
そう言ってきた。漫画授業中に読んでるくせに。
「それにね、余命があるからって変に生活変えるのって変じゃない? 負けた感じがするし。だから生活スタイルを変えないわけ」
そしてその後、「まあお母さんとお父さんに心配させないためってのもあるけどね」と笑いながら言ったが。
確かに一理ある。運命に負けるのが嫌。
まるで漫画みたいなセリフだが、今の鈴奈にはまさに当てはまるワードだ。
俺には本当にわからない。なんでこんなに元気なのか。
「でもさ、お前じゃあなんでマンガ読んでるんだ?」
「ギグッ!」
図星かよ。ギグッなんてセリフ漫画でしか見ないぞ。
「それは……いいじゃない。余命僅かなんだから」
「さっきと言ってることが違うくね?」
「うるさい!」
そして、授業が終わったのち、俺たちは、一緒に下校した。
その際に、ファミレスに寄ることにした。
「そういやさ」
「ん?」
「もうすぐ中間テストだろ、お前どうするんだ?」
もうそろそろそんな時期だ。鈴奈にとってはもうテスト勉強をする意味はないが、勉強するのか、しないのか。
「まあ、赤点取らないくらいに頑張るつもりだよ。うーん……平均四十五点くらい狙おっかな」
「四十五点……」
うちの赤点の点数が四十点であることを考えると、まさにぎりぎりの点数だ。
「うん四十五点。まあ、所詮今の私には遊びだしね。進級出来なくてもいいけど、補講に行くのは面倒くさいからね」
それから、「あ、でも」と付け足して、
「浩二君はまじめにやってよね。私と違って先があるんだからさ」
「……お前にもあるだろ」
「私にはないよ。だって十八の誕生日に殺されることが確定してるんだから……あ、いま死神さんが人聞きが悪いって言った。だってそうじゃん、殺されるようなもんじゃん。ねえ浩二君」
俺にはどう返していいかわからない。俺たち高校生は本来死には無関係なはずだ。それが今、現実のものとなってきている。それが俺にはどうも理解はできても納得ができない。
むしろなんで、笑い話にできるんだろうとも思った。当事者だから出来るのか、それとも、本当は死なんて怖くないという事なのか……。
「ねえ、何でそんなにだんまりしてるの? せっかくのファミレスがもったいない!!」
そう言って、鈴奈はスパゲッティをすすった。
お前がこの空気にしたんだろ。
なんで鈴奈の問題に関して、俺の方が深刻になっているんだ。
そして、鈴奈はテスト前になっても勉強するそぶりはなかった。
なぜか俺の家に来て俺が勉強しているさまを見ながらゲームをするという悪魔の所業をしている。そんな鈴奈を見ながら、「勉強したら?」と訊いたが、「んーん。大丈夫」としか言わなかった。
それで大丈夫なのか? と言いたい。
それ、四〇点も取れんだろ。
「鈴奈、勉強しないんなら家から出て行ってくれ」
そう、鈴奈に言う。もう、目の前でゲームをされている方が迷惑だ。
「浩二君も勉強じゃなくてゲームしてもいいんだよ」
「別にお前が許可することじゃねえだろ」
「やろうよ!」
そして、腕を引っ張られた。しかし、俺は推薦狙いの受験生だ。中間テストが大事なのだ。
「帰れ!!」
そう怒鳴ると、「分かった」と言って、別の部屋にゲーム機を持って行った。……結局ゲームはするのかよ。
そして、うざいやつがいなくなったので、俺は必死に勉強する。
そして、二時間後、流石に頭が疲れた。鈴奈は今どうしてるのかなと、思い、鈴奈がいる部屋に向かう。
「あ、浩二君!!」
思い切り手を振っている。
「お前、まだ帰ってなかったのかよ」
「いいじゃない。邪魔してるわけじゃないんだから」
「それはそうだが」
そして、鈴奈のゲーム機を見ると、じっくりとイベントストーリーが流れてた。これは……第六章か。確かこの章では、敵のボスが現れ、主人公たちをフルボッコするが、謎の人物が現れ、主人公たちが助かると言ったものだったはず。
「楽しいのか?」
「うん。もちろん。勉強しないでゲームしている背徳感も相まって楽しいね」
「そう思うんなら、勉強しろよ」
「残念。そんな無駄なことに余命を使いたくありません」
「なら背徳感を持つな」
「ところでさ、一緒にしない?」
「ゲーム? 俺はただの休憩なんだけど」
「休憩だったらなおさらいいじゃん。やろうよ」
そう言って鈴奈はゲーム機を俺に手渡してくる。そしてそれにはもう逆らえなかった。
……勉強しなくてはならないのにだ。
とにかくだ! 俺は席に座りいつもと同じように授業を受ける。いくらあいつと一緒にいたって学校に行けば、それはいつもと同じ日々だ。休み時間以外は。
「えーつまり、このXを移行させれば、解が求まるわけですね」
そんな先生の説明と式を必死でノートに写す。そういえばあいつはノート取ってるんだろうか? と思い、鈴奈のノートを見る。すると、真面目では到底なさそうだった。それどころか、ちゃんと授業を聴いているのかすら怪しい。
てか、よくよく見たらあれ、隠れてスマホでマンガ読んでるだろ。
とりあえず彼女は余命四ヶ月、ノートを取る理由なんてない。
だからこそ俺もとやかく言うつもりはないが……流石に漫画に熱中しすぎな気がする。
ここまで露骨にやられたらバレるんじゃないか?
「榊原さん、ちゃんと授業を聴いてください。後スマホは没収です」
ほら怒られた。
「なんで。謝りますから返してください」
「お前は俺を馬鹿にしてるのか!!」
鈴奈が助けを乞うように俺の方を見る。だが、これは完全なる自業自得だ。俺には助けてやることは出来ん。
そして休み時間
「浩二君、助けてよ!」
早速泣きついてきた。
「いや、あれは助けられないだろ」
「何よ、冷たいじゃん」
そして、
「そういやさ、」
気になったことがあった。
「何?」
「なんでちゃんと学校は、行ってるんだ?」
それが俺が感じだ疑問だ。
どうせ死ぬのが分かっているのに知識を蓄えとく意味がない。俺たちは吉田松陰ではないのだ。
それに、漫画を読みながら授業出てるし。
「それはねー、ふふん! 最期の瞬間まで普通の生活をしたいからです!」
そう言ってきた。漫画授業中に読んでるくせに。
「それにね、余命があるからって変に生活変えるのって変じゃない? 負けた感じがするし。だから生活スタイルを変えないわけ」
そしてその後、「まあお母さんとお父さんに心配させないためってのもあるけどね」と笑いながら言ったが。
確かに一理ある。運命に負けるのが嫌。
まるで漫画みたいなセリフだが、今の鈴奈にはまさに当てはまるワードだ。
俺には本当にわからない。なんでこんなに元気なのか。
「でもさ、お前じゃあなんでマンガ読んでるんだ?」
「ギグッ!」
図星かよ。ギグッなんてセリフ漫画でしか見ないぞ。
「それは……いいじゃない。余命僅かなんだから」
「さっきと言ってることが違うくね?」
「うるさい!」
そして、授業が終わったのち、俺たちは、一緒に下校した。
その際に、ファミレスに寄ることにした。
「そういやさ」
「ん?」
「もうすぐ中間テストだろ、お前どうするんだ?」
もうそろそろそんな時期だ。鈴奈にとってはもうテスト勉強をする意味はないが、勉強するのか、しないのか。
「まあ、赤点取らないくらいに頑張るつもりだよ。うーん……平均四十五点くらい狙おっかな」
「四十五点……」
うちの赤点の点数が四十点であることを考えると、まさにぎりぎりの点数だ。
「うん四十五点。まあ、所詮今の私には遊びだしね。進級出来なくてもいいけど、補講に行くのは面倒くさいからね」
それから、「あ、でも」と付け足して、
「浩二君はまじめにやってよね。私と違って先があるんだからさ」
「……お前にもあるだろ」
「私にはないよ。だって十八の誕生日に殺されることが確定してるんだから……あ、いま死神さんが人聞きが悪いって言った。だってそうじゃん、殺されるようなもんじゃん。ねえ浩二君」
俺にはどう返していいかわからない。俺たち高校生は本来死には無関係なはずだ。それが今、現実のものとなってきている。それが俺にはどうも理解はできても納得ができない。
むしろなんで、笑い話にできるんだろうとも思った。当事者だから出来るのか、それとも、本当は死なんて怖くないという事なのか……。
「ねえ、何でそんなにだんまりしてるの? せっかくのファミレスがもったいない!!」
そう言って、鈴奈はスパゲッティをすすった。
お前がこの空気にしたんだろ。
なんで鈴奈の問題に関して、俺の方が深刻になっているんだ。
そして、鈴奈はテスト前になっても勉強するそぶりはなかった。
なぜか俺の家に来て俺が勉強しているさまを見ながらゲームをするという悪魔の所業をしている。そんな鈴奈を見ながら、「勉強したら?」と訊いたが、「んーん。大丈夫」としか言わなかった。
それで大丈夫なのか? と言いたい。
それ、四〇点も取れんだろ。
「鈴奈、勉強しないんなら家から出て行ってくれ」
そう、鈴奈に言う。もう、目の前でゲームをされている方が迷惑だ。
「浩二君も勉強じゃなくてゲームしてもいいんだよ」
「別にお前が許可することじゃねえだろ」
「やろうよ!」
そして、腕を引っ張られた。しかし、俺は推薦狙いの受験生だ。中間テストが大事なのだ。
「帰れ!!」
そう怒鳴ると、「分かった」と言って、別の部屋にゲーム機を持って行った。……結局ゲームはするのかよ。
そして、うざいやつがいなくなったので、俺は必死に勉強する。
そして、二時間後、流石に頭が疲れた。鈴奈は今どうしてるのかなと、思い、鈴奈がいる部屋に向かう。
「あ、浩二君!!」
思い切り手を振っている。
「お前、まだ帰ってなかったのかよ」
「いいじゃない。邪魔してるわけじゃないんだから」
「それはそうだが」
そして、鈴奈のゲーム機を見ると、じっくりとイベントストーリーが流れてた。これは……第六章か。確かこの章では、敵のボスが現れ、主人公たちをフルボッコするが、謎の人物が現れ、主人公たちが助かると言ったものだったはず。
「楽しいのか?」
「うん。もちろん。勉強しないでゲームしている背徳感も相まって楽しいね」
「そう思うんなら、勉強しろよ」
「残念。そんな無駄なことに余命を使いたくありません」
「なら背徳感を持つな」
「ところでさ、一緒にしない?」
「ゲーム? 俺はただの休憩なんだけど」
「休憩だったらなおさらいいじゃん。やろうよ」
そう言って鈴奈はゲーム機を俺に手渡してくる。そしてそれにはもう逆らえなかった。
……勉強しなくてはならないのにだ。