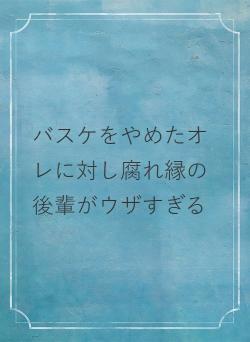それから数日が経ち、鈴奈の葬式の日となった。
正直、俺としては行くのが少し億劫である。
何しろ、鈴奈が最期に俺と共にたという事実は広まっているのだから。
俺が鈴奈を殺した! とまではいかないものの、鈴奈を助けられなかった役立たずのように思われていてもおかしくない。
それに何より、俺はまだ立ち直れていない。
ただ、鈴奈は俺が行かなければ悲しみそうな感じがする。
というより許してはくれないだろう。
だから俺は行くしかない。そこで鈴奈が死んだという事実を受け止めなくてはならないのだ。
俺はそう心で決め、鈴奈の葬式に向かう。
そう式場の待合ロビーには相原さんがいた。
正直会いたくはない。なんて言われるのかもうわかっているのだ。
どうせ俺が責められるだけだろう。
でも、普通に考えて俺を攻めない方がおかしい。
だけど、それでいいのかもしれない。それで、相原さんの心の傷が癒えるのならば。
「ねえ、町田君……鈴奈の最期に立ち会ったんだって?」
相原さんは消え細りそうな声でそう言った。
「ああ、そうだ。俺は鈴奈が死ぬ瞬間隣にいた」
「鈴奈を助けてあげられなかったの? それで、鈴奈と一緒にいたのもそう言う事だったの? もしかして鈴奈が死ぬのが分かってたの?」
「ああ、そうだ。鈴奈は死ぬのが分かっていた。四カ月も前からずっと、今日死ぬことが分かっていた。そして俺は鈴奈がそれを知って泣いている現場に立ち会った。だからこそ、俺と、秘密を共有している俺と一緒にいたという訳だ」
死神のことは明かしてもいいが、それにもまたリスクが生じる。
俺が変人だと思われてしまうリスクだ。
「信じがたい事ね。何しろ、突如とした心臓麻痺っていう話じゃない。……どこかの漫画じゃあるまいし」
「そうだな。……だが、鈴奈はそれを知っていたんだ。誕生日になるあの日に死ぬっていう事をな」
俺にはもう、そうとしか言えない。
いくら非現実的でも、それがあの日に俺が体験したことのすべてなのだから。
「一つ聞いてもいい? 鈴奈は幸せだった?」
「俺から言えることは楽しそうだった。その一言だけだよ」
「……そう」
そして、相原さんは歩き出す。
相原さんは今何を考えているのだろうか。
「一つ言いたい」
俺は立ち去ろうとする相原さんに向けて叫ぶ。
「鈴奈がお前に秘密を伝えなかったのはお前が好きだったからだと思うぞ」
そして立ち止まる相原さんに一つの紙を渡す。
「これは、鈴奈から託されたお前への手紙だ。時間があるときに読んでくれ」
「そう……分かった」
そう言って相原さんは手紙を受け取った。
「今は時間がないから後で読むね」
そして、鈴奈のお母さんにも会った。
「ありがとうね。鈴奈に良くしてくれて」
「いや、俺が鈴奈に良くされましたよ。友達がいない俺を大事に思ってくれていて」
「そう……鈴奈はね、昔はもっと活発だったのよ。でもね、お父さんが亡くなったのよ。その時に少しだけ悟りを開いたようになって」
それは初めて聞いたな。
「でもね、その時相原恵美ちゃんが助けてくれたの。ずっと傍にいるって。だから、あの子恵美ちゃんに弱音を吐かなかったのかしらね」
それで、そのしわ寄せが俺に来たと。
実に鈴奈らしい理由じゃねえか。
相原さんを悲しませないようにしてたのは知ってたけど、やっぱり鈴奈にとって相原さんは大事な人だったんだな。
そしてその後、鈴奈の遺書を読んだらしい鈴奈ママに家に連れてこられた。
「以外だったわね。本当にこんな残してたなんて知らなかったわ。やっぱり死期が分かってたのね」
そう鈴奈ママは言って俺に荷物を渡してきた。それをリュックと段ボール箱に入れる。
中々重い。
どれだけ入ってるんだよ。
「俺もです。しかしこれを本当にただで受け取っていいんですか?」
「あの子の意志だもの。仕方ないわよ」
「そうですか」
俺はそれを受け取って帰った。
そして学校に行くと、相原さんに話しかけられる。
「ねえ、鈴奈の遺書読んだよ」
「……そうか。どうだった?」
「どうって……私納得できないよ。もっと私があの子に出来ることがあったはずなの。なのに、あの子は教えてくれなかった。私が苦しむのが嫌っていうのは分かるけど、教えてくれない方が苦しいよ。なんでよ」
そう言って相原さんは泣き出してしまう。
「私はあんたも正直恨んでる。なんで教えてくれなかったのって。あの時は幸せならいいかと思ったけど、でもやっぱり私は嫌だよ。遺書を読んだあとだったらなおさら……」
「それは本当に済まないと思っている。鈴奈がそう言っていたし、俺もお前には話さない方がいいと思っての行動だ。だから詰ってくれてもかまわない」
「それは遠慮しておく。だって、気分が良くなるわけじゃないし、今更不平を言っても、何かが変わるわけじゃないもの」
そして、いつの間にか文化祭の季節が来た。
勿論鈴奈はもういない。
俺も休んじゃおうかと、一瞬思ったが、それは鈴奈が嫌だろうと思い学校に行く。
早速始まった。俺はそこまでシフトがないから、遊びに行く。
だが、隣には鈴奈はいない。分かっていた事ではあるが、なんだか悲しくなる、
「ねえ、一緒に回らない?」
そう俺に言ってきたのは、メイド服を着る相原さんだ。俺と相原さんのシフトは基本かぶっている。
「急にどうしたんだ?」
「鈴奈の穴を渡しで埋めてあげようと思って」
「埋まらないだろ。似合ってないし」
「あ、またそう言うこと言って……」
顔が沈んだ。
「やっぱりまだ鈴奈がいない生活に慣れない。この文化祭だって、鈴奈が頑張ってくれてたのに、本人がここに居ないんだもん」
それはそうだ。
「だが、あいつはそれを織り込み済みで頑張っていた。確かに不条理だよな、ここに居ないっていうのも」
「そうね……」
「本当に神様の馬鹿野郎だ」
今でも鈴奈の姿が忘れられないからな。
「でも、」
俺はカバンを探る。
「こいつがいる。鈴奈が当てたぬいぐるみがな」
「海遊館のだよね。……鈴奈が死ぬ前に見せてくれたもん」
「ああ、鈴奈が当てたんだ」
「へー、うらやましい」
「だろ、あいつ凄いんだよ。常に笑顔を絶やさないしさ、辛いのにもかかわらず頑張るしさ。流石に死の直前は頑張りすぎてたと思うけどさ」
「そう……町田君は鈴奈のことが好きだったの?」
「……ああ」
その言葉に対し意外そうな顔をする相原さん。
「俺は鈴奈が大好きだ。それは今も変わらない。俺は人生であいつよりも好きになる人が出てくるとは思わない」
「出てほしいんじゃないの? 鈴奈的には」
「かもな」
そして、近くにあった店のソーセージを買う。
「相原さん。俺は鈴奈の死に意味を持ちたいんだ。意味のない死にはしたくない。だからこそ、考えていることがあるんだ」
「どうしたの?」
「俺はこの死を題材にした創作物を書きたいんだ」
それは月並みなものだ。これが小説内だと、百回見たわなどと、思われるかもしれない。それに、そんな素人が書いた小説なんて大したことがないだろう。
でも、書くこと自体に意味があると思う。
そう、それはずつと考えていた事だ。
鈴奈の最期に立ち会った経験。それを書いて鈴奈の死のたわ向けにしたい。
「だからさ、手伝ってくれないか?」
「手伝う?」
「俺の執筆を」
「……分かったわ。でも実名は出さないでね」
「分かってる。それが鈴奈のためになるんだから」
そして翌日から、俺たちは一緒に小説を書くことになった。
本名を伏せ、鈴奈との思い出を書いていく。
正直こういうかくのは初めてだし、受験もある。そう言う訳でゆっくり満足に賭けるわけでは無い、が出来る限りのことは書こうと思う。
幸い、相原さんは小説を普段から読む人みたいで、彼女が詳細なことについては教えてくれた。
例えば三点リーダーを使う事や、改行などなど。
参考になる。
そして、大学生になった。
まだ三分の一しか完成していない。だが、妥協なんてするつもりはない。
大学生活のすべてを費やしてでも完成させてやる。
だがmやはり市場が入ってしまう。
その時愛荒さんがいたら、俺を止めてくれるが、やはり鈴奈は可愛く書きたい欲が出る、と同時に、至らぬ点が出てくる。
そんな感じで数年の月日をかけ、ついに俺は書き終えた。
大学三年生の年だった。
「これでどうだ」
そう、相原さんに手渡す。相原さんは俺が送ったワードの文章をじっくりと読む。これで、相原さんが満足いけば次は持ち込みだ。
「うん、いいわね」
相原さんがそう言った。
「やった」
「かなり中立的に、書かれてるし、心情表現もいいし、行けると思う」
「分かった」
早速賞に出した。結果が出るのはだいぶ先だが、緊張してしまう。
そして三か月後結果が出た。
結果はだめだった。賞に入選することはできなかった。
だが、それでもいい。
俺はこの結果を受け止める。
「残念だったね」
そう、相原さんが言った。
「大丈夫だ。これでよかったんだ、鈴奈と一緒の思い出は無理にみんなに触れさせなくてもいいんだ。それに……」
俺はパソコンを開く、
「上げようと思ったらここにあげられるし」
「そうね」
結局小説投稿サイトにあげることにした。
結果はそこまで読まれなかった。11万時の小説を書いたが、PV数は1000も行かなかった。
でも、書いたことに意味がある。
それに康介からは面白いという感想がメールで来た。
それは、兄に対する色眼鏡もあるだろうが。
「相原さん」
俺は相原さんを呼び出して言った。
「今まで手伝ってくれてありがとう」
そう、今までの感謝を。
「いいえ、町田君が頑張ったからよ。私こそこんな魅力的な物語を生み出してくれてありがとう。……私もこの計画?に付き合えてよかった。ありがと」
そして俺たちは手をつなぎ合った。
それから俺は相原さんと友達として付き合った。
俺は、ずっと鈴奈のことは忘れない。鈴奈のことを、鈴奈との思い出を胸に抱いて生きていく。
死ぬまでずっと。
正直、俺としては行くのが少し億劫である。
何しろ、鈴奈が最期に俺と共にたという事実は広まっているのだから。
俺が鈴奈を殺した! とまではいかないものの、鈴奈を助けられなかった役立たずのように思われていてもおかしくない。
それに何より、俺はまだ立ち直れていない。
ただ、鈴奈は俺が行かなければ悲しみそうな感じがする。
というより許してはくれないだろう。
だから俺は行くしかない。そこで鈴奈が死んだという事実を受け止めなくてはならないのだ。
俺はそう心で決め、鈴奈の葬式に向かう。
そう式場の待合ロビーには相原さんがいた。
正直会いたくはない。なんて言われるのかもうわかっているのだ。
どうせ俺が責められるだけだろう。
でも、普通に考えて俺を攻めない方がおかしい。
だけど、それでいいのかもしれない。それで、相原さんの心の傷が癒えるのならば。
「ねえ、町田君……鈴奈の最期に立ち会ったんだって?」
相原さんは消え細りそうな声でそう言った。
「ああ、そうだ。俺は鈴奈が死ぬ瞬間隣にいた」
「鈴奈を助けてあげられなかったの? それで、鈴奈と一緒にいたのもそう言う事だったの? もしかして鈴奈が死ぬのが分かってたの?」
「ああ、そうだ。鈴奈は死ぬのが分かっていた。四カ月も前からずっと、今日死ぬことが分かっていた。そして俺は鈴奈がそれを知って泣いている現場に立ち会った。だからこそ、俺と、秘密を共有している俺と一緒にいたという訳だ」
死神のことは明かしてもいいが、それにもまたリスクが生じる。
俺が変人だと思われてしまうリスクだ。
「信じがたい事ね。何しろ、突如とした心臓麻痺っていう話じゃない。……どこかの漫画じゃあるまいし」
「そうだな。……だが、鈴奈はそれを知っていたんだ。誕生日になるあの日に死ぬっていう事をな」
俺にはもう、そうとしか言えない。
いくら非現実的でも、それがあの日に俺が体験したことのすべてなのだから。
「一つ聞いてもいい? 鈴奈は幸せだった?」
「俺から言えることは楽しそうだった。その一言だけだよ」
「……そう」
そして、相原さんは歩き出す。
相原さんは今何を考えているのだろうか。
「一つ言いたい」
俺は立ち去ろうとする相原さんに向けて叫ぶ。
「鈴奈がお前に秘密を伝えなかったのはお前が好きだったからだと思うぞ」
そして立ち止まる相原さんに一つの紙を渡す。
「これは、鈴奈から託されたお前への手紙だ。時間があるときに読んでくれ」
「そう……分かった」
そう言って相原さんは手紙を受け取った。
「今は時間がないから後で読むね」
そして、鈴奈のお母さんにも会った。
「ありがとうね。鈴奈に良くしてくれて」
「いや、俺が鈴奈に良くされましたよ。友達がいない俺を大事に思ってくれていて」
「そう……鈴奈はね、昔はもっと活発だったのよ。でもね、お父さんが亡くなったのよ。その時に少しだけ悟りを開いたようになって」
それは初めて聞いたな。
「でもね、その時相原恵美ちゃんが助けてくれたの。ずっと傍にいるって。だから、あの子恵美ちゃんに弱音を吐かなかったのかしらね」
それで、そのしわ寄せが俺に来たと。
実に鈴奈らしい理由じゃねえか。
相原さんを悲しませないようにしてたのは知ってたけど、やっぱり鈴奈にとって相原さんは大事な人だったんだな。
そしてその後、鈴奈の遺書を読んだらしい鈴奈ママに家に連れてこられた。
「以外だったわね。本当にこんな残してたなんて知らなかったわ。やっぱり死期が分かってたのね」
そう鈴奈ママは言って俺に荷物を渡してきた。それをリュックと段ボール箱に入れる。
中々重い。
どれだけ入ってるんだよ。
「俺もです。しかしこれを本当にただで受け取っていいんですか?」
「あの子の意志だもの。仕方ないわよ」
「そうですか」
俺はそれを受け取って帰った。
そして学校に行くと、相原さんに話しかけられる。
「ねえ、鈴奈の遺書読んだよ」
「……そうか。どうだった?」
「どうって……私納得できないよ。もっと私があの子に出来ることがあったはずなの。なのに、あの子は教えてくれなかった。私が苦しむのが嫌っていうのは分かるけど、教えてくれない方が苦しいよ。なんでよ」
そう言って相原さんは泣き出してしまう。
「私はあんたも正直恨んでる。なんで教えてくれなかったのって。あの時は幸せならいいかと思ったけど、でもやっぱり私は嫌だよ。遺書を読んだあとだったらなおさら……」
「それは本当に済まないと思っている。鈴奈がそう言っていたし、俺もお前には話さない方がいいと思っての行動だ。だから詰ってくれてもかまわない」
「それは遠慮しておく。だって、気分が良くなるわけじゃないし、今更不平を言っても、何かが変わるわけじゃないもの」
そして、いつの間にか文化祭の季節が来た。
勿論鈴奈はもういない。
俺も休んじゃおうかと、一瞬思ったが、それは鈴奈が嫌だろうと思い学校に行く。
早速始まった。俺はそこまでシフトがないから、遊びに行く。
だが、隣には鈴奈はいない。分かっていた事ではあるが、なんだか悲しくなる、
「ねえ、一緒に回らない?」
そう俺に言ってきたのは、メイド服を着る相原さんだ。俺と相原さんのシフトは基本かぶっている。
「急にどうしたんだ?」
「鈴奈の穴を渡しで埋めてあげようと思って」
「埋まらないだろ。似合ってないし」
「あ、またそう言うこと言って……」
顔が沈んだ。
「やっぱりまだ鈴奈がいない生活に慣れない。この文化祭だって、鈴奈が頑張ってくれてたのに、本人がここに居ないんだもん」
それはそうだ。
「だが、あいつはそれを織り込み済みで頑張っていた。確かに不条理だよな、ここに居ないっていうのも」
「そうね……」
「本当に神様の馬鹿野郎だ」
今でも鈴奈の姿が忘れられないからな。
「でも、」
俺はカバンを探る。
「こいつがいる。鈴奈が当てたぬいぐるみがな」
「海遊館のだよね。……鈴奈が死ぬ前に見せてくれたもん」
「ああ、鈴奈が当てたんだ」
「へー、うらやましい」
「だろ、あいつ凄いんだよ。常に笑顔を絶やさないしさ、辛いのにもかかわらず頑張るしさ。流石に死の直前は頑張りすぎてたと思うけどさ」
「そう……町田君は鈴奈のことが好きだったの?」
「……ああ」
その言葉に対し意外そうな顔をする相原さん。
「俺は鈴奈が大好きだ。それは今も変わらない。俺は人生であいつよりも好きになる人が出てくるとは思わない」
「出てほしいんじゃないの? 鈴奈的には」
「かもな」
そして、近くにあった店のソーセージを買う。
「相原さん。俺は鈴奈の死に意味を持ちたいんだ。意味のない死にはしたくない。だからこそ、考えていることがあるんだ」
「どうしたの?」
「俺はこの死を題材にした創作物を書きたいんだ」
それは月並みなものだ。これが小説内だと、百回見たわなどと、思われるかもしれない。それに、そんな素人が書いた小説なんて大したことがないだろう。
でも、書くこと自体に意味があると思う。
そう、それはずつと考えていた事だ。
鈴奈の最期に立ち会った経験。それを書いて鈴奈の死のたわ向けにしたい。
「だからさ、手伝ってくれないか?」
「手伝う?」
「俺の執筆を」
「……分かったわ。でも実名は出さないでね」
「分かってる。それが鈴奈のためになるんだから」
そして翌日から、俺たちは一緒に小説を書くことになった。
本名を伏せ、鈴奈との思い出を書いていく。
正直こういうかくのは初めてだし、受験もある。そう言う訳でゆっくり満足に賭けるわけでは無い、が出来る限りのことは書こうと思う。
幸い、相原さんは小説を普段から読む人みたいで、彼女が詳細なことについては教えてくれた。
例えば三点リーダーを使う事や、改行などなど。
参考になる。
そして、大学生になった。
まだ三分の一しか完成していない。だが、妥協なんてするつもりはない。
大学生活のすべてを費やしてでも完成させてやる。
だがmやはり市場が入ってしまう。
その時愛荒さんがいたら、俺を止めてくれるが、やはり鈴奈は可愛く書きたい欲が出る、と同時に、至らぬ点が出てくる。
そんな感じで数年の月日をかけ、ついに俺は書き終えた。
大学三年生の年だった。
「これでどうだ」
そう、相原さんに手渡す。相原さんは俺が送ったワードの文章をじっくりと読む。これで、相原さんが満足いけば次は持ち込みだ。
「うん、いいわね」
相原さんがそう言った。
「やった」
「かなり中立的に、書かれてるし、心情表現もいいし、行けると思う」
「分かった」
早速賞に出した。結果が出るのはだいぶ先だが、緊張してしまう。
そして三か月後結果が出た。
結果はだめだった。賞に入選することはできなかった。
だが、それでもいい。
俺はこの結果を受け止める。
「残念だったね」
そう、相原さんが言った。
「大丈夫だ。これでよかったんだ、鈴奈と一緒の思い出は無理にみんなに触れさせなくてもいいんだ。それに……」
俺はパソコンを開く、
「上げようと思ったらここにあげられるし」
「そうね」
結局小説投稿サイトにあげることにした。
結果はそこまで読まれなかった。11万時の小説を書いたが、PV数は1000も行かなかった。
でも、書いたことに意味がある。
それに康介からは面白いという感想がメールで来た。
それは、兄に対する色眼鏡もあるだろうが。
「相原さん」
俺は相原さんを呼び出して言った。
「今まで手伝ってくれてありがとう」
そう、今までの感謝を。
「いいえ、町田君が頑張ったからよ。私こそこんな魅力的な物語を生み出してくれてありがとう。……私もこの計画?に付き合えてよかった。ありがと」
そして俺たちは手をつなぎ合った。
それから俺は相原さんと友達として付き合った。
俺は、ずっと鈴奈のことは忘れない。鈴奈のことを、鈴奈との思い出を胸に抱いて生きていく。
死ぬまでずっと。